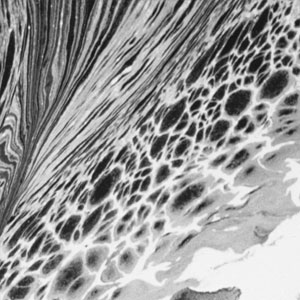ダヴィッド・ファルー,ラングロワとバザンと共に革命的であること
David Faroult, « Révolutionnaire avec Langlois et Bazin », Cahiers du Cinéma, n⁰ 791, octobre 2022, p. 86-87.
この忠実さは、驚くべきことだろう──ゴダールは、政治的に最もラディカルだった時期に、つまりカイエ・ドゥ・シネマがマルクス主義の高揚の中でバザン的な理想主義を追い詰めて いた時期においてさえ、アンドレ・バザンとアンリ・ラングロワ[訳註1]の遺産に導かれ続けていた。恐らくゴダール自らも意識することがない忠実さ。当時は十分に広く共有されたひとつの転換期であり、革命的な政治を優先させることで、多くの人々に映画との利害関係を築くリスクをもたらす瞬間であった。それでもなお、ジャン=リュック・ゴダールは、ジャン=ピエール・ゴラン[訳註2]をはじめとする集団と共に、「芸術への配慮 (souci de l’art[1])」を持ち続けていた。この態度の条件は、今日我々が当時とは必ずしもそうではなかった形で、我々自身のために再構築しようとすることができるいくつかの前提にある。 シネマという概念における4つの論点を、登場する年代順に区別してみよう。
技術──シネマトグラフ、土台となる機械。それは動くイメージの撮影と投射の両方を可能にする機械であり、そこから派生するあらゆる技術である。
映写機の集団的な収益性によって発達する産業。(個人的に用いられるエジソンのキネトスコープとは対照的。)
産業の成功によって、映画はメディアに、そして大衆のコミュニケーションの道具になる。その結果、やがて国家や産業による表現規制への懸念が生じることとなる。(ドレフュス事件を題材にしたことで検閲対象となったメリエスの初期作品が想起される。)
長い間議論されてきた映画の芸術としての価値は、1915年以降に増加した作品に基づいている。もし、この時代以降、映画が広く国際的に展開されていなかったら、おそらくアンリ・ラングロワのような、映画が芸術となるまでの20年間の中から、まだ救えるものを救う情熱のある人物さえいなかっただろう。
映画の実践者としての思想家は、可能な限り自己を欺くことなく、常に自らを位置づける必要がある──この4つの問題のうち、どこに重心を置くのか? しかし、このことは逆に、自らを占める特異で常に複雑な立ち位置において、他者との連関を解きほぐすことから免れるものではない。そして、政治(革命)と映画芸術という異なる領域間の困難な出会いにおいては、コミュニケーションの問題──それは彼らが目指す政治的効果に関連する──を優先してしまうという大きな誘惑が存在する。だがしかし、ゴランとゴダールは、特異なことにあえて逆の選択を取った。闘争的な映画はまず闘争的な聴衆を惹きつける。大衆を扇動するものとして映画を捉えるのは錯覚である。なぜなら、これらの映画を見に来るのは大衆ではないからだ。そこで彼らは、問いを反転させる──いかなる映画が、それを見にくる少数の闘争的聴衆にとって有益なものになりうるだろうか? ジガ・ヴェルトフ集団による応答は、すでにマルクス主義者である活動家たちの理論的教育の水準をさらに上げるような映画を作ることであった。すなわち、プロレタリアであろうとなかろうと、すでに集団的な実践を意識し、それに参加している人々に対して、自分たちの活動をよりよく理解し、思考することへの渇望を訴えかけられているかどうかが問題なのである。
このプロパガンダ的な野心(これら「黒画面」の映画は、弁証法的に思考する方法を示す)の特異な問題点は、芸術の発明が持たねばならない余地を残している。なぜなら、この教育主義は、概念へとつながる具体的対象のイメージを見つけ、秩序づけることが必要となるような抽象化の度合いを目指しているからである。『万事快調』が公開された際に形作られた転換点のひとつは、映画芸術を突き動かす弁証法、すなわち、のちにユセフ・イシャグプール[訳註3]によって極めて簡潔に言い表された「現実のイマージュとイマージュの現実[訳註4]」の間に加わることである。つまり、映画は、現実の機械的な記録[2]と、スクリーンの白い四角形に映し出されるあらゆるイメージの「極めて抽象的な」性格との間を常に行き来し、想像力に訴えかける「イマージュの現実」を構成するのである。このシネマトグラフ的なイメージの現実は、少なくとも4つの側面(技術、産業、コミュニケーション、芸術)を包含する「映画」という名の下に制定された社会的関係のなかに刻み込まれている。投射された映画は特異な地位にあり、それこそがシネマトグラフ的なものなのである。シネマトグラフ的なものは、現実と想像の不毛な二項対立から、第3項へと抜け出すことを可能にしてくれる。現実の中で見られる対象のイメージと、(フレームや光、持続時間などの選択を通して)スクリーンに映し出される同じ対象のイメージは、決して同一状態ではないのだ。
「見せる行為 (L’acte de montrer[訳註5])」(セルジュ・ダネー)には特別な責任が課せられている。映画作家はその責任を負い、すべての観客はそれを問う「権利」を有している。しかし、機械の「現実的」な構成は、作品を位置付けるための唯一の宣言された基準(「現実に忠実」であるか否か)を、映画外の現実の中で怠惰に探すことを促しているように思われる。また、ゴダール映画を前にしたときの、判読不可能だという非難や、定められた意味を明確にすることの困難は、多くの人が「映画」が従うべき形式の規範を内面化してしまっていることを示している。ほとんど実践されていないがために、映画芸術の可能性の射程は、もはや認識すらされていないこともある。それゆえ、不完全な、あるいは失敗したコミュニケーションに対して異議申し立てを行うのである。それは、『さらば、愛の言葉よ』(2014年)以来、まさにテーマの核心をついている場合であってさえも、意表を突く手法で3D技術を活用することで、あるカップルの同じ物語を(とはいえ、必ずしも同じ瞬間ではない)、現実(「自然[訳註6]」)の側と「隠喩 メタファー[訳註7]」の側で、異なる俳優を使って対立させている。ゴダール的なユートピアの探求とは、象徴的なものが、もはや言葉によって支配されるのではなく、映画の地平として考えられたモンタージュによって支配される人類の探求であるのかもしれない──言葉なしで、言葉を習得する手前で、イメージと音を結合すること。
「映画とは何か」という、バザンが一つ一つの映画を検証する中で立てた問いに忠実であることで、ゴダールは映画作家としてその問いを思考し、政治が主題となっているときでさえも、映画の芸術的な可能性を作品ごとに再発明している。
ラングロワへの忠実さは、映画芸術の歴史の中に自分を位置づけようとする配慮にあらわれていた。闘争の時代において、彼らはとりわけブレヒトに没頭しつつも、旗印にしていたのはジガ・ヴェルトフであり、エイゼンシュテインとは過剰なまでに相反していた。そして、闘争の時代の終焉を目前にした1973年(つまり、ラングロワの存命中)、『映画史』の企画が初めて立案される[3]。1977年、シネマテーク・フランセーズの創設者の死によって、ゴダールは、たとえそれが長い作業であったとしても、このプロジェクトを立ち上げることとなったのである。
芸術家たちは、言葉にするまでもなく心得ていることがある──残りのもの(コミュニケーション、産業、技術)に自らの野心を内側から蝕まれないようにするための条件のひとつは、自らの芸術の歴史とその未来、あるいはその死の可能性との対話の中に、自らを位置づけることだ。この対話は、しばしば秘密裏に行われるものだが、ゴダールは対話者を求めてそれを公に向けて共有した。シネマテーク・フランセーズは礼拝堂かと聞いたジャック・シャンセルに対し、ラングロワは次のように即答している──「いいや、シネマテークは運動場(ギムナジウム)だ! 」つまり、形式=体型を維持する[訳註8]必要性をもって、信心深いシネフィルの崇拝と対立したのである[訳註9]。
Notes
-
[訳註1]
アンリ・ラングロワ(1914-1977)は、フランスのフィルム・アーキヴィスト。シネマテーク・フランセーズと映画博物館の創設者として、映画修復・保存の基礎を確立した人物として知られている。
-
[訳註2]
ジャン=ピエール・ゴラン(1943-)は、フランスの映画作家、映画研究者。ゴダールと共にジガ=ヴェルトフ集団を結成し『万事快調』(1973)などの作品を共同監督した。同集団解散後は、映画製作を継続しながらカリフォルニア大学サンディエゴ校などで映画史を研究している人物としても知られている。
-
[1]
Olivier Neveux, « Le souci politique de l’art », Théâtre public n⁰ 242, janvier-mars 2022.
-
[訳註3]
ユセフ・イシャグプール(1940-2021)は、テヘラン生まれのフランスの批評家。文学・映画・絵画・哲学など様々なジャンルのテクストを執筆するとともに、独自の映画理論を確立した人物として知られる。
-
[訳註4]
以下の議論を参照。Youssef Ishaghpour, Le Cinéma, Éditions Flammarion, collection Dominos, 1996(『ル・シネマ―映画の歴史と理論』三好信子訳、新曜社、2002年).
-
[2]
アンドレ・バザンの主張した「写真映像の存在論」は、技術的な与件であり、リアリズムの美学の規定ではない。
-
[訳註5]
ドキュメンタリー映画作品Serge Daney – Itinéraire d’un ciné-fils (Pierre-André Boutang, Dominique Rabourdin, 2004)を参照。セルジュ・ダネーによると道徳は、作者が見せる行為に対する責任を負う映画では存在し得るのであり、見せる行為への責任が希薄なテレビでは存在不可能であるという。
-
[訳註6]
『さらば、愛の言葉よ』(2015)の第1部の題名である。ファルーはこの言葉の意味に合致する語として、補足的に前にréelを置いている。
-
[訳註7]
同2部の題名である。尚訳出に際しては同作品の日本語字幕の表記に倣った。
-
[3]
David Faroult, Godard. Inventions d’un cinéma politique, Paris, Les Prairies Ordinaires, Éditions Amsterdam, 2018.
-
[訳註8]
« garder la forme »という表現は運動にかかわる表現であり、「健康を維持する」「体系を維持する」といった意味で使われることが多い。ファルーによると美学や美術史的な視点からとらえると、美的な形態の維持への配慮という意味にもなりうる。ファルー氏本人よりご教示いただいた。
-
[訳註9]
本論文はDavid Faroult, « Révolutionnaire avec Langlois et Bazin », Cahiers du Cinéma, n⁰ 791, octobre 2022, p. 86-87の全訳である。
この記事を引用する
ダヴィッド・ファルー「ラングロワとバザンと共に革命的であること」 高部 遼・小城 大知 訳、 『Résonances』第14号、2023年、ページ、URL : https://resonances.jp/14/revolutionnaire-avec-langlois-et-bazin/。(2024年07月27日閲覧)