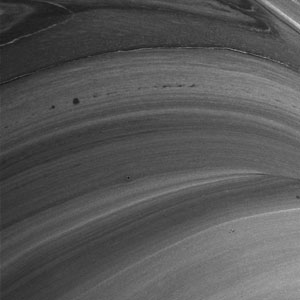婚礼の花、葬儀の花ブランショ「牧歌」を読むコフマンについて
モーリス・ブランショ(1907-2003)は、自身の執筆活動の最初期にあたる1936年に「牧歌」を書いた。この謎めいたフィクションは、11年の空隙を経て1947年春『リコルヌ』誌第1号に発表され、以後「最後の言葉」(1935年執筆)とともに『永遠の繰り言』(1951)、『事後に』(1983)とそれぞれ異なる名を冠した書物に収められることになる。本稿は「牧歌」を含む『事後に』と『災厄のエクリチュール』(1980)に応答するようにしてペンを執ったサラ・コフマン(1934-1994)が1986年の『窒息する言葉』で展開したブランショ読解をひもといてゆく。彼女が『窒息する言葉』を書いたのは、ユダヤ教の師として安息日を遵守したためにアウシュヴィッツ強制収容所で亡くなった父に、ユダヤ人であるという理由で死んでいった同胞たちに、収容所から生還し『人類』を著したロベール・アンテルムに、そしてモーリス・ブランショに敬意を表するためであった。
しかしながら、コフマンにとって「牧歌」を読むことは、物語る行為に随伴する表象不可能なものの表象を問いに付すことと不可分であった。たとえばブランショの「牧歌」を、第二次世界大戦下に起こった事実と重ねる類推的読解について彼女は次のように述べる。「アウシュヴィッツについての物語−フィクションは許容されえないのであり、この出来事を「先取りする」ことはどんな文学であれ無理だろう。たとえば『牧歌』というこの物語でも」[1]。「アウシュヴィッツ以前に書かれた物語である『牧歌』は、一切の嗚咽や叫び声が白日の下に露呈されるのを禁じているが、それがアウシュヴィッツを先取りした物語となりうるには、スキャンダルなしには済まされないだろう」[2]。ところが『窒息する言葉』の中心をなす「牧歌」論を概観すると、コフマンの主張は「牧歌」を「アウシュヴィッツ」のアレゴリーとみなすことへの純粋な否定に集約されるものではないことがわかる。彼女が重点を置くのはむしろ「牧歌」と「アウシュヴィッツ」が直面せざるをえない事態、すなわち物語化が根本的に完遂されえないという事態についてなのであった[3]。
本稿では、コフマンによる「牧歌」読解を二つの観点から整理する。第一に「牧歌」の異邦人(étranger)が「法」とのあいだに保つ距離について、第二に「牧歌」そのものがもつ非牧歌性について、解釈を試みる。これらの作業を通して、先に紹介したコフマンにおける表象不可能性の議論の前段階を示すことを目指す。
異邦なるもの、分離
「牧歌」とはいかなるフィクションであるのか、実際にみてみよう。物語冒頭、名もなき町を訪れた異邦人がホスピスへ案内される。ドアを開けた若い女性(ホスピスの所長の妻ルイーズ)は、彼を歓待する。彼女はこの異邦人の空腹を満たす前にまずシャワー室に連れてゆき、ホスピスの外の泥を洗い流すよう促す。異邦人は自らをもてなすルイーズの顔をこの上なく美しいものとして記憶する。彼女はこの異邦人をアレクサンドル・アキムと命名する、「それではまたあとでね、アレクサンドル・アキム」。それ以降、この三人称フィクションの語り手もまたこの男を「アレクサンドル・アキム」と呼ぶようになる[4]。コフマンは、このアレクサンドルという名からギリシア語のアレクソーを想起する。この語は「遠ざける、隔てる」を意味するフランス語écarterの語源である。「アレクサンドル、それは外の人間、共同体の平衡を断ち切りに来る者、断絶の庇護者、法を侵犯する者、取り決めを侵害する者、言葉を保つ〔約束を守る〕こと(tenir parole)ができない者」とコフマンは言う[5]。ルイーズはこの身元不明の男にアレクサンドル・アキムと命名することによって、彼を文字通り「異邦人」にしてしまう。しかしながら、ルイーズというこの女性は、自らホスピス内部の人間でありながらも、アキムを内部へ順化するよう強制しない。それはつまり彼女が外部を排斥の対象としないことを意味する。「『この人は異邦人なのですよ』ルイーズは楽しげに言った。『私はずっとそう考えていました、彼は決してこの土地の人間になるはずはないでしょう』」[6]。
ルイーズのこの考えは、しかしながら、ホスピスの所長である夫ピエールにおいて本質を成さない。アキムが「あなたの妻が先ほどおっしゃったように、私は永遠によその町の人間でしかないのです」と述べると、所長は次のように返す「いいえ違います、まあ、気を落とすことはありませんよ。妻は頭に浮かんだことをすべて言ってしまうのです。妻の話を真剣に受け取る必要はありません」[7]。ピエールという人物は、自らが全権を握るこのホスピスを「家(maison)」と呼びながら、いつになったら外出できるのかと尋ねるアキムを諭す。ここではいかなることにも疑念を持たずホスピスにいる人間にすべて委ねればよい、と[8]。このようにしてピエールは外部の者を内部としての「家」に順化するよう促す。しかしながらホスピスに足を踏み入れた者は、内部の法の遵守を強いられる。彼らは採石場での労働を義務付けられ、許可のない外出は禁じられているのだ。
コフマンの「牧歌」解釈の要の一つは、異邦性にある。しかしながらそれはアキムという人物の特性としてのみ重要なのではない。「牧歌」において異邦な者は「家」の内部の女性ルイーズによって外部を意味する名を与えられ、歓待される。それによって内部における外部が可能となる。ここでの異邦性とは、「法」が拘束力を持つある特定の場において「法」から永遠に距離を取る者の態度を指す。以上のように、コフマンは「牧歌」のルイーズを分離ないし隔たりによって「家」に関与する人間とみなしていることがわかる。「分離し、乗り越えることのできない距離に残るもの[…]、それこそが真の意味で関係を持つことである。近さと伝達の力は分離の力に依拠する[…]。共同ではありえないものの異邦性のみが共同体の基盤を支える」[9]。したがって「牧歌」の異邦性は、外部からやってきたアキムにのみ特有のものではなく「家」に内在するルイーズのうちにも見出すことができる[10]。
ところで、コフマンにおける「牧歌」はもう一つの観点からも重要である。というのも、このフィクションはブランショにおける牧歌という語が何を含意するのかという問いを提起するからである。次節では、異邦人によって問われる牧歌がいかなるものであるのか、分析を試みる。コフマンによれば、文学史において田園牧歌や恋愛詩を指す牧歌(idylle)という語は「形相=像」を意味するギリシア語エイドスの指小辞エイデュリオンに由来し「小さな形式(物語作品)」を表すという。本稿の肝要となるのは、ブランショの「牧歌」というフィクションに表される牧歌がユートピアとしてのそれでは決してなく、むしろ〈幸福/不幸〉という凡庸な二項対立に先立つ不可分な何かがアイロニカルな仕方で提示されることにより、牧歌そのものの両義性がフィクションにおいて顕現するという点にある。
牧歌を問う異邦人
実際、それはどのようなことだろうか。アキムは〈牧歌なるもの〉をひとまず男女の結婚に結びつける。たとえば彼はルイーズとピエールの間に牧歌を見出すが、その内実はきわめて奇妙である。ルイーズとピエールはアキムに、婚約の思い出を仄めかす。換言すれば、婚姻の「法」が物語としての幸福を支えていることを証左するために、外部者を必要とする。たとえば、ピエールは婚約の思い出の写真アルバムを異邦人にわざと見せびらかす[11]。アキムに向かって「私の物語をあなたに話したいの」と言い出したルイーズが子供っぽく冷たい声で話すのは、婚約の物語である[12]。アキムは彼女に言う、ぼくはあなたが幸福だと知っているが、あなたがなぜ思い出をぼくに打ち明けるのかは理解できない、と。
アキムに「彼ら〔所長と妻〕は幸福なのか? 不幸なのか? 」と問いかけられた監視人の男はこう語る。結婚したばかりの頃の彼らには「気だるく澱んだ沈黙、人に対する荒々しさのない、不幸とは無縁で沈黙を説明する空気」があり、その居心地の悪さゆえ自分はそこに留まってはいられなかった。するとアキムは次のように応答する。「でもあなたがいま説明したことは、穏やかな幸福、異常な何か、あらゆる牧歌の核心にある感覚、言葉のない真の幸福なのです」[13]。アキムにとっての「真の幸福」とは、心地よい言葉が横溢する状態に生成するのではなく、言葉の不在——ここでそれは「沈黙」とほとんど同義である——によって保持されるものであるらしいことがわかる。アキムにとっての「牧歌」は、また別の場面で、ピエールによる疑念を経由して提示される。ある夜のこと、ホスピスで恐ろしい悲鳴を耳にしたアキムが様子を伺いにいくと、夫が自分を殺そうとしていると想像したルイーズが廊下で取り乱していた。ドアの向こうからピエールが現れ、異邦人に歩み寄ってこう問いかける「これが牧歌なのか? これは本当に牧歌なのか? 」アキムは次のように答える「牧歌? そうですとも、当然でしょう? 」[14]このように、たとえばアキムとピエールのあいだでは、牧歌という言葉が想像させるものは大きく異なっている。「牧歌」においては、正常なものと異常なものはいずれも価値判断以前の不可分な何かとして弁証法的に止揚されるのだ。それゆえ、法から永遠に隔たり続ける異邦人アキムは、結婚で結ばれている二人のあいだから、牧歌的共同体の空虚さを浮かび上がらせるのである。ここで『災厄のエクリチュール』においてシモーヌ・ヴェイユを引きながら述べたブランショの言葉が思い出される、「平穏さによる以外に極限的なものは何もないのだと。並外れた平穏さによる狂気、穏やかな狂気。思考すること、消滅すること、すなわち平穏さの災厄」[15]。
物語の終盤、アキムは結婚することでホスピスの外へ出ることができるという「法」に従って、老人の姪エリーズと婚約を結ぶ。結婚式の前夜、彼は禁じられた外出を試みる。疲労の末に倒れ込んだアキムは翌朝、十発の鞭打刑に処されることになる。太陽が照り輝く空の下、六回目の鞭が打たれる時、婚礼を知らせる華やかなファンファーレが鳴り響く。この場面においては、残酷さと平穏さがコントラストを成しながらも両立してしまう。苦しみながら生死をさまよった末、アキムは死を迎える。皮肉にも婚礼は葬儀に姿を変えてしまう。眩い白日が死の呆気なさをよりいっそう際立たせる。このようにして「牧歌」は結末を迎える。一度は法に従うことを決めたアキムだったが、最後の最後あと一歩手前というところで彼はやはり法に背く。真の意味で、法に対し異邦であり続けた。コフマンにとって、また私たちにとって、「牧歌」というフィクションはそれが決して牧歌的でないという限りで本質的なものとなるのだ。
Notes
-
[1]
Sarah Kofman, Paroles suffoquées, Paris, Galilée, 1986, p. 22.
-
[2]
Ibid., p. 39.
-
[3]
たとえば、山邑久仁子は「牧歌」「最後の言葉」を第二次世界大戦の「先取り」とする読解を明確に否定した上で、この二作品の度重なる回帰をブランショにおける「戦後」の認識へと接続している。山邑久仁子「モーリス・ブランショの二つの短編を巡って——回帰する〈外〉」『桐朋学園大学研究紀要』第17号、1991年、187−203ページを参照。
-
[4]
Maurice Blanchot, « L’Idylle » (1936), Après Coup précédé par Le Ressassement éternel, Paris, Minuit, 1983, p. 12.
-
[5]
Kofman, op. cit., p. 27. 強調原文。
-
[6]
Blanchot, op. cit., p. 31.
-
[7]
Ibid., p. 32.
-
[8]
Ibid., p. 31.
-
[9]
Kofman, op. cit., p. 36. コフマンはブランショ『明かしえぬ共同体』に所収されたマルグリット・デュラス論「恋人たちの共同体」を典拠として、「牧歌」のルイーズにデュラスの『死の病い』の少女を重ね合わせている。
-
[10]
関わりなくして関係に参与するというブランショにおける「分離」「隔たり」の思考は、彼の「中性的なもの(le neutre)」をめぐる思考とも深く通底している。郷原佳以「ブランショにおける「中性的なもの」」、『年報 地域文化研究』第5号、2002年、147−165ページを参照。
-
[11]
Blanchot, op. cit., p. 15.
-
[12]
Ibid., p. 24.
-
[13]
Ibid., p. 38. 強調引用者。
-
[14]
Ibid., p. 44.
-
[15]
Id., L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 16. 強調引用者。
この記事を引用する
村田 真衣「婚礼の花、葬儀の花——ブランショ「牧歌」を読むコフマンについて」 『Résonances』第14号、2023年、ページ、URL : https://resonances.jp/14/kofman-lisant-lidylle-de-blanchot/。(2026年03月15日閲覧)