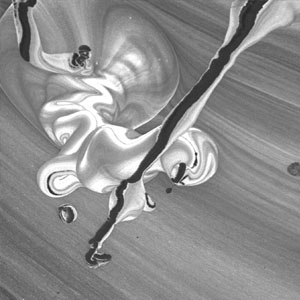一歩引いて見る宗教事象教育感情的なものとの関係を問う
フランスの公教育で宗教に関する知識を盛り込む必要があるという認識が知識人の間で高まるきっかけは1980年代に遡る。85年のピエール・ブルデューの提唱を皮切りに、歴史学者のフィリップ・ジュタールによる報告書や[1]、哲学者レジス・ドゥブレによる宗教事象教育に関する報告書などが発表され、以来多くの研究が蓄積されてきた。同時に、教育現場への反映も早くから試みられてきた。宗教的な知識の教育が社会的課題として浮上してから30年以上経つが、今日、宗教と教育をめぐる状況はいかなる様相を見せているのか。現実的に実施は停頓を見せているという見解を示す研究者も少なくない。宗教社会学や哲学の分野で模索されてきた道を簡単に振り返り、教育現場での行き詰まりの背景にあるものに少し焦点をあててみたい。
*
19世紀末に制定されたフェリー法から100年を経て、公教育と宗教の問題が社会的な議論として再燃した理由は主に二つある。ひとつは80年代半ば頃から目立ち始めた、自国の文化と歴史に対する若者の無知と無関心が顕著になったことがあげられる。こうした状況に対する教育関係者の危機感が、さまざまな分野の専門家が関わる議論のきっかけとなり、宗教知識教育のあり方が検討されはじめた[2]。当初は、キリスト教やユダヤ教など、フランスに長く根づいている伝統的な宗教に関する知識の伝達に重きが置かれた。
ほどなくして、グローバル化の進展や移民の増加などの影響からフランスの宗教風景は大きく変わり、とりわけ従来の伝統宗教には含まれないイスラーム教の存在が議論を新たな方向へと舵を切らせる。同じアブラハム宗教に属してはいても、ユダヤ教やキリスト教とは異なる風習や生活習慣をもつイスラーム教の人々の社会的統合に、公教育が一役買うだろうという期待が高まった。これは何もフランスに限った話ではなく、ヨーロッパ諸国で共有される課題だった。そして「共生(vivre ensemble)」や「他者理解(comprendre autrui)」などの言葉が謳い文句として掲げられ、宗教的知識の必要性を訴える声は次第に大きくなる。90年代以降の宗教と公教育に関する議論は、何のための宗教知識教育かという具合に、その目的を強調する傾向が強くなる[3]。
フランスが他のヨーロッパ諸国と一線を画すのは、原則として宗教に特化した科目を公教育のカリキュラムに設けない点である。周辺の国々では、必修や選択科目というかたちで宗教科の授業があるが[4]、フランスの場合はライシテの観点から、いかに既存のカリキュラムの中だけで宗教的な知識を扱うかということがまず大きな争点である。こうした制限があるなかで伝統宗教を教育で扱うにあたり、最も適しているとして当初注目されたのは歴史の科目であり、その枠組みで宗教史(histoire des religions)を取り上げることで十分だという見解が専門家の間で多かった。そうした機運のなか、冒頭であげたドゥブレは、2002年に当時のジャック・ラング国民教育大臣から要請を受け、既存の公教育のカリキュラムの中に「宗教事象(fait religieux)」を盛り込むことがライックな公教育に適うフランス式の宗教知識教育だと強調した[5]。とりわけ彼は「知的理解のためのライシテ(laïcité d’intelligence」」と「無知のライシテ(laïcité d’imcompétence)」を対置して前者の推進を提唱し、宗教事象に対して無関心でいることはもはや時代にそぐわないとして宗教事象教育を積極的に支持した。この後に蓄積されていく研究は、ドゥブレの議論をたたき台にした方法論に関するものが多くなっていく[6]。
*
宗教事象教育をめぐる議論が、その内容や目的、アプローチに集中してきたのはある種必然的なことである。公教育の領域ではまずライシテの原則という大きな壁があったため、これに抵触しないための理論的枠組みの構築に注力されてきた。ただしここには、時代の変化に伴うライシテの新しい解釈や、共生社会に向けた理念を理論的に提示できれば、共和国の市民は宗教事象教育に対する理解を示すだろうという専門家の希望的観測も見受けられる。目的やアプローチと同様に精緻化する必要のあった論点は、世俗化が進んだフランス社会がこの教育の実施を受け入れられるかどうかという感情的な問題であり、従来の宗教事象教育研究はこの点を十分に考慮してこなかったように思われる。おそらくこの点になかなか踏み込めなかったのは、ヴェールやブルキニに関する社会的議論や、相次ぐテロ事件、近年起こった中学校教員のサミュエル・パティー氏の殺害事件など、国民感情を刺激する出来事が相次いだ影響もあるだろう。宗教事象教育の必要性はその都度再確認されてきたものの、国民の間の抵抗は依然として強く見られる。
この分野の研究を牽引する一人、イザベル・サン゠マルタンも、近年のル・モンド紙のインタビューで、宗教事象教育に関する社会的議論が「明らかに感情的な負荷」を帯びていると指摘しており、そこでは信仰に関するものと知に関するものとの混同が頻繁に見られるという[7]。この「感情的な負荷」の仕組みに少し分け入っていく必要があるだろう。この「負荷」はほとんどの場合、実際に宗教事象教育を受ける子どもではなく、すでに共和国の市民教育を受けた大人によってかけられていることが多い。そこにはカトリック教会のような伝統宗教が再び学校に侵入してくることへの抵抗感や、イスラーム教のような「外来の」宗教によって共和国のあり方が変容してしまうのではないかという不安などがあるだろう。こうした感情の抑制が難しい状態は、その感情を誘発する特定の事象との適度な距離が取れない、すなわち一歩引いて見ることが困難なことを示している。そこでは「共生社会を実現するため」という理想主義的な謳い文句もほとんど効力がない。
宗教事象教育において「距離をとること(distanciation)」が重要であることは宗教社会学者のミレイユ・エスティヴァレーズも早い段階から指摘していたし[8]、ムスリム知識人の哲学者ラシッド・バンジーヌも、宗教事象教育に直接言及したわけではないものの、宗教的な事柄を客観的に分析するための「一歩引いて見る教育(éducation à la distance)」の必要性を説いている[9]。一見すると、さまざまな事象、とりわけ宗教事象から「距離をとる」あるいは「一歩引いて見る」ための課題の対処として、まず適切な知識の伝達が考えられるが、宗教事象教育を通してそのような姿勢を教育することは果たして可能なのか。宗教事象教育は、共和国の市民教育の新たな側面として期待されてきたが、エスティヴァレーズによれば、どうやらそれは少々望みをかけすぎているようである。共和国の市民を育成する「ライシテの神殿」としての学校は、知識の光による無知の克服や、寛容な精神の涵養を掲げているかもしれないが、真に他者を尊重するためには、それだけでは不十分だという[10]。
*
無知の闇に対する知の光という二項対立的な図式は、市民教育の原点にあるコンドルセのような啓蒙の世紀の思想を想起させるだろう。特にこの時代においては蒙昧な宗教に対して理性の光が讃えられたが、歴史学者のアントワーヌ・リルティは、この啓蒙の思想をめぐって現代で見られる一つの傾向を指摘する。近年、とりわけテロ事件など国民感情を揺さぶるような出来事があると、政治家は党派の垣根を越えて「啓蒙の伝統」や「フランスは啓蒙の国」などと、共和国の一体感を再確認するかのように強調することが多い。実際は啓蒙の思想家の立場にも様々あり、時に相互的な緊張関係もあったにもかかわらず、このような文脈で言及される「啓蒙」とは、理性の力、表現の自由、寛容、科学の優位性などの象徴的な概念がひとまとめにされた「近代のクレド」のようだとリルティはいう[11]。クレドとはフランス語で「信条」の意味で用いられることが一般的に多いが、これは必ずしも合理的な判断のみに依拠しているとは限らず、環境的な変化に柔軟に対応するというよりも、同じものを堅持していく姿勢を表す。注目したいのはその語源がラテン語の「我信ず」にあり、キリスト教における信仰告白を意味する点である。「啓蒙」の力を信じるあまり、その姿勢がかえって宗教的(あるいは狂信的)に見えてしまうという現象は、ライシテにも馴染みあるものである[12]。
共和国の基本的原則であるライシテも、市民のアイデンティティに訴えかけるようなかたちで政治的な言説などを通して「フランスはライシテの国である」と言及されることが少なくない。主に1905年の法律で規定されるライシテは、大まかに言えば公的な次元において政教分離として機能し、個人の次元では「信じる自由」と「信じない自由」を良心の自由として保障している。ところでこの「信じない自由」は、ときに「(宗教事象について)知らずにいる自由」とも捉えられる。これはいささか厳格なライシテ(あるいはドゥブレの言う「無知のライシテ」)の捉え方だが、実際にこうした立場も良心の自由の一つのあり方であり、宗教事象教育の議論にも関わってくる点である。宗教事象教育自体、当初は宗教に関する科学的かつ客観的な知識を公教育の枠組みで生徒に教育し、知的に啓かれた共和国市民の育成が目されていた。しかし、そもそも「知る必要がない」あるいは「宗教事象に触れないでいる自由もある」という、ほとんど反宗教的な立場や宗教を敵対視するような感情と親和性が高い「共和国のクレド」のようなライシテは、マジョリティに共有されているものではないものの一定の影響力を持っている[13]。すなわち、サン゠マルタンが指摘したような「信じること」と「知ること」に関する知を身につけ、一歩引いて宗教事象を見ることができる力を培う教育そのものが、宗教事象との絶対的な距離を保つ権利の主張によって足踏みを強いられているという状況が生じている。ライシテに関する言説は、殊に政治的なものと宗教的なものとの関係に焦点が当てられるが、個人と宗教的なものとの関係も再考の余地がある。感情的なものはその一つの手がかりとなるかもしれない。
*
歴史的に見れば、理性は感情に対置されることが多く、それはほとんど科学と宗教との関係に近いものがある。ここで問うべきは、人間は科学的知識を身につければ、それをもって感情的なものも制御できるのかということである。知識を得ることによって、物事をより多角的にそして合理的に見ることができるようになることは間違いない。ただしそれに伴って感情的なものもより高度なかたちで制御できるようになるかというと、必ずしもそうではないと思われる。すなわち知識を身につけることそれ自体は、人間が自らの感情から完全に自由になることを意味せず、それらは別個の問題であると捉えるのが妥当であり、今後の宗教事象教育の議論ではこのような点も考慮する必要があるだろう。
本稿は日本学術振興会特別研究員奨励費(20J21514)の助成を受けている。
Notes
-
[1]
Philippe Joutard, « L’enseignement de l’histoire des religions à l’Ecole », Paris : Ministère de l’Education nationale / La Documentation française, 1989.
-
[2]
本稿における「宗教知識教育」というのは、いわゆる信仰心を育む宗派教育や宗教情操教育とは一線を画す、科学的な知見に基づいて宗教的な知識を教育現場で扱うことを指す。
-
[3]
Cf. Jean-Paul Willaime (dir.), Des maîtres et des dieux, écoles et religions en Europe, Paris, Belin, 2005.
-
[4]
詳しい分布は、伊達聖伸編著『ヨーロッパの世俗と宗教 近世から現代まで』(勁草書房、2020年)の資料編「4.公立校における宗教教育」(xvii-xixページ)を参照されたい。
-
[5]
Régis Debray, « L’enseignement du fait religieux à l’école de la République », Paris : Ministère de l’Education nationale / La Documentation française, 2002.
-
[6]
Cf. Jean-Paul Willaime, Europe et religions, les enjeux du XXIesiècle, Paris, Fayard, 2004 ; Philippe Gaudin, Vers une laïcité d’intelligence? L’enseignement du fait religieux comme politique publique de l’éducation depuis les années 1980, Aix-en-Provence, PUAM, 2014 ; Isabelle Saint-Martin et Philippe Gaudin (dir.), Double défi pour l’école laïque. Enseigner la morale et les faits religieux, Paris, Riveneuve, 2014.
-
[7]
« Pourquoi l’enseignement du fait religieux reste un sujet hypersensible ? », Le Monde, 25 octobre 2020. https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2020/10/25/pourquoi-l-enseignement-du-fait-religieux-reste-un-sujet-hypersensible_6057288_6038514.html [最終閲覧日:2022年7月29日]
-
[8]
Mireille Estivalèzes, Les religions dans l’enseignement laïque, Paris, PUF, 2005, p. 257.
-
[9]
Delphine Horvilleur, Rachid Benzine, Des mille et une façons d’être juif ou musulman. Dialogue., Paris, Edition du Seuil, 2017, p. 140-141.
-
[10]
Mireille Estivalèzes, « L’enseignement du fait religieux à l’Ecole, un faux problème ? », Spirale. Revue de recherches en éducation, n° 39, Laïcité, croyances et education, sous la direction de Jean-Paul Martin, 2007, p. 93-105.
-
[11]
Antoine Lilti, L’héritage des Lumières, Paris, EHESS / Gallimard / Seuil, 2019, p. 383.
-
[12]
Cf. 伊達聖伸『ライシテ、道徳、宗教学 もうひとつの19世紀フランス宗教史』勁草書房、2010年。
-
[13]
たとえば哲学者のセバスティアン・ユルバンスキは、公教育のカリキュラムの複数の科目を通して、生徒に半強制的に宗教事象を学ばせることに反対の意を示す有識者の一人である。
この記事を引用する
白尾 安紗美「一歩引いて見る宗教事象教育——感情的なものとの関係を問う」 『Résonances』第13号、2022年、29-33ページ、URL : https://resonances.jp/13/prendre-du-recul-par-rapport-a-lenseignement-du-fait-religieux/。(2026年02月28日閲覧)