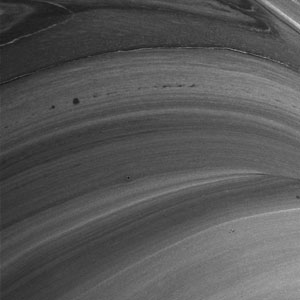ヴォドゥからヴードゥーへ
はじめに
2010年のハイチ地震の直後、ニューヨークタイムズは「根底にある悲劇」と題する論説記事で、ハイチの貧困の理由のひとつに「ヴードゥー教」を挙げた[1]。また、ウォールストリートジャーナルは、「ハイチとヴードゥーの呪い-ハイチの絶えざる悲惨の文化的ルーツ-」と題し、過去、ハイチが総額数十億ドルの支援を受けながら後発開発途上国に留まる理由に「ヴードゥー」の影響を挙げ、倫理性を欠いた高度のパラノイア、または、進歩を拒む力とした[2]。
現地社会で「ヴードゥー」は、災因・病因論的な体系として大きな影響力を保ち、生物医療へのアクセスを妨げることも、逆にそれへの繋ぎ役を担うこともある。ハイチ政府が震災後に策定した医療・保健計画では、生物医療の環境整備を第一に、伝統的医療の発展も目標の一つとなっている[3]。
「ヴードゥー」という呼称について補足すると、ハイチでは一般に「ヴォドゥ」と呼ばれ、「ヴードゥー」は英語圏を経由したもの、さらに言えば、20世紀初頭のアメリカ占領期以降の大衆文化によって広がったものだ[4]。本稿では、ハイチでの一般的な呼称の発音に近い「ヴォドゥ」を表記の基本とし、「ヴードゥー」はアメリカ占領軍が見た「ヴォドゥ」を意図する際に用いたい。
アフリカ起源の諸信仰とキリスト教が混淆して生まれたとされるヴォドゥは、既に、19世紀の欧米社会で、フランスから独立したハイチに内在し、発展を阻んでいる野蛮な本質を表すものとして捉えられていた。
文化人類学者のタラル・アサドによれば、19世紀ヴィクトリア朝の人類学者たちは、自然の因果関係の誤った理解の体系として呪術を捉え、呪術が支配的な社会では責任の主体としての自由なエージェンシーは成立せず、また、立憲主義、法の支配、自決を意味する「責任統治」の仕組みも根付かないと考えていた[5]。19世紀のハイチにも同様のことが言える。欧米社会は、独立後のハイチを、呪術の影響下にある元奴隷の黒人たちが殺戮を繰り返すばかりで、責任ある主体としての自己統治が不可能な国として捉えてきた。この時期のハイチで、憲法が「宗教」の自由を認めながら、刑法はヴォドゥを「呪術」として禁じたことに、欧米社会の眼差しを内面化したハイチ指導層の胸の内が映し出されていると言えよう。
そして、19世紀までのヴォドゥ表象は、20世紀初頭のアメリカ占領期に受け継がれ、ヴォドゥは、占領軍にとって、武力介入を正当化する道具として、つまり、ヴードゥーを演じ続けることになる。
本稿は、17世紀から19世紀に至るハイチのヴォドゥ表象の形成史を考察しつつ、そのヴォドゥ表象がアメリカ占領初期にいかに受け継がれ、利用されたかを、関連する文献史料をもとに明らかにすることを目的とする。また、本稿は、アメリカ占領期半ば以降に活発化する公衆衛生政策において、生-権力的な機制が発動する契機としてヴォドゥがいかに機能したかを検証する博士論文の一部を成すものである。
まず、本稿第1節では、1685年の黒人法発布以降のフランス領サン=ドマング期の呪術的行為に関連する法規などを手掛かりに、仏領サン=ドマング社会で呪術や毒薬が次第に現地の白人社会を中心に問題化していった過程を考察する。
第2節では、1804年のフランスからの独立後、宗教の自由が憲法で認められる一方、ヴォドゥは刑法により呪術の一種として禁じられたが、19世紀を通じて、ヴォドゥがハイチの諸呪術一般の総称、さらに、文明化に抗うハイチの後進性の証とされるに至った過程を考察する。
第3節では、19世紀までのヴォドゥ表象が引き継がれた20世紀初頭のアメリカ合衆国占領期初期に焦点を当て、ハイチが奴隷制の記憶とともに長年怯えた他国による占領、介入を正当化したナラティブにおいてヴォドゥが果たした役割を考察する。
1. フランス領サン=ドマングの不安
フランスがイスパニョーラ島への奴隷貿易を1670年に開始して間もない1685年に黒人法は制定され、1697年のライスワイク条約を経て島の西側3分の1がフランス領サン=ドマングとなる。17世紀にサン=ドマングに導入された奴隷の数は約16万人とされるが、翌18世紀にかけて奴隷の数は9倍近くに膨れ上がる[6]。
まず、黒人奴隷の爆発的な増加前に発布された黒人法のうち宗教に関連する条文を見てみると、キリスト教徒に敵対する存在として島内からのユダヤ人の退去を求めた第1条と、奴隷の洗礼を義務付けた第2条に続き、第3条では公におけるカトリック以外の宗教の礼拝行為を禁じた。そして、第5条では「改革宗教(la religion prétendue réformée)」、つまり、プロテスタントの活動を制限している[7]。これらの条文は、プロテスタントやユダヤ教を念頭に置いたもので、アフリカ起源の諸呪術を禁じているわけではなかった。また、第16条でも、奴隷たちが婚礼の儀礼等と称して昼夜問わず集まることを禁じているが[8]、アフリカ起源の信仰を明示的に名指していない。より具体的な内容の規制法が発布された翌世紀と比較すると、当局は、奴隷たちが集まることの危険性を意識しつつも、この時点でアフリカ起源の呪術的諸実践と騒擾の危険を明確に結びつけてはいなかった。
18世紀を通じてサン=ドマングに売られた奴隷たちは、主にアフリカのセネガンビア、風上海岸、黄金海岸、ベナン湾、ビアフラ湾、西中央部の諸港から来た。初期はベナン湾界隈が多かったが、フランス革命前夜には西中央アフリカの諸港に中心が移っていた。独立革命前夜のサン=ドマングの黒人奴隷社会は一枚岩ではなかったとされる[9]。
18世紀に発布された関連法規を見てみると、まず、1704年に黒人奴隷による日曜の夜と礼拝の祝日における集会と踊りを禁ずるオルドナンスが発布される。同オルドナンスは曖昧な黒人法を補うかのように、礼拝の間に打楽器を叩くことや、「騒々しい集会(des Assemblées tumultueuses)」を開催することを禁ずる[10]。ある司祭による1727年の書簡には、現地社会で「黒人呪術師(des Nègres sorciers)」の嫌疑がかけられた者への言及があり、呪術が現実的な脅威を持ち得る旨が綴られている[11]。
次に、1758年のオルドナンスでは、奴隷たちが仲間の死を弔う際に行う「迷信的な集会や儀礼(les assemblées et cérémonies superstitieuses)」や、毒薬を意味する「マカンダル(Makandals)」の売買等が禁じられる[12]。ここでは、先の1704年のオルドナンスにおける「騒々しい集会」から「迷信的な集会や儀礼」へと、呪術的な実践を思わせる文言に変化し、また、毒薬を禁じる条項がそれに続いている。マカンダルとは、プランターの殺害を目的に毒薬の知識を奴隷社会に広めた逃亡奴隷の名に因んだものだ。マカンダルは処刑されるが、奴隷社会には毒薬の調合にも転用可能な薬草の知識を持つ者が他に多数存在したとされる。サン=ドマングでは、本国の任命を受けた内科医が現地の制度的医療のヒエラルキーのトップに立ち、島内で活動する医師や薬剤師らに対する営業ライセンスの発行や、感染症対策など、現地の医療・保健行政全般を監督していた。しかし、その監督は十分に行き届いていたとは言えず、例えば、医薬品や劇薬の紛失といった問題が度々生じていた。時代は下るが、1780年に、ネズミ駆除目的で用いられていた劇薬のヒ素について、厳密な管理や売買のルールを定めた法令が発布されており、現地社会がこの問題に神経を尖らせていた様子がうかがえる[13]。
そして1765年になると、「カランダ(Calendas)」という名称の踊りが、具体的な内容は示されないまま、オルドナンスで禁じられる[14]。カランダとはどのようなものだったのか。マルティニーク出身の法曹で、1780年にサン=ドマングの高等評議会のメンバーとなり、ルイ16世の命を受けてフランス領アンティル諸島の法令集の編纂を行ったメデリック・ルイ・エリー・モロー・ドゥ・サン=メリー(以下、サン=メリー)が[15]、1797年にアメリカで出版したサン=ドマングの『地誌』にその記録がある[16]。それによると、カランダは、時に弦楽器を加えるなどの大小様々な打楽器隊の演奏に合わせて女たちが拍子を取り、リード・シンガーの歌にコーラスが応え、サークルの中央で男女がペアになって踊るものとされる。この形式は、現代の西及び中央アフリカの余興のダンスの形式の一部との類似が近年の研究で指摘されている[17]。また、『地誌』では他に「シカ(Chica)」や「コンゴ(Congo)」と呼ばれる踊りが紹介されている。
こうして、奴隷の踊りや儀礼らしきものを禁じる関連法規において、当初、禁止対象の輪郭は曖昧だったが18世紀を通じて少しずつ具体的になり、明確な定義は示されないものの、ひとまず、カランダという名の踊りに辿り着く。しかし、ヴォドゥの名はまだない。その名が初めて現れるのは、上述のサン=メリーによる『地誌』においてとなる[18]。
同書でサン=メリーは、島の西側を中心にヴォドゥという踊りが活発に行なわれていたことに触れ、それが迷信的な一団によって執り行われていた点に注意を促している。そして、当該の一団を構成するのは西アフリカ系の人々で、ヴォドゥとは、この世の全事象に影響を及ぼす超自然的な存在の信仰であり、その化身である蛇が、司祭にその意思を伝える。司祭は何かが憑依したような痙攣的な状態で神託を授け、参加者も感覚を失うまで踊り、催眠状態へと至る。売春行為が伴うこともあり、当局の警戒を解くために単なる踊りの振りをしているが、実はとても危険なもの、と見なす。フランスとハイチにおける革命を生き延びたサン=メリーは、『地誌』の発表当時、アメリカのフィラデルフィアを拠点に書店を経営しており、ヴォドゥの記述を含むサン=メリーの著書はフランスだけでなくアメリカの知識層に多く読者を持っていたとされる[19]。
また、ヴォドゥとカランダの関係について、文化人類学者のメトロ-は、20世紀半ばに行ったフィールド調査をもとに、サン=メリーの時代にカランダとして認知されていたものがヴォドゥの一種だった可能性を指摘しているが、歴史家のラムジーは、ヴォドゥの定義が歴史的に変化した可能性に触れながら、少なくとも18世紀末のサン=ドマング社会では、カランダとヴォドゥは別個のものとして生きられ、実践されていたとしている[20]。
2. ハイチのヴォドゥ、この呪われたもの
1804年の独立後に南北への分断を経たハイチは1818年に統一を果たす。統一時のボワイエ大統領は法制の整備に取り組み、1825年から1835年にかけ農民法などを順次発布した。フランスの法規を参考に法制の整備は進められたが、1835年発布の刑法には一部特異な条文が含まれていた[21]。それが、第6セクションの「呪術(sortilèges)」に関するものである。該当箇所のうち特徴的な第405条を、一部省略し以下に紹介する。
第405条:ウアンガ、カプルラタ、ヴォドゥ、ドンペドル、マカンダル及びその他の呪術を実施するものは、違警罪裁判所によって、3か月から6か月の禁固刑、並びに、60から100グルドの罰金刑に処せられる。[…]物神崇拝と迷信を人々のうちに育む性質を持つ、あらゆるダンスやその他の任意の行為は呪術と見なされ、同様の処罰を受ける。
ここでヴォドゥは他に列挙された幾つかの呪術的行為の一つとされている。一連の行為の具体的な内容は示されていない。ヴォドゥは同時代の出版物であるサン=メリーの記述が参考となるが、それ以外の行為が19世紀に何を意味したのか。まず、「ウアンガ(ouanga)」とは、治癒可能な病などの軽微な呪いを指す[22]。次に、「カプルラタ(caprelatas)」も同様に軽い呪いを意味するが、呪術師を騙る詐欺師を指す場合もある[23]。また、「ドンペドル(donpèdre)」は、ハイチに暮らしたスペイン人の血を継ぐ人物が名称の由来とされ、弾薬を混ぜたラム酒を飲みながら踊る催しを意味する[24]。「マカンダル(makandals)」は先述の通り毒殺を意味する。
ハイチ独立翌年のジャン=ジャック・デサリーヌ統治下(1804-1806)の1805年憲法は「支配的な宗教(religion dominante)」を認めず、「諸崇拝の自由(la liberté des cultes)」を認めていたが[25]、ボワイエ政権下(1818-1843)の憲法では、「宗教」としてローマ・カトリックを国教として保護する旨を定めた条文の直後に、「他の全ての宗教的崇拝(tout autre culte religieux)」については、法に則る限り認める旨を定めている[26]。つまり、ローマ・カトリック以外の「宗教的崇拝」は条件付きでその活動が認められているが、1835年発布の刑法の呪術に関する条項によってヴォドゥは「宗教的崇拝」にさえ含まれない「呪術」として違法化されたことになる。宗教に関する憲法の条文は、ハイチ史を通じて、大別するとデサリーヌ型とボワイエ型の間を揺れ動き続けるが、ヴォドゥを禁じた刑法はボワイエ政権以降も残存し、ヴォドゥが合法化されるのは1987年となる。
逃亡奴隷たちがサン=ドマング北部の森で催した儀礼が独立戦争の起点となったことが、その後、ハイチのナショナル・ヒストリーにおいて重視され、他でもないヴォドゥの儀礼として繰り返し言及されたことからすると、いささか奇妙に思われる。なぜヴォドゥを禁ずる必要があったのか。その理由について、以下ではふたつの可能性を示し、本稿では、ヴォドゥの表象の形成に直接的に関わったと考えられる第2の理由に注目して検討したい。
まず第1の理由として、人種主義的な傾向を持ったボワイエ大統領による権威主義的な政権が[27]、元黒人奴隷からなる農民たちと密接な関係にある呪術としてのヴォドゥを違法化することで、権力基盤を脅かしかねない勢力を潜在的に周縁化し、反乱を未然に防ぐことを意図した可能性である[28]。
ボワイエ政権以前、南北に分断していたハイチの北部は元黒人奴隷のアンリ・クリストフが、南部は黒人の母とフランス人宝石商の父を持つムラートのアレクサンドル・ペティオンがそれぞれ統治していた。サン=ドマング時代、平野部の多い北部では大量の奴隷を必要とする砂糖プランテーションが発展していたが、平野部の少ない南部ではコーヒーなどの小規模なプランテーションが形成され、ムラートの経営も多く見られた。独立後も、北部では黒人が、南部ではムラートの力が有力になったとされる[29]。
自身もムラートのボワイエ大統領は、フランスによる独立の承認と引き換えに1825年に約束した独立戦争時のフランス側の被害に対する賠償金の支払いの必要から、税収増を期待し、指導層のムラートたちの支援を得ながら、結局は失敗に終わるものの、大規模なプランテーション制の復活を目論んでいた[30]。19世紀後半にハイチの歴史家ルイ=ジョセフ・ジャンヴィエが「鞭を用いない奴隷制」と揶揄した1826年制定の農民法は、ボワイエ大統領のこうした企図を反映したもので、禁固刑などの罰則付きで農民の移動の自由を制限するなどしたため、農民たちからは不評を買っていた[31]。
1843年のボワイエ大統領失脚に繋がる反乱は、南部出身のムラート議員であったエラール・デュメスルが主導した。デュメスルは、ボワイエ大統領と異なり、ムラートだけでなく元黒人奴隷たちが独立運動以来果たしてきた功績を評価していた[32]。デュメスルが著したハイチ北部の旅行記には、ハイチ北部の森で行われ独立運動の起点となったヴォドゥの儀礼に関する記述があるが、これは、当該儀礼の記述のうち最も古いもののひとつとして後世に影響を与えた[33]。
しかし、ボワイエ政権崩壊後の憲法では、公序に反しない限り「あらゆる崇拝(tous les cultes)」の自由が認められたにも拘わらず、ヴォドゥを禁じる刑法は残った。
次に、第2の理由として、文明国としての体面を保つ一種のパフォーマンスとして当該条文を策定した可能性である。傍証として、ハイチ政府は在ハイチの各国領事や国外に一連の法規の配布に腐心していたことがあげられる[34]。実は、刑法発布の1835年に至るまで、サン=メリーの他に、欧米では既にいくつかの文献でヴォドゥに関する否定的な記述が登場していた。例えば、独立戦争期のサン=ドマングでフランス人でありながら医師として独立軍に従軍した博物学者ミシェル・エティエンヌ・デクルリッツは、1809年に発表した自著で、ヴォドゥを、蛇を神格化した呪術と見なし、実践者らを「偶像崇拝のセクト(une secte idolâtre)」としている[35]。また独立戦争の際にフランス軍の竜騎兵として戦ったシャルル・マリー・フランソワ・マランファンは1814年に発表した自著でヴォドゥの信徒を「狂ったものたち、ばか、愚か者(des fanatiques, des sots, ou des imbécilles)」と形容していた[36]。
19世紀を通じて、ハイチでは、独立国としての新たな枠組みを模索する試みが続けられたが、国内情勢は不安定なまま、経済も追い詰められていく[37]。こうした国内事情は海外にも伝わり、ヴォドゥを巻き込みながら、否定的なハイチ像を生み出してゆく。
1853年になると、在ハイチ・フランス総領事を務めたギュスターヴ・ダローは、サン=メリーを参考に破廉恥なヴォドゥの解説をしながら、当時、ハイチ皇帝を名乗ったフォスタン・スールークがヴォドゥ信者であることに触れる[38]。同書は1861年に英語版も出版された。また同年、アルチュール・ド・ゴビノーの『諸人種の不平等に関する試論』が出版される。同書にヴォドゥへの直接の言及はないが、ゴビノーはハイチに紙幅を割き、まず隣国の「ドミニカ人(les Dominicains)」について、彼らには白人の血が混ざっているため、「有用な市民(des citoyens utiles)」と成り得るが、文明化に適さない黒人が統治を担っているハイチでは、民主主義という「博愛的(philanthropiques)」な仕組みにも拘わらず殺戮が繰り返されているため、外国の庇護を必要としているとした[39]。
そして1884年に元在ハイチ・イギリス総領事のスペンサー・バッキンガム・セイント・ジョン卿による『ハイチ、または黒人共和国』(Hayti:or, the Black Republic)が出版され、サン=メリー以来のヴォドゥ像を更新し、凄惨なイメージを決定付ける。同書では、「角なしの山羊(goat without horns)」という隠語で呼ばれる人身御供の儀礼で人肉食の嫌疑をかけられた一団が逮捕され、裁判後、8名が公開処刑となった1864年のビゾトン事件が紹介された[40]。
セイント・ジョン卿は同書でハイチのキリスト教事情などに触れた「宗教、教育、司法」と題する章とは別に、「ヴォドゥ崇拝とカニバリズム」と題する章を設け、大半のハイチ国民は、残忍な信仰のヴォドゥに夢中になっているとする。さらに、ハイチは形式的には共和主義だが実際は軍事独裁と評し、ヴォドゥを信じる国民は「無知なアフリカ人(ignorant Africans)」から成るため、文明など発展しないこと、法の支配は根付かない旨などを記した。同書は、科学誌ネイチャーが1884年12月号の書評欄でも紹介し、セイント・ジョン卿によるカニバリズムの記述にも触れながら、当時のハイチ社会についての「誠実で偏りのない説明」として評価している[41]。
19世紀半ばまでにハイチ国外で出版された諸文献は、ヴォドゥを特別視しながらも呪術の特殊な一形式と見なしていたが、セイント・ジョン卿に至っては、ヴォドゥはもはや単なる呪術の一形式ではなく、ハイチ人の大半が信仰する根源的で包摂的な何かとなっている。
他方で国内にはヴォドゥについて様々な議論があった。例えば、ハイチの外交官であり著述家だったフィリップ・ハンニバル・プリスは、ヴォドゥを、不快に見えるかもしれないが、アフリカ起源の無垢な踊りであり、その悪評はハイチ国民を利用する一部の「ウーンガン(houngan)」の仕業によるものとした。ウーンガンとは一般にヴォドゥの司祭を意味するが、ハンニバル・プリスは医師や科学者を意味するアフリカ起源の言葉として紹介している[42]。他に、ヴォドゥを、黒魔術的な意味合いを持つ呪術から峻別しようとする潮流もあった[43]。
3. 占領を正当化したヴードゥー
アメリカによるハイチ占領は、カリブ海におけるアメリカの覇権とパナマ運河の安全保障の脅威となり得るドイツの影響力排除を目的に、第1次大戦中の1915年に始まった[44]。海兵隊介入後、両国間で条約が取り交わされ、ハイチ財政の立て直しを主軸に各分野の「支援」がアメリカ主導で実施された。
財務等の諸分野専門の文官を含む占領軍の大半は、海兵隊を中心とした組織だった。条約に従い1916年にハイチ憲兵隊が結成され、既存のハイチ軍及び警察が解体された。115名の海兵隊員が1300名のハイチ人憲兵隊の指揮に当たった。1917年には、治安維持に加えて地方行政を監督するローカルの諮問機関の役割も担うことになった[45]。
ハイチ各地の現場に展開した海兵隊は占領の目的をどう理解していたか。例えばイーライ・K・コール大将は、1921年のアメリカ上院公聴会で、ハイチ国内の混乱を取り除き独立国家として存続する条件を整えること、彼らがしばしば用いた表現に倣うなら、ハイチを「掃除すること(clean that place up)」が占領の目的であり、道徳的義務と答えている[46]。
この公聴会は、ハイチ占領が大統領選挙を控えたアメリカ国内で問題化して開かれたものだが、開催までの経緯はおよそ以下のようなものだ。
1916年の憲兵隊結成後、海兵隊員らには刑法からの一部抜粋が付された1864年版のハイチ農民法の英語版が配布された。補填された刑法は前節で紹介した呪術に関する条文だった。1918年に憲法が一部修正されたが、占領期においても引き続き憲法で宗教の自由を認めつつ、刑法でヴォドゥを呪術として禁じるという法制上の建て付けは踏襲されていた。
憲兵隊は刑法の呪術関連の条文を根拠に取り締まりを強化するが、強化には治安維持以外の目的があった。これが農民の反乱を引き起こすことになる。
憲兵隊発足当初、占領要員をハイチ各地に効率的に展開する道路整備の必要が説かれ、1864年版の農民法を根拠とした強制労働のスキームが利用された。この強制労働は、フランス語の「コルヴェ(corvée)」がハイチ・クレオール語化し「コヴェ(kòve)」と呼ばれていたもので、その起源はボワイエ政権下の1826年に税収増を期待してプランテーションの復活を目論み作られた農民法である[47]。19世紀を通じて断続的に適用されていたが、アメリカ占領当初には廃れていたスキームだった[48]。
占領軍は、道路のメンテナンスのみをコヴェの作業として想定していた過去のハイチ政府の解釈を変更し、新設工事も可能とし、作業期間を延長した。銃器を携行した見張りの下、作業員はロープで繋がれて移動し、逃亡を試みた者はしばしば射殺されるなど、凄惨な環境だった[49]。強制労働作業員の徴用は憲兵隊が各地で行ったが、呪術を禁じた条文などが農民の恣意的な逮捕を正当化し、作業員の徴用を容易にした。こうした高圧的な方法はやがて「カコ(cacos)」の反乱と呼ばれる農民中心の反対運動を引き起こす[50]。
諸説あるが、カコの名は島に生息する「タコ・イスパニョーラ(Tacco Hispaniola)」と呼ばれる、大蜥蜴を食べる小鳥が由来とされる。ハイチ革命の折にはゲリラ戦を繰り広げた元奴隷たちを指した[51]。占領期の海兵隊の各種記録では「盗賊(bandits)」とほぼ同義に用いられていたカコについて、例えば1926年の海軍医療年鑑所収の論考では次のように記されている[52]。
野蛮人たちは残虐さの虜だ。敵は死体を獲得して士気を高めているようだ。このことは、怪我人の扱いと同様、死体を保護する特別な予防措置が必要なことを意味する。ハイチのカコたちの間では、アメリカ人兵士の心臓を食べると、食べた者は弾で打たれても死なないという迷信があるのだ。少なくとも、心臓を食べられた一例がある。
この記述に典型的に見られるカコの猟奇的なイメージは、確たる証拠のないまま流布していたものだが、占領初期から続いたカコの反乱を経て、カコを貶めることに躍起になっていた占領軍界隈で共有されていた。他方で、一部のカコたちが残した数少ない私信などからは、猟奇的というよりは、占領軍の暴力に対する正当な怒りをあらわに1804年の独立と自らの活動を重ねて再び主権回復を願う一介のナショナリストとしての姿が映し出されている[53]。
こうした状況下の1919年、留置場でハイチ人2名が裁判を経ずに海兵隊員によって射殺される事件が発生する。本件は隊内で明らかになり、事態を重く受け止めた海兵隊上層部は、当該事件と同様に殺人の疑いがある他の事例について調査を行った。その結果、類似の事例がいくつか明らかになるが、熱帯地域でしばしば起こり得る、取るに足らない出来事と見なされ、関係者の処分が決まる。そして、隊の行動規範の見直しやコヴェの中止等が決定され、事態は収束したかに見えた矢先の1920年に、当件に関する極秘の公電がメディアに漏れ、大統領選挙に向けたアメリカの政局で問題化し、占領の是非を問う公聴会の開催(1921-1922年)が決まった[54]。
実は、事件が明らかになるまで、民主党のウッドロー・ウィルソン政権下(1913-1921年)のアメリカ国民はハイチ占領に大きな関心を寄せていなかった。ウィルソン政権は、第一次大戦後の1919年にハイチからの撤退を試みるも、続くカコの反乱を受けて、反対に、占領軍の増強を余儀なくされていたが、ネイション誌など一部の例外を除き、事件まで、アメリカのメディアの多くは占領に好意的な論調だった。公聴会の開催に先立ち、調査委員会による現地調査も1920年に行われたが、公聴会の結果、道路建設などの様々な「成果」をハイチにもたらしたものとして占領は肯定的に評価され、指揮系統の強化を目的とした占領軍の組織再編を経て、占領継続が決まる。公聴会開催の数か月前に共和党のウォーレン・G・ハーディング政権が発足していたが、歴史家のシュミットが指摘するように、ハーディング政権は、ウィルソン政権下のハイチ占領における混乱の「罪滅ぼし」の機会として公聴会を利用し、占領軍を一部刷新し、占領を引き継いだ格好となった。公聴会の議長で共和党のメドミル・マコーミック上院議員は、公聴会開催前の1920年の時点で組織再編後の占領継続案を表明していたとされる。つまり、占領継続は既定路線であり、ハイチ占領は政争の具にすぎなかったと言えよう[55]。
「罪滅ぼし」としての公聴会では確かに占領軍の問題行為にも言及されたが、占領による文明化が必要な国としてのハイチ像が繰り返し強調され、ハイチを代理し表象するものとしてヴードゥーに注目が集まった。例えば、
ハウ(国際法弁護士):現地の人々の様子はどのようなものか。あなたはハイチ人をどのように思い描くか。
[…]
バトラー(海兵隊):ハイチ人は二つの階級に分けられる。一方は靴を履く階級、他方は履かない階級だ。靴を履く階級はおよそ1%しかいない。また、せいぜい人口の1%の4分の1しか読み書きができない。靴を履く人も多くは読み書きができないのだ。 […]99%のハイチ人は、私が知る限り最も親切で、気前よく、温かく人をもてなし、喜びを愛する人々だ。彼らは誰も傷つけない。彼らは、自然な状態にいるうちは、とても親切だ。しかし、[…]1%の人々が、お酒とヴードゥーの道具で彼らを焚き付けるとき、この親切な人々は最も恐ろしい残忍な行為もできるようになるし、人肉食も行う。ある海兵隊員は肝臓を食べられた[56]。
また、
ハウ:ヴードゥーの実践は、占領期に現地で起きた数々の出来事に何か影響を与えたか。
[…]
ウォラー(海兵隊):ヴードゥーは、農民や下層の人々に見事な効果をもたらしていた。エリート層にもいくらか影響力を持っていた。ヴードゥーはハイチの法に反していたが、ハイチ人たちは法を執行していなかった。私たちが法を執行し、集会を解散させ、全てのドラムを没収した。ヴードゥー・ドラムが聞こえるところではどこでも、私たちは即座に音を追跡し、できる限り解散させた。[…]ヴードゥーでは人身御供があらゆる悪を癒すと信じられているが、ハイチでは暫くの間、人身御供に頼るようなことは起きていないと思う。ヤギや羊を犠牲にしているが、とても残忍な方法で行っている[57]。
大半のハイチ国民は寛大で従順なまま人を傷つけることはないが、ほんの一握りの人々がお酒とヴードゥーの力で彼らを人肉食さえ厭わない残忍な存在に変貌させるという旨の語りは、占領軍内で度々繰り返されてきた。
また、公聴会の記録に付されたもので、旅団長が在ハイチ・アメリカ軍代表に宛てたハイチ情勢に係る1917年の公電では、ハイチ人は、一見どんなに洗練されていても一皮剥けば残忍であり、ヨーロッパで教育を受けても、アフリカ由来の残忍な精神状態にすぐに戻ってしまうとされ、また、ハイチ人の9割以上が信じるヴードゥーが真の危険だとする[58]。ここでヴードゥーは、単に、ハイチの呪術の特殊な一形式でも、呪術一般の総称でもなく、セイント・ジョン卿が主張したように、ハイチ社会の後進性と不可分の文化と見なされている。
公聴会では、人肉食の信憑性に疑義を挟み、比較的冷静な第三者として証言をする大学研究者もあったが、当の研究者においても、アフリカの様々な習慣の「ブレンド(a blend)」であるヴードゥーの儀礼にはしばしば性的乱交が伴うと考えていた。さらに、ハイチにはふたつのハイチがあり、一方はヨーロッパ的で教養があり、フランス語を用い、洗練され、キリスト教を信ずる人々からなるハイチ、他方はアフリカ的で教養がなく、クレオール語を用い、ヴードゥーを信じる洗練されない人々からなるハイチという、先のバトラーの証言と共通するハイチ像を提示している[59]。
他に、1920年の旅団長がワシントンに宛てた海兵隊活動レポートなど、占領を正当化する公聴会の趨勢を後押しするような記録の数々が資料として次々に提出された。曰く、「ヴードゥーイズムの忌まわしい行い(the abhorrent practice of voodooism)」に対して海兵隊が示した断固たる態度が、人身御供を打ち砕き、野蛮な状態に生きるハイチ人を文明化するとし、充分な教育を受けたハイチ人ならば、占領軍への敬意と称賛を抱くだろうとする[60]。
ここでは、仮に海兵隊による暴力的な逸脱行為があったとしても、残忍なヴードゥーを前に止むを得ず採った行為となり、文明国としての規範を逸脱するヴードゥーの野蛮な行為に対する正当なカウンターと見なされる。ヴォドゥは単に呪術の総称として遅れたハイチの残忍さを表すだけに留まらない、それに見合った暴力的介入を認める口実としてのヴードゥーを分身に持つことになったのである。
おわりに
本稿は、17世紀から19世紀にいたるヴォドゥ表象の形成史をふまえながら、20世紀初頭のアメリカ占領期において、コロニアルな欲望の正当化のために、ヴォドゥがヴードゥーとして担わされることになった役割について考察を試みた。考察の対象となった期間は、17世紀から占領期間中に実施された公聴会(1921-1922年)までとなるが、占領自体は、先述の通り、公聴会を経て再編された新体制で1934年まで続く。新体制の下、公衆衛生政策が活発化し、生-権力的な機制がヴードゥーといかなる関係を結ぶことになったかについては、別途論考を試みたい。
Notes
-
[1]
Brooks, David, « The Underlying Tragedy », New York Times, 14 Janvier 2010.
-
[2]
Harrison, Lawrence, « Haiti and the Voodoo Curse–The cultural roots of the country’s endless misery– », Wall Street Journal, 5 Février 2010.
-
[3]
Ministère de la Santé Publique et de la Population de la République d’Haïti, Politique Nationale de Santé, 2012, p. 17-21. ; 今井達也「対ハイチ援助-復興から、社会基盤の強化へ」、『日本の国際協力中南米編』所収、ミネルヴァ書房、2021年、115-120ページ。
-
[4]
ヴォドゥはvodou、vaudou(x)、ヴードゥーはvoodooと一般的に綴られる。
-
[5]
アサド、タラル『世俗の形成 キリスト教、イスラム、近代』みすず書房、2006年、116-118ページ。
-
[6]
浜忠雄「ハイチ革命研究序説(I):黒人奴隷制、法と現実」、『北海道教育大学紀要第1部B社会科学編35(1)』所収、北海道教育大学、1984年、1-16ページ。
-
[7]
Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le Calvaire de Canaan, Paris, Press Universitaire de France, 2018, p. 86-95.
-
[8]
ibid., p. 116-117.
-
[9]
David Patrick Geggus, Haitian Revolutionary Studies, Bloomington, Indiana University Press, 2002, p. 76. ; 鈴木英明『解放しない人々、解放されない人々』東京大学出版会、2020年、106-107ページ。
-
[10]
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, « Ordonnance du Gouverneur, qui défend les assemblées et danses des Nègres Esclaves », Loix et Constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome II, Paris, p. 12-13.
-
[11]
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, « Lettre du Ministre à M. M. de la Rochalard et Duclos, sur plusieurs objets d’humanité et de religion », Loix et Constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome III, p. 221-222.
-
[12]
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, « Arrêt en Réglement du Conseil du Cap, touchant la police des Esclaves, 7 Avril 1758 », Loix et Constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome IV, p. 225-226.
-
[13]
Weaver, Karol K., Medical Revolutionaries – The Enslaved Healers of Eighteenth-Century Saint Domingue –, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 2006, p. 26-40.
-
[14]
Moreau de Saint-Méry, Loix et Constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome IV, op. cit., « Ordonnance du Gouverneur Général, portant création d’un Corps de Troupes Légeres, désigné sous le nom de Premiere Légion de Saint-Domingue, Janvier, 1765 », p. 825-831.
-
[15]
Rosengarten, G. Joseph, « Moreau de Saint Mery and His French Friends in the American Philosophical Society », Proceedings of the American Philosophical Society, May-Aug., vol.50, no.199, 1911, p. 168-178.
-
[16]
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et histoire de la partie française de l’isle Saint-Domingue, tome I, 1797, p. 44-45.
-
[17]
Gerstin, Julian, « Tangled Roots : Kalenda and Other Neo-African Dances in the Circum-Caribbean », New West Indies Guide, vol. 78, No.1/2, 2004, p. 5-41.
-
[18]
Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et histoire de la partie française de l’isle Saint-Domingue, tome I, op. cit., p. 45-51.
-
[19]
Rosengarten, G. Joseph, art. cit.
-
[20]
Alfred Métraux, Le Vaudou Haïtien, Paris, Gallimard, 1958, p. 26. ; Kate Ramsey, The Spirits and the Law -Vodou and Power in Haiti, Chicago and London, The University of Chicago Press, 2011, p. 275.
-
[21]
Laénnec Hurbon, Le Barbare Imaginaire, Port-au-Prince, Éditions Henri Deschamps, 1987, p. 113-114.
-
[22]
Métraux, op. cit., p. 252-253.; Ramsey, op. cit.,p. 60.
-
[23]
Drouin de Bercy, De Saint-Domingue, de ses Guerres, de ses Révolutions, de ses Ressources, et des Moyens à Prendre pour y Rétablir la Paix et l’Industrie, Paris, 1814, p. 175. ; Métraux, op. cit., p. 326.
-
[24]
Moreau de Saint-Méry, Description, op. cit., p. 69.
-
[25]
« Constitution du 20 mai 1805 », Maury, Jean-Pierre (éd.), Digithèque de matériaux juridique et politiques (https://mjp.univ-perp.fr/constit/ht1805.htm).
-
[26]
« Constitution du 2 juin 1816 », Maury, Jean-Pierre (éd.), Digithèque de matériaux juridique et politiques (https://mjp.univ-perp.fr/constit/ht1816.htm).
-
[27]
Dubois, Laurent, Haiti – The Aftershocks of History – , New York, Metropolitan Books, 2012, p. 119.
-
[28]
Hurbon, op. cit., p. 115.
-
[29]
浜忠雄『カリブからの問い-ハイチ革命と近代世界-』岩波書店、2003年、179ページ。
-
[30]
Trouillot, Michel-Rolph, Haiti – State against Nation, The Origines and Legacy of Duvalierism – , New York, Monthly Review Press, 1990, p. 48.
-
[31]
Janvier, Louis-Joseph, Les Constitutions d’Haïti, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, Gallica, 1886, p. 149.
-
[32]
Dubois, op. cit., p.93.
-
[33]
Dumesle, Hérard, Voyage dans le Nord d’Hayti, ou Révélations des Lieux et de Monumens Historiques, Les Cayes, Imprimerie du Gouvernement, 1824, p. 85-90.
-
[34]
Thomas Madiou, Histoire d’Haïti, 1819-1826, tome VI, Port-au-Prince, Éditions Henri Deschamps, 1988, p. 533.
-
[35]
Michel Étienne Descourtilz, Voyages d’un Naturaliste, et ses Observations, tome III, Paris, Père Dufart Libraire-Éditeur, 1809, p. 180.
-
[36]
Colonel Malenfant, Des colonies, et particulièrement de celle de Saint-Domingue : Mémoire historique et politique, Paris, Chez Audibert, 1814, p. 216-217.
-
[37]
浜、『カリブからの問い』、前掲書、197-208ページ。
-
[38]
Gustave D’Alaux, L’Empereur Soulouque et son Empire, 2ème édition, Michel Lévy Frères, Libraires-Édituer, Paris, 1860, p. 64.
-
[39]
Le Comte de Gobineau, Essai sur l’Inégalité des Races Humaines, tome I, 2ème édition, Paris, Librairie de Firmin-Didot et cie., 1884, p. 48-50.
-
[40]
Sir Spenser Buckingham Saint John, Hayti; or, the Black Republic, London, Smith, Elder, & Co., 1884, p. 182-228
-
[41]
Keane, A.H., « The Haytian Negroes », Nature, Dec. 4, 1884, p. 99-100.
-
[42]
Hannibal Price, Philippe, De la Réhabilitation de la Race Noire et de la République d’Haïti, Port-au-Prince, Imprimerie J. Verrollot, 1900, p. 413-443.
-
[43]
Ramsey, op. cit., p. 100.
-
[44]
Hans Schmidt, The United States Occupation of Haiti 1915-1934, New Jersey, Rutgers University Press, 1995, p. 9.
-
[45]
Ramsey, op. cit., p. 121-122.
-
[46]
United States Senate 67th Congress First and Second Sessions, op. cit., p. 692.
-
[47]
Dubois, op. cit., p. 105.
-
[48]
Ramsey, op. cit., p. 125.
-
[49]
United States Senate 67th Congress First and Second Sessions, op. cit., p. 479-480.
-
[50]
Ramsey, op. cit., p. 124-130.
-
[51]
Alexis, Yveline, Haiti Fights Back: – The Life and Legacy of Charlemagne Péralte, New Jersey, Rutgers University Press, 2021, p. 82 ; Mary A. Renda, Taking Haiti –Military Occupation and the Culture of U.S. Imperialism, 1915-1940, Chapel Hill & London, The University of North Carolina Press, p. 140.
-
[52]
W.L. Mann, « Medical Tactics in Naval Warfare », United States Naval Medical Bulletin, no.4, 1926, p. 818.
-
[53]
Alexis, Yveline, op. cit., 2021, p. 131-134.
-
[54]
Ramsey, op. cit., p. 133-139.
-
[55]
Blassingame, John W., « The Press and American Intervention in Haiti and the Dominican Republic, 1904-1920 », Caribbean Studies, Jul., 1969, vol.9, no.2, p. 27-43 ; Ramsey, op. cit., p. 134-135 ; Schmidt, op. cit., p. 108-123.
-
[56]
United States Senate 67th Congress First and Second Sessions, op. cit., p. 517.
-
[57]
ibid., p. 630-631.
-
[58]
ibid., p. 1777-1785.
-
[59]
ibid., p. 1285-1288.
-
[60]
ibid., p. 1272.
この記事を引用する
今井 達也「ヴォドゥからヴードゥーへ」 『Résonances』第12号、2021年、1-13ページ、URL : https://resonances.jp/12/du-vodou-au-voodoo/。(2025年07月02日閲覧)