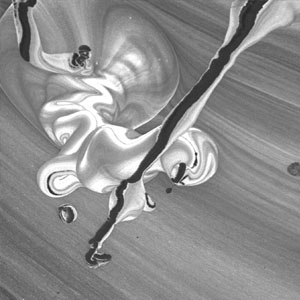新たな男性性を求めてオリヴィア・ガザレ『男らしさの神話』とイヴァン・ジャブロンカ『正しい男たち』書評
ボーヴォワールの『第二の性』から70年余、フランスで女性解放運動(MLF)始まってから50年が経ち、女性の解放が進む世界にあって、男性は自らの男性性や男らしさとどのように付き合えばいいのか。そもそも男性性、男らしさとは何なのか。フランスにおいてこうした問いは新しくはないものの、これまで多くは議論されてこなかった。だが近年それが変わりつつあるようだ[1]。アラン・コルバンら監修の『男らしさの歴史』[2]のような記念碑的な研究のほか、学校で処罰を受ける生徒の大半が男子であるがそれはなぜなのかを調査した教育学者シルヴィー・エラルの『男の子の作られ方──中学校における懲罰とジェンダー』(2011年)[3]や、いわゆる「ナンパセミナー」を調査した文化人類学者メラニー・グラリエの『アルファ男──男同士で尊敬し合うために女を誘惑する』(2017年)[4]といった研究書、あるいはラファエル・リオジエの短いエッセイ『男の核心に迫る』(2018年)[5]など、近年「男性性」に着目する著作は数多く出ている。
本稿では、なかでもオリヴィア・ガザレ『男らしさの神話──両性にとっての罠』(2017年)[6]およびイヴァン・ジャブロンカ『正しい男たち──家父長制から新しい男性性へ』(2019年)[7]について簡単な紹介を試みたい。
オリヴィア・ガザレはパリ政治学院などで教鞭をとってきた哲学者で、一般向けの民間の哲学学校「哲学の火曜日」の創設者でもある。ガザレの著作は題名が示す通り、男らしさの神話を問い直すものである。今、男らしさが危機に瀕しているという言説は世界各地で見られる──米トランプ大統領の当選はそれを象徴する出来事であった──が、それは現実の現象を言い表したものなのだろうか。あるいは欺瞞なのだろうか。この問いに対しガザレは、「本書の仮説は、男性に特有の問題系はたしかに存在し、痛ましい社会的な影響をもたらしているが、それは女性の責任ではない、というものである」[8]と述べ、「男性の不安は本物だが、それは最近のフェミニズム的革命(そのプロセスは達成されるには程遠い)の結果というより、男性が三千年近く前に、男性を女性の絶対的な主人とする男長制革命(révolution viriarcale)を達成することによって、自らに対して仕掛けた罠」[9]であるとする。ガザレは男であれば「父」でなくとも権力を握っているのだから、これまで使われてきた「家父長制(patriarcat)」ではなく(ラテン語で男を意味するvirをとって)「男長制(viriarcat)」という語を用いることを提唱しており[10]、ここでもそれを用いている。このおよそ三千年前の男長制革命によってそれまでの男女混合社会が崩れ去り、女性が権力を奪われ、「この新たな文明の黎明期に男性の優位に関する大きな物語が始まり、それはその後何世紀にもわたって、神話(イメージと象徴)、形而上学(概念)、宗教(神の法)、そして学問(生理学)によって強化されることとなった」[11]。その後、確かに女性解放運動によって世界は変わった(今も変わり続けている)し、フェミニズムがイデオロギー的に勝利を収めたが、それが男性の敗北や「終焉」を意味するというわけではない。「昔から、男性は自らの抑圧をもたらす主体である[…]。男らしさの構築を研究していくと、それはもともと危機にさらされている、強制的であるとともに矛盾した規範と命令に基づくモデルである、ということが明らかになってくる」[12]と述べるガザレは、今起きている男長制の衰退と男らしさの神話の解体は、この「罠」にとらえられ苦しんできた男性たちにとっても変化のチャンスである、と主張する。
こうした仮説のもと、ガザレは第一・二部では先史の母系社会がその後いかに男性化したかを説明していく。文化人類学の知見を参照しつつ、新石器時代に農耕・牧畜を始めた人類が動物を観察することにより生殖において男性にも役割があることを知ることとなったこと、そこからいかに「男長的なシステム」が構築され、主にアリストテレスによって理論化され、広まっていったかを明らかにしている。第三・四部では女らしさ、男らしさの神話についてそれぞれ取り上げている。その後、男性の抱くコンプレックスの根本にあるのは男性が自らの性器と結ぶ関係であるという仮説のもと、男性器をめぐる男らしさの規範の文化的変遷をたどる第五部を挟みつつ、最後の「男らしい世界の脱構築」と題された第六部では、男らしさはつねに亡霊にすぎず、どの時代にも男らしさの危機があるとしたうえで、父性、フェミニストの戦い、戦争、労働という、今特に重要とされる4つのテーマを取り上げている。全体として議論は非常に明快で、主に古代ギリシア・ローマ以降のヨーロッパの文献、事例が豊富に参照されている。
ガザレがフランソワーズ・エリチエなどの議論を引きつつ、新石器時代にそれまでの女神崇拝や母系社会に代わり男性支配の世界ができあがったと推測している点、あるいは第四・六部で男性に支配される男性像としてユダヤ人、同性愛者、黒人・植民地の現地人や労働者・失業者を取り上げている点は、実はジャブロンカの『正しい男たち』に通じる部分である。
ジャブロンカの著作は、男性がフェミニストであるためには、すなわち女性の権利の推進に味方する側であるためにはどうすればよいのか、という問いに答えようとするものである。このため、第一部では家父長制社会の成り立ちを説明し、第二部ではそれに対するフェミニストたちのこれまでの戦いを概説し──ここまでは特筆すべき点はない──、そのうえで第三部では男性性の亀裂、すなわち男性性規範がもたらす様々な問題を取り上げている。扱われているテーマは、理想とされる男性性とそれに従属する男性性、男の子の教育、男性の女性より短い平均寿命と高い自殺率、性暴力、職業上の差別、表象上の性差別、革命期以降の反フェミニズムの歴史や男性中心主義的な反動など幅広い。そして最後の第四部はジャブロンカの呼ぶところの「非支配の男性性」、「尊重する男性性」を作り上げるための指針を提示している。
この著作で示されるジャブロンカの主張自体は目新しいとは言い難いが、興味深いのはむしろ、彼が歴史家ではあるが特にジェンダーを専門としているわけではない大学教授であり、かつ白人で異性愛者である(と公言している)ということ、つまりこうしたテーマで本を書かなそうな人物であることにあるのかもしれない。というのもジャブロンカが指摘するように、「ヨーロッパでもアメリカでも、ジェンダーに関する社会科学の書物のほとんどすべてが女性研究者によって出版されている」[13]からである。ジャブロンカ自身は「男のフェミニズムは新たなセクシズムにすぎない」[14]といったクリスティーヌ・デルフィの主張の存在も認識しつつ、それでも「文化的領有に対する非難が今日、男性がフェミニズムについて語ることを禁じている」ことは「恐るべき後退」[15]であるとして自ら本書に取り組んでいる。
ここで思い起こさなければならないのは第一に、ジャブロンカが2016年に刊行し、メディシス賞を受賞して話題になった『歴史家と少女殺人事件──レティシアの物語』[16]である。これは2011年に18歳で殺害されたレティシアという少女をめぐって書かれたもので、彼女は何重もの性暴力に苦しんだ末に殺されたことが知られている。この作品は彼女の生涯をたどると同時に事件について調査を進めるジャブロンカ自身の主観も混じりあうような、ジャンルを特定しがたいものだが、特にフェミニズムの観点から書かれたというわけではなかった。しかし作者にとって『正しい男たち』は当然の「続き」として構想されたのかもしれない。第二に思い起こしたいのは、ジャブロンカが歴史家としては異端であり、『歴史は現代文学である』[17]などの著作では歴史を19世紀以来の伝統にのっとって「科学」とのみとらえるのではなく、「文学」に近いものとしてとらえるべきだと提唱し、自らも『私にはいなかった祖父母の歴史』[18]では主観的な「私」を消し去ることなく、文学でも歴史でもあるようなテクストを書いている、ということであろう。こうした文学に踏み込む歴史家としてのスタンスもまた、ジャブロンカの男性性やフェミニズムへの関心と地続きであることが次の一節から伺われる。「『科学的なもの』に『文学的なもの』を対置して拒むこと、実験から逃げること、学術的な立場とそれが許す権威的な言説にくみすること、それは制度の人間になること、何かの専門家、男性的な意味での歴史家になることである。逆に、「私」に基づいた調査、亀裂をはらみ、理解を可能にする感情に開かれ、新たな形式を生み出すことを望む調査について書くとき、われわれはジェンダーの平等を取り戻すのである。」[19]『正しい男たち』ではそうした「私」はあまり見えないが、いつの日か男性性をテーマにジャブロンカが「文学」を書くだろうという期待を抱いてもいいのかもしれない。
Notes
-
[1]
« L’homme enfin inclus dans les études de genre », Le Monde, le 19 mai 2018. この『ル・モンド』の記事によれば、フランスにおいて男性性に関する研究は1970年代以降いくつかあるもののまとまったものはこれまでなかった。また英語圏ではマイケル・キンメルやレイウィン・コンネルなどが議論の基礎を確立したが、フランスではブルデューの『男性支配』が一枚岩な男性像を作り上げてしまい、一部の男性による他の男性に対する支配という問題系が考えづらくなり英語圏での議論が輸入されなくなってしまった、といった点も指摘されている。
-
[2]
Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire de la virilité, Paris, Seuil, 2011.(アラン・コルバン、ジャン=ジャック・クルティーヌ、ジョルジュ・ヴィガレロ監修、『男らしさの歴史』鷲見洋一・小倉孝誠・岑村傑監訳、全三巻、藤原書店、2016年。)
-
[3]
Sylvie Ayral, La Fabrique des garçons. Sanctions et genre au collège, Paris, PUF, 2011.
-
[4]
Mélanie Gourarier, Alpha mâle. Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes, Paris, Seuil, 2017.
-
[5]
Raphaël Liogier, Descente au cœur du mâle, Paris, Les liens qui libèrent, 2018.
-
[6]
Olivia Gazalé, Le Mythe de la virilité. Un piège pour les deux sexes, Paris, Robert Laffont, 2017. 以下ではMVと略記する。
-
[7]
Ivan Jablonka, Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités, Paris, Seuil, 2019. 以下ではHJと略記する。
-
[8]
MV, p. 9.
-
[9]
MV, p. 15.
-
[10]
MV, p. 47.
-
[11]
MV, p. 16.
-
[12]
MV, p. 9-10.
-
[13]
HJ, p. 355.
-
[14]
HJ, p. 164.
-
[15]
HJ, p. 411.
-
[16]
Ivan Jablonka, Laëtitia ou la fin des hommes, Paris, Seuil, 2016.(イヴァン・ジャブロンカ『歴史家と少女殺人事件──レティシアの物語』真野倫平訳、名古屋大学出版会、2020年。)
-
[17]
Ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Seuil, 2014.(イヴァン・ジャブロンカ『歴史は現代文学である──社会科学のためのマニフェスト』真野倫平訳、名古屋大学出版会、2018年。)
-
[18]
Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, Paris, Seuil, 2012.(イヴァン・ジャブロンカ『私にはいなかった祖父母の歴史──ある調査』田所光男訳、名古屋大学出版会、2017年。)
-
[19]
HJ, p. 356.
この記事を引用する
中村 彩「新たな男性性を求めて——オリヴィア・ガザレ『男らしさの神話』とイヴァン・ジャブロンカ『正しい男たち』書評」 『Résonances』第11号、2020年、63-66ページ、URL : https://resonances.jp/11/nouvelles-masculinites/。(2025年07月11日閲覧)