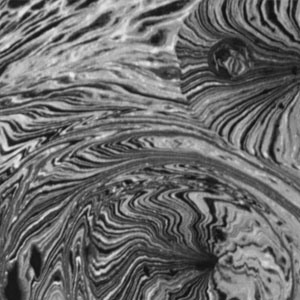ドゥルーズ『差異と反復』における「プラトン主義の転倒」についての一考察「徴との遭遇」と「思考のイメージ」から出発して
はじめに
周知の通りドゥルーズは、「転倒したプラトン主義」を標榜し「あらゆる価値の価値転換」を企てたニーチェの影響下で、西洋哲学の起源のひとつであり続けているプラトン主義と正面から対決し、それを転倒させることこそが現代哲学の使命であると主張した[1]。そして彼の第一の主著『差異と反復』は、この書物が書かれた68年5月の反時代的な空気を纏いつつその使命を全うしている。すなわち『差異と反復』は、その厳密な哲学体系の至る所でプラトン主義への反抗を企てており、その試みは「シミュラークル」や〈理念〉などの、すでに多くの研究が扱ってきた概念によって代表されているのである[2]。これらの先行研究に倣い、本稿もまた『差異と反復』における「プラトン主義の転倒」について論じたい。そしてその際本稿は、この書物で提示されている「超越論的経験論」をプラトン主義批判の文脈で捉えなおすことを目指して、さしあたりは「徴との遭遇」と「思考のイメージ」という二つの論点から議論に取り掛かろう[3]。もちろん、本稿の紙幅の関係上それがあくまでも試論であり、のちに取り組むべき包括的で厳密な解明作業を示唆する以上の役目を担いえないことは自明である。しかし我々は、西洋哲学における「思考」のあり方そのものを規定してきたとさえ言えるプラトン主義──この点を指摘するにあたっては、「西洋哲学の伝統の最も穏当な一般的特徴づけは、それがプラトンへの一連の脚注からなるというものである」というホワイトヘッドの有名な言葉を思い起こしてもよい──を転倒したドゥルーズが、「思考」といういわば「哲学以前的な」営みそのものに投げかけた問い──哲学の境域としての思考の再発明、そしてそれに起因する哲学それ自体の再定義──をさえ垣間見ることになるだろう。このようにして、ドゥルーズが西洋哲学史に対して企てた「革命」の核心を目指すこと──これこそが本稿のもう一つの企図である。
1.徴との遭遇、あるいは思考と感性の紐帯
第一に、「徴との遭遇」に取り掛かるとしよう。その際取り上げるのは、プラトンにおける真実在の探求である。
『国家』第七巻においてプラトンは、〈感性だけで判別できるもの〉と〈感性が信頼できるものを与えないもの〉の区別を論じたうえで、後者こそが我々を真実在の探求へと駆り立てるとしている[4]。このときプラトンは、感性に、探求の開始という特権を与えていると見てよいだろう。そしてドゥルーズは『差異と反復』でこの二つの区別を「思考をしずまらせるもの」と「思考を強制するもの」の区別と言い換え、自身の思索を展開している[5]。まずドゥルーズは、思考は常にこの「思考を強制するもの」としての「徴(signe)」ないし「強度(intensité)」との感性的な遭遇から開始されるとする。ここでいう強度とは、『差異と反復』の別の箇所で説明されている通り、同一的な量や質に還元されえない「純粋な差異」を意味している[6]。すなわちドゥルーズは、『国家』で論じられた感性の特権を参照しつつ、出来合いの言葉では語りえない強度の体験こそが我々を思考へと駆り立てると主張したのである。そのとき思考は感性との間に、さらには感性を刺激し揺さぶる芸術との間に、分かちがたい同盟を結ぶことになるだろう[7]。
このようにドゥルーズは、プラトン哲学から重要な示唆を受け取っている。しかしそれがドゥルーズをプラトン主義の方へ導いたとは言い難い。なぜなら当のプラトンは、思考を促す感性的な対象を「同時に反対の感覚」としてしか定義していないからである[8]。このときプラトンは、確かに一度は垣間見ていたはずの不定形の差異が蠢く強度的な世界を抑圧し、それを同一性と対立によって歪めてしまったのではないだろうか。そうだとしたら、ドゥルーズにとってプラトンは、自身の思考の出発点をなすにもかかわらず、あるいはなすからこそ批判しなくてはならない、いわば両義的な存在になるのである。
2.「思考のイメージ」の批判、あるいは「思考」の再定義
さて、ここでもう一度ドゥルーズの「思考を強制するもの」という表現に立ち返ろう。これは一見すると、『国家』で言われている「感性が何ひとつ信頼できるものを与えない」ものという表現の忠実な翻訳に見えるが、そこではすでにプラトン主義に対する叛逆が企てられていると言わなくてはならない。というのも、そこでドゥルーズが用いている「強制(力)(force)」という語には、プラトン主義が打ち立て、さらに哲学史のなかで保持されてきた思考についての道徳的な先入見、すなわち「思考のイメージ」に対するラディカルな批判が込められているからである。ドゥルーズが指摘する通り、プラトン以来「哲学」という営みは「知への愛」を、言い換えれば思考への自発的な意志を前提としてきた[9]。すなわちプラトンは、思考の端緒としての「遭遇」を発見しつつも最終的にはそれを放棄し、自ら思考へと向かう良き意志によって思考の開始を説明したのである。
そしてドゥルーズは、ニーチェ、プルースト、そしてアルトーと共にこのような「思考のイメージ」を厳しく批判し、哲学の原体験としての思考を、プラトン主義とは別の仕方で定義している。まず『ニーチェと哲学』では、従来の独断的な思考のイメージに対して「新たな思考のイメージ」が措定され、思考は暴力によって強制的に開始されると言われる[10]。さらにドゥルーズは、ニーチェが芸術を「力の意志の刺激剤」として定義し、能動的な生における芸術の意義を強調していたことにも言及している[11]。このことから、前節でふれた思考と芸術の深い紐帯はニーチェの影響下で構想されたものと見てよいだろう。次に『プルーストとシーニュ』では、抽象的な真理を求める「哲学のイメージ」が批判され、他方で徴との遭遇によって思考の開始を説明する「思考のイメージ」が高く評価される[12]。そして『差異と反復』では、アルトーが抱える「思考に成功すること」への希求のなかに、すなわち自身の苦悩を思考へと昇華させる闘いのなかに、思考を人間的本性とする「思考のイメージ」の破綻と、もはや人間のものではないような「イメージなき思考」が到来する希望を見て取っている[13]。かくしてドゥルーズ哲学は、芸術を生の関数として理解したニーチェの影響下で、そして徴との遭遇によって生起する思考の素材を生の中に見出し、それについて哲学者とは異なる言葉で語る文学者たちとの連帯のなかで、思考という営みを再創造する。そのときドゥルーズは、かつてプラトンが自身の理想国家から追放した詩人とともに、芸術によってこの理想国家への叛逆を開始したと見てよいだろう[14]。そしてドゥルーズは、いわば感性的な経験=実験としての芸術作品や、自身が生きた体験の只中で言葉を紡ぎだす文学者たちとのせめぎ合いのなかで、思考を生の極限的な地点として構想し、たえずそこにおいて新たなる言葉が、新たなる〈私〉が、すなわち新たなる生が創造されるような、「根源的な始点」として思考を定義したのである[15]。そうだとしたら、ドゥルーズの哲学は「現実的な経験/可能的な経験」というあくまでも理論的な二項対立を踏み越えて、生の実践の現場へと、そしてそこで胎動する思考へと差し向けられているに違いない。そしてドゥルーズは、このような思考を哲学的な「既成の諸価値」への批判的闘争として再定義することで、西洋哲学の歴史と正面から対決する。具体的には、ドゥルーズは思考を経験的な世界を規定する超越論的な〈理念〉を脱臼させ、変形させる「脱根拠化(effondement)」として定義している[16]。このようにしてドゥルーズは、プラトンのイデア論をさえ転倒させるのである。
「〈神〉の支配(hiér-archie)」のもとで同一なる「思考する〈私〉」に束縛されていた思考は、今やそれらから解放され、かつての縄張りを飛び出す。すなわち思考は、この世界の至る所で蠢き続けている強度が〈私〉を揺さぶるたびに、哲学の占有物であることをやめ、澄ました現状肯定であることをも拒むのだ。かくしてそれは、文学や芸術、さらには政治をも含めたあらゆる分野の柵や境界を飛び越え、かつてない熱気を帯びた一つの運動としてこの世界を埋め尽くすだろう。まさしくこのような運動こそが──永く哲学が契りをかわしてきた〈神〉や〈私〉に、さらにはこの世界の至る所にはびこる「既成の諸価値」に牙を剥き、絶えず「あらゆる価値の価値転換」を求める闘争こそが──「真に新しいもの」の、あるいは「差異」の反復としての永遠回帰にほかならない[17]。そしてこのような哲学思想こそが、これまで主人に飼い馴らされていた哲学の「生命力」を解き放ち、哲学を何か怪物的なものへと変貌させることになるだろう。我々が扱った『差異と反復』とは、哲学概念の比類なき体系によってこのような思想を提示する書物の名である。だが同時に、このような過酷な闘争の気配を伝えるひとつの徴──ツァラトゥストラがついに受け取った〈徴〉──でもあるのだ。
Notes
-
[1]
Gilles Deleuze, Différence et répétition, PUF, 1968, p. 82. 以下DRと略す。
-
[2]
関連する主な先行研究として、Gregory Flaxman, « Plato », Deleuze’s Philosophical Lineage edited by Graham Jones and Jon Roffe, Edinburgh University Press, 2009、鹿野祐嗣「ドゥルーズによるプラトニズムの反時代的な転倒──シミュラークルの叛乱、出来事としてのIdée──」、『表象・メディア研究(第3号)』、早稲田表象・メディア論学会、2013年を挙げておく。そのなかでも本稿は、とりわけ鹿野の研究から多くの示唆を得た。
-
[3]
紙幅の関係上、本稿では「シミュラークル」や〈理念(イデア)〉にはふれることができない。むしろ本稿では、先行研究を踏まえつつ、ドゥルーズとプラトンの関係を論じるにあたってそれらとは別の観点が可能であるということを示したい。
-
[4]
プラトン『国家』523A-B.
-
[5]
DR, 181.
-
[6]
DR, 187.
-
[7]
さらにドゥルーズは、感性的な遭遇とそれによって駆り立てられる思考の例として、「薬力学的な経験=実験」や「超絶主義」にまで言及している(DR, 305)。そのうち「薬力学的な経験」については、メスカリンによって自身の「知覚の扉」を開け放ったハクスリーを想起してよいだろう。また、自然をめぐる特異な体験を描写したエマソンやソローらの超絶主義思想については、彼らの思想とドゥルーズ哲学との交点を探る研究が求められる。
-
[8]
プラトン『国家』523B-C ; DR, 184.
-
[9]
DR, 170 ; Id., Proust et les signes, PUF, 1964, p. 24. 以下PSと略す。
-
[10]
Id., Nietzsche et la philosophie, PUF, 1962, pp. 118-119. 以下NPと略す。
-
[11]
NP, 116-117.
-
[12]
PS, 24-25, 115.
-
[13]
DR, 191-192.
-
[14]
プラトンの詩人追放論とその「転倒」を論じるにあたっては、以下の『ニーチェと哲学』の記述を参照したい。すなわち、「芸術は偽なるものの最高の力能であり〔……〕、欺く意志を高次の理想にする」(NP, 117)。この記述からは、鹿野、前掲論文が指摘している通り、ドゥルーズが「芸術」を、「オリジナル‐コピー」というプラトン主義的な二項図式に反抗する「オリジナルに似ても似つかないコピー」、すなわち「シミュラークル」に結びつけて論じていることが分かる。
-
[15]
このような主体の絶えざる再創造は経験論的な射程をも有している。すなわち我々は、感覚的経験と主体性の成立について論じる経験論の極限的な一形態としてドゥルーズの思想を理解しなくてはならないのである。実際ドゥルーズは、「〔感覚的〕所与のなかでの主体の構成」を問うヒューム哲学の研究によって思索を開始し、ベルクソンやニーチェの思想を「高次の経験論」と形容したうえで、自身もまたその思索の全体において経験論者であったと認めている。すなわち我々は、ヒュームやベルクソンらの思想的系譜の中に超越論的経験論を位置づけ、この系譜の本質を問わなくてはならないのだ。
-
[16]
DR, 251. なお、超越論的な〈理念〉と「脱根拠化」としての思考については、拙稿「ドゥルーズ『差異と反復』における思考の問題──脱根拠化としての思考とそのプロセスについて──」、『In-vention(第8号)』、早稲田大学文学研究科表象・メディア論コース、2020年を参照。
-
[17]
DR, 4, 121-122, 314, 327. なお、『差異と反復』の主題である「差異と反復の永遠回帰」については、鹿野『ドゥルーズ『意味の論理学』の注釈と研究』、岩波書店、2020年の序論を参照。
この記事を引用する
氏原 賢人「ドゥルーズ『差異と反復』における「プラトン主義の転倒」についての一考察——「徴との遭遇」と「思考のイメージ」から出発して」 『Résonances』第11号、2020年、34-37ページ、URL : https://resonances.jp/11/le-renversement-du-platonisme/。(2025年07月09日閲覧)