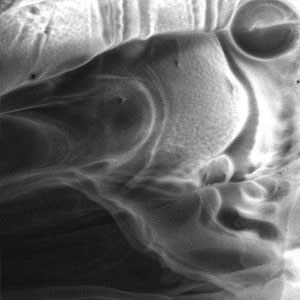クーザンの戦略勃興する哲学史における哲学者たちの形象
ヴィクトル・クーザン(1792-1867)は、19世紀フランスにあって哲学教育と哲学史を制度化した立役者として知られる。彼がドイツからフランスへと輸入した「哲学史」は、本人や弟子たちによる大哲学者の著作集や全集の校訂・翻訳作業、高等師範学校やソルボンヌでの講義、教科書・概説書の出版、本人が長らく主宰したアグレガシオン(哲学教授資格試験)や「道徳科学・政治科学アカデミー」の課題論文のプログラム化などを通じて、新たな学問領域として定着し、今日でも哲学教育・研究の枢要な部分を占め続けている。近年の研究では、このように一見して学究に徹している勃興期の哲学史の営みの背後にクーザン(学派)のさまざまな戦略が控えていたことが詳らかにされつつある。哲学史の戦略的「編集」にあたって、個々の哲学者、あるいは哲学史を画する「時代」はどのように表象されたのだろうか。本稿では、こうした観点から最新のクーザン研究の一端を紹介してみたい。
クーザンの哲学史にあってもっとも重要な登場人物は、おそらくデカルトであろう。1836年のアグレガシオンの課題「ソクラテス革命とデカルト革命の比較」が象徴的に物語っているように、デカルトの地位は、哲学の起源ともいうべきソクラテスのそれと比肩されるほど特権的である。こうしたデカルトへのこだわりには二重の動機が指摘されてきた。第一には、クーザン自身の哲学的主張である「スピリチュアリスム」である。感覚的事実のみを確実とし、唯物論的あるいは懐疑主義的傾向を帯びているとされていた18世紀的な(コンディヤックや観念学派に由来する)経験論・感覚論を修正し、魂=意識の実体性と能動性を積極的に認める「心理学」(ひいては、それに立脚した新たな形而上学)を企図していたスピリチュアリスムにとって、思惟する魂あるいは自己反省的な意識(コギト)の実在を証明したとされるデカルトは、恰好の理論的な後ろ盾だったのである[1]。第二の動機は、クーザンらの政治的イデオロギーにかかわる。いわゆる純理派と同様にクーザンは、旧体制=絶対王政への回帰を訴える右の教権・王党派と、大革命の急進化を目指す左の共和派をともに退け、「中道」政治(具体的には、1814年の「憲章」に表明されたような立憲王政)を支持していた。デカルトの名はまさにこの政体を正当化するものとして引き合いに出されるが、彼はどのような論理で動員されるのだろうか。ある研究者は以下のように整理している。デカルトは中世的な権威に基づく独断を拒み、理性を自律的に使用することで、思考する自我の実在自体に確証を与え、近代的な「理性主権」を確立した。1829年のソルボンヌ講義でクーザンは、この主権が知の領域にとどまることなく、18世紀にはさらに社会全般に広まり、大革命という決定的な出来事を介して、現実政治上のさまざまな自由へ進展すると述べている。つまり、大革命がもたらした議会政治、言論や出版、信教の自由といった進歩は、理性による個人の知的自律という原理が集合的に拡大した帰結なのである。しかしこうした政治的遺産は、大革命後の混乱を経て、七月王政が十全に体現することになる立憲王政下でこそ安定的に実現される。このようにクーザンは、デカルトによって哲学史上に達成された知的自律を、立憲王政によって体現された文明史上の政治的自由の起源に仕立て上げることで、デカルトを生み出したフランスを実質的な始点とし、立憲王政という政体を編み出したフランスを事実上の終点とする目的論的な歴史を描いた。理性の普遍的自己展開というヘーゲルに着想を得たはずの(本来ドイツをモデルとしていた)物語が、デカルトという形象を活用することで、フランス中心史観へと転換されているのである[2]。
デカルトのこうした特権視と呼応するように、後続する近代の哲学者たちはデカルト主義の名の下に一括され、その程度の劣る亜種という評価を下される傾向にある。たとえば、代表的なデカルト主義者の一人として数えられることの多いマルブランシュは、主にその神学的な色彩ゆえに「忠実でない弟子」とされる。観念のありかを魂ではなく神に置き、堕罪後の魂には明晰判明な認識は不可能であるとするマルブランシュは、デカルトが達成した魂=意識の自律という到達点から後退しているのである[3]。また、感覚論に批判的なクーザン学派の姿勢は、感覚論に近接しかねない生理学的な議論をも含むマルブランシュの浩瀚な著作の大部分が軽視されていく遠因となっているという指摘もある[4]。著作に軽重をつける方針はさらにデカルト自身の著作にも適用されている。心理学を重視するクーザンの方針のもと、『方法序説』はそれに後続する自然科学的・数学的諸論文から切り離され、『序説』同様にコギトが論じられる『省察』の導入であるかのように扱われていく[5]。このように「心理学者」化されたデカルト像の特殊性は、同時代のコントら実証主義者の描く数学者・科学者としての側面に重きを置くデカルト像と比較するならばより際立つだろう[6]。
1820年に復古王政下の政治の反動化を受けて講壇を追われたのち、クーザンはデカルト著作集の編纂に着手するが、ほぼ同時に始められたのがプラトンの仏訳『著作集』刊行の企画である。1840年に全十三巻で終結することになるこの試みは、講義以上に学術的な装いをしているが、ある研究者はこの『著作集』各巻の刊行順序に注目し、やはり同時代の哲学的=政治的論戦の文脈が看取されると指摘している。当初慣例にならって踏襲されていたトラシュロスによる著作の配列は、第二巻(1824年)の段階ですでに改変されている。トラシュロスが『クラテュロス』、『テアイテトス』、『ソフィスト』、『政治家』をまとめて四部作としていた(そもそも後三者の連続性はプラトン自身が示唆していた)にもかかわらず、収録されたのは『テアイテトス』と『ピレボス』の組み合わせであった。この編集は、両者がいずれも感覚論(あるいはその相関物としての快楽主義)の反駁という主題を共有しているということに重きを置いた結果であり、プラトン『著作集』は、クーザンによる感覚論批判が展開される密かな論戦の場となっていたのだ[7]。自由主義勢力の巻き返しにともなうクーザンの講壇復帰(1828年)を経て、1831-32年には第七、八巻が刊行されるが、これらの巻は、慣例では先立つはずの中期の『国家』ではなく後期の『法律』にあてられた。この一見してささやかな順序変更も、刊行年直前の七月革命(1830年)を背景にしたある政治的な意図に基づくと指摘される。立憲王政とブルジョワ自由主義を具現するべき七月王政を迎えたばかりのクーザンにとって、専制とも見なしうる「哲人王」の統治や、私有財産の否定を想起させかねない「財産共有制」が語られる『国家』を刊行するのは時局にそぐわず、望ましくもなかったに違いない。それに代わって優先的に刊行されたのが、(議会と君主の融合を目指す立憲王政に重ね合わせうる)「混合政体」の称揚、(ブルジョワ階級の選挙観に親和的な)所得に応じた制限選挙といった主題が扱われる『法律』であったというのである。プラトンはこのように当時の政治的現実に即した「政治哲学者」として演出されてもいるのだ[8]。
「中世への回帰」を訴える教権派・王党派という右派の論敵に対峙するクーザンらであったが、彼らは中世スコラ哲学を決して蔑ろにはしていない。とはいえ、クーザン学派にとっての中世は、トマスではなくアベラールの時代として集約される。エロイーズとの「醜聞」などから周辺的な扱いをされることも少なくなかったアベラールが中心人物とされるにいたった背景には、「普遍論争」への関心があったようである。普遍の実在を認める実在論と、普遍を単なる名辞とみなし個物の実在のみを認める唯名論、そして両者を調停したとされるアベラール。ある研究者は、クーザンがこの対立と調停の構図を同時代の論争に重ね合わせているとする。普遍の実在のような「独断」を主張するのが右の教権・王党派であり、個という経験的実在しか認めない唯名論が18世紀的な感覚論の祖であるならば、両者を融和したアベラールは、教権派と極端な感覚論の中庸を自認するクーザンに重ね合わせられる[9]。中世12世紀のフランス人アベラールの形象は、さらに近代17世紀のフランス人デカルトのそれと相似形をなすように描かれていく。既存の学説を「検討しては疑い[…]明証的なものにのみ依拠する」理性重視の姿勢は、この二人が「フランス精神から借り受けた共通の特徴」であるとさえされる[10]。かくして、フランスのアベラールを焦点とされた中世は、17世紀のデカルトと、19世紀のクーザンという光源から遡って照射されることで、合理的近代の延長された起源という像を結ぶ。中世は、もはやカトリック教会勢力の占有物ではなくなるのである。
クーザン学派における「デカルトの近代」と「アベラールの中世」の称揚は、その間の時代であるルネサンスの排除という帰結を伴った。クーザンは、15〜16世紀のイタリア思想は総じて確たる「方法」をもたず、文献学を通じた古代の模倣しか生み出さなかったと述べ[11]、弟子アドルフ・フランクの編になる全六巻の『哲学辞典』(Dictionnaire des sciences philosophiques, 1844-1852年)にも、この時代にあてられた項目がない。ある研究者は、亡命イタリア人教師ジュゼッペ・フェラーリのクーザン批判を通して、こうしたルネサンスの軽視がフランス・ナショナリズムと相関していると指摘する。1840年代にフランス初のルネサンス哲学史をストラスブールで講じていたフェラーリは、近代の始点を17世紀のデカルトではなくイタリア・ルネサンスに設定しクーザン学派に挑戦する。彼のこうした挙措は、フランスとイタリアの「思想の国籍」同士の争いというだけでなく、政治イデオロギー的な闘争という意味合いも帯びていた。民主主義的、社会主義的な展望をもつフェラーリにとって、フランス革命を準備するのもやはりデカルトではなくルネサンスであり、ブルーノからカンパネラに至る封建制や宗教的権威への抵抗によって特徴づけられるこの時代は、大革命、そして未来の急進的な社会の理念的な起源となるのである。デカルトから大革命に引かれ、立憲王政の中庸に落ち着くクーザンの物語は、ルネサンスから大革命に引かれ、より急進的な社会を志向する左派の物語からの挑戦を受けていたのである[12]。
このように、フランスにおける勃興期の哲学史は、フランス・ナショナリズム、立憲王政、スピリチュアリスムの擁護と正当化というクーザン学派の党派的戦略と不可分の装置であった。では、第二帝政開始以後のクーザンの失脚を経て、哲学者たちの序列や、彼らの名のもつ価値はどのような変動を被るのだろうか。たとえばライプニッツは、クーザンの乗り越えを図る新たな「スピリチュアリスム」の拠り所とされていき[13]、青年期にクーザンが心酔し、その後「無神論」の咎が自ら(とデカルト)に波及するのを恐れ軽視していたスピノザは、教権派と共和派の熾烈な対立という世紀転換期の時代的文脈のなかで積極的な役回りを与えられていく。狭義の哲学史研究に従事する者たちも、こうした哲学者たちの形象をつぶさに分析するならば、彼らの名の裏に、変遷していく19世紀フランスの知的・政治的な状況が織り込まれているさまを明らかにできるにちがいない[14]。
Notes
-
[1]
François Azouvi, Descartes et la France. Histoire d’une passion nationale, Paris, Fayard, 2002, p. 178-179.
-
[2]
Mario Meliadò, « Géopolitique de la raison. Sur la pratique de l’histoire de la philosophie à l’école de Victor Cousin », Catherine König-Pralong, et al. (eds.), The Territories of Philosophy in Modern Historiography, Turnhout / Bari, Brepols Publishers, 2019, p. 174-175.
-
[3]
Delphine Kolesnik-Antoine, “Is the History of Philosophy a Family Affair? The Example of Malebranche and Locke in the Cousinian School”, Mogens Lærke, et al. (eds.), Philosophy and Its History. Aims and Methods in the Study of Early Modern Philosophy, New York, Oxford University Press, 2013, p. 169.
-
[4]
Ibid., p. 164.
-
[5]
Cf. Pierre-François Moreau, « Victor Cousin, la philosophie et son histoire », Le Télémaque, Presses universitaires de Caen, n° 54, février 2018, p. 62 ; Azouvi, op. cit., p. 179.
-
[6]
Ibid., p. 163-168.
-
[7]
Michel Narcy, « Le Platon libéral de Victor Cousin », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, n°37, janvier 2013, p. 43-49.
-
[8]
Ibid., p. 52-57.
-
[9]
König-Pralong, « Découverte et colonisation française de la philosophie médiévale (1730-1850) », Revue des sciences philosophiques et théologiques, n° 96, avril 2012, p. 695-696.
-
[10]
Cf. Victor Cousin, Ouvrages inédits d’Abélard, Paris, Imprimerie royale, 1836, p. IV, cité in ibid., p. 696.
-
[11]
Cf. Cousin, Cours de l’histoire de la philosophie, t. I, Paris, Pichon & Didier, 1829, p. 433, cité in Meliadò, art. cit., p. 174.
-
[12]
Ibid., p. 182-183.
-
[13]
Cf. Jeremy Dunham, « Leibniz et la philosophie française au XIXe siècle », Lærke, et al. (dir.), Leibniz. Lectures et commentaires, Paris, Vrin, 2017, p. 345-355.
-
[14]
クーザンとその弟子セセにおけるスピノザの受容については、Moreau, « Autour du spinozisme en France au XIXe siècle : panthéisme, spiritualisme, positivisme », Philosophia OSAKA, No. 15, March, 2020, p. 15を参照。
この記事を引用する
飯野 雅敏「クーザンの戦略——勃興する哲学史における哲学者たちの形象」 『Résonances』第11号、2020年、29-33ページ、URL : https://resonances.jp/11/la-strategie-de-victor-cousin/。(2025年07月13日閲覧)