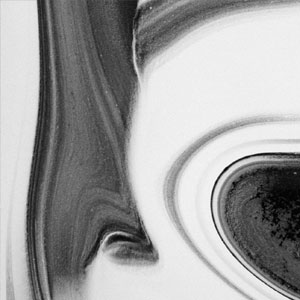ヴァンサン・ド・コールビテール,イメージ、身体と精神の間でサルトルの高等教育修了論文
Vincent de Coorebyter, « L’Image entre le corps et l’esprit. Le mémoire de fin d’études de Sartre », Sartre Studies International, 2019, vol. 25, issue 1, p. 1-21.
今回訳出したのは、北米の『国際サルトル研究』誌に掲載されたヴァンサン・ド・コールビテールの論文である。論文の主要な狙いは、サルトルの高等教育修了論文『心的生におけるイメージ、役割と本性』(1927年)[1]を解説することにある。2018年にフランスの『サルトル研究』誌に公刊された高等教育修了論文の刊行に至る経緯については、本論文の冒頭にも紹介されており、また修了論文の序として付された編者ゴーティエ・ダッソンヌヴィルの解説も参考になるが、これが『想像力』(1936年)及び『イマジネール』(1940年)に先立つテクストとして、サルトル研究にとってだけでなく、同時代の哲学と心理学に関心を抱く者にとって一級の重要性をもつことに疑いはない。既に幾つかの研究論文も発表されており [2]、日本語圏の関心ある読者にもその主要な問題系を共有できればと、翻訳を考えるに至った次第である。
コールビテールはベルギーのブリュッセル自由大学の教授であり、今日のサルトル哲学研究を牽引する第一人者である。主著『現象学に直面するサルトル』(2000年)[3]はあわせて50ページに満たないサルトルの初期哲学論文──「志向性」論文と『自我の超越』──に700ページ近くの詳細な検討を施し、サルトル哲学の研究状況を一新させた。続く『現象学以前のサルトル』(2005年)[4]は、『嘔吐』と『真理伝説』を中心に、現象学以前のサルトルを主導した哲学的直観を解明し、前著と併せ、同時代の哲学的状況に対するサルトル哲学の独自性を明確にした。近年ではサルトルの想像力論への関心を深めており、『想像力』と『イマジネール』の間でのフッサールに対する態度の変遷を明らかにしていた[5]。また、高等教育修了論文については、それをロマン主義的想像力論の系譜に位置づけるという試みも既に発表している[6]。要するに、サルトルの哲学上の出発点と言うべき高等教育修了論文の解説者としては至適の人物である。
とはいえ本論文が難解であることは否めない。そもそも高等教育修了論文が「いかなる総括的な紹介、とりわけ要約を寄せ付けない」ものであるだけに、単なる解説に留まることはできないだろう。むしろ、青年サルトルの思想的限界を認め、テクスト内部に幾多の矛盾があることを踏まえた上で、その「内的緊張」を取り出すことを目的にしていると言ってよい。この点で重要なのは、後年のサルトルの思想的到達点があたかもそれ以前のテクストに萌芽しているかのように考えること、レトロスペクティヴな視点から初期サルトルを評価することは、これを慎む、という姿勢である。たとえば、「イメージは代理=表象的ではない」という27年時点でのサルトルの中心的主張が精査される際、それと『想像力』や『イマジネール』における「内在性の錯覚」批判との論点の相違が強調されている。また、1933年に現象学を「発見」するサルトルの思想的展開のなかで、27年の想像力論と現象学期の想像力論の間に連続を見るか断絶を見るかというのは研究上の主要な関心であるが、著者の見解はあくまで慎重である。なるほど、「いくつかの洞察において知性の輝きや炯眼が見て取れる」としても、同論文は現象学的と呼びうる水準にはない、というのが著者の結論である。そして最終節では、同論文を構成する三つの地平──身体、精神、イメージ──がそれぞれ提示する「理論的な不安定」が立ち入って検討されている。
凝縮された論理展開はフランス語原文でも辿りやすいものではなく、翻訳はなるべく読みやすさを心掛けるようにしたが、他方で註をいたずらに増やすことは控えた。今日のフランス語圏サルトル研究の水準の高さをできるだけ正確に追体験していただければ訳者としては幸いである。
1927年6月、サルトルはパリ高等師範学校に学位論文「心的生におけるイメージ、役割と本性」を提出した。論文提出の目的は哲学の高等教育修了免状を取得するためで、当時、この免状取得の要件としては、他の課題と合わせ、「候補者が選び学部が承認した主題に関する哲学史または哲学の論文」を執筆することが求められていた[1]。論文はアンリ・ドラクロワの指導で書かれたが、このドラクロワが数年後、イメージに関する諸理論をまとめた書籍の執筆をサルトルに依頼することになる。この書籍が当初の形式のまま世に出ることはなかったが、これを基に『想像力』(1936)と『イマジネール』(1940)が刊行されることになる。
サルトルの論文の元原稿の所在は特定されていないが、1970年頃にミシェル・リバルカがタイプ原稿を作成しており、これは272ページと付録からなる。このタイプ原稿も完全なものではない(シモーヌ・ド・ボーヴォワールがミシェル・リバルカに当時手渡した原稿のうち、初めの4ページが欠落している)。それでもこの原稿を検討すると、同論文が複数行にわたりそのまま『想像力』と『イマジネール』に再録されていることがわかる。それゆえ本資料はサルトル思想とその生成を研究する上で重大な意義をもつものであり、その重要性に鑑み、ITEM(近代テクスト・草稿研究所、CNRS-ENS)のサルトル班は、ゴーティエ・ダッソンヌヴィルの担当のもと、論文の学術校訂版を『サルトル研究』誌に用意した。本稿ではこの校訂版[2]に依拠し、サルトルからの引用に際しては同誌の該当ページを簡潔に指示することで出典とする。
学位論文の目次は『イマジネール』のそれを予告するものだ。複数の主題が1927年の論文と1940年の著作に共通している。──たとえば、情動性、運動、心的イメージにおける事物の出現様態、象徴図式、イメージと思考と知覚の関係、心的生におけるイメージの役割、非現実を前にした主要な行動様式、といった主題である。こうした共通項に基づき、両著作の比較に着手してみるのも魅力的なことだろう。またそこから、想像的なものについてのサルトルの現象学におけるフッサールの貢献の度合いを測ることもできよう。だが、サルトルは『想像力』のなかで現象学を、イメージに関する既存の学説の一切を根本から転倒させる源泉として紹介しており、サルトル自身の従来の理論もその転倒を免れないのだから、このような比較の試みは恐ろしく煩雑なものとなるだろう。そのため、紙幅の制約もある本稿でかかる対照を行うのはやめておく。1927年の記述が現象学に接近していると思われるとき、その説明を行うに留めておきたい。
同じく紙幅を理由に、1927年の学位論文に関する我々の議論には遺漏がある。実際、同論文はいかなる総括的な紹介、とりわけ要約を寄せ付けない。表面的な構造がかなりシンプルであっても、『サルトル研究』誌版で200ページに及ぶ同テクストは、高等師範学校時代にサルトルが博していた、数々の理論の驚異的な発明家という名声を見事に裏付けている。本稿に許された紙幅のなかでは、論文の大部分は影に留まらねばならないだろう。──たとえば、心的生の諸機能におけるイメージの役割や、多重知覚(surperception)に関する独自の理論(63-70、190-192、206-207ページ)、あるいはまた、対象の動きを規定する法則と想像力と完全に一体になった思考の法則の間に、あたかも自然の働きと精神の働きの間に生来の親近性があるかのように、大胆な平行関係が想定されていること(140ページ)。イメージに関するサルトルの中心的な命題の数々でさえ、本稿では手短に扱われるに留まる。というのも、それらは数も多く、錯綜しており、時には一貫性に欠け、またほとんど常に、鮮やかであると同時に面喰らわせるものだからだ。本稿における我々の目的は、サルトルの論を概略的に整理することにある。それによって彼の論に相当の単純化を施し、同時に一定の距離を置いて眺めるように努めよう。
I. 中心的命題:イメージは代理=表象的(représentative)ではない
学位論文の提出当時、サルトルはまだ22歳だった。だとすれば、『心的生におけるイメージ、役割と本性』が自説の開陳より批判的着眼点において堅実なものと見えるのも意外でない。他の多くの人たちと同様、サルトルはまず対立することで自分の立場を固めるのだ。
この学位論文の場合、主要な論敵は明確に見定められている。いかなる形をとったものであれ、イメージを感覚の派生物、たとえば感覚や知覚の想起・痕跡・再生として定義する伝統、これが彼の標的となるのだ。究極的に言えば、この伝統はアリストテレスの立場を継承したものだ。『魂について(デ・アニマ)』(第三巻第八章)のアリストテレスは、84ページでサルトルが引用する短い一節のあとで次のように書いていた。「イメージは感覚に似たものである。ただしイメージは非物質的なものであるが」。サルトルが強調するように、イメージを感覚の痕跡と捉える発想は広く共有されていた。一方には、デカルト、マルブランシュ、スピノザのように、[心身]二元論あるいは合理主義の立場をとる哲学者たちがおり、彼らはイメージなしで「純粋な概念によって」(71ページ)思考することを学ぶように推奨していた。他方で、たとえばホッブズのように、経験論、感覚論、唯物論の立場をとる哲学者たちがおり、彼らは「一切の心像は人間の内部における運動の、つまり感覚に際して刻み込まれた運動の残存物である」(『リヴァイアサン』第三章、サルトルは71-72ページにラテン語で引用)と考えた。だがいずれの立場にせよ、イメージを感覚の痕跡と捉える発想は共有されていたのである。イメージを再生感覚だと捉えるこうした考えは、なるほど実に多様な教説に利用されたとはいえ、長きにわたる諸世紀の間、「イメージの本性に関しては一般的な見解の一致が存在していた」(72ページ)ことに違いはない。サルトルはこうした「共通の前提」に挑戦するのだが、その前提とは、つまり「想像的表象は感覚に起源をもつ」(88ページ)という前提である。
この[論敵となる]枠組みにおいて、イメージとは「弱まった感覚」(73ページ)に他ならない。したがって、合理主義者でも唯心論者でもない書き手たちは、感覚によって刻まれた「脳の痕跡」(233、240ページ)がイメージによって再活性化されるのだ、という仮説を立てることになる。これら唯物論、経験論、観念連合論の書き手たちにとって、イメージとは「脳の変容の単なる産物」(77ページ)、「再生した感覚」(81、164、210ページ)に過ぎない。こうして、サルトルが嫌悪する科学主義的、決定論的な還元主義への道が開かれる。この立場を最も象徴するのは、『心的生におけるイメージ』の時点から既に、[イポリット・]テーヌである。サルトルが引用するテーヌの有名な一文によれば(79-80ページ)、心的生とは「よく選び抜かれた、重要な、意味のある小さな諸事実」[3]に還元されるのであって、これら諸事実は、究極的には生理学に基盤を有する組み合わせに従うことになる。テーヌは心的生を原初的感覚、「分子運動」[4]に連れ戻し、イメージを生の感覚をはみ出す一切のものと同一視する。イメージを身体に結びつけ、同時に感覚を超過するものとして定義するという、この両義的な地位は、イメージに固有のダイナミズムを付与し、それを創造的な力、現実的なものから人を解放する力として認識・定義することを可能にしえたかもしれない。だが、自らの出発点を生理学、さらには唯物論に据える、テーヌや他の多くの心理学者にとって、この超過[としてのイメージ]は、反対に、それがよってきたる源泉、つまり感覚によって定義されてしまう。サルトルが引用するテーヌの言い回しに従うなら、イメージとは「感覚の自発的な反復」[5](81ページ)に過ぎないのだ。
こうした──サルトルが学位論文を執筆していた当時支配的だった──見解にあって、イメージは、「機械仕掛け(mécanique)」(80ページ)にとまでは言わずとも、何らかのメカニズムに帰属することになる。とりわけ観念連合説の場合がそうで、この立場は、「思考をイメージの連合として呈示する」(97ページ)ことにより、なるほどイメージを意識の流れ全般のなかに組み入れたという功績は認められる。とはいえそれを、創造性は皆無なのにダイナミズムと称するもの[=観念の連合]に服せしめることで、「心的生の死せる要素」(85ページ)にしてしまったのだ。たとえば、過去のイメージは現在の状況との隣接関係を理由にして再生されるという[観念連合説の]仮説は、イメージを「表現的な価値」(127ページ)を一切欠いた「死せる要素」にしてしまう、ひとつの自動運動を想定するものでしかない。同様に、サルトルが要約するかぎりでの[テオデュール・]リボーの説によれば、人間は「既に与えられたものを様々な仕方で組み合わせることしかできない」(182ページ)。
この点を踏まえ、しかも130-131ページで、サルトルの論文全体が「観念連合の視点を別の視点に置き換えるための試みと見なしうる」とされているのを読むと、彼が目指すのは経験論の伝統の真逆を行き、イメージを精神・思考・創造の領域に一義的に分類することなのだと考えたくなるかもしれない。ところが、129ページ以降、短い──他のほのめかし的な記述に続く──一節によって読者は、彼の立場がより複雑なものであることに注意を促される。というのも、サルトルは彼なりの仕方で連合説のいくつかの説を引き受ける(endosser)のであり、とりわけ連合説がイメージを「特定の生理的状態を冠したもの、何らかの生理的状態への心的反応」として呈示するときにそのことが明らかになる。換言するなら、サルトルが彼らに対立するのは、支配的伝統においてイメージが身体に組み入れられ、想像的なものが生理的なものに連れ戻されるためではない。反対に、サルトルにとって、支配的伝統の唯一の功績はそこに、つまり[イメージを精神・思考・創造に一義的に結びつけるという]唯心論の安直さを回避させてくれる点にあるのだ。
実際のところ、サルトルがとくに批判しているのは、支配的見解の根底にある自動運動(automatisme)の前提──およびその前提が、自由に対してだけでなく、とりわけイメージそれ自体に対して有する諸帰結──である。というのも、支配的見解は、イメージを「感覚的起源」(特に88ページ)に連れ戻すことで、その表現的な力能を奪い去り、イメージが想起・再生するところの感覚以上のもの、あるいは感覚以外のものを当のイメージがもたらすことを不可能にしてしまうのだ。感覚の蘇生として理解されるイメージは、身体的経験の翻訳・象徴化として、その経験に別の地平で新たな生を与えてくれはしない。そうではなく、かかるイメージは、語の二重の意味において、その経験の単なる再現(=複製(reproduction))である。つまり、身体的経験の反復であると同時に、それを「版画」(特に103ページ)、一種の心的な絵に変容させてしまうのだ。この複製は、見られた、ないし生きられた光景に忠実ではあるが、いまや物としての不透明性と不動性を得てしまい、いかなる固有の意味も象徴的な射程ももたなくなる(132ページ)。支配的見解は、イメージに感覚としての核を与えることで、サルトルが論文で用いる語彙に従うなら、「代理=表象的な」[訳註1](54、66、67ページ等)ものにする。つまりイメージは生体験のコピー、ないし精神の眼差しに供される代理=表象にされてしまう。あるいは心的なスペクタクルにされてしまう、あたかも「外界の所与を前にするようにしてイメージの前に」(182ページ)立つ人の場合のように。だとすれば、サルトルの真の標的は、イメージについての支配的見解の根底にありはするものの、多かれ少なかれ彼も引き受けてしまっている決定論だとは言えない。むしろ、そうした見解がイメージを、精神なり感覚なりが浸透できるような意味を喪失した、凝固した光景に還元してしまうことが問題なのだ。かかる見解において、イメージは虚構の次元に属するものではなく、ましてやファンタジア、つまり現実から身を引き離す力能とは程遠い。反対に、こうした見解は我々を現実に──しかも、死せる現実、過ぎ去った現実に連れ帰すのである。イメージは記憶、ないし記憶の組み合わせに過ぎないものとなり、サルトルが望むような、形相(forme)と質料(matière)を創造する力にならない(184ページ)。
こうなると、サルトルの論文で最も繰り返される命題のひとつは、心的イメージの代理=表象的性格に反駁する、という点にあることになる。これはサルトルの読者にはよく知られた主張であるが、1927年と、それ以降の現象学的著作におけるのとでは異なる形をとっている。サルトルは1927年時点ではまだイメージの志向的性格を強調していないが、この性格こそ[現象学的著作においては]イメージを内在性から免れさせ、外の世界を目指す方法にしてくれるだろうものだ。たしかに、サルトルは既に論文のなかで、イメージは内面の絵画のようなものだとする考えを批判しており、これは『イマジネール』冒頭の「内在性の錯覚」[6]批判を予告するものである。だが、1927年の時点では、イメージが内面的なものだと想定すること自体は非難されていない。サルトルが非難しているのは、それが絵画として、現実に外見上忠実な代理=表象として、「再生感覚」(81、164、210ページ等)として定義されることである。高等教育修了論文によると、イメージによって「我々は自身のうちに対象を有する」(234ページ)──フッサールを読んで以降のサルトルはこの説を明晰に批判する[7] ──だが、それを代理=表象的な形では有さないのだ。イメージは知覚の側に分類されない。なぜなら、知覚の性質とはまさにイメージに欠けている性質だからだ。つまり、事物の表面的性質の正確さとか明瞭さ、安定性といったものは、イメージには欠如している。イメージは、一貫しないもの、流動的なもの、束の間のものの側に属するのである(117ページ)。
この点に関してサルトルは、のちに『イマジネール』でもそうするように、アランの文章を引用する。そのテクストでアランは読者に、パンテオンのイメージを心に抱いているとき、その列柱の数を数えてみるよう仕向けていた[8]。検証してみると、列柱はうまく数えられない。イメージは、対象についての正確さや完成度というよりも、絶妙な流動性や、一貫性の精妙な欠如──言い換えると、サルトルが論文のなかで言うように、その「不断の湧出」、自由な「創造」によって特徴づけられるのだ。実際、イメージは「思考の性質の一切」(117ページ)を有している。これを根本的な理由に、唯心論的な位相から、サルトルはイメージを絵画と捉える見解に反対することになる。「イメージが代理=表象的だと信じるのは、精神を物質化するものであり、心的生のなかに、まるで川のなかに壁を崩落させるかのように、巨大な物質を導きいれるようなものだ」(234ページ)。イメージは代理=表象的ではない。それは精神が身体ではないからだ。イメージは記憶の痕跡や、知覚経験の心的な再構成ではなく、「自発的な湧出」(234ページ)であり、その素材[=質料]は身体から借用されているものの、知覚の素材とは異なるのだ。
II. 方法の諸問題
サルトルが進めるこうした解明は、現象学的な位相に属するものだろうか。ここまでの要約で我々はそう考えるよう仕向けたかもしれず、また1927年の論文のなかの2ページ[135-136ページ]も、もし部分を全体と見なすのであれば、同じ方向の見解に向かわせることだろう。実際、136ページにおいてサルトルは、イメージを「それ自体において」、つまり──そう言いはしないものの──現象学における現象と同じ仕方で取り扱う必要性を主張している。現象学における現象は、自分自身の[存在を照らす]光の担い手だと想定されていた。何故なら、現われこそが存在を開示するのであり、存在とは現われの法則に他ならないからだ。イメージをあるがままに眺めるという、こうした方法的規定から、サルトルは明確で力強い結論を引き出してみせる。それはつまり、「我々はイメージを知覚するのではない、イメージを意識するのだ」(135ページ)という結論であり、これは一種の現象学的還元によって獲得される。サルトルはそれと知らずにエポケーを実践しているのだ。これらのページにおいて、彼は一切の理論を括弧に入れ、[紙の上に描かれた象徴図式は個別的なものか一般的なものか、という]明確な例を基に、イメージに「個別的な」とか「一般的な」とかの性質を付与することを拒否している。こうした性質は、イメージの外部にある現実性の領野から借りられてきたものとして、当時専門家の間で深刻な議論の的になっていたのだ(136ページ)。イメージの特種性を擁護したいサルトルは、非の打ち所なく現象学的な結論を引き出すのだが、それは『嘔吐』の最もフッサール的な一節を、文字通りに予告するものである。つまり、『嘔吐』には「事物とはそのすべてが現われるものだ──その背後には……何も存在しない」[9]とあるのだが、それが論文の136ページでは、こうなる。「実際、我々が意識するイメージの背後に何かがあると信じるのは大きな過ちだ。イメージはそのすべてが現われるものであり、不完全に現われるのではなく、しかも知覚には同化不可能なものなのだ」。
この点で改めて念を押しておくべきは、1927年のサルトルはまだフッサールを読んでおらず、論文では二度、「ヒュッサール」[10]という名の「論理学者」として言及されるに過ぎないということだ(98、118ページ)。フッサールは仏独の様々な文献で既に注目を促されていたものの、それ以上の存在ではなかった。「現象学」という用語について言えば、こちらは論文には一切登場しない。この事実から、現象学はサルトルに何ももたらしはしなかった、と結論すべきだろうか。あるいは、別の仮説だが、これもやはりフッサールによる寄与を相対化するものとして、サルトルは現象学者となるためにフッサールを必要とはしなかった、と結論すべきだろうか。この独創的な仮説にも魅力がないわけではないがが[11]、そのように結論するのはサルトル青年をあまりに買いかぶることになるだろう。
実際のところ、『イマジネール』でも決定的な役割を果たすパンテオンの例[が27年の論文にも登場すること]や、「イメージ=絵画」理論への135-136ページでの反駁によって惑わされてはならない。高等教育修了論文のこれら数節は、『イマジネール』と比較すると、極めて貧しいものだ。1927年のサルトルは、パンテオンについてのアランの文章を用いてはいるが、そこにどんな注釈も加えていない。この例は、明示的には、[本論を展開させるための]前置き的な要素として議論に登場しており(225ページ)、暗示的には、イメージは代理=表象的ではない、とするサルトルの説には高名な先行者がいるのだと想起させるための、権威に訴える論法になっているのだ。
それに、アランを引用している論述展開の全体で、サルトルはとりわけアンリ・ピエロンの研究に依拠しているのだが[12]、これは現象学的ではなく実験心理学的なものである。この論の展開は、被験者が図像を呈示された後でそれを絵に描くことができるかという課題──この課題は、もし被験者がその図像についての代理=表象となる心的イメージを保持しているなら、達成できるはずのものなのだが──を検証するための試験を単純に寄せ集めたものになっている。
さて、これらの試験を受けた被験者たちは、自分が見た図像を再現するのにことごとく失敗した。彼らがこうして繰り返し試験に失敗することから、ピエロンは、『イマジネール』第一章を予告するような説を結論として引き出している。すなわち、心的イメージは「欠如」や「非在」によって特徴づけられる、という結論だ(サルトルが226ページで引用するピエロンより)。『イマジネール』では、同じものが「準観察」[13]や「無」[14]によって特徴づけられる、と言われることになるだろう。ところで同書は、その副題を「想像力の現象学的心理学」としていたのだった。もしサルトルが本当にフッサールを読む以前から現象学者だったとするなら、イメージの非知覚的起源に関する自らの主張に一致する、こうした[ピエロンの]所見を拝借していたことだろう。さらにピエロンの結論を敷衍して、あからさまな不完全性、未完成性や、知覚の諸法則からの撤退、といった性格こそがイメージの存在論的な品位、イメージが物質よりも精神の領域に属すことの証明になるという事実を示していただろう。もしピエロンに追随することを受け入れていたなら、サルトルは心的イメージを積極的に特徴づけることができていただろうし、その仕方は、心的イメージとは「独創的な視覚表象であって、観念連合や記憶ではなく、創造的な想像力から到来する」(203ページ)という表現よりも正確なものになったろう。だが、論文執筆時のサルトルにとっての唯一の目標は、イメージそのものとその心的生への優れた貢献を評価することにあった。そのため、イメージの欠如や非在に関するピエロンの結論は、それが決定的なものであっても受け入れられないのだ。ピエロンは「イメージの個別性を否定する」(226ページ)に至ったかどで批判されている。──だがこれは理屈に合わない、ピエロンはそれと正反対のことをやっているのだから。彼はイメージの特種性、その比類なき存在体制、出現体制を確立したのだ。青年サルトルはと言えば、それをイメージの実在自体を否定するやり口だと同定することで、こうした[欠如、非在としての]〕特種性には取り組まず、ピエロンの実験から、確固とはしているものの明晰さを欠く結論を引き出すに留まっている。「ここでは被験者がその対象について抱いているイメージに従って対象の絵を描くことが不可能だということを[…]確認しておこう」(226ページ)。
1927年の時点でフッサールを読んでいなかったという理由でサルトルを批判することはできない。執筆以前にフッサールを読んでいれば、という仮定に基づいて、そうなりえていたはずの在り方からサルトルの論文を批評するような、理想主義的な基準を押し付けることは我々の考えにはない。問題は、当時の状況、当時の武器でもって、このテクストが現象学的水準に到達していると称しうるのか、を検証することに他ならない。はたして、この線で研究を進めてみると、答えは全体としては否定的なものとなる。たとえいくつかの洞察において知性の輝きや炯眼が見て取れるとしても、だ。
引き続き、イメージが代理=表象的な性格を有しているか否か、という主題に関して、サルトルはある問題を扱っていない。だが、この問いは彼の論証から生じてくるものだし、フッサールならずともカントに着想を受けて浮かびえたはずのものである。つまり、我々の内なる「イメージ」と呼ばれるものと、対象との関係はいかなるものなのか、という問いだ[15]。これはサルトルの論文の枠組みでも避けられない問題である。というのも彼は、「イメージ=絵画」という説が心理学関係の文献に支配的なだけでなく、常識が確信するところのものでもある、ということを強調しているからだ。被験者に質問すると、その大半は自分がイメージを「見ている」と信じている(219ページ)。だとすれば、自身のイメージを記述しようと試みるとき、哲学者・心理学者・実験装置(dispositifs expérimentaux)の被験者たちの圧倒的多数は[イメージの本性について]誤解している可能性がある。このような誤解がどうして起こりうるのかというのは、避けがたい──かつ深刻な──問題である。もし、心的イメージが実際に目に見えるものでないのであれば、またもし、サルトルが136ページに書くように、イメージが内的な写真として現われるものでないことを理解するには、イメージを「それ自体として」偏見抜きに眺めるだけで充分なのであれば、現実には見ていないものを見ていると信じてしまうことをどう説明すればよいのか。こうした錯覚を説明し、それが必然的なものであることを理解するのは、現象学の枠組みでは問題にならない。イメージは志向的であり、表象された対象それ自体を狙うことに役立つ──この対象の諸々の性格は、対象を狙うことを可能にしているイメージに帰属させられる──のだから、明らかに表象的なものなのだ。しかし、こうした理論的枠組みが欠けているとき、実験心理学の用いる装置[=仕組み]に対して、どんな信頼を置きうるというのか。なにしろ、実験心理学は被験者に自分が見たと信じるものを語るよう依頼するのだが、おそらく被験者はそれを見ていないのだ。というのも、彼らが質問されているのは、まさしくイメージ、つまり純粋に心的な代理=表象についてなのだから。
サルトルはこうした問いに答えていない。理由は単純で、方法論的問題は、論文内で幾度も言及されているものの、それ自体として、先決問題として問われてはいないからだ。イメージ、その役割と本性だけがサルトルの関心の対象である。イメージへの賞賛は、134ページで主張されているように、彼を次第に「イメージを心的生の全領域に導入する」ことに──つまり思考・言語・推論・情動・自己意識・創造性等の全領域に導入することに──導いてゆく。先に言及した現象学的な見かけをした数節は、むしろ例外に属する。サルトルの論文の最も際立った特徴のひとつは方法論的な無秩序にあるのであって、本稿ではその非常に限られた概要しか示せないだろう。
先に引用した見かけ上は現象学的な数節に対応して、サルトルは方法に関する一般規則を定めている。事実を優先する、イメージをあるがままに考慮する、というのがそれだが、これはフッサール的な規則と思えるかもしれない──だが、事実を歪めるとか現実を無視するとか称する書き手がどこにいるだろうか。事実への訴えを、コギトや、生体験から流出する自然な光への──現象学における体験(Erleibnisse)を予期させる、デカルト的な「見テイルト私ニ思ワレル(videre videor)」への──訴えと理解してはならない。同時代人たちと同じく、サルトルが探し求めているのは、実験装置由来のものも含め、心理学に研究データを提供しうるあらゆる事実である。ただ、そこから唯物論的・還元主義的な解釈を引き出すことを拒否するのだ。そのため、サルトルは論文中でどんな性質のデータでも大量に収集し、しかも滅多に批判的な距離を取らない。こうして次々に、しかも同じ水準で、サルトルのイメージ論を支える「事実」や証言が登場することになる。心理学者が被験者に自身の体験を質問することで入手した内観データ、回答者の大半がその方向で証言しているからという理由で選ばれた、あれこれの理論に寄った統計データ、幼児に関する行動観察、経験に順応した被験者への質問記録付き実験装置、サルトル自身が行った観察や経験、個人的な記憶、プルースト、ジャック・リヴィエール、スタンダール、さらにはポールとヴィクトール・マルグリット(『ポウム、小さな少年の冒険』)等のテクスト、「読書に由来する心的興奮」(151ページ)に関する実験方法、高等師範学校の同窓であるダニエル・ラガーシュの夢や[レイモン・]アロンの証言、フロイトが分析したイルマの注射の夢が裏付ける圧縮の現象(もっともサルトルはフロイトの教説については批判しているが)、等である。
サルトルは、[それらのデータのなかには]まずく提起されている問いもあること、哲学的前提によって実験装置やその結果の解釈がバイアスで歪められている恐れがあることを充分に意識している。論文中、方法論的批判は極めて巧みに提示されているのだ。だが、自分自身のこととなると、選択可能な様々な方法の間で決め切ろうとはしていない。サルトルは、自分の理論に適合する諸事実を収集することを欲するあまり、ひとつの方法に自らを限定できなかったのだ。たとえば、ヴィルヘルム・ベッツが内観を手立てに獲得した結果とフランシス・アヴェリングが実験を基に得た結果の間の相違を確認しながら、サルトルは恐れることなく次のように結論する。「だが我々はベッツの内観もアヴェリングの実験も間違っていると批判することはできない。私はアヴェリングの実験をやり直してみたが(確かにただひとりの例だが)、結果は彼の実験の全体的路線と合致するものであった」(93ページ)。あまりの素朴さにこれでは困惑してしまいかねない。それというのも、端的に言ってサルトルにとっての問題とは、正しく自己観察すること(221ページ)、「限界まで自己分析する」(109ページ)ことにあるので、その方法が妥当かどうか、分析が完遂されているかをどんな基準が決めるのかまで知る必要はなかったのだ。せいぜいのところ、133ページで彼が「観想的内観」なるものを引き合いに出しているのが知られるが、この方法は、彼がそれから得ているところから判断するかぎり、生体験のなかに現われない諸要素を用いることを観察者に可能にするようだ──ただ、これでは率直に言って、反省についての反省、つまり反省されていないものが反省のなかで、また反省によって歪められることについての反省を行わないので、恣意的な分析に落ち込んでしまう恐れがある。サルトルが望む「限界まで自己分析する」というのでは、あまりに遠くまで行き着き、事実を逸脱してしまう恐れが大きいのだ。
とはいえ、サルトルにも正当な評価を与えねばならない。こうした自由放埓は局所的にのみ容認されているのであって、彼の方法論的立場の全体的路線は明確だ。サルトルが収集する[実験]装置や証言の全体、あるいは事実尊重への訴えといったものは、目には見えず確認もできない、サルトルが「形而上学的」(102ページ)と呼ぶような審級──権利上の推論や心的生の可能性の条件を見極めるという目的のもとで引き合いに出される審級──に依拠した唯心論的・超越論的な諸理論を警戒するためのものなのだ。『自我の超越性』冒頭の、[カントにおける]超越論的なものを「現実化」[16]しようとするフランス哲学の傾向に関するよく知られた論の展開がサルトルの学位論文に登場することはないものの、事実と権利の間の区別は明確な趣旨のもとで既に呈示されている。すなわち、権利上の推論は純粋な事実に場を譲り、実証主義が唯心論に対抗すべきだという趣旨である。そのため、1927年のサルトルはイメージの身体的な「生産の条件」(124ページ)を進んで探求し、フッサールなら自然的態度、心身的因果性、「実在的な」生成と呼ぶであろう地平に意図して身を置いている。サルトルは心理的実証性と身体的実証性の間の相互作用を駆使しているが、それは精神(l’Esprit)や、心的・超越論的な無意識に安易に訴えるのを回避するためである──また、そのような訴えかけの結果として、ある種のフェティッシュを別のフェティッシュに取り換えたり、形而上学的実体・超越論的審級を心的所与とか生物学的所与とか呼ばれるもの(この点には後で立ち返るが)に差し替えたりするのを避けるためなのだ。1933年、サルトルがベルリンに旅立つにあたって[訳註2]、立候補書類の文言に曰く「心的なものと生理的なものの関係一般」[17]の研究を目的にしていたのは、ただアカデミズムの慣例に従ってのことではない。学位論文において、サルトルは哲学者である以上に断乎として心理学者である。そのため彼は、人間個人の身体的・心的な組織に基づいた、自然主義的タイプの精神現象の「諸法則」に訴えるのにも躊躇しない。こうした反現象学的な思考の動きは、1927年の論文の言い方では、「心理学にも生理学にも妥当する[…]一般法則」、つまり、イメージの出現の究極的説明のための鍵となる「代理の法則(loi de suppléance)」に準拠するとき、頂点に達する。不在の対象や不可能な知覚の代理を果たす「志向」があるだけで、あるイメージを身体と精神の協働によって出現させられる、というのだ。この身体と精神の協働において、前者すなわち身体は運動によってイメージの素材を提供し、後者の精神は「特定の運動の精神的綜合」(236ページ)によってこの素材[=質料]に形相とダイナミズムを与える、とされるのである。
III. 身体と精神
サルトルの論文において、方法論的な不安定と交差し重なり合うのが理論的な不安定である。彼は事実に導かれて論を進めると称するが、事実より下位に、あるいは上位に属する説明や基盤にしばしば準拠している。それはたとえば、生物学や心理学からの借用であったり(欲求、傾向性、情念、共感、欲望、嫌悪、生理学的状態、代理の法則……)、場合によっては、形而上学への飛躍──それは精神やその創造の能力・綜合の能力への次第に執拗さを増す訴えを特徴とする──であったりする。単純化して言うなら、『心的生におけるイメージ、役割と本性』は、三つの地平[身体、精神、イメージ]の間で絶えず揺れており、この地平はしばしば二つ組みになって作動しているが、そのうちひとつの地平(これ[=イメージ]には最後に言及しよう)が他の二つの地平の境界面、出会いの場となっている。それでいてこの地平は、表向き、他の二つの地平に由来するものとされるのだ。
1/ 最初の地平は身体である。論文の数節を読むかぎり、すべてはこの身体から出発するように思われるし、なんにせよサルトルはそこから本質的なものを汲み出している。実際、ここには当時のフランス哲学に典型的な生物学的基盤が見出されるのであり、合理論や唯心論を矯正する役割を果たしてくれる。つまり、身体には、イメージの出現を説明するのに寄与する、という役割が与えられている。1927年の論文における人間は、1931年の『真理伝説』[18]においてと同様、世界へ、自らの欲求の充足へと向かう。それは純粋に生物的な欲求だったり、社会や文化によって昇華された欲求だったりするが、この「まず生活せよ(primum vivere)」の原則は、結果として意識についてのプラグマティズム的な概念をもたらす。すなわち意識とは「外界への適応手段である。原始的には、意識のなかには知覚のための場所しか存在せず、知覚に続いてただちに行動が現れる」(156ページ)。
こうした原理はコント、ニーチェ、ジェイムズ、ベルクソン、アランからの借用である。サルトルはそれに基づき、身体の優位を、想像的素材の起源としてではなくとも、少なくともその貯蔵庫として定める。彼が用いる語彙はそのニュアンスが説明されておらず、安定したものに思われないが、イメージは身体の状態、とりわけその運動や情感的状態の「翻訳」(130-131ページ)、「表現」(195ページ)、「心的反応」(129ページ)、「象徴化」(131ページ)と目されている。運動や感情と言うことで、サルトルは身体のダイナミズムに──「イメージ=絵画」説に見られるような惰性的な感覚的痕跡にではなく──訴え、そこからイメージを理解しようと試みる。そのうえでなお、134-135ページでは、身体のダイナミズムがイメージのダイナミズムによって二重化されているが、そこには正確に掴めない点がある。つまり、いくつかの節で示唆されているように(特に238ページで身体の運動が強迫的イメージを惹き起こすとき)、イメージのダイナミズムは身体のダイナミズムによって作られているのか、それとも、他の数多くの節が考えさせるように、イメージのダイナミズムはそれ自体で独自の生命をもち、しかるのちに身体運動を伴わせるのか、という点だ。いずれにせよ、イメージの出現の根底にあるのは我々の身体的生の最も日常的で最も基礎的な骨組みであり、それによって出現したイメージは「特定の生理的状態を冠したもの」(129ページ)、あるいはより大胆な説によれば、我々がそれについて「直接的な意識を」(204ページ)もつことができない自らの身体を認識するための唯一の手段である。
率直に言うと、身体がイメージの領域に移し替えられるプロセスは際立って明晰に記述されているとは言えず、章ごとに、さらには段落ごとに変化している。しかし、サルトルが主張する論の全体的方向性は明快である。イメージに素材を与えるのはとりわけ運動なのだが、これは知的イメージの場合にもあてはまる。サルトルの主たる主張のひとつは、イメージなき思考は存在せず[19]、運動や身体状態なきイメージも存在しない、という点にあるからだ。──たとえ、「イメージと思考」に関する章を読むかぎりでは、思考それ自体がイメージを生み出し、身体の運動がそこに貢献せずとも、思考は目標に到達するためにイメージになる、という印象をはっきり受けるとしても。情感に関しては、サルトルはかなり混乱しているのだが──情感がイメージの素材となるのか動因となるのか、読むかぎり明らかではない──、「どんなイメージも意識にとっては少なくともひとつの情感的状態の翻訳である」ことを確認しておこう。これは「フロイトの仕事から確認すべきであろう点」(131ページ)である。『存在と無』でそうするように、サルトルは精神分析の根本メカニズムを取り込みつつ、フロイトの理論は拒絶している。それはあたかも、身体(1927年)や「意識」(1943年)が無意識に取って代わりうるかのようだ。
2/ 第二の地平は「精神(l’Esprit)」である。サルトルが議論を組み立てるにあたり、精神は、表向き、それが不可欠なものである、というかぎりにおいてしか介入してこない。実際、精神に準拠することで論理が変化してしまうことにサルトルは充分自覚的であるように見える。というのも、精神のアプリオリな法則は、心理学にではなく、実証的探究や事実領域を逃れる前意識的なもの、無意識的なものの領域に属するからだ(63ページ)。精神は、こうした超越的なもの、権利上の実在に我々を向かわせるのだが、それは純粋な「事実」を擁護するためにサルトルが忌避していたはずのものだ。このとき、精神は、意図的に漠然とした、総称的な名称としてしか問題になりえなくなる。この[精神という]名は、それ自体としては確証されえない、ただしその効果からすれば疑いの余地なく存在すると言わざるをえない、何らかの力に与えられるものである。この精神という語を、サルトルが自分の言葉として最初に用いるのは96-97ページのことである。このとき精神の語は、了解という独自の作用──具体的状況、出来事、芸術作品、フレーズに対する了解──に際して生ずる、「生産的思考」や「創造」の同義語として用いられる。了解の例に関して、サルトルが精神を引き合いに出すのは、それが[了解という]作用を認めるものであるから、また、この作用はそれを現実化する感覚的条件や生理的条件に還元されないものだから、である。サルトルは純粋な事実の領域を離れ、形而上学へと飛躍する。それは、事実というものがそれ自体において、心理学的実証性の領野や説明の自然主義的領域を超え出るものだからだ。
こうした[精神の審級を名称としてのみ保持する]慎重さはカントから想を得ている。つまり、不可視にして無意識の超越論的なものは、経験の対象がそれ自体として経験の可能性の条件を指し示す、というかぎりにおいてのみ引き合いに出されねばならないのだ。とはいえ、この超越論的なものに関しては、疑いえないものとしての経験の事実それ自体を理解するために想定する必要がある、ということ以外は何事も言いえない。こうしてサルトルは、純粋な観念作用による理論、たとえば『思考についての試論』のバダルーによる理論[20]を拒否するにあたって、非の打ち所なくカント的な語彙を用いている。
一切の意識の外側にある純粋な思考を想定するこの説は、心理学と称してはいるものの、[…]形而上学だと見なされなければならない。心理学が依拠するのは事実確認であって演繹ではないし、いかなる経験にも対応しない抽象的実体を定立することほど心理学の対象と方法からかけ離れたことはない。(102ページ)
論文の最も長い章、「イメージと思考」(71-164ページ)では、より一般的な仕方で、精神に依拠するのは回避され、せいぜい思考が、身体の情感的状態をイメージの形で翻訳するためのベクトルとして引き合いに出されているに留まる。これは、サルトルによれば「情感と思考は決して切り離されない」(131ページ)だけに、依然として実証的所与の分節作用と見なされうる。
反対に、最終章および結論部では、サルトルが創造的と呼ぶ想像力は──再生感覚を忌避するサルトルにとって、創造的想像力のみが唯一可能な想像力なのだが──精神に帰属させられる。しかもこの主張は、「想像力には形相と質料の創造」(231ページ)があるという中心的命題を強く再説するときに導入されている。こうしてサルトルは、イメージは「記憶の組み合わせ」(231ページ)だとする古典的心理学──彼の見方では、この立場はベルクソンにまで連なる──と手を切る。こうした組み合わせは、件の記憶の保存それ自体が理解不可能なものであるため(それが脳の痕跡というかたちであれ、唯心論者において心的無意識というかたちをとるのであれ)可能ではない。このことを明らかにしてから、サルトルは結論として、依然として慎重さを留めつつも、「イメージとは精神の作用である。精神を抹消すれば、これから我々が解明を試みるように、イメージは運動のなかに消え去ってしまう」(233ページ)と述べている。
また反対に、234-235ページで決定的説明を試みるとき、サルトルはベルクソン主義者たちに批判していた飛躍を自ら行う。確かに、彼は事実の確認、つまり「意識の内部には、外界の対象の代替となる、非代理=表象的個別性の不断の湧出」が存在する、という確認から出発する。イメージはそれ自体として、つまりある綜合の個別的だが代理=表象的ではない産物として尊重されねばならない、と述べるときにも、サルトルは事実の水準に留まっている。諸要素に還元しようとすれば、[綜合としての]イメージは破壊されてしまうのだ。だがどうして、「意識なくしては説明できない」とサルトル自身も判断するところのイメージは、「精神を含意する」のだろうか。どうしてイメージは、意識それ自体の参加に加えて、「形而上学的観念」としての精神を前提するのだろうか。この意識は、既に見たように、非代理=表象的イメージの「不断の湧出」の場だというのに。サルトルの答えは、これまでと同じように、作用の一語でもって済ませられる。「なぜなら、実際、イメージには諸要素と、それに加えて、その諸要素にイメージとしての価値を付与する精神の作用がある」。この説は、ここでの精神がカントの『実践理性批判』における叡智的な自由として解されるなら、受け入れうるものかもしれない。叡智的な自由とは、構想的[=想像的]理性の一種の要請であり、イメージの生産の特徴を十全に説明するために定立せざるをえないものである。ここでイメージとは、身体の運動の能動的綜合であり、かつこの綜合は運動それ自体では説明しえないものであった。だが、サルトルが精神の語を大文字で飾り立てているのを見るにつけ疑わしくもなるように、精神は、カントの枠組みにおいては保持すべきであるはずの禁欲的役割、つまり神秘に名前を与えるための用語としての役割に制限されるままではいられない。「精神は、一切が準拠する最初の要素であって、他のものによっては説明されえない」──これは超越論的統覚に関するカントの説を想起させよう──と彼は述べ、精神が説明不可能であることを理解するために「我々の認識の現状」も引き合いに出すのだが、これはこの不可能性が将来的には取り除きうるのではないかと思わせる。それに実際、サルトルが議論を構築するにあたって精神が第二の地平となるのは、それが議論の構築の外側の境界、イメージの記述がそこにつながるような究極にして内容のない要請であるからだけではない。精神は、自身を特徴づけることにつながるような説明、自らを認識することの原理的な不可能性を無視するような説明を提供するのである。実際、サルトルは精神を我々の創造能力、自由と同一視している──この同一視は、どうしてこの役割が意識という、心理学的であって形而上学的ではない観念それ自体に委ねられていないのか、という問いを引き起こすものだ。だがサルトルはここで二度目の形而上学的飛躍を遂げる。あたかも精神が突如としてアクセス可能なものになったかのように、最終章および結論部では、精神に二つの性質が与えられるのだが、サルトルはどうしてそれを認識しえたのかを説明してくれないのだ。
精神の援用が些末な事柄ではないことの証拠として、第一の性質が1939年の志向性論文では批判されるということが挙げられる[訳註3]。その性質とは、精神は自分以外のものとは関係せず、それが同化しうる諸要素、つまり、心的生の全体と同じ組織で作られているため、精神に抵抗しない諸要素としか関係しないことを要求する、というものである。──同様に、サルトルが結論部で理解する意味でのイメージは、唐突に、もはや形相と質料を自由に創造するものではなくなり、精神の諸期待に従わねばならないものとなる。ここで精神は、「どこからも入り込むことができないイメージ、空気が有機体のなかを循環するようには循環もできず、反抗的で思考不能、消化不能で自律的であるような、知覚の写しとしての堅固なイメージを作ることしかしない」(242ページ)。精神に付与される第二の性質について言うなら、こちらは言うなれば第一の性質と正反対のもので、とはいえこちらもそれ相応の仕方で心的イメージの本性の説明に貢献する。この心的イメージの本性は、究極的には、心的・身体的現象よりも、精神の法則から到来するものである。この第二の性質とは、イメージは常に過去の経験の類似品を探し求め、その経験の代替物を作り上げようとする、というものだ。この代替物は、「対象の再創造」を目指し、「知覚として成就されようとする」(241ページ)。もっとも、言うまでもなくこの目標に辿り着くことはできないが、とはいえ「再構築の不断の試み」が断念されることはない。この試みのなかに、サルトルは、究極的には「我々のイメージが外的に実在するということへの思い込み」の説明、イメージを絵画的なものだと思い込む理由の説明を見ている。それは、イメージを信じ込むことができる、という私たちの「あまりに強い」意志に由来しているのだ……(242ページ)。
3/ 最後の、かなめとなる第三の地平は、イメージそれ自体の地平である。ここで我々は、この地平を彼の理論から取り出し、[他の二つの地平の]境界面としての役割を与えるべく、アンリ・ドラクロワとサルトルの権威に依拠してよかろう。サルトルの論文への書き込みのなかで、アンリ・ドラクロワは彼の理論を「ロマン主義的なもの」(90ページ)と形容していた[21]。ところで、サルトルにとってロマン主義とはイメージに「身体と精神の中間領域」(73ページ)を見出す立場である。これは論文の結論部でサルトルが研究しようとする場、つまり「心理学と生理学の中間領域、一種の辺獄[=天国と地獄の中間]」(235ページ)と言ってよいものだ。我々を生物学的なものへと下降させる身体と、超越論的なものへと連れてゆく精神との合間に、イメージの地平は自らの居場所を定める。というのもサルトルにとって、イメージは事実の地平、内観や実験装置によって明らかにされる意識の諸状態の地平をなすのであって、言い換えるなら、それは心的なものの場そのもの、心理学者に提供される所与であるからだ。そしてサルトルはその場が全面的にイメージによって織りなされていること、それがイメージの巨大な錯綜体に他ならないのだということを証明しようと試みる。たとえば、結論部の次のような驚くべき一節を見られたい。
我々は、外界の対象によく似た対象が展開するような心的空間を構築する傾向にある。イメージとは精神が身体を外界に導くときの方向付けに他ならない。そして、この意味で、心理的生の一切の現象、つまり思考・苦しみ・喜びと言ったものは、イメージの形をとるのである。(242ページ)
この奇妙な「心的空間」は、サルトルが前の箇所で「知的な純粋空間」とか「アプリオリな」ないし「内的な」空間とか呼んでいたものと対をなすものだ(115、133、139、140、178ページ)。サルトルによれば、後者の空間が用いられるのは、空間的イメージによって論理関係を把握しようと試みるときで、この空間的イメージが同じ数だけこの知的な純粋空間の「アプリオリな規定」をなす(115ページ)──このイメージは、不在の対象の代替物ではなく、空間的想像力による純粋な図式であり、サルトルはこれを、ベルクソンに反して、思考の条件と見なし、思考それ自体と同一視さえするのだ。「心的空間」および「知的な純粋空間」によって、サルトルはイメージに関する文献に鏡写しのように現われる二つの実体から守るつもりだった領域を、かえってフェティッシュ化してしまう。ここに言う二つの実体のひとつとは、「イメージ=絵画」説の支持者の生理学的還元主義の源泉となる、原初的感覚という実体である。もうひとつは、ベルクソン主義者や精神分析家たち、そしてカント主義者のような人々、つまり、不可視にして証明不可能な機械仕掛けの神を、あまりに性急にイメージのダイナミックな創造の根底に据えようとする人々によって作り上げられた、精神ないし無意識という形而上学的実体である。
こうして読者は最後になって、学位論文の構造全体が同じフェティッシュ化のプロセスに属しているのではないか、という疑念に導かれることになる。このプロセスは、[余計な仮定を排除する]オッカムの剃刀で切断されるべきものではないか。だが、これがサルトルの論文の内的緊張に関して我々が呈示する最後の例となるのだが、彼自身がいくつかの節では、多かれ少なかれ形而上学的な実体を捏ね上げるのを回避するため、オッカム的矯正を用いることを提案しているのだ。
まず、サルトルのテクストにおいて精神が果たしている役割は、意識が担いうるような役割である。このことは、身体運動の綜合が思考や意識それ自体によって導かれるとするページで確証されている。同じように、別の節によれば、身体や感情そのものについての直接的意識が存在しないとしても、身体イメージや感情イメージの意識は存在する──身体についての意識とイメージはそれ自体で充足しうるものであり、精神に助けを求める必要はないのだ。唯心論的実体を利用するのを避けるためには、なおまた別の解決策も存在する。身体感覚的運動の綜合は、既に見たように、身体と精神にのみ依存するのではない。ある志向、つまり過去の知覚や到達不可能な知覚の代替物を探求することにも依存するのだ──この探求は、[精神でなく]意識にも帰属させうるものだろう。意識の流れは、他の基盤を要求することなく、意識の諸作用の流れとまじりあうのだから。大半の場合、『心的生におけるイメージ、役割と本性』は、意識さえあれば精神抜きで済ませられるのである。
身体に関しては、一読するかぎりでは実定性を凝縮させたもの、還元不可能な所与のように現れる。だが実際には、1927年の論文において、身体はイメージの力能を例証するための、心的空間や知的な純粋空間に必要な支えとしてしか機能していない。「生理的説明は[…]心理的事実の諸要素を与えるに過ぎない。この諸要素の綜合は精神の作用である」(235ページ)。言い換えるなら、身体は初読時にそう思われるような、塊として自足した、フェティッシュ化された実体、一種の有機的で生産的な主体ではない。身体の一貫性は、イメージのために存在する、という点にしかないのだ。身体とは何からなるものか。それは、我々を世界に連れ出し、不在の対象のイメージ化された代替物を探求するときの根底にある、欲求・欲望・情念からなるものである。それはまた、心的イメージに唯一可能な素材を提供する、運動からなるものである。それはまた、最終章最終節で、イメージ的代替物の補足的動因として現われる、情感性や感情からなるものである。情感性を担った経験のみが、その経験の心的な再生をイメージ形式で認識したい、つまり身体運動の精神的綜合の形式で認識したい、という欲望を掻き立てるのだから。逆説的なことだが、身体は、学位論文に終始一貫して現われるものの、最終的には、相互に区切られた階層やダイナミズムに細分化、解体されたものとして現われることになる。その階層やダイナミズムのひとつひとつは、サルトルの議論構成が割り振る特定の役割を演じるのだ──選び抜かれた切り口の総体として、あるいは身体的生の部分的実体をひとつなぎにしたものとして。
身体が、サルトルもしばしば追随してしまう唯心論的飛躍とのバランスをとるために存在するのだとすると、それは自身に固有の割り振りを担っていないことになる。となれば、イメージに[身体とは]別の支えが見つかれば、それによって補われ、取って代わられることもありうる。その証拠に、『イマジネール』の、1927年の論文に最も近い章、つまり第二部「蓋然的なもの」では、その章の第二項および第三項で、情感性と運動が心的イメージのアナロゴンの構成要素として取り上げ直されるのだが、そこにアナロゴンの非身体的な構成素、この場合は知的領域に属す構成素が付け加えられる。つまり、第二部の第一項にあたる「知」と、第四項にあたる「心的イメージにおける言葉の役割」がそれである。この箇所を通して、身体と精神が外見上でしかイメージの還元不可能な二重の基盤にならないことが確認される。1927年には、身体と精神はイメージをめぐる構造の必然的要素の役割を充たしており、そのためこの要素は実体化されていた。とはいえ、こうした要素は、場合によって補われたり、描き直されたり、抹消されたりする可能性がいつでもある。ただ、そのためには、イメージの本性、さらには心的なもの一般の本性が、フッサールおよび現象学との接触によって再定義されるのを待たねばならないだろう。
Notes
-
[1]
Jean-Paul Sartre, « L’image dans la vie psychologique : rôle et nature », Études sartriennes, no 22, sous la direction de Gautier Dassonneville, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 43-246.
-
[2]
刊行以前から草稿を閲覧していた研究者らによる読解としては以下を参照されたい。Alain Flajoliet, La première philosophie de Sartre, Paris, Honoré Champion, 2008, p. 305-532. Frédéric Fruteau de Laclos, La psychologie des philosophes : de Bergson à Vernant, Paris, PUF, 2012, p. 197-224.
-
[3]
Vincent de Coorebyter, Sartre face à la phénoménologie. Autour de “L’intentionnalité” et de “La transcendance de l’Ego”, Bruxelles, Ousia, 2000.
-
[4]
Vincent de Coorebyter, Sartre avant la phénoménologie : autour de « la Nausée » et de la « Légende de la vérité », Bruxelles, Ousia, 2005.
-
[5]
Vincent de Coorebyter, « De Husserl à Sartre. La structure intentionnelle de l’image dans L’Imagination et L’Imaginaire », Methodos [En ligne], 12|2012.
-
[6]
Vincent de Coorebyter, « Sartre romantique : du diplôme sur l’image (1927) à L’Imaginaire (1940) », dans Riccardo Barontini et Julien Lamy (dir.), L’histoire du concept d’imagination en France (1918-2014), Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 97-110.
-
[1]
「大学の文学部における高等教育修了論文を制定する令」(1904年6月18日)からの抜粋。同文は以下で引用されている。Gautier Dassonneville, « Une contribution sartrienne au roman de la psychologie. Le Diplôme sur l’image (1927) », Etudes sartriennes, n° 22, 2018, p. 15, n. 1.
-
[2]
Jean-Paul Sartre, « L’Image dans la vie psychologique : rôle et nature », Etudes sartriennes, n° 22, 2018, p. 43-243. 論文の本文に続いて、『想像力』と『イマジネール』の構想期に書かれた、イメージに関するいくつかの断章が収録されている。その後にも別の重要な未刊行テクスト、つまりサルトルが1924年から1928年にかけて高等師範学校文学部図書館で借りた633冊の書籍の全リストが掲載されている。この二つの未刊行テクストに関して、学術校訂版を担当したゴーティエ・ダッソンヌヴィルが長文の紹介を付している。
-
[3]
Hyppolite Taine, De l’intelligence (1870), Hachette, Paris, s. d. (16e édition), t. I, p. 2.
-
[4]
Ibid., p. 7.
-
[5]
Ibid., p. 18.
-
[訳註1]
ここでreprésentatifの語は「表象」より「代理」の意に重きをおくべきと思われる。というのも、問題になっているのは、心的イメージがタブローのように現実の対象の代理としての役割を果たしてしまうことだからである。代理物としてのイメージは、心的生の内部の「物」として、「内在性の錯覚」を涵養するが、この点に『イマジネール』のサルトルは反論する。このように理解すれば、心的イメージの代理=表象的な性格に反駁するという論点が「サルトルの読者にはよく知られた主張である」という次段落の記述も理解しやすい。逆に、サルトルはイメージの表象的性格まで否定するわけではない。それはコールビテールも後段で「イメージは志向的であり、表象された対象それ自体を狙うことに役立つ[…]のだから、明らかに表象的(représentatif)なものなのだ」と記述していることから明らかだろう。
-
[6]
Jean-Paul Sartre, L’Imaginaire (1940), Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1994, p. 17(ジャン=ポール・サルトル『イマジネール』澤田直訳、講談社学術文庫、2020年、38ページ). 旧訳では「内在幻想」と訳されていたもの。
-
[7]
よく知られた論文、「フッサール現象学の根本的理念」を参照。〔『哲学・言語論集』白井健三郎訳、人文書院、2001年、15-19ページ。〕
-
[8]
Cf. Alain, Système des Beaux-Arts (1926), Note II, « Sur les images » (Paris, Gallimard, « Tel », 1991, p. 345).
-
[9]
Jean-Paul Sartre, La Nausée, dans Œuvres romanesques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1981, p. 114(『嘔吐』鈴木道彦訳、人文書院、2010年、161ページ。翻訳を参照しつつ文意に合わせて訳した).
-
[10]
この綴り(Hüsserl)はタイプ原稿から確認されている。
-
[11]
この説はフレデリック・フルトー・ド・ラクロによって以下の論文で主張されている。Frédéric Fruteau de Laclos, « Structure intentionnelle de l’image ou construction de l’imaginaire ? Sartre face à Malrieu – et à lui-même », dans Riccardo Barontini et Julien Lamy (dir.), L’Histoire du concept d’imagination en France, de 1918 à nos jours, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 111-123.
-
[12]
Cf. Henri Piéron, « Recherches comparatives sur la mémoire des formes et celle des chiffres », L’Année psychologique, vol. 21, 1914, p. 119-148.
-
[13]
L’Imaginaire, op. cit., p. 22-30(『イマジネール』前掲書、45-53ページ).
-
[14]
Ibid., p. 30-35(同書、53-60ページ).
-
[15]
カントの有名なマルクス・ヘルツ宛書簡(1772年2月21日)参照。「我々の内なる代理=表象と呼ばれるものと、対象との関係は、どこに基礎づけられるのでしょうか」
-
[16]
Cf. Jean-Paul Sartre, La Transcendance de l’Ego et autres textes phénoménologiques, textes introduits et commentés par V. de Coorebyter, Paris, Vrin, « Textes & Commentaires », 2003, p. 94.
-
[訳註2]
1933年、先にベルリンに留学していたレイモン・アロンから現象学を紹介されたサルトルは、ただちにベルリンに一年間留学することを決め、フッサールの著作を熟読した。
-
[17]
Cf. Annie Cohen-Solal, Sartre, 1905-1980, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1989, p. 182.
-
[18]
Cf. Jean-Paul Sartre, « Légende de la vérité », paru dans la revue Bifur en 1931 et repris dans Michel Contat et Michel Rybalka, Les Ecrits de Sartre. Chronologie, bibliographie commentée, Paris, Gallimard, 1970, p. 531-545, ainsi que « Fragments posthumes de la Légende de la vérité », dans Juliette Simont (dir.), Ecrits posthumes de Sartre, II, Paris, Vrin, 2001, p. 27-57.
-
[19]
これは『言語と思考』(パリ、アルカン社、1924年)におけるアンリ・ドラクロワの主張、すなわち「言語なき思考は存在しない」という主張を引き継ぎ、よりラディカルなものとする立場である。
-
[20]
Cf. Dan Badareu, Essai sur la pensée, Jassy, Editions de l’Opinia, 1924. (他の場合と同様、この出典指示はサルトルによる論文の校訂版におけるゴーティエ・ダッソンヌヴィルに負う。)
-
[訳註3]
「フッサール現象学の根本的理念:志向性」(1939年)においては、意識はつねに自らではないものを目指す、という点が強調されている。
-
[21]
この書き込みについては以下の論文で検討した。« Sartre romantique : du diplôme sur l’image (1927) à L’Imaginaire (1940) », publié dans Riccardo Barontini et Julien Lamy (dir.), L’Histoire du concept d’imagination en France, de 1918 à nos jours, Paris, Éditions Classiques Garnier, 2018, p. 97-110.
この記事を引用する
ヴァンサン・ド・コールビテール「イメージ、身体と精神の間で——サルトルの高等教育修了論文」 関 大聡 訳、 『Résonances』第11号、2020年、38-57ページ、URL : https://resonances.jp/11/le-memoire-de-sartre/。(2025年07月04日閲覧)