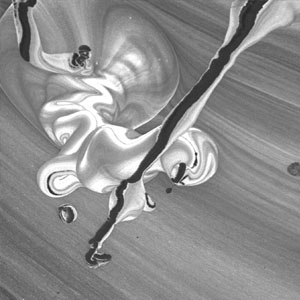宗教事象とライシテフランスの公教育における宗教的なものへのアプローチ
はじめに
2002年、哲学者のレジス・ドゥブレが「ライック[1]な学校における宗教事象教育(l’enseignement du fait religieux dans l’École laïque)」に関する報告書(以下、ドゥブレ報告書)を国民教育省に提出した。以降、フランスの公教育カリキュラムには宗教事象教育が導入され、今日に至っている。
宗教事象教育という言葉は日本ではあまり聞き慣れないかもしれない。これは宗教学の分析概念として定着している宗教知識教育に分類されるもので、特定の宗教・信条の立場に依拠せず、科学的知見に基づいて諸宗教に関する知識の習得を目的とする教育である[2]。独立した教科はなく、歴史、文学、哲学など、中等教育課程の複数の科目を通して宗教的知識を身につける宗教事象教育は、いわばフランス式の宗教知識教育である。ここであえてフランス式と付け加えているのは、「宗教事象(fait religieux)」が共和国の国是であるライシテ(laïcité)との関係のなかで選ばれた用語であると言っても過言ではないからだ[3]。ライシテとは、共和国憲法の第一条にも記載されている国家の非宗教性ないし政教分離の原則のことで、より広くは宗教的なものと政治的なもの(ひいては公的なもの)の関係を表す意味でも使われる。そして、学校はその主戦場である。
本稿はドゥブレ報告書に至るまでの、公教育における宗教的知識をめぐる議論の過程に注目するものである。当時の争点や実際に導入されたカリキュラム、今日的課題に関してはすでにフランスで豊富な研究の蓄積があるが[4]、それらを踏まえた上で問うのは、フランスの宗教知識教育はなぜ「宗教事象」の教育でなければならなかったのかということである。ヨーロッパの国々では公立学校で宗教教育を行うことが珍しくないが、「宗教事象教育」と銘打った教育を行っているのはフランスだけである。本論文はこうした言葉の選択を切り口として、主に1980年代から1990年代にかけて発表された、政府や教育省への提言、報道記事、シンポジウムの報告書などを通して、「宗教事象」がどのような文脈で選ばれ、その過程で何が退けられたのかを論じていく。そして同時期に、北東部アルザス=モゼルの公立学校において実施が検討されていたculture religieuse[5]の教育に関する議論も参照することで、フランスの選択を際立たせることができるだろう。
宗教的知識の教育の必要性が教育界と学術界で認識されたのは1980年代のことである。本稿は、教育連盟(la Ligue de l’enseignement)が表した、若者の宗教的無教養に対する危機感を出発点とし、その対策として当初は歴史的アプローチが注目されたことを見ていく。次に、フランスの文脈におけるcultureの語を分析し、「教養」を意味するはずのこの言葉が、宗教知識教育を表すには相応しくないとされた理由、そしてこれがアルザス=モゼルでは受け入れられた背景を検討する。最後に、1989年のスカーフ事件の影響とライシテの変容を踏まえ、「宗教事象」はライシテの再定義の文脈で採用された概念であることを明らかにしていく。
I. 文化的遺産としての宗教の危機
ドゥブレ報告書は現在の公教育カリキュラムで導入されている宗教事象教育の出発点であり、20年近くにわたる議論の着地点である。事の発端には、教育連盟が示した、中高生の宗教的教養の欠如に対する危機感があったのだが、1980年代の学校教育でなぜこのような問題が浮上したのか。何が争点となったのか。本章では、20世紀後半における宗教的・文化的遺産と若者の関係の変化から、歴史学者のフィリップ・ジュタールが1989年に国民教育省に提出した報告書までの流れを中心に検討する。
I-1. 教育連盟の警鐘—若者の宗教的教養の欠如
1982年、教育連盟はその年次大会で「主要な宗教の創始に関わる原典や神話の学習、それらの歴史、文明の発展への正負の寄与」について学校で学習する必要性を訴えた。この教育連盟は1866年に教育活動家のジャン・マセによって創設され、無償でライックな公立学校を支持し、公立学校の脱宗教化=ライシテ化[6]を後押しした組織だが、およそ100年後「今度は宗教を学校に呼び戻そうとした」[7]。
同様の声は教育界からもあがる。現場の教員や校長、視学官らは中高生の宗教的教養の深刻な欠如に対して警鐘を鳴らした。宗教的な知識が不足しているということは、文学作品や歴史的出来事、芸術作品を読み解くための最低限の指標を持ち合わせていないということである。フランスおよび西洋の芸術や文学など、文化的遺産と称されるものの多くはユダヤ=キリスト教的世界観を土台としている。フランスを代表する思想家や文豪の作品の読解、宗教改革やフランス革命の歴史的意義の理解にはユダヤ教やキリスト教の知識が欠かせないが、多くの生徒がそれを持ち合わせていない実態に教育現場は危機感を覚えたのだった。ある高校の教員は「クラスの半数の生徒にとってイースターやペンテコステ、受胎告知、主の昇天、聖母の被昇天は理解不能か何の意味も持たないかで、恵みや罪、三位一体などについてはもはや尋ねるまでもない」と、実情を明かしている[8]。
それまで宗教に関する知識が公教育のプログラムで全く扱われていなかったのかというと、そのようなことはなく、文学作品や歴史、古典語(ラテン語、ギリシャ語)などの学習には宗教的なものがたしかに含まれていたが、教員が宗教的な主題を把握していなかったり、駆け足で済ませられたりすることも珍しくなかった。宗教的な知の基盤が揺らいだ背景には、1960年代以降、理系の科目を重視したカリキュラム編成が行われたこと[9]、宗教の社会的影響力の低下など複合的な要因があるが、20世紀半ば以降に起こった重要な変化として、社会の世俗化にともない、家庭内における宗教的実践が衰退したことがあげられる。そして、伝統宗教に関心を持たなくなった親は子どもを教会に行かせなくなったのである。
宗教社会学者のダニエル・エルヴュ=レジェは『記憶のための宗教』(La religion pour mémoire)で、宗教実践を継承する家庭の機能低下を記憶との関係の中で論じている。「伝統、すなわち一筋の信仰の系譜を、宗教に関する問題の中心に据えると、その行末は直ちに集合的記憶の問題と結びつけられる」と考えるエルヴュ=レジェは、家庭における宗教的継承の断絶が記憶の伝達に決定的な影響をもたらしたと分析している[10]。従来、宗教的な実践や伝統が次の代に伝えられるとき、そこには社会全体で共有された、過去と未来をつなぐ記憶、すなわち宗教に関する体系的な知識も伴っていた。ところが家庭で宗教的伝統が引き継がれなくなると、ユダヤ=キリスト教的文化と次の世代との関係は途絶えてしまう。こうして教会に通うことで自然と身についていた経験的な知識はアクセス不能なものとなり、それを補填する場はなかったのである。歴史学者のフィリップ・ジュタールによれば、宗教に関する知の喪失はフランス人の「集合的記憶の大部分が脅威にさらされる」[11]ことを意味していた。
I-2. 「諸宗教の歴史」に集まる注目—宗教的知識に特化した科目は必要か
1980年代後半になると、専門家の間の議論では歴史の科目に注目が集まり、諸宗教に関する歴史(histoire des religions)に特化した科目を設けるべきか否かという議論が浮上する。記憶の問題と直接的に結びつく科目といえば歴史であるし、諸宗教の始まりや歴史的事件に対する宗教の影響を学べる上、既存のカリキュラムで対応が可能な点から期待されたのだった。そのような機運のなか、上述のジュタールは1989年、リオネル・ジョスパン国民教育大臣(当時)の要請で「歴史、地理、および社会科学の教育に関する考察を目的とする報告書」(以下、ジュタール報告書)を提出し、1991年には、この報告書を主題とした大規模なシンポジウムがブザンソンで開催された[12]。
このイベントには「ライックな手法で諸宗教の歴史を教授すること」という題目が付され、授業の名称、独立した科目の有無、教員の養成や方法論、フランスおよび諸外国の宗教知識教育の歴史と現状などをテーマにした四つの分科会を通して網羅的な議論が行われた。なかでも大きな争点となったのは先述の通り「諸宗教の歴史」の科目を設けるか否かという点である。このシンポジウム以前にも、宗教的知識に特化した科目の設置には賛否両論あったが、その開設にはいかなる争点があったのか。
たとえば、キリスト者を表明している教育哲学者のギー・コックは、宗教は歴史の専売特許ではないとして科目の創設には反対した。コックによれば、単一のアプローチに偏ることによって宗教のイメージに歪みが生じかねない事態になるよりは、たとえアプローチに統一感がなくても、複数の科目に宗教事象を分散させる方が適当な選択だった[13]。また、歴史的アプローチへの偏りは、宗教をもっぱら過去の事柄に限定させてしまい、現代社会と宗教の関係について学習する機会がないというデメリットがあった。
一方、ライシテの観点から懸念されていたのは、宗教知識教育の名のもとに宗派的な宗教教育が行われることである。哲学者のカトリーヌ・キンツレーのようにライックな学校を厳に守ろうとする立場の識者は、たとえ「歴史」という形であれ、19世紀末に公教育から排除されたカトリックの教理教育が「トロイの木馬」のように再び学校に戻ってくることに危機感を抱いた。
他方で、ライシテ研究の第一人者であるジャン・ボベロやイスラーム研究の権威として知られるムハンマド・アルクーンは、諸宗教の歴史に特化した科目の設置を支持していた。ボベロは、近代公教育とライシテがフランスで確立した後、「二つのフランスの闘い」[14]の一方を代表したカトリシズムが宗教の代表的存在となってしまい、結果として宗教的少数派の存在を考慮した、真に多元的な文化は築かれなかったと指摘する。したがってボベロによれば、諸宗教の歴史に関する授業の導入は学校を宗教的多元性に開かれた場にすることを可能にするし、それは現代の民主主義社会にとって必要なことだった。そして宗派的な宗教教育の入る余地もなく、ライシテを遵守する宗教知識教育を実施するには、社会学的な知見に基づいた一つの科目を設けることで適切に運営されると提言したのである[15]。当初、宗教知識教育は主にナショナルな文化的遺産の記憶との関わりのなかで検討されていたが、ボベロが示すように、多元性を考慮した宗教知識教育の課題もあったことがわかる。
最終的にジュタールは、ブザンソンのシンポジウムでの報告を踏まえ、宗教に特化した科目を設置する案を退けて、中等教育課程の既存の科目で宗教的な現象をより強調することを提案した[16]。ここにおいて、複数の科目で宗教事象を教える「宗教事象教育」の青写真ができたといえよう。
1980年代、若者の宗教的知識の欠如の問題は教育現場を困惑させ、文化的遺産の危機として認識された。学校は失われつつあった宗教的知識を教会や家庭の代わりに取り戻す場だった。しかし知識という形であっても、19世紀末のフェリー法でカリキュラムをライシテ化したフランスの公教育で、宗教的な事柄を積極的に学習することには少なからず慎重さが求められた。すなわち何をどのように学ぶかという問題に加えて、フランスの場合、客観的な知識としての宗教をどのような概念で表すかという問題があった。
II. 包括的な概念を求めて—cultureの場合
フランスの公教育で宗教的知識を教授するにあたり、方法論や内容の他に論争となったのがこの教育の名称である。教養の不足が問題なのであれば、宗教的教養を身につけるための教育が必要であるという議論になることを想像するが、宗教知識教育の名称に「教養」を意味するcultureを使うことにためらいを覚えた専門家は少なくない。本章ではこのcultureの多義性に注目し、いかなる点でcultureがライックな教育に相応しくないとみなされたのか、その一方で、公立学校で宗教教育が実施されているアルザス=モゼルではなぜこれが評価されたのかについて検討していく。
II-1. 多義的なculture religieuse
宗教的な知識が欠如している状態のことをフランス語ではinculture religieuseと言う。このincultureは「無知」あるいは「教養がない」と訳される。一方でドイツ語のKulturに由来するcultureは、「教養」「文化」「涵養」などの意味を持っており、教育の文脈におけるこの多義性はしばしば指摘されている[17]。これらは互いに意味が重なるところがありつつも同義ではないため、同じ単語でも日本語で考える場合は文脈から読み解く必要がある。そしてこの区別は、フランスの宗教と教育の問題を理解する上で重要なものとなるのである。
レジス・ドゥブレは、公教育で行うのはculture religieuseの教育ではないことを報告書の提出後に念押ししていた[18]。こう付言する必要があるのは、そのように捉えられてはいけない理由があるからであり、ここには「culture=文化/教養/涵養」と「religieuse=宗教的」が組み合わさった時に帯びるニュアンスの問題と、ライシテの原則を有するフランス特有の理由がある。以下ではフランス語のcultureの意味を確認し、これが「宗教的」と形容された際のニュアンスの違いを分析する。
まずは辞書における意味から確認していこう。代表的なフランス語辞典のラルース(オンライン)と『プチ・ロベール』を見ると、cultureとは「知的訓練によって精神を豊かにすること」「特定分野の知識」「批判的思考、審美眼、判断力を発達させるための体系的な知識」とある[19]。その対義語には「無知」や「無教養」が記載されていることから、日本語の「教養」に該当すると考えて差し支えない。この意味のcultureであれば、宗教的と形容されても宗教に関する教養だと理解できるため、公教育で行う上での中立性は担保されるだろう。
次に「文化」の意味に該当する項目をフランス語辞典で見ると「ある民族集団、国民、文明を特徴づけ、他のグループや国民と区別する物質的ないしイデオロギー的事象の総体」とあり、これは「人間行動の様式(型)および意味づけの象徴体系」[20]と規定している社会科学の定義にも通ずるものである。ただし、宗教は「人間の営みであるかぎりにおいて文化の1領域もしくは1側面をなすもの」[21]であることから、宗教と文化は厳然たるかたちで分化しきれない。ではフランス語で「宗教(的)文化」と言うとどのようなニュアンスを帯びるのか。
前節でも参照したエルヴュ=レジェは、『カトリシズム—ひとつの世界の終焉』(Catholicisme, la fin d’un monde)のなかで、カトリック的伝統との結びつきが強いフランスで「宗教文化の喪失」に言及すると、カトリック的伝統の記憶の伝達に問題が生じていることを連想させると述べている[22]。すなわち、この言葉には集合的記憶が失われることに対する危機感が含まれており、宗教というよりも文化的アイデンティティの問題に関わる。そしてこれを強調することは、個々人の信条を問わず、歴史的に継承されてきたある種のフランス性(francitude)をすべての人が共有していると自明視することになる[23]。フランスにおける宗教文化は、歴史的に(支配的だった時期が長くても)カトリックに限定されるものではないし、今日であればなおのこと多様化している。同様に宗教社会学者のミレイユ・エスティヴァレーズも、「宗教文化」には、宗教はフランスの文化の中に浸透しているのだから、生徒はそれを読み解けて当然であり、そこに価値を見出すことまでもほのめかす語感があると指摘する[24]。生徒たちのバックグラウンドを考慮し、宗教に関して彼らが客観的かつ批判的に考えるための教育を行うには、語感から誘導される価値判断は可能なかぎり排除されている必要があった[25]。
最後に、cultureには一義的に「土地の耕作」の意味があるが、これが転じて「心を耕し養うこと」、すなわち「修養」や「涵養」を意味することもある[26]。ライックな公教育の性質を踏まえた時に問題となるのはこの意味である。なぜなら受け手によっては、culture religieuseが「信仰心の涵養」にも聞こえるからだ。教育社会学者のジャクリーヌ・ゴトゥランによれば、culture religieuseは「信仰への目覚め(éveil à la foi)」、「宗教的感性への手引き(initiation à la sensibilité religieuse)」と並んで、カテキスム的な教育(つまりは宗派的な宗教教育)になりかねない意味合いを含んでいる。そのような教育は、宗教の「特異な経験だけでなく、信徒共同体への参入の呼びかけ」にもなり、生徒の良心の自由を十分に保障することができない[27]。したがってこの表現を冠した教育は文化的中立性を担保できないだけでなく、ライシテにも抵触するのではないかという警戒がつきまとうことになる。
II-2. 宗派的宗教教育からculture religieuseの教育へ
他方で、地方に目を向けると、多義的なculture religieuseが好都合な場合もあることがわかる。北東部のアルザス=モゼルである。本節ではその用法を見る前に、宗教と教育に関するこの地域の事情を概観する。アルザス=ロレーヌの名称でも知られるこの地域は、19世紀後半から20世紀半ばまで、独仏の領土争いの標的となり、帰属が変わったことで地域固有の制度が形成された。そのひとつが宗教と教育に関する制度で、代表的なのは19世紀初頭にナポレオンが締結したコンコルダートと独仏両時代の公教育法である。これらが今日も依然として効力を持っているため、この地域では公認宗派のカトリック、プロテスタント(ルター派、カルヴァン派)、ユダヤ教の宗教教育が公立学校で実施されている[28]。つまり国家と諸教会の分離を定めた1905年法が適用されていないのである。
この宗教教育は、伝統的に、一つの宗派の視点から教授される信仰教育(宗派的宗教教育)だったが、1960年代以降、こうした形式の宗教教育は壁にぶつかるようになる。I章で触れたように、背景には宗教の社会的影響力の低下と、人々の日常生活から宗教実践が後退したことがあった。そしてこのような宗教離れは宗教教育の受講者数の減少をもたらした。特に著しい変化があったのは中等教育課程で、その数字を見てみると、1977年に中等課程全体で55%だった受講率が、1997年には34%にまで落ち込んでいる[29]。宗教教育が選択必修科目である初等教育課程と異なり、中等教育課程では選択科目であるため、カリキュラムの負担の観点からも宗教教育は敬遠された。この状況に、宗教教育を管轄するカトリックやプロテスタントの代表機関は少なからず危機感を覚えた。
宗教教育に対する危機感が募っていた時期は、国内で宗教的無教養の問題が議論されていた時期と重なっている。当時のアルザス=モゼルは、宗教教育の受講者数の減少のほか、国内の他の地域同様、中高生の宗教的知識の欠如と、増加しつつあったムスリム人口への対応という三つの課題に直面していた。特に最後の点に関しては、制度的な限界を越える必要があった。この地域で宗教教育を開講できるのは基本的に公認宗派のみであるため、イスラーム教の代表者は不満を覚え、他の公認宗派に認められているような宗教教育の設置を希望していたのである[30]。コンコルダートとの結びつきが強い初等教育課程でこの要望を実現することは容易ではなかったが、中等教育課程にはそのような制限がなかったため、既存の宗派的な宗教教育とは別に、イスラーム教をはじめ他の宗教も扱える新しい宗教教育の設置が検討されたのだった。
II-3. アルザス=モゼルにおけるculture religieuseの意味
国内の教育的課題と地域の事情に対処するため、1990年代以降、アルザス=モゼルの宗教教育は再編成に向けて議論が重ねられる。そしてその過程で注目されたのは「諸宗教の歴史」でも「宗教事象」でもなくculture religieuseだった。国内の議論では退けられたculture religieuseが、なぜアルザス=モゼルでは採用されたのだろうか。
先述のとおり、フランス語のcultureは、文化、教養、涵養の意味を持つ多義的な言葉であり、「宗教的」と形容すると文脈によって意味が変わるため、日本語で考える際は訳しわける必要がある。ただし以下で見ていくように、アルザス=モゼルの事例は三つの意味が混在する文脈であるため、一つの訳を充てるのが容易ではない。したがって本節では補足を加えながらフランス語表記のまま議論を進めていく。
ジュタール報告書を踏まえたシンポジウムがブザンソンで開催された1991年、アルザスのストラスブールではculture religieuseの教育に関する国際シンポジウムが行われた。この場を取り仕切った宗教法を専門とするフランシス・メスネルは、アルザス=モゼルの中等教育過程で実施するべき新しい宗教教育は、culture religieuseの教育になると述べている。メスネルによれば、「宗派的な宗教教育」と「諸宗教の歴史」をめぐる当時の国内の議論は、歴史的にフランスで展開されてきた「宗教」と「ライシテ」の対立、言い換えれば「二つのフランスの闘い」の再燃に映った。一方でculture religieuseの教育というアプローチであれば、その二項対立にとらわれず、さまざまな事象を包括的に学習できる点で妥当な選択だった[31]。つまりculture religieuseは、ライックな宗教知識教育との差別化を図るために選ばれたということができるが、宗教に関わる事柄を幅広く扱うことを前提としているため、これは宗教文化、宗教的教養の両方の意味で捉えられなくもない。そこで1999年に行われたルター派およびカルヴァン派[32]の総会で提案された定義を見ながら、もう少し踏み込んでこの意味について考えてみたい。
両プロテスタント教会によれば「culture religieuseの教育とは、教区主導のカテキスム(キリスト教の教理教育)とも、単なる歴史の教育とも一線を画すものである。それは他の教員や教科との対話のなかで行われ、知識を提供するものである。同時にこれは一人の証人として話す教員が担当する。そこでは宗教への勧誘は一切なく、多様な信仰のあり方が尊重される。」[33]
宗派教育と歴史の教育が言及されていることから、この定義は国内で進行していた宗教知識教育の議論を踏まえたものと考えられる。そしてculture religieuseの教育を行うことは「他の一連の教科の中に宗教を組み込むことを意味する」とあるが、ここで言われる他の教科とは、言い換えれば「ライックな科目」である。この一文は、新たな宗教教育と他の教科(文学、歴史など)とは互いに隔絶されたものではなく、「知識を提供する」点において相互補完的な関係にあることを示唆している。これはある意味で、従来の宗派教育を脱宗教化するような意図が垣間見える表現であると受け止めることもでき、この文脈においてはculture religieuseを宗教的教養と訳しても差し支えないだろう。
一方で「宗教文化」としてのculture religieuseに関してはどうだろうか。上記の定義は「多様な信仰のあり方」にも言及しているが、これは他者の文化に根ざす宗教も含む表現であり、イスラーム教の存在を意識した表現であることは想像に難くない。このような読み方をすればculture religieuseを「宗教文化」の意味で理解することも可能であり、異文化理解のための教育という名目も成り立つ[34]。
最後に、上記の定義で見落とせないのは、culture religieuseの教育を行う教員が信仰の「証人」として教壇に立つことである。布教活動のような積極的に勧誘を行わないとはいえ、「信仰心の涵養」の目的が見え隠れしていると、ライシテを厳に守ろうとする立場からの批判が聞こえてきそうだが、この新しい宗教教育はライックであることを目指してはいない。あくまで「宗派的な〔教育を行うという〕性格を持つ学校の規定を遵守」[35]する前提があり、この点が揺らぐことはないのである。この文脈ではむしろ、教員が一人の証人として、多様なバックグラウンドを持つ生徒と対話を行うことを肯定的に捉えているところもあるだろう。このような意味のculture religieuseに主軸を置いた教育は、1990年代後半から試験的に導入され、今日まで実施されている。
Cultureは、教養という包括的で一般的な意味を持っているにもかかわらず、「宗教的」と形容することで公教育に適さない語感を帯びるのはフランス特有の事情だろう。他方でアルザス=モゼルの宗教教育では、culture religieuseの内包する三つの意味それぞれが有効である。もともと公立学校に宗教の科目があることや、ライシテの遵守が必ずしも至上命令ではないことが、この言葉の選択を可能にしたと考えられる。このような比較から、宗教事象教育に至るまでの議論がいかにライシテを中心に検討されていたかがわかるだろう。多義的で曖昧な概念は中立性やライシテの観点から退けられてしかるべきもので、それはスカーフ事件を経た後のフランスであればなおのことだった。
III. ライシテの再定義の流れのなかにあった「宗教事象」という選択
90年代に入ると宗教事象に対する関心が高まるが、その動向を検討する前に、80年代には異なる文化や宗教的他者の理解に関する議論があったことにも触れておく必要があるだろう。ここで他者として想定されているのは移民の増加とともに定着しつつあったイスラーム教である。本章ではまず、公教育のカリキュラムで他者の宗教を学ぶ意義が80年代に検討されていたことを見ていく。そして1989年のスカーフ事件がライシテの議論にもたらした影響について触れた後、宗教を「事象」として扱うことがフランスの公教育に適しているという着地点に至った理由を検討する。
III-1. 文化的他者との共生に向けた教育
周知のように「栄光の30年」と呼ばれる高度経済成長期の間、フランスは旧植民地の北アフリカから大量の労働者を受け入れた。1973年のオイルショックを機にその勢いが減速すると、以降は移民の流入ではなくフランスへの定着が促される。70年代後半は政府の後押しもあり、労働者は家族を呼び寄せたが、彼らの多くはムスリムで、フランスにとってイスラーム教は他者の宗教だった。そこで課題となったのが彼らの「統合」であり、これは1980年代以降の政治的スローガンとなる。
このような新しい文化的他者との共生に直面する教育は大きく見直される必要があり、政府は専門家に提言を求めた[36]。なかでも重要な指摘は、1985年にピエール・ブルデューを中心としたコレージュ・ド・フランス教授団からフランソワ・ミッテラン大統領(当時)に提出された「未来の教育のための提言」(以下、「提言」)にある。題に提言とあるが、邦訳を務めた堀尾輝久によれば、これは「現実の問題点の分析と未来のあるべき学術・教育・教養についての考え方の原則的な視点をまとめたもの」[37]である。したがって宗教的知識の教育と直接的に関係する文書ではないが、先述のジュタールは、自身の報告書は「提言」の示した見通しに基づいており、それを一つの具体的実践に移すものであったと哲学者のフィリップ・ゴダンに明かしているため[38]、ここには連続性があると考えられる。
他者の宗教について、「提言」で多くは論じられていないが、学校が新たな他者との共生を促す場としての機能を持つべきであるとの指摘は見られる。学校では「別の文化の形態を理解し受け容れるのに必要な手段(哲学、言語学、民族学、歴史学、また社会学が提供する諸手段)が念入りに準備」されなければならず、そのような「開かれた学校」は「古くからの居住者と新たな移住者」との「出会いの場」となることが期待されている[39]。この新たな移住者とは無論、移民のことである。
さらに「提言」は次のように続ける。「すでに小学校から、子どもに、(身体技法や衣、食、住における)習慣の多様性や思考システムの多様性を受け入れることに慣れさせるような地理学的、民族誌学的な要素を導入し」、教育は「科学がめざすものに内在する理性の普遍主義と、歴史諸科学の教える文化的な知恵と感性の多様性に注意を向ける相対主義とをあわせ持つものでなければならない。」[40]ここで、衣食住の習慣に関する多様性を受け入れること、科学に基づく普遍主義と文化的多様性を考慮する相対主義に言及されていることに注意したい。宗教はこうした多様性のなかに含まれるものであり、客観的な事象、知の対象として理解されるべきものだろう。ところが仮に知の対象となることが可能であっても、それを理性に基づいて多様性として受け入れられるかどうかということは全く別問題であることが1989年のスカーフ事件と、これに続くライシテをめぐる論争によって明らかになる。そして「衣」の習慣にあたるスカーフの着用に対して教育界も学術界も大きく賛否が分かれ、その論争のなかで教育とライシテの関係は大きく再編成される。
III-2. スカーフ事件で露呈した矛盾
スカーフ事件とは1989年9月の新学期、パリ郊外クレイユ市の中学校で、三人のムスリム女子生徒が教室でスカーフを外さなかったことが理由で退学処分になった出来事である[41]。この一件について、リオネル・ジョスパン教育相(当時)は、コンセイユ・デタ[42]の意見に基づき、公的機関としての学校の秩序に混乱を生じさせないかぎり「生徒たちによる宗教的標章の着用は、それ自体ライシテの原則と相容れないことはない」[43]と、少女たちの宗教的自由を尊重する趣旨の通達を発表した。しかし、ほどなくしてアラン・フィンケルクロート、エリザベート・バダンテール、レジス・ドゥブレなど、左派を代表する知識人は、この通達に対する反論を雑誌『ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール』に発表した。記事は「教師たちよ、妥協してはならない!」と題され、ジョスパンが擁護した「すべての子どもを受け入れる」場としての学校では、子どもたちが「親の宗教をそのまま学校に持ち込んでくること」までも容認されていないと主張し、公立学校でのスカーフの着用に強く反対した[44]。これはいわゆる「(宗教に対して)戦闘的なライシテ」と呼ばれるものであり、記事のなかでも支持されている姿勢である。
スカーフに対するこのような拒否反応は、端的にいえばコミュノタリスム/共同体主義[45]や多文化主義への警戒であり、フランスが標榜する共和主義の限界を表している。憲法学者の山元一の言葉を借りれば「〈フランス共和主義〉の基本的な発想」において、市民は「いわば一旦〈裸〉になり、全ての属性をかっこに入れて市民社会の一員とならなければ真の自律性を獲得できない」[46]。この市民を育成し、共和国のもとに統合していく装置が公立学校であることから、マイノリティのアイデンティティに根ざした要求や、文化的差異を容認する多文化主義的考え方は原理的に共和主義と対立せざるをえない。「戦闘的なライシテ」を支持する知識人にとって、スカーフの着用は、共和国の価値を尊重する市民から構成される社会と、その市民を育成する学校の根幹を脅かす問題だった。この事件以降、公的空間としての学校の中立性を重視し、宗教的アイデンティティの表出を認めない厳格なライシテと、多様な文化的背景をもつ生徒に配慮し、宗教的多元性を尊重する妥協的なライシテという図式が生まれたのである[47]。そして社会の機運はスカーフ着用を禁止する方向へと向かい、2004年、宗教的標章の着用を禁止する法が制定される。
このスカーフ事件を、宗教的知識の教育をめぐる議論の文脈に位置づけてみると、コレージュ・ド・フランス教授団による「提言」で推奨された移民との共生のための教育は一つの難題に直面することがわかる。宗教とライシテをめぐる言論空間に、帰属としての宗教(ここではスカーフ)は排除し、知識としての宗教は積極的に取り入れるという、一見すると相反する動きが同時に生じたからである。
III-3. 「宗教事象」という着地点
ジュタールは1991年のシンポジウムの結論で「他者性」や「異なるもの」への接近を可能にするライシテの可能性を説いたが[48]、スカーフ事件を経た90年代のフランスでは、公立学校における宗教の扱いが極めてデリケートな主題となっていた。共和国の学校が「脅威」に直面していると主張するライシテ主義者の警戒心を煽らない範囲で、他者の文化を含めた宗教的なものを客観的に学ぶ教育を行うには、その中立性が徹底される必要があった。過去のみならず現代も射程に含み、信仰教育が入る余地もなく、さまざまな科目から宗教現象にアプローチできる概念とは何か。前章で見たとおり、多義的なcultureはこれに適していない。このほか「歴史」「現象」「出来事」あるいは「比較宗教史」「宗教社会学」など複数の候補が挙げられていたなか、有力視されたのが「事象」である。
「宗教事象」自体は、20世紀の終わりになって突如として現れた言葉ではない。宗教社会学者のオリヴィエ・ロタによれば、19世紀からプロテスタントとカトリックの間の論争で既出しており、エミール・デュルケームの仕事によって「社会的事実/事象(fait social)」としての宗教が理論化される[49]。同じく宗教社会学者のジャン=ポール・ヴィレームは、「宗教事象」の「事象」はデュルケームやマルセル・モースの概念を「必ずしも忠実に継承しているわけではないが、社会学的アプローチが持つ客観化の関心に連なるものではある」[50]と述べている。
公教育との関係で論じられるようになったのは90年代に入ってからのことだ[51]。1993年、エルヴュ=レジェによって社会科学高等研究院(EHESS)と国立科学研究センター(CNRS)に設けられた宗教と社会科学の研究所は「宗教事象の学際研究センター(Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux)」と名付けられた。同じ年、歴史学者のジャン・ドゥリュモーが編者を務めた『宗教事象』(Le Fait religieux)と題された論集が出版された。16人の研究者が参加したこの論集は、ヨーロッパだけでなく、アフリカやアジアの諸宗教の教義や聖典、神話、組織運営などを扱う百科事典的な特徴を持っているが、歴史的内容に偏らず、宗教が直面する現代的状況にも触れている。宗教的な遺産との断絶が懸念されていたなか、その豊かさや現代的課題を広く訴えることを試みた著作で、「宗教事象」という表現が広まるきっかけともなる。そして90年代後半から2000年頃になると、ル・モンドのような全国紙の記事にも出現するようになるため、この頃にはメディアでも市民権を得ていたことがわかる[52]。ヴィレームによると「社会科学のアプローチに依拠し、歴史家も受け入れるようになった『宗教事象』という表現は、『宗教的』というラベルを貼られた社会現象に科学的なアプローチで迫るという客観化の側面を強調するもの」[53]だった。この「客観化」可能である点が、ライシテに基づく宗教的知識の教育の条件に合致したのである。
「事象」は観察可能で、中立かつ多元的であるため、ライシテの原則に適う特徴を十分に備えていたとドゥブレは述べる[54]。そして宗教を「事象」と認識すれば、公教育において「教養の対象(objet de culture)」となるし、それは「信仰の対象(objet de culte)」としての宗教と明確に区別される[55]。重要なのは、学習の対象となる知が、経験や体験の観点からすべての生徒にとって平等に理解可能なものか否かという点である。「信仰」とは、スカーフのように個人や特定の集団の経験の領域に関わることで、万人が共有できる知とはならない。しかし「事象」というアプローチであれば、文化的・宗教的属性の如何を問わず、知的に理解可能な範囲内で扱うことができ、そのように獲得した知は共有しうる「教養」となるのだった。
宗教事象教育を具現化する上で強い後押しとなったのは、2001年のアメリカ同時多発テロである。イスラーム教に対する警戒心が急激に高まり、フランスにも一定数のムスリム人口がいたことから、文化的な軋轢を防ぐ対策として、公教育で宗教的な知識の教育を行うことが急がれ、ジャック・ラング国民教育大臣(当時)は「教育機関で行う宗教事象教育に関する考察」をドゥブレに要請したのである[56]。ドゥブレ報告書はそのような逼迫した文脈で提出されたものだった。
おわりに
1980年代から1990年代の宗教的知識の教育に関する議論は、公立学校におけるライシテの再定義の動きのなかに位置づけられる。フランスの宗教知識教育をめぐる議論の一つの特徴は、公立学校の中立性ゆえに、教育の名称自体と、宗教に対するアプローチに非常に高い厳密性を求める点にあるだろう。
宗教事象教育の発端には、中高生がユダヤ=キリスト教的文化遺産と無縁になってきていることへの危機感があった。同時に、移民の増加にともないフランス社会の人口構成が変容しつつある時代であったため、教養も、異文化に対する理解も、いずれも深める教育のあり方が模索された。19世紀末、カトリックとの対立の末に脱宗教化がなされた公教育の歴史と性質を踏まえると、学校で宗教的な知識を扱うにあたり、客観性と中立性の担保は最も重要な条件だった。そして、80年代から90年代にかけて展開された議論を追うと、1989年が一つの分水嶺であったことは否めない[57]。この年は、一方ではジュタールの報告書が提出されている。これは1991年のシンポジウムにつながるもので、複数の科目を通して宗教的な知識を学ぶ方向性を定めた。他方で、同じ年にはスカーフ事件が起きており、学校とライシテの議論を新たなフェーズへと移らせた。それまで「歴史」や「教養/文化」、「宗教社会学」など、知識としての宗教へのアプローチにはさまざまな提案があったが、ライシテ主義者の視線もあるなか、その選択肢は限られた。「客観化」可能という条件を備えた「事象」という語の選択は、1989年以降の文脈とは切り離せないものだったと言えるだろう。
ところで、本稿で参照したアルザス=モゼルの事例から国内の議論を照らしなおしてみると何が見えるだろうか。本稿では、「事象」とcultureの二つの概念に注目し、ライシテの遵守がより保障されるのは前者であることに触れた。ただ、ドゥブレ報告書が提出された後、「事象」もまた曖昧さや不十分な点が指摘されて批判の対象になる。本稿でも言及したロタによれば、宗教的なものを厳に観察可能な事象に限定したことで、実はドゥブレはデュルケームが「社会的事象」に含んでいた、宗教のスピリチュアルな側面までも削ぎ落としたと指摘する[58]。観察可能な事象は結果的なものであり、その原因の部分にある、さまざまな信仰・精神のあり方を抜きにした宗教的知識の教育とは可能なのか。それは本来語られるべきことをあえて遠ざけたのではないかとロタは指摘する。ライシテの遵守を過度に意識した結果、宗教的他者の理解につながる教育の道を狭めてしまったのではないだろうか。導入から20年が経つが、今日の宗教事象教育は暗礁に乗り上げているという指摘も少なくない[59]。
この点を踏まえると、アルザス=モゼルにおけるculture religieuseの教育は中立ではないかもしれないが、最も包括的な選択であったようにも映る。共和主義的なライシテの弊害から一定の距離を置いている地域から提案される宗教知識教育のあり方も、何らかの示唆を与える可能性があるかもしれない。もっとも、culture religieuseの教育は果たして宗教知識教育なのかという疑問は残る。宗教学では宗教に関する教育を、特定の宗教の信仰心を育むことを主眼に置く宗派的宗教教育と、批判的思考力を身につける宗教知識教育とに大別してきたが、アルザス=モゼルの事例はいずれの分類をまたぐものであるため、この考察は別稿にゆずりたい。
本稿は日本学術振興会・特別研究員奨励費(研究課題番号:22KJ0495)の助成を受けたものである。
Notes
-
[1]
ライック(laïque)は、フランス語のライシテ(laïcité)の形容詞。本稿では公立学校の性質に関わる語として、非宗教的ないし脱宗教的、特定の宗教によらない、宗教的・思想的に中立などの意味で使用する。
-
[2]
このほかには特定の宗教の信仰心を育むことを目的とする「宗派的宗教教育」がある。教会主導のカテキスムや、ミッションスクールなどで実施される宗教教育がここに分類される。
-
[3]
本稿では公教育において宗教を知の対象として扱い、教授することの意味で「宗教知識教育」を使用し、ドゥブレ報告書以降フランスで定着し、ライシテとの関係の中で生まれた「宗教事象教育」とは区別して用いる。
-
[4]
代表的な研究を以下に挙げる。Mireille Estivalèzes, Les religions dans l’enseignement laïque, Paris, PUF, 2005 ; Dominique Borne et Jean-Paul Willaime, Enseigner les faits religieux, quels enjeux ?, Armand Colin, 2007 ; Philippe Gaudin, Vers une laïcité d’intelligence ?, L’enseignement du fait religieux comme politique publique de l’éducation depuis les années 1980, PUAM, 2014 ; Isabelle Saint-Martin, Peut-on parler des religions à l’école ? Plaidoyer pour l’approche des faits religieux par les arts, Albin Michel, 2019.
-
[5]
筆者のこれまでの研究では、culture religieuseを「宗教文化」と訳出してきたが、本稿では文脈によって訳しわけ、複数の意味が重なっている場合はフランス語表記のまま記載している。
-
[6]
「脱宗教化」はフランス語のlaïcisationの訳である。ライシテ研究を代表するジャン・ボベロは「脱宗教化(laïcisation)」と「世俗化(sécularisation)」を区別したが、本稿ではこの理念型を使用している。前者は政府主導で行われる、学校や病院など公的サービスの非宗教化を表すのに対して、後者は社会や規範に対する宗教の影響力が徐々に後退する過程を表す(ジャン・ボベロ『フランスにおける脱宗教性(ライシテ)の歴史』三浦信孝/伊達聖伸訳、白水社文庫クセジュ、2009年)。
-
[7]
伊達聖伸『ライシテから読む現代フランス』岩波新書、2018年、37ページ。
-
[8]
Le Monde, le 10 novembre 1988.
-
[9]
例として1968年以降、中学の第一学年の科目からラテン語が削減されている。なお古典語は、社会的エリートを再生産するものであるとブルデューやパスロンなどからその教育的効果を批判されていた(Nancy Maury-Lascoux, « Latin et grec dans l’enseignement secondaire : une approche historique », Anabases [Online], 23 | 2016. URL :http://journals.openedition.org/anabases/5652
-
[10]
Danièle-Hervieu Léger, La religion pour mémoire, Paris, Les éditions du Cerf, 1993, p. 177-201.
-
[11]
Philippe Joutard, « Propositions pour l’enseignement de l’histoire des religions », dossier réalisé par Dominique Borne, La laïcité : mémoire et exigences du présent, Documentation française, 2005, p. 44.
-
[12]
Enseigner l’histoire des religions, Actes du colloque 20 et 21 novembre 1991, Besançon, CNDP/CRDP de Besançon, 1992.
-
[13]
コックはここですでに「宗教事象」を用いて論じている。Guy Coq, « La religion dans la culture scolaire », Migrants formation, no 82, septembre 1990, Religions et intégrations, p. 169.
-
[14]
19世紀後半、学校のライシテ化を推進する共和主義者と宗派的な教育を保ちたいカトリックとの間にあった対立を表す。世論がこのように二分していたのではなく、二つのマイノリティが思想的に激しく争っていた。
-
[15]
Jean Baubérot, « La Laïcité. Recherches et problèmes », Enseigner l’histoire des religions, Actes du colloque 20 et 21 novembre 1991, op. cit., p. 309-310.
-
[16]
Philippe Joutard, « Conclusions », Enseigner l’histoire des religions, Actes du colloque 20 et 21 novembre 1991, op. cit., p. 330.
-
[17]
Estivalèzes, op. cit., p. 50. 伊達聖伸『もうひとつのライシテ ケベックにおける間文化主義と宗教的なものの行方』岩波書店、2024年、196ページ。
-
[18]
Régis Debray, « Le “fait religieux” : définitions et problèmes », L’enseignement du fait religieux : actes du séminaire national interdisciplinaire organisé à Paris les 5, 6 et 7 novembre 2002. Versailles, Sceren/Crdp Académie de Versailles : 15-19 (coll. « Les Actes de la Desco »), 2003.
-
[19]
参照したのは以下の辞典である。Larousse en ligne(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue) ; Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Collectif Robert et Collins, 2008.
-
[20]
「文化と宗教」小口偉一・堀一郎監修『宗教学辞典』東京大学出版会、1973年、662ページ。
-
[21]
同上。
-
[22]
Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, Bayard, 2003, p. 96.
-
[23]
Ibid., p. 109.
-
[24]
Estivalèzes, op. cit., p. 49.
-
[25]
余談だが、日本の文脈における「宗教文化教育」とは宗教知識教育の範疇に入るものであり、「異文化教育の一環」でもあるとして理解され、違和感なく用いられているが、フランスで指摘される「文化」の語感の問題が日本の文脈には当てはまらないのかどうかは検討の余地がある(井上順孝『グローバル化時代の宗教文化教育』弘文堂、2020年)。
-
[26]
「文化と宗教」小口偉一・堀一郎監修、前掲書、661ページ。
-
[27]
Jacqueline Gautherin, « Les religions à l’école ? Pluralité, universalité, accord social », Enseigner l’histoire des religions, Actes du colloque 20 et 21 novembre 1991, op. cit., p. 38.
-
[28]
正確には、フランス時代に成立した1850年のファルー法で初等教育の宗教教育が必修となり、1871年以降のドイツ時代になると中等教育課程の宗教教育も義務化された。
-
[29]
Jean-Paul Willaime, « L’enseignement religieux à l’école publique dans l’Est de la France : une tradition entre déliquescence et recomposition », Social Compass (3), 2000, p. 387.
-
[30]
ムスリムの生徒のための宗教教育や、ストラスブール大学にイスラームの神学部を創設する案なども浮上したが、実現には至っていない。詳しくは佐藤香寿実の『承認のライシテとムスリムの場所づくり 「辺境の街」ストラスブールの実践』人文書院、2023年を参照されたい。
-
[31]
Francis Messner, « Introduction », Francis Messner (dir.), La culture religieuse à l’école, Éditions du Cerf, 1995, p. 8.
-
[32]
正式にはアルザス=ロレーヌ改革派教会(Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine, ERAL)およびアルザス=ロレーヌ・アウグスブルグ信仰告白プロテスタント教会(Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, ECAAL)と呼ぶ。両組織は2006年に統合して、アルザス=ロレーヌ・プロテスタント連合(Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, UEPAL)に名称を改めた。
-
[33]
UEPAL, « Enseignement religieux protestant en Alsace-Moselle. Programmes de culture religieuse, revu en 2010 », p. 4.
-
[34]
「文化」は、フランスではカトリック的な文化の記憶と深い関連性があり、中立性に欠けることをI章で確認したが、アルザス=モゼルの宗教教育をめぐる議論ではその点は問題視されていない。この点については別途考察が必要である。
-
[35]
UEPAL, op. cit..
-
[36]
歴史学者のルネ・ジローやイスラーム学者のジャック・ベルクは、今後、移民労働者の出身国の文明に関する知識や、他者の文化の寄与に関する学習も避けて通れないことを指摘した。René Girault, L’histoire et la géographie en question : rapport au ministre de l’Éducation nationale, Paris, Ministère de l’Éducation nationale, 1983 ; Jacques Berque, L’immigration à l’école de la République : rapport d’un groupe de réflexion animé par le professeur Jacques Berque au ministre de l’Éducation nationale, La Documentation française, 1985.
-
[37]
コレージュ・ド・フランス教授団「未来の教育のための提言」(堀尾輝久解説)『世界』512号、岩波書店、1988年3月、291ページ。
-
[38]
Gaudin, op. cit., p. 57.
-
[39]
コレージュ・ド・フランス教授団、前掲書、296ページ。
-
[40]
同上。
-
[41]
クレイユの校長が生徒たちにスカーフを外すように指示したのは教室の中であり、校内や図書室など、教師がいない場での着用は容認されていた。Jean Baubérot, « L’affaire des foulards et la laïcité française », L’Homme et la société, No 120, Les équivoques de la laïcité, 1996, p. 15.
-
[42]
フランス最高位の行政裁判・諮問機関。政府が法案を準備する過程で、諮問を受け答申を行う。法に関わる問題について、政府から意見を求められることもある。
-
[43]
Circulaire du 12 décembre 1989.
-
[44]
Le Nouvel Observateur, 2-8 novembre, 1989.
-
[45]
フランスで「コミュノタリスム(communautarisme)」というと、宗教やエスニシティに基づくコミュニティをつくって共和国の社会の一体性を脅かす、望ましくない集団主義と捉えられる。
-
[46]
山元一「多文化主義の挑戦を受ける〈フランス共和主義〉」内藤正典、阪口正二郎『神の法 VS. 人の法—スカーフ論争からみる西欧とイスラームの断層』日本評論社、2007年、107ページ。
-
[47]
Le Monde, le 8 mars 2024.
-
[48]
Philippe Joutard, « Conclusions », Enseigner l’histoire des religions, Actes du colloque 20 et 21 novembre 1991, op. cit., p. 332.
-
[49]
Olivier Rota, « “Enseigner les faits religieux” » ? Aléas d’une expression malheureuse, du rapport Joutard (1989) aux préconisations du Conseil des sages de la laïcité (2018) », Carrefours de l’Éducation, n° 51, juin 2021, p. 156.
-
[50]
ジャン=ポール・ヴィレーム「宗教事象」(伊達聖伸訳)、増田一夫/伊達聖伸/鶴岡賀雄/杉村靖彦/長井伸仁編訳『宗教事象事典』みすず書房、2019年、230ページ。
-
[51]
Jean-Marie Husser, « “Le fait religieux” : de quoi parle-t-on ? », Les nouvelles de l’archéologie [Online], 160 | 2020. URL : http://journals.openedition.org/nda/9822
-
[52]
Le Monde, le 21 janvier 1999.
-
[53]
ジャン=ポール・ヴィレーム、前掲論文。
-
[54]
Debray, op. cit., 2003.
-
[55]
Debray, op. cit., 2002, p. 13.
-
[56]
Le Monde, 7 décembre 2001.
-
[57]
ボベロは、フランスの脱宗教化の歴史を三つの段階に分けて分析し、それらは「敷居」を意味するseuilという言葉で表されている。第一にはフランス革命期から複数公認宗教体制の整備に至るまでの時期、第二には1880年代の公教育の脱宗教化から1905年法の政教分離法成立までの時期、そして最後が、世俗化が進行する1960年以降である。その特徴の一つとして「さまざまな『宗教』の権利要求が(新たな仕方で)現れてくる」時代であるとボベロは指摘する(ボベロ、前掲書、167ページ)。
-
[58]
Olivier Rota, op. cit., p. 159.
-
[59]
拙稿では、近年の宗教事象教育が置かれた社会的状況を国民感情の観点から検討した。「一歩引いて見る宗教事象教育 感情的なものとの関係を問う」、『Résonances』第13号、2022年、URL : https://resonances.jp/13/prendre-du-recul-par-rapport-a-lenseignement-du-fait-religieux/。(2024年7月6日閲覧)
この記事を引用する
白尾 安紗美「宗教事象とライシテ——フランスの公教育における宗教的なものへのアプローチ」 『Résonances』第15号、2024年、ページ、URL : https://resonances.jp/15/fait-religieux-et-laicite/。(2025年07月06日閲覧)