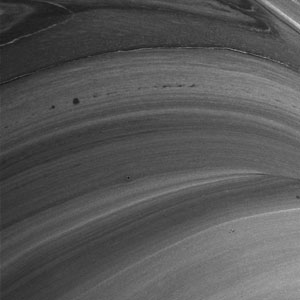フランソワ・ラリュエル,ドゥルーズへの応答(序&第一部)
François Laruelle, « Réponse à Deleuze », François Laruelle (éd.), La Non-Philosophie des Contemporains, Paris, Kimé, 1995, p. 49-80.
訳者の言葉:
1991年に出版された『哲学とは何か』(Qu’est-ce que la philosophie ?)において、ドゥルーズ=ガタリはフランソワ・ラリュエルの「非‐哲学」を「現代哲学における最も興味深い試みの一つ」[訳註1]であるとして絶賛した。その前にも、ドゥルーズとラリュエルは手紙で意見を交換し続けていた。ラリュエルはすでに1988年の手紙の中でドゥルーズの「非‐哲学」に対する誤解を指摘していたが[訳註2]、ドゥルーズはそれで納得できず、自分の理解を維持するまま『哲学とは何か』における評価を書いたようである。自分の弁明が無視されたことに気づいたラリュエルは、この肯定的な評価に反発し、長い論文(すなわち本訳文)で応酬した。
原文には注釈が一切書かれていないので、本文の注釈は全部訳注である。
哲学的な議論は、それが思考の外部へと逸脱していくのでない限り、面白くもないし、おそらく可能ですらないだろう――ドゥルーズがこのことをかくも明確に、そしてかくも厳密に根拠づけられた仕方で述べてくれたということに、我々は感謝しなければならない。しかし本書、『哲学とは何か』のもう一つの重要性は、それがあまりに無邪気かつ挑発的な仕方で哲学的な素朴さを謳うものだから、各人が自身と哲学の関係における最も根本的な前提条件の数々を明確にせざるを得なくさせる、というところにある。各人をその限界まで追い込んで、彼ら自身に固有な諸々の「詭弁」を自白するよう強制するのである。しかし、哲学の「ゲリラ戦」的な――「実体のない戦争」とまではいかないが――本質、その好戦的なスタイルを認識してなお、論争するということそのものに対する拒絶をくじけることなく維持するというのは、単に困難だというばかりではない。それはまさしく、論争の放棄それ自体について、そして思考と実在の本質におけるその理由について、説明しなければならないのである。あらゆる「交流」に対する批判[訳註3]の最終的な残余は、「交流」を放棄する理由を交流させることである。この本の著者たち[ドゥルーズとガタリ]のように「交流的なもの」の過剰性をあざ笑うというだけでは、哲学的な素朴さや信仰を謳い上げても、本当に素朴なだけなのだと見做されてしまう危険を犯すことになる。哲学は、思想の「至福」を愚者たちに約束する「山上の垂訓」であったことは、一度もない。少なくとも、教条主義の模範であるように見える哲学者は、交流や手紙による「関係」を〈存在〉の本質に刻み込んだ人でもあるということは忘れないようにするのが適切だろう。ところでライプニッツの例はおそらく次のようなことを意味している。彼の哲学そのものが自らとの交流に全体的に失敗している、ということが示しているように見える通り、彼の概念、そして彼の交流の実践は、それら自体教条主義的なものであり、自己破壊的かつ自己物象化的なのである。同じパラドクスが、しかし今度は逆転した仕方で、ドゥルーズの哲学に作用しているのではないか。すなわち、見たところ非常によく「交流されて」いるのにほとんど理解されておらず、ましてや用いられてはいない、という仕方で。
この問題はおそらく、哲学的な用語では決定不可能なものである。それぞれの哲学は「交流」についてそれぞれ固有の概念を定義しており、交流的なものと非-交流的な(non-communicationnel)ものの諸力能、及び(両者の結合として、哲学的なものを定義する)没交流的な(incommunication)ものの力能に対する「客観的」な評価を可能にする、諸々の指標や規範を曖昧にしてしまっている[訳註4]のだ。逆に、この本のように全体として成功を収め、その力を確固たるものとしている本は、芸術の「科学そのもの」を犠牲にして、哲学的なアフェクトを大いに伝達している(芸術や科学「それ自体」あるいはそれにほど近い何かではなしに、科学や芸術の哲学的な概念を。また映画「そのもの」あるいはそれにほど近い何かというわけではなく、映画の概念を、などなど)。それゆえ、「科学そのものおよび芸術そのもの」による概念なき内在的実践としての純粋な反乱は、哲学的な正統性なく自己を合法化せんとする営みなのであり、同じく自己自身を確固たるものとしている哲学に対抗して立ち上がる他ないのである。ここでは、「哲学に対して反抗することは正しい」と促すような哲学こそ最高の勝利を収めている哲学である。哲学者が科学と芸術の自律性をかつてなかったほど明白に認識したと思われる瞬間、彼はもっとも精緻な仕方でその自律性を否定しているのである。この本の「和議協約」的なスタイル、少なくともその相互尊重における「近隣」的なスタイル――それはおそらくこの本が交流に対置しているものであるが――はここで、本書の持つ最大の危険であり最も目につきにくい罠であると同時に、そのようなトリックを看破できる者にとっては治療薬そのものとなる。哲学の自己‐確認、その再‐確認が、自身の歴史的かつ世界的な不安定性への抵抗として方向づけられているということは、他の哲学者たちを悩ませずにはおかない。反対に、科学と芸術のため組み上げられ、いまや崩壊しつつある台座は、思想に対して再び次のような仮説を提起するよう強制する。「思想‐芸術」と「科学」は可能なのであるが、それはおそらく哲学がそうであるように再‐確認されることはできないために、経験的に確かめられねばならないのだという仮説を。
それでは、この本をどのように問題にすることが、それも新しいタイプの問題にすることができるだろうか。というのも、この問題はそれ自身すでに、問題とは何であるかという問題に対する解になってしまっているからである。『哲学とは何か』というタイトルがついている本があると仮定しよう。そしてその本はこの問いに対して、自身に固有の実存あるいは現出によって応答しているのだとしよう。その場合、その本について語ることは不可能になる。なぜならこの本は哲学の中心にあり、また哲学がこの本の中心にあるからだ。なぜなら哲学ハ即チ自然(philosophia sive natura)[訳註5]なのであり、ひとは神と対話することはなく、自然現象と交流することもなく、スピノザと論争することもないのだからである。それは一冊の絶対的な本であり、自らを書き、自らを言説し、自らそれ自身を作り、「一冊の本に何ができるのか、とりわけその本が『哲学』と呼ばれるとき何ができるのか」という問いに対して、このように応答する。自分で自己を書くことしかできないと。そしてこの本の読者は、読者なしに自らを作り上げる哲学について、享楽する以外に何ができるだろうか。
そうして残るのは、友人の間で遠い昔の時代や異国のことについて交わされる、親しみ深くて暮れ方のように穏やかな会話の調子、あるいは哲学についての不可思議なお話を語りに来た非‐哲学者の声の調子である。それはまたこの本の持つ語りの調子であり、哲学者による信仰告白と、その哲学者が老後に好んで住まうおとぎ話との間に位置する、耐え難いばかりの調子の軽さなのである。われわれはこれ以上譲歩してはならない。なぜなら、彼らが言ったことを言うよりもむしろ彼らがやったことをやるということが問題であれば、おそらく彼らが予想していなかったような最後の可能性がなお残っているということになるだろうからだ。彼らがやったと言ったことを、あるいはそれを言っただけでまだやっていないことを、実際にやってしまうこと。「創造」の名の下で、あらゆる哲学者がやるように、それをやることと言うこととをごちゃ混ぜにしながら。哲学者たちが言う内在性、なおも哲学的な言葉でしかあり得ていないような内在性をすること、あるいは実践すること、単に実践することが残っている。彼らが言うところの内在性に関してそれを実践することが残っているのである。この本についてコメントしないこと、問題にしないこと、それはおそらく、彼らがしたことの他にはもはや何も望まない、ということではありえないだろう。というのも、「哲学とは何か?」という問いを脱構築し[訳註6]、ウィトゲンシュタインやハイデガー、デリダを彼らに対して再び対立させようとすることは、容易であると同時に、無駄あるいは不可能でもあるだろうからだ。あなた方は哲学の出来事それ自体を、キリストを、あるいはスピノザ‐キリストを、どのように脱構築したいと望むのだろうか。逆に、彼らが現実にしようと考えていたこと(現実=実在(le réel))、ここではそれはおそらく、もはや哲学の〈他者〉ではないだろう)を実際にやってしまうことは、おそらく可能なのではないか。
Ⅰ‐スピノザの模倣と哲学の福音
それは生ける死者たちによる興味をそそられる対話であり、生成と変容によって死にながらもなお生きている人物たちの劇場であり、小声でなされる対話である。この劇場にはギリシャ人たちがいる――エピクロスあるいはルクレティウスというよりは、ソクラテス、そしてプラトンが。スピノザ、ニーチェ、ベルクソンがいる――フェティッシュの三位一体だ。ブノワ、フレデリック、アンリ(それぞれ前三者のフランス語表記のラストネーム)、そして他の者どもがいる、あるいは哲学の事柄どもが。カントとフッサールがいる――哲学の悪しき陣営、派生的な陣営、哲学の領域――そう、「浮浪者的」な哲学者(philosophes “zonards”)どもが。さらに言えば、現代哲学の偉大なる「交流主義者」たちがいる。加えて、特異性の機能の担い手としての、あるいは出来事の、この一回限り(ですべてを決着する)のもの/万人のための唯一の信仰(l’une‐foi(s)‐pour‐toutes)の空虚[訳註7]のマス目としてのキリストがいる。この位置はスピノザによって占められている。キリスト教徒以上にキリスト的な一人のスピノザ、彼に対してはキリストも一枚の新たな仮面であるようなスピノザによって――この場所は、おそらくまたデュオニュソスによっても占められている。そのことを忘れないようにしておこう。というのは、キリストは最終的に、スピノザとニーチェの間で磔刑に処された、あるいは再び磔刑に処されたがゆえである。哲学者の信仰告白は、内在性の啓示者たるスピノザを模倣することへ完全に還元される。スピノザを見たものは、栄光をまとった哲学を見てしまったのだ。哲学的信仰は待機することではなくなってしまったが、その自己実現は哲学の抑圧ではない。逆にその再臨(parousie)は哲学の実存そのものなのであり、すなわちここでは、哲学の生成なのである。充溢せる、あるいは自然な信仰。スピノザは、あたかもキリストが信仰を実現したような仕方で、哲学を実現する。次のように言われるだろう。両者の場合について、両者の可能なエクリチュールのもとで彼らは、それぞれ全てのための唯一の信仰を一回限り(une-foi(s)-pour-toutes)実現したのであると。すべてのための哲学。もしお望みであれば、「一者‐全体(l’Un-Tout)」の別の言い方であると言ってもよい。
いかにそれを隠すのだろうか? 我々は、(すべてを網羅的に包括するような)「グランド・スタイル」がこのように哲学へと回帰してきたことに、少しばかり驚いているのではなかろうか? プラトン、スピノザ、あるいはヘーゲルへの対抗によって? 分散しており、交流的で、世界規模の哲学的舞台は、ある愛知(philosophia)によって一挙に見渡されるのだが、その愛知は少なくとも、固定的な見渡し、あるいは共‐外延、愛知自身あるいはその生成に対する共‐志向によって、ほとんど永続的・永遠的なもの(perennis)に近くなっている。我々の著者たち(ドゥルーズ=ガタリ)はなおも論理を信じている。それは明らかにアングロ・サクソン的な論理ではなく[訳註8]、スピノザ的な属性やニーチェ的な観点、あるいはヘーゲル的な論理性によって代表されるような論理性なのである。自分たちなりの仕方で、彼らは絶えずウィトゲンシュタインの「大いなる鏡」[訳註9]を、すなわち内在性の平面の千の表面を磨き続ける。彼らはそのような内在性を折りたたみ、また折りたたみ直す、まさしくその鏡が割れてしまったり、散種してしまったり、他の内在性のうちへ、すなわち(例えば、しかし例はなんだって構わないのだが)言語ゲームやテクスト的な諸力の内在性のうちへ沈み込んでいってしまうのを防ぐために。彼らは絶えず、「自分自身を見せ」、また自分自身を見せる以外のことをしないのは、諸概念だけであると言い続けている。彼らは絶えず、論理に対して永久に沈黙していることを、そして単に否定的なだけではないような定式を要求し続けている。彼らは歴史が好きではない[訳註10]。それはおそらく彼らにとって、「がたがた」しすぎている土地なのである。そして彼らは生成を平滑化することを好む。そのような生成は、彼ら自身が愚か者と呼ぶような人々によって語られるようにするため、少なくとも我々のうちのある者らにとっては、近代性をなしているところの喧騒や熱狂を欠いているのである。この出来事はストア派的であるが、放縦な仕方でプラトン化させる傾向をも持っている。そしてこれらの生成と伴走し、耐え忍ぶ私的人間(l’homme privé)は、台風の目の中に留まっている。そこを支配しているのはおそらく奇妙な平和なのであるが、それが一つの平和であることに変わりはない。
この永遠的にすぎる本は、20世紀の哲学の大部分を規定している哲学的近代性とユダヤ的転回[訳註11]とを、同時に欠いてしまっているのだと言えよう。例えばヘーゲルであれば、ドゥルーズはまた「個人性の原理(principe de personnalité)」を、すなわち主観性における反省とカント的な発見とを欠いていると断じるだろう。しかしこの本は、絶えずヘーゲルに触れ続け、いくつかの点では彼と一致し続ける。哲学的な活動としての概念によって。「哲学」の出来事の、また「哲学」の完成と開かれの象徴的形象としてキリストを用いることによって。自己‐定立(auto‐position)の円環によって。無限の肯定性によって。しかしながら、これらを「ヘーゲルへの回帰」として語ることは不可能である。
ユダヤ的転回に関して彼は、哲学の権威が許容する最低限のものしか採り入れない。それはホメオパシー的な、あるいはまさしくスピノザ的な服用量であって、レヴィナス的な、あるいはヘテロパシー的な服用量ではない[訳註12]のだ。ここでの賭け金は明らかに無限であり、〈他者〉、〈他人〉、〈友人〉そして兄弟である[訳註13]。それらは本の冒頭において合図を送り、前書き的に予告している。我々スピノザ主義者もまた、現代人なのである! これら二つの点(哲学的近代性とユダヤ主義)を取り上げ、ユダヤ主義の緩和と、それによってドゥルーズがあらゆる対立を解決したところの、諸生成についてのある種残酷な柔弱さの上で、これらについて検証してみよう。実際〈他人〉に関して言えばそれは、私を人質(otage)に取る、概念‐外的かつ世界‐外的な無限などではなく、なおも一つの概念であり、一つの世界である[訳註14]――おそらくそれは「可能世界」ではあるのだが、それでも一つの世界であることに違いはない。その上ここに、ニーチェ的な哲学者がいる。弟子というよりはむしろ友人たちをもち、その主要なアフェクトは友愛であるような哲学者が。もっとも、その友愛は生成あるいは変化としてのそれである。我々は兄弟であるのではない。我々は兄弟になるのであり、それは〈他者〉たる人の守護者や人質であることを拒絶するための他の方法なのである。ニーチェは、スピノザという「兄」を自らに与えた。ドゥルーズが彼ら二人の弟なのだとは言えない。そうではなくて、彼は――兄弟であるのとは他の仕方で、つまり、兄弟の遥かな彼岸というよりむしろ――血のつながりがないもう一人(=他者として)の兄弟であると言えるだろう。この友愛のアフェクトは、民主主義を作ることにも、またここではそれを基礎づけることにも適していない。もっとも、貴族制的な本質を持つ共同体への偽装された回帰が問題である、というのでもないのだが。ドゥルーズの興味を惹いたもの、それは民主主義と貴族制の間で起こる、あるいはその間を通過していくものなのである[訳註15]。それゆえ確実に、生成としての完成された哲学の本質は「民主主義」ではない――それは我々にとってこの語が持つように見えるあらゆる意味においてそうなのであって、単に自由民主主義とか、あるいは〈他者〉たる人に関する倫理といった意味においてのみそうだというわけではない。
無限に関しては、もし、他のあらゆる哲学者と同様、ドゥルーズがたった一つだけ問題を抱えていたのだとすれば、それはまさしく次のような事態であろう。つまり、もはや無限そのもの(l’infini)について考えることが問題なのではなくて(有限な存在たる「私」が、どのようにして無限なものそのものについて考え得るだろうか? )、無限的であるということ(infini)を考えるのが問題だ、ということである。そのためには、無限に自分自身を考えさせれば十分である。
無限そのものが自身を考えるためには、ある三位一体が必要である。まず自己‐定立、あるいは自己‐産出――かつては欲望する諸機械のそれであったが、今日においては諸概念のそれである。続いてある平面。かつては器官なき充溢せる身体であったが、今日では固定的な俯瞰の状態にある内在性の平面である。最後に、これは今まで述べてきた二者の結果でもあるが、行為と情熱としての人間主体の避け難い周縁化である。スピノザが「人間は思惟する」と言ったときにつけたのと同じ留保をつけて、「人間は享楽する」と言うことができよう。しかしこれは、無限そのものの問題を解決するため設計された機械である。この機械はやはりなお、何かを生み出すのでなければならない。ドゥルーズに固有の哲学的な発見とは何なのだろうか。もしそれが、対象とテーゼを欠き、機械と共にあるような一つの哲学であるならば、もし彼の著作がテーマによる統一を持っておらず、対象やテーマや方法による古典的な分節化に沿って切り分けられることができないのだとすれば、もしそこには諸機能以外の何もないのだとすれば、何なのだろうか。彼に固有な哲学的発見、それはスピノザ・ニーチェ・ベルクソンの三位一体ではない。というのも、彼は世間で言われているのとは逆に哲学史家などではなく、哲学を生成の中へ置いたがゆえなのである。その固有な哲学的発見はまた出来事でもなく、それを発見したのはストア派である。多様体でもない――それはニーチェに帰すべきである。それはおそらく出来事の無限な力能であり、スピノザ、ニーチェ、ベルクソンの無限に変奏する力能である。すなわち哲学が自身を完成させ、魚‐水のキメラのように自身のうちへと滑り込んでいくときにもつ力能なのである。彼の固有の発見、それは思考における、あるいは「創造」における、溶解(solution)と変奏の原理としての無限で無制限な生成についての発見なのだ。
キリストと福音が問題となっているからには、ドゥルーズは哲学における聖ヨハネであると言ってよいだろう。しかしア・ポステリオリなヨハネであり、明らかに聖パウロを妨害しているヨハネ[訳註16]であり、その仕事が我々の目を唯一無二の出来事へ開いていくことであるようなヨハネである。その出来事は我々を思考することへ仕向けるのであるが、唯一無二であるがゆえに、反復され、無限なものの力能へもたらされることしかできない。そこからドゥルーズの実践が始まる。哲学者たちのポテンシャルを発揮させ、彼らを複数の出来事、生成、享楽へと変えてしまい、絶えず概念を変えながら機能は変えないでおき、スピノザ、ニーチェ、そして他の哲学者たちを覆い隠す。そこから彼の風習(ethos)が導き出される。人間は自分自身にいるとき、無限なものの「中に」いるのではない。無限なものに対して、人間は隣人なのである――こう言ってよければ、無限で、習慣形成的な(éthologique)生成に対して。そこから彼の倫理学が始まる。スピノザ‐キリストの模倣、哲学者たちとの常に部分的であるような同一化[訳註17]。創造としての知慮。もっとも、何ものも無カラ(ex nihilo)創造されることはないのであってみれば、その創造は永遠の創造であり、柔弱で弱められた創造である。彼がニーチェとベルクソンを結合することで「創造」と呼んでいるものは、この無限の機能、自己原因(causa sui)である。この注釈は歴史に注目するにもかかわらず永遠のものであり、歴史から解釈学的な仕方で意味を奪い去る代わりに、そこから諸機能を奪い去り、諸々の出来事を引き出し、固有名の数々を輝かせる、ほとんど神がかった注釈である。ドゥルーズはある秘密を再発見したのだ――哲学の秘密、あるいは哲学に固有のものを。ひどく古びていて、失われていたものだという印象を我々に与えるような、そういう秘密を[訳註18]。彼は哲学に固有の表現(l’idiome)を取り戻した。それは哲学自身に対して異質なものになってしまっているのだが、それがなおも哲学に固有の表現であり続けているのは、それがまさしく無限なものについての言語になったからである。福音の言語は絶対的に私的なものであり、絶対的に普遍的なものなのである。両者の一致は、哲学的な共同体の自問自答(l’auto‐contemplation)の頂点にあるものである。そこから、超越的な人工物であるところの合意と交流に対する、公然たる恐怖感が出てくるのだ。
Notes
-
[訳註1]
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991, p. 43.
-
[訳註2]
François Laruelle,“Letter to Deleuze”, From decision to heresy: Experiments in Non-Standard Thought, Translated by Robin Mackay, Christopher Eby, Miguel Abreu, Ray Brassier, and Taylor Adkins, Cambridge, MIT Press, 2012, p. 393-401.
-
[訳註3]
『哲学とは何か?』において、ドゥルーズ=ガタリは、「哲学は交流ではない」と主張しつつ、あらゆる交流に基づく学科が(哲学が取り扱う)「概念」を決して把捉できないと強調する(op. cit., p. 11-15.)。ここでドゥルーズ=ガタリが想定する批判対象は、明らかにハーバマスの「コミュニケーション的理性」に当てはまる。その上、周知のように、ドゥルーズは実生活においても一貫して「交流」の場としての学会に抵抗感を示し、思考にとって孤独さの重要性を主張しつづけていた。
-
[訳註4]
「異質的なもののセリーの交流(communication de séries hétérogènes)」や「差異と差異との媒介なき関係性」(Gilles Deleuze, Différence et repetition, Paris, Presses Universitaires de France, 1968, p. 156.)といった前期ドゥルーズの概念はおそらくラリュエルのこの指摘に当てはまるだろう。あるいは『狂気の二つの体制』における表現を借りれば「交流があるが、それは常に非‐交流的な容器の間で行われる。開放性があるが、それは常に閉ざされた箱の間で行われる」(Gilles Deleuze, Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, Paris, Minuit, 2003, p. 38. )。
-
[訳註5]
これは明らかにスピノザのdeus sive naturaに対するパロディーである。
-
[訳註6]
この数行の指摘は、デリダが提起した「哲学への権利」の問題を想定しているように思える。つまり、哲学は「哲学とは何か?」という問いに答える権利を持っているだろうか? もしそうであれば、哲学はその合法性を本来的な仕方で所有するがゆえ、もはやこのような問いに答える必要もなくなるだろう。つまり、ラリュエルがここで指摘しているように、その実存あるいは顕現自体が答えになっている。しかし、この指摘は、ドイツ観念論における「哲学の始まり」についての論述に適用できるかもしれない。とはいえ、少なくとも前期ドゥルーズの著作を読む限り、彼は明らかにデリダと同じように、思考の不可能性、つまり愚かさを(哲学的な)思考の超越論的条件と見なしている意味で、哲学を非‐哲学的な外部に開かせようと試みただろう。この意味で、ラリュエルは、自分の指摘が決してこの「脱構築」に収められないということを強調しているだろう。
-
[訳註7]
神学的なコンテクストにおいて理解する限り、キリストは一人の人間として受肉するために、自分自身をまず「虚しく」する、つまり「ケノーシス」しなければならない。このキリストの虚しさは、神の明かしえぬ神秘性の刻印だと思われている。それゆえ、もしキリストが一つの場所であるなら、後期デリダが一連の神学的な著作において指摘した通り、それは場所なき場所、もしくは砂漠のような場所でなければならない。
-
[訳註8]
論理性は一般的に合理性と同等視されてきたが、ズーラヴィシヴィリの指摘によれば、ドゥルーズは論理主義者であると同時に、非‐理性主義者でもある。彼の哲学はこの二つの立場の両立によって特徴づけられている。François Zourabichvili, Deleuze : Une philosophie de l’événement, Paris, Presses Universitaires de France, 1994.を参照。
-
[訳註9]
『論理哲学論考』5.511を参照。要するに「大いなる鏡」は、世界を包括的に反映できる論理のことである(Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus [1922], ed. Luciano Bozzochi, Anthem Press, “Anthem Studies in Wittgenstein“, 2021, p. 188.)。
-
[訳註10]
前期ドゥルーズのヘーゲル批判によれば、歴史は結局のところニヒリズムへの弁証法的な生成運動にすぎない。この判断はガタリとの共著においても保持されているように思われる。例えば『千のプラトー』において、彼らは歴史をニーチェのいう「反時代性」および彼らのいう「ノマドロジー」の対立面として位置づけたのである(Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 34, 363.)。その上、『哲学とは何か?』において、ハイデガーとヘーゲルは、概念を歴史の自己展開に還元する意味で「歴史家」として批判されている(op. cit., p. 91.)。
-
[訳註11]
ラリュエルは、現代フランス哲学における「他者」の問題系を古代ギリシアから由来する「存在」の哲学伝統に抗する「ユダヤ的転回」と見なしている。François Laruelle, Dictionnaire de la non-philosophie, Paris, Kimé, 1998, p. 30-33.
-
[訳註12]
レヴィナスは一貫してスピノザに対して批判的である。彼は自分が主張する「存在における不安定」を彼がスピノザから読み取った「存在への固執」と対置させる。
-
[訳註13]
ドゥルーズは、とりわけその文学評論においてよく「兄弟」という概念を駆使して精神分析的な「父の不在」に対抗する。一方、ドゥルーズはこのような普遍的な兄弟姉妹の関係性に基づいて、独身者、つまりオイディプス的な三角形を構成しない人々によって構成される共同体を構想したのである(Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 109.)。他方、このような理念の現実的な反映として、ドゥルーズは自分のサークルや学派を作ることに対して非常に警戒している。
-
[訳註14]
周知のように、レヴィナスの哲学は「他人」や「他者」の概念を重視するが、異他性を先行させるような哲学ではない。むしろ、他人との出会いないし他人の身代わりになることは、つねにすでに主体の自己同一性を前提視している。つまり、必ず一人の主体が最初からいて、その後主体が人質になる、ということである。これはやはり最低限の地平概念、一つの世界を想定しているのではないだろうか。
-
[訳註15]
民主主義に対するドゥルーズ(=ガタリ)の批判は、冒頭部分で提起された「交流」への批判に結び付けられる。つまり、「交流」はつねにすでに公開で、透明な検討を平等的に行える(理性を備える人であれば誰もが参加できる)空間を仮定しているように、いわゆる民主主義の条件もまた同じような場所である。しかし既に注13で指摘したように、ドゥルーズが構想した共同体はラディカルな父殺しを行う意味で、ヒエラルキーを覆したのである。彼らが愛用するアルトーの造語を借りれば、この両義性はまさに「戴冠せるアナーキズム」によって表現されるだろう。
-
[訳註16]
ニーチェは反キリスト教主義者として有名である。しかし、彼が激しく批判したのは、イエス・キリストというより、キリストの特異的な力からある種の普遍的な道徳を抽出した聖パウロである。キリストの福音は、決して服従を要求する奴隷の道徳ではないとニーチェは主張する。
-
[訳註17]
ローレル・シュナイダーの主張によれば、キリストは単に一回きりのイエス・キリストとして受肉したわけではなく、世界の全き他者として、万物の生成に随伴しながら、そこから消去されていく。この普遍的な随伴は、道徳としての普遍性と違い、生成の産物に固有の特異性を否定しない普遍性である。このように、キリストの特異性と多様性を同時に堅持するシュナイダーの「多様体の神学」は、ドゥルーズの立場に非常に近いし、ここでのラリュエルの言葉の解釈にもなっているだろう。
-
[訳註18]
要するに、哲学にはある絶対的に不可侵で、理性的な交流において伝達不可能な秘密が存在している、この秘密こそ哲学に自問自答――つまり「哲学とは何か?」という質問に答える、絶対的な権能を与えるのである。ラリュエルの前期作品を参照すれば、彼は一貫してドゥルーズ哲学における「カオス」をデリダの言う「コーラ」と同等視してきた。そして「コーラ」はまた後期デリダの著作において、「秘密」のほぼ同義語として使われていた。ラリュエルはこの意味で「秘密」という言葉を駆使しているかもしれない。
この記事を引用する
フランソワ・ラリュエル「ドゥルーズへの応答——(序&第一部)」 孫 宇辰・石原 威 訳、 『Résonances』第15号、2024年、ページ、URL : https://resonances.jp/15/reponse-a-deleuze/。(2025年07月09日閲覧)