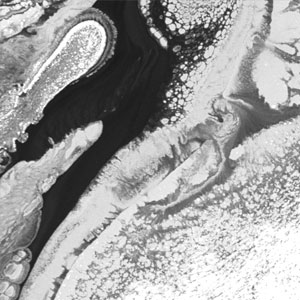誓約の宗教ボシュエ『政治学』における「宗教的な原理」
1. 『聖書の言葉から引かれた政治学』
ジャック゠ベニーニュ・ボシュエは、1670年から、約10年にわたって、ルイ14世王太子ルイ・ド・フランスの教育係を務めた。この時期、ボシュエは、歴史、政治学、文法、論理学など、多数の分野の教科書を執筆したが、このうち、『普遍史論』[1]および『聖書の言葉から引き出された政治学』[2]の2冊は——『フランス王国および全欧の国制』と題されながら、ついに書かれなかった書物と併せて——王太子の教育課程を締め括るものとして計画された。
『政治学』は、題が示すとおり、聖書に記されたユダヤ人指導者の事績から範例ないし悪例を汲み、君主に対して統治者の規範を示す書物である。西欧には、聖職者がキリスト教的な原則に基づきつつ、現実の君主にそのあるべき姿を鏡に映し出すように提示する、「君主の鑑(speclum regis)」と呼ばれる中世以来の著述伝統がある[3]。学問的な政治理論の体系というよりもむしろ、教育的・道徳的な目的に向けられたこの伝統の流れに、『政治学』が棹差していることは疑いない[4]。ただし、『政治学』の出版前検閲を担当したソルボンヌ神学博士ピロの証言は、同時代の受容について異なる側面を教えている。ピロによれば、『政治学』は、「君子教育(éducation princière)」の書物としてはあまりに一般的な問題に拘泥しすぎるきらいがある。このジャンルの書物に期待されるのは、王に固有の義務を簡潔に伝えることであるのに、『政治学』はさまざまな事物の本性や原理を論じることで、しばしば本題から逸れているというのである[5]。
本論考が対象とする第7巻冒頭部の「誓約の宗教」に関する議論も、ピロからすれば、逸脱的であるのかもしれない。というのも、そこで論じられるのは、王が関わるべき社会的な機構としてのカトリック教会でもなければ、真理の源泉としてのキリスト教でもなく、社会を構成する原理としての宗教一般であるからである。「誓約の宗教」についての議論をはじめるにあたり、ボシュエは次のように述べている。
国家体の良い構成は、ふたつの事柄に存する。つまり、宗教と司法である。これらは国家にとって内的かつ構成的な原理である。一方によっては、神に対して神に負うものを返し、他方によっては、人間に対して人間に適したものを与える[6]。
ここで宗教は、司法と並んで、「国家にとって内的かつ構成的な原理」である。しかも、この場合の国家とは、すぐに見るように、キリスト教圏の国家に限定されるのではなく、歴史上に存在したあらゆる国家を含んでいる。つまり、ボシュエは人間集団が国家——ないし有機的な構成物としての社会——を形成するための一般的かつ普遍的な原理としての宗教を考え、それを「誓約の宗教」と呼ぶのである。
「誓約の宗教」は、このように、ボシュエ自身によって、その国家論・社会論における核心的な概念として提示されているにも関わらず、先行研究で詳細に扱われることはほとんどなかった。テレーズ・ゴイエの古典的研究『ボシュエのユマニスム』(L’Humanisme de Bossuet)では、『普遍史論』と『政治学』について、とくにcivilitéの語の特殊な用法を取り上げ、本稿の関心にも近接する議論がなされるが、分析の対象は専らプラトンおよびアリストテレス哲学の解釈伝統からの影響に集中し、社会を構成する一般原理としての宗教については記述がない[7]。これより総論的であるジェラール・フェリロルの論考もまた、ボシュエの社会思想について『政治学』を主要な典拠としながら論じるものの、「誓約の宗教」概念をそれとして取り上げることはない[8]。
こうした等閑視の理由として、3つの事柄が考えうる。第一に、「誓約の宗教」についてのボシュエ自身の説明が、決して詳細とはいえないことである。また、「誓約の宗教」という語が同時代に有していた政治的な文脈が、これまではあまり注目されてこなかったこともあるだろう[9]。さらには、この概念の議論構成における位置づけも等閑視のひとつの理由に想定されうるだろう。「誓約の宗教」は、聖書のうちに系譜が辿られる「真の宗教」の原則を一旦括弧に含み、国家および統治と関係する限りでの宗教的な一般原理を考察するための概念である。したがって、カトリック司教の著作として当然予想される通り、そこで取り出された一般的な原理は、後続の議論でただちに、「真の宗教」の原則のうちに再び回収されることになる。別言すれば、「誓約の宗教」は、一見して、作業上の便宜のためにひとたび仮設された足場のようにも映るのである。
ただし、以上のような研究上の事情は、「誓約の宗教」を傍らに置く十分な根拠とはならない。実際、神の創造と人間の堕罪から社会と統治を論じる『政治学』にあって、「誓約の宗教」は、そこで説かれるべき諸々の「統治の原則」の可能性の条件を明らかにする議論なのであり、つまりは、書物全体におけるひとつの結節点——人間本性をめぐる議論と統治をめぐる議論の結節点——を構成しているのである。
以下、本論考の構成を予め述べておく。まずは、社会の成立条件を問うとき、ボシュエが前提としている人間本性の理解について、第1巻の議論から検討する。そのうえで、宗教的な原理がなぜ国家ないし社会にとっての構成的な原理であるとされるのか、その際にその原理が担う働きは何かという点について、第7巻冒頭の議論の読解を通して明らかにする。最後に、歴史的な状況との関係を整理し、「誓約の宗教」の議論を同時代の言説配置のうちに位置づけるために今後ありうる研究の方向を示唆することができれば、本論考の目的は達成される。
2. 「野蛮」の形成——人間の社会的本性
第7巻冒頭で、ボシュエは、「人類の蒙昧と堕落の中でも、何らかの宗教的な原理はつねに保持されていた」[10]ことを、主にパウロの宣教活動の記録に典拠を求めながら例証し、次のように記している。
これに類似した神の観念は、どんな土地にも、どれだけ古い時代にも存在する。宗教なき民族などというのは、絶対的な野蛮にあって、社会秩序も国家も持たないものを除けば、存在しないのである[11]。
宗教をもたない人々は、「社会秩序(civilité)」も「国家(police)」もない、「絶対的な野蛮(absolument barbares)」にある。つまり、宗教は社会の条件であり、人間が集団を構成して文明化する際に不可欠な原理である。
だが、第1巻の記述によれば、そもそも人間は「社会で生きるように作られている」[12]。神は、アダムを自らの象りとして作った。そして、そのアダムから、すべての人間が生まれた。この聖史上の事実から、人間の社会的な本性について、2つの事柄が導かれる。まず、あらゆる人間には、神の象りがあることになる。とすれば、神を愛することを目的としてつくられた人間は、他の人間の内にある神の象りを愛さねばならないはずである。さらに、人類はひとりの父——霊としては神、肉としてはアダム——から生まれたのだから、みな兄弟である。つまり人間は、その起源をみれば、神の象りを共有する者らとして、また、ひとりの父から生まれた兄弟として、愛しあい、共にいることがむしろ自然なのである[13]。
キリスト教が、おおむね以上のような教義を持つことは、広く知られている[14]。さらに、こうした人間の本性的な社会性が、堕罪によって歪められたという教義もまた、よく知られていると言ってよいだろう。
『政治学』を、とりわけ「誓約の宗教」をめぐる議論を特徴づけているのは、このような神学的な前提が、社会学的ないし法社会学的とも形容できよう省察へと、直接に結びつけられるような構成である。具体的には、聖書の記述から引き出される人間本性の理解を基盤としつつ、そこから人間社会の一般的な条件を、神の介入に頼ることなく、コミュニケーションの問題から導き出そうという企図に、当該の議論の特徴がある。
だが、急くことなく、まずはボシュエの人間本性論を確かめることにしよう。起源からすれば、本性的に社会的であるはずの人間が、なぜ、そのままに社会を形成することができないのか。別言すれば、人間が起源において社会的である以上、社会を欠いた「絶対的な野蛮」の状態は、事後的に形成されねばならないはずだが、その次第はいかに説明されるのか。
[国民を形成し、民族を団結させるために]人間たちが同じ土地に住み、同じ言語を話すのでは十分でない。なぜなら、人間たちは、情念の激しさゆえに頑なで、気質の違いゆえに協調性を欠くので、全員を支配するひとつの統治に、皆が一緒に服従することなくして、団結することはできないからである[15]。
段落末尾の「統治」に関して、いまは措く。人間が集まってあり、言葉を交わすだけでは、国民のようなひとつのまとまった集団にはならない。「情念の激しさ(la violence de leurs passions)」と「気質の違い(leurs humeurs différentes)」が、「頑な(intraitable)」、「非協調性(incompatible)」と表される性質を人間に与えるからである。ボシュエの人間本性論を、とくに(非)社会性との関係において理解するとき、鍵語となるのは「情念」である[16]。「情念」こそが、同じ場所で同じ言葉を話しながら、互いに離れてまとまることのない状況に人間を置く。以下、同じ場所で同じ言葉を話しながらもなお離散しているとはどういう状態かということにも注意しつつ、「情念」の人間的な帰結についてボシュエの説明を辿ることにしよう。
堕罪後の人間のあり様を語るとき、つねにボシュエが原型とするのは、カインとアベルである。「神は人間社会の紐帯であった。最初の男[アダム]が神から離れ、その正当な罰として彼の家族に分断が持ちこまれた。カインが自らの兄弟アベルを殺めたのである」[17]。カインの弟殺しは、人類がひとりの父から生まれた兄弟であるという(聖史上の)事実と、その帰結としての本性的な社会性とを切断する。つまり、この出来事が徴すのは、神という全ての人間が共有する項が、もはやそのままでは人間の社会性の直接的な根拠とはならない状態の到来である。
それと同時に注目するべきは、カインとアベルが、2人兄弟という双数的かつ対称的な関係をなす点であろう。次いで見るように、この双数性・対称性は、ボシュエが人間の結ぶ関係を論じる際に、特徴的なモチーフである。
さて、カインによる最初の殺人ののち、人類は2つの系統、すなわち殺人者の系譜である「カインの子」と、アベルの代理的な系譜である「セトの子」[18]に分かたれ、そのことが堕落を促進させるかたちで、やがて「人間の考えがいつも悪にばかり向き、神は人間を創造したことを悔いている」[19]といわれるまでに至る。
この倒錯が人間を非社会的にすることは容易に理解されよう。情念に支配された人間は、自らを満足させることしか頭になく、他人のことは考えない。イザヤ書の傲慢な者は、「私がいる。そして、この世界には私のほかに誰もいない(Je suis ; et il n’y a que moi sur la terre.)」と言っている[20]。
「倒錯(perversité)」と言われるのは、情念によって、人間の考えが悪に向けて固定される事態である。そのことの第一の徴候は、人間が「自らを満足させること」だけを考え、他の人間のことを思慮の外に置くことだとされる。言い換えれば、堕罪後の人間は、独我的と形容できる意識に閉じこもるのである。ボシュエはこうした意識の在り様が、カインの言葉のうちに典型的に表されているとする。「カインの言い方が、至るところに蔓延っている。『私は弟の面倒を見なくてはならないのでしょうか』、つまり、私は弟のことなど気にしない、気にかけない」[21]。これが、同じ場所で、同じ言葉を喋りながら、ひとが決して自然には社会を構成することなく、離散の状態にとどまる理由である。
けれども、情念はただ人間を離散させておくのではない。野蛮のうちにある人間は、ただ各々に孤絶しているのではなく、ある種の関係を結びもする。それは、「嫉妬(jalousie)」である。
人間のあいだに遍く存在する嫉妬こそ、人間の心にある悪意がどれほど根深いものであるかを見せてくれる。われわれの兄弟は、われわれを損なったり、われわれから奪い去ったりはしない。それなのに、その兄弟がわれわれの憎しみの対象になる。ただ、兄弟がわれわれよりもずっと幸福で、ずっと巧みで、ずっと立派な者にみえるというだけで[22]。
ここでもカインとアベルの関係がモデルとされていることは、言うまでもない。とはいえ、「嫉妬」はどのような意味で、数ある情念のうちでもとりわけ、人間の「悪意」の根深さを教えるというのだろうか。まず指摘されるのは、「嫉妬」には現実的な根拠がないということである。もし人間が、あくまで独我的な意識のうちに閉じており、つながりを欠いて各々に離散しているのなら、自分への明らかな攻撃以外には無関心であるだろう。別言すれば、もし人間が、ただ自己保存と自己充足に突き動かされるだけの存在であるなら、自らの所有物を奪われたり、自分が危害を加えられたりする現実的な危険以外は問題にならないだろう。だが、情念に突き動かされる人間は、そこにとどまることをしない。人間は、自分に対して危害を加える可能性があるわけでもない他人を、それでも「憎しみの対象」にしてしまうのである。しかも、他人が実際に自分よりも優越しているかどうかは問題にならない。ただ、優越しているように「見える」だけで、つまり現実的な根拠ではなく、想像的に描かれた像によって、人間は「兄弟」、双数的・対称的な関係にある他人を、「憎しみの対象」にする。「嫉妬」の根拠が、現実ではなく想像に存するという点については、ラ・ロシュフーコーの断片がよい参考になる。
嫉妬は、ある意味で正当かつ理性的である。というのも、嫉妬は、己れが所有している、または所有していると思い込んでいる財を守ることに向かっているからだ。これに対して、羨望は、他人の財を許容することができないというのだから、狂乱である[23]。
ラ・ロシュフーコーは、「嫉妬(jalousie)」と「羨望(envie)」を対比して、後者を「狂乱(fureur)」とする。だが、ここで「羨望」に与えられている定義が、ボシュエのいう「嫉妬」の簡にして要を得た説明となっていることは明白だろう。情念のうちでも、顕に人間的な悪のあり様を映し出す「嫉妬」は、現実的な必要や危険を超え出る点において、「狂乱」である。こうした想像的な性質を持つからこそ、ボシュエによれば、人間の情念は「飽くことをしらない(insatiable)」[24]のである。
原初において、人間は本性的に社会的であった。この社会性は、神という共通のひとつの起源によって与えられ、つねにその起源に遡行することで担保されるものであった。だが、カインの殺人によって、人間はひとりの父から生まれた兄弟である、だから人間はひとつである、という論理的な接合が切断されてしまう。そのことの帰結は、次のような順序で説明することができよう。まず、神という共通項が結合の効果をもたなくなることで、各人は独我的な意識に閉じ込められ、互いに離れてしまう。その独我的な意識そのものが、人間のあいだに別の関係、双数的・対称的であり、また、想像的である関係を結ばせ、その虜とする。神ではなく、情念によって結ばれるこの関係は、人間的な悪の根底にある問題である。この関係は、現実的な必要や危険ではなく、想像によって描かれた像に由来するために、歯止めをしらない。
「気の触れた情念の数々とそこから生じるさまざまな利害関心によって、人間のあいだには信用も保証も皆無となる」[25]。かくして、「数多くの神聖な結びつきによって築かれた人間社会は、情念に犯された」[26]のである。アウグスティヌスの記述を約めてボシュエがいうところでは、「その本性によっては、人間よりも社会的なものはない。だが、その堕落によっては、人間よりも付き合いづらく非社会的なものはいない」[27]のである。
「神は人間社会の紐帯であった(Dieu était le lien de la société humaine)」。だが、その紐帯は、情念の作用によって毀損され、過去のものとなっている。しかしそれでは、たしかに存在しているはずのその後の社会において、人間は何を紐帯とするのか。「言葉が人間の社会の紐帯である。言葉によって互いの考えを伝達しあうからである。(La parole est le lien de la société entre les hommes, par la communication qu’ils se donnent de leurs pensées)」[28]。神との関係による社会性が、神からの離反によって毀損されたのち、人間の社会的紐帯は「言葉」に代わる。この紐帯の転換こそ、「誓約の宗教」の理論的な前提であり、また、神学的な枠組みの議論から、コミュニケーションの条件をめぐる省察への移行を要請するものである。
3.誓約の(条件としての)宗教
人間社会の紐帯は、言葉によるコミュニケーションであるとボシュエはいう。しかし、他方で、社会が形成されるためには「人間たちが同じ土地に住み、同じ言語を話すのでは十分でない」のでもあった。では、言葉がたしかに社会的紐帯であるためには、言語それ自体の他に何が必要なのか。ボシュエによれば、要請されるのは「信用」と「保証」である。
「誓約の宗教」の概念が現れるのは、第7巻第2章「国民と社会の益としての宗教について」[29]内の第3提題「これらの宗教的な原理は、偶像崇拝や誤謬に適用されていても十分に国家と統治の堅い構成を築きうること」[30]の論証過程である。ボシュエ自身の言葉を引くなら、「あらゆる国民がもつ誓約の宗教は、私たちの命題を証明するもの」[31]として議論に導入される。
以上を整理すれば、「誓約の宗教」が担うべき課題は、以下の2つである。第一に、宗教が社会の維持に益するものであり、また(本稿第1節冒頭に引用した箇所を踏まえれば)社会の条件であることを示すこと。第二に、その原理の社会的な機能が「偶像崇拝や誤謬に適用されていても」、なお有効であることを示すこと、言い換えれば、真の神——より正確には、神の介入——を要請することなく宗教的原理の社会的な機能を説明することである。
まずボシュエは、パウロのヘブライ人への手紙の一節を引きつつ、誓約という行為を構成する要素について考察している。パウロの当該の箇所は、神の約束を主題とする議論であり、人間の誓約については、議論の前提的な確認である一行でしか触れられない(補足的に確認するなら、神の約束が問題になっているということは、つまり、まずは事後的に履行される契約が想定されている)。さらに、その一行も、ボシュエがパラフレーズする内容と厳密には一致しない[32]。しかし、ここではパウロのテクストとの異同については棚上げして、あくまでボシュエの記述に即して分析することにしよう。
聖パウロは、誓約の宗教に2つの事柄を認めた。第一に、ひとは己れよりも大きなものに誓うということ。第二に、ひとは何か不変なものに誓うということ。以上から、この使徒は次のように結論している。「誓約は、人間のあいだに最後的な確立、最後的にして究極の決議を打ち立てる」[33]。
段落末尾の引用は、新共同訳では「あらゆる反対論にけりをつける保証」と訳される。つまり、誓約は、解決不能の係争に、「最後的にして究極の決議(la dernière et finale décision des affaires)」を与えるために要請されるのであり、また、誓約がその機能を果たしうるのは、それが人間に対して超越的な存在を保証とするためである。
一見して、特段変わった点のない言明に思われる。というより、ごく当然の事柄の確認として読み流されかねない一節である。とはいえ、あえていうならただの人間の言葉にすぎない誓約が、なぜ容易に解決できない係争に「究極の決議」を与えるなどということがありうるのか。素朴な問いのように映るかもしれないが、議論の焦点を捉えるには都合がいい。実際、ここでの議論が偶像崇拝者の誓約までを含むものである以上、ボシュエの問いはそのような地平にあると考えるべきである。
ボシュエは、パウロによる2つの条件に、さらに1つを付け加えている。『政治学』において、ボシュエが典拠に対して明示的に補足を加えることは決して多くない。しかもこの場合、典拠となるテクストは、使徒パウロによる最大級の権威をもつテクストである。それゆえ、この付加の意味については、しばし立ち止まって考察する必要があろう。ともあれ、まずは該当の箇所を見てみよう。
さらに第3の条件を追加しなくてはならない。それは、良心の最も隠された秘密までを見通す力に誓うことである。そうすれば、ひとはその力を欺くことはできないし、偽の誓約の罰を逃れることもできない[34]。
付加される条件は、誓約者の「良心(conscience)」に関するものである。つまり、誓約者の秘められた判断や意図を、誓約の場面において、どう制御するかが焦点となっている。翻って、ここでは誓約の当事者間にある裏切りや瞞着への不信が俎上に挙げられていると指摘することもできよう。そもそもボシュエは、堕罪後の「人間のあいだには信用も保証も皆無」であるとしていたのだった。
しかし、パウロによる2つの条件においても、というよりも、誓約という行為一般の前提には、そもそも不信があるとはいえないか。ひとが自分の言葉に対して超越的な保証を立てるのは、自分の言葉を他人が信じていない、自分の言葉には相手を信用させる力がないと考えるときだろう。だとすれば、ボシュエの付加は、パウロの時点ですでに伏在していた問題を前景化させたにすぎないのか。
だが、当該段落に表れる「偽の誓約(parjure)」の一語に留意するとき、パウロからボシュエのあいだには、徴候的な、しかし確かな展開の跡が認められるようにも思われる。改めて指摘しておくべきは、「良心の最も隠された秘密までを見通す力」、「偽の誓約の罰」という表現が用いられているからといって、真の神の介入について言われているわけではないということだ。言い換えれば、この箇所で、「誓約の宗教」の概念に偶像崇拝や誤謬の宗教を含むという前提が撤回されていると考える必要はない(そのように考えることは難しい)。つまり、あえてボシュエの表現を改変するのなら、ここで問題とされているのは、「良心の最も隠された秘密までを見通すと誓約者が信じている力」なのである。だが、さらに付け加えるなら、そもそも誓約は人間間に信用を築くためにあるのであった。つまり、誓約は誓約者当人だけでなく、誓約の相手にも信を生まなくてはならない。であれば、当該の表現は、より正確には「良心の最も隠された秘密までを見通すと誓約者が信じていると、誓約の相手が信じる力」を指していると考えるべきではないか。
ここまで歩みを進めてみると、「偽の誓約」という表現が、このようなコミュニケーションの場面における想像的な入れ子構造を前提として、はじめて現れるものであることがわかってくるだろう。誓約者は、自分の言葉を相手が信じていないと考え、超越的な保証に頼む。しかしこのとき、誓約の相手が誓約自体を偽であると考えるなら、事態ははじめに戻り、当事者間の不信は拭われない。「偽の誓約」という一語は、誓約の場面に、こうした原理上は無窮の猜疑を導入してしまうのである。であるからこそ、そこでは「良心の最も隠された秘密までを見通すと誓約者が信じていると、誓約の相手が信じる力」という入り組んだ条件が要請される。このような力に誓うとき、誓約の相手は、誓約者の良心がたしかに拘束されていると信じることができるからである。
以上のような問題構成は、つづくアウグスティヌスを典拠とする議論を読むことで、より明瞭になるだろう。というのも、そこでは、互いに異なる神を信じる者の間での誓約について論じられるからである。
だからといって、真の神に誓うことが絶対に必要だというわけではない。そうではなくて、各々が自身の認める神に誓えばよいのである。それゆえ、聖アウグスティヌスが記したように、野蛮人との条約が、野蛮人の神々への宣誓によって確立されるということもあったのである[35]。
典拠となるアウグスティヌスのテクストは、辺境の農主プブリコラ宛の書翰である。異教徒による偽の神への誓約を、キリスト教徒は認めてよいのか、というプブリコラの問いに対して、アウグスティヌスは次のように答えている。「偽の神に対して真の誓いをすることが、真の神について虚偽の誓いをすることよりも、少ない悪であることは疑いありません」[36]。つまり、ここでの善悪の基準は、誓われる神の真偽ではなく、その誓いの真偽にある。ボシュエが踏まえているのは、こうした議論である。
アウグスティヌス(とボシュエ)は、創世記のヤコブとラバンの挿話を引いている。ヤコブは、父を欺き兄になりすましてその祝福を受けたのち、伯父ラバンのもとに身を寄せていた。初めは歓待を受け、ラバンの2人の娘を娶ったが、次第に家族の男たちとの不和が生まれ、妻を連れてラバンのもとから脱走する。このとき、妻がラバンの崇拝する神像(つまりラバンは偶像崇拝者である)を盗んでいたことで、ラバンの追跡を受ける。追いついたラバンとヤコブのあいだに少しく問答があるが、最終的にラバンはヤコブの独立を認め、その印として石を立てる。「このとき、両者は各々の神に誓ったのである。ヤコブは真の神、父イサクが畏れ崇めた神に。偶像崇拝者ラバンは、彼の神々に[37]」。
重要な点は、もちろん最後の箇所にある。「偽の神々」への偶像崇拝者の誓約が、聖書のうちに正当かつ真正な誓約として記されているというこの事実こそ、「真の神」に対する虚偽の誓いをする方が、「偽の神」に対して真の誓いをすることよりも悪いという、アウグスティヌスの主張の論拠である。もし偶像崇拝者ラバンが「真の神」に誓ったとすれば、ラバンは自分が信じていない神に誓ったことになり、つまりは偽の誓いをしたことになってしまう。とすれば、ラバンは「真の神に対する虚偽の誓い」と「虚偽の神に対する真の誓い」のどちらかを選択しなければならなかったことになる。このとき、ラバンは結果として後者を選択し、その選択が真正な誓約として認められたと——少なくとも旧約聖書内にこの誓約を批判する文言はないのだから——考えられる以上、2つの選択肢では後者の方がより適切だと結論することがたしかに可能である。
以上のアウグスティヌスの議論を踏まえつつ、ボシュエは次のように述べる。
かくして宗教は、真であれ偽であれ、人間のあいだに良い信を築くのである。というのも、偽の神に誓うことは異教徒の涜神であるとはいえ、条約を確立する誓約に対する良い信はまったく涜神ではないのだ。その反対に、良い信それ自体は、この博士[アウグスティヌス]が同じ箇所で教えているとおり、神聖不可侵である。それゆえ、神は異教徒間の偽の誓約に懲罰を与えずにはいなかった。偽の神への誓約は神の前では忌まわしいものであるとはいえ、それでもやはり、この方法によって築かれようとしているのは、良い信の庇護者であるからである[38]。
神の真偽ではなく、誓いの真偽こそが問われるのは、ここでの焦点が「良い信」確立の成否にあるからである。このことを言い換えれば、誓約の場面で問われるのは、神と人の関係ではなく、人と人の関係である。
ヤコブとラバンのように、真の神を知る者と偽の神を崇拝する者のあいだで誓約が交わされるとき、真の神を知る者は、当然、偽の神を崇拝する者が誓う神には「良心の最も隠された秘密までを見通す力」などないことを知っている。だとすれば、偽の神の崇拝者の誓いは——少なくともこの崇拝者が誓う神からは——「偽の誓約の罰」を受けることはない。それでも両者の間に「良い信」が確立されるのは、真の神を知る者からみて、偽の神の崇拝者が己れの神を「良心の最も隠された秘密までを見通す力」の持ち主だと信じていることが、信じられるからである。つまり、ここで偽の神は「良心の最も隠された秘密までを見通すと誓約者が信じていると、誓約の相手が信じる力」として機能しているのである。
ボシュエによって付加される第3の条件が開くのは、こうした双数的・対称的な2者間における想像的なコミュニケーションの次元である。良心は、他人の目からは秘匿されている。だからこそ、人間が結ぶ関係において焦点を構成するのであり、そのあるかなきかの考えをめぐって、無窮の猜疑が生じるのでもある。このことが、独我的な意識への閉じこもりとそれから生じる想像的な(嫉妬をひとつの典型とする)他者関係という、前節でみた堕罪後の人間の在り方に対応することは論を俟たない。「誓約の宗教」は、この無窮の想像的関係に対する歯止めとして要請される。「信用も保証も皆無」である人間のあいだに「信」を築き、取り決めを成立させ、言葉をして社会的な紐帯たらしめること。社会の条件としての「誓約の宗教」が担う役割はそのように表しうる。
4. 叛乱と誓約——「誓約の宗教」の歴史的背景
以上が、あらゆる時代のあらゆる地域の国民が有していたといわれる、国家の条件としての宗教的な原理の内実である。宗教的な原理は、情念によって、放っておけば倍加的に募る人間間の不信に歯止めをおくために要請されるのであった。そして、再三になるが繰り返せば、この宗教的な原理は、あくまで形式的なものであり、偽の宗教においても働くものである。
だが、その直後、ボシュエは次のように述べる。
偽の宗教は、人間的な事柄が服従せねばならない何らかの神的なものを認識させるのだから、善や真を有するといえ、その点で、国家の構成に対しては絶対的に十分であるのではあるが、それでもなお、偽の宗教はつねに、良心の根底に不確かさや疑いを残してしまい、これらが完全な堅固さを築くことを妨げるのである[39]。
偽の宗教も、たしかに、国家の構成にとって「内的かつ構成的な原理」としての資格は十分に満たしている。だが、それはその機能の面において、つまり人間間の信の形成という点に関して、真の宗教には劣るとされるのである。教会人として王君の教育にあたる者としては、ごく当然の言明と受け取られるかもしれない。実際、偽の宗教であれ、「国家の構成に対しては絶対的に十分である」という言明をそのままにして次の主題へと移ることが、ボシュエにとって難しいことは容易に想像される。
とはいえボシュエは、何をもって偽の宗教は脆弱であるというのか。それは、端的にいって、その教義が偽であるからである。といって、やはりここでも、神への冒涜であるとか、神罰とかいうことが取り沙汰されるのではない。そうではなくて、その教義が偽であることが招く、社会的な帰結こそが問題なのである。
ボシュエは「異教徒の賢者の書き物」のうちには、「偽の宗教を成しているものの弱さ」への恥じらいが読み取れるという[40]。異教徒の神は、天体や大地など「物言わぬ無感覚の事物」であったり、偶像など「自らの手になる作品」であったりする。「賢者(sage)」はこうした事物を礼拝するという愚昧を内心で嫌い、ただ「言葉の上で政略的にだけ神々を崇拝」し、「民衆の作法に迎合」して外面的な礼拝を行うだけになる。ここにこそ——何はともあれ「宗教」ではある「偽の宗教」から、さらに一線を踏み越えた——無宗教と無神論の根があるとボシュエはいい、知識人が陥るふたつの対をなす事例として、神を信じるといいつつ感覚にへつらうエピクロス主義者と、信仰対象であるはずのユピテル神よりも賢者の方を好むストア派を挙げる。
ここでボシュエが挙げている例はいずれも、外的な行為や発話と内心の隔たりが起こす事態である。国家にとっての宗教の効用とは、良心の拘束を通じて、発話者の内面と発話を一致させる点、さらにいえば内面の発話が一致しているという社会的な信を形成する点にあるのであった。偽の宗教の場合、とくに知識人のあいだに、その教義の愚かしさゆえに不信を呼び、宗教そのものが外面と内面の乖離を引き起こす動力に転じてしまう。ボシュエは、あくまで社会維持に観点を限定しつつ、こうして「偽の宗教」の有効性を批判するのである。
ところで、こうした知識人を動かしている「熱意(zèle)」について、ボシュエが、「無知」や「盲目」と並んで、「不穏(séditieux)」、「荒ぶる(turbulent)」、「欲得づく(intéressé)」といった形容詞を用いていることは注目に値する[41]。これらはいずれも——「叛乱(sédition)」に直接由来する「不穏(séditieux)」を典型として——、叛乱を想起させる語であるからだ。ここでボシュエは——「言葉の上で政略的にだけ(en paroles et par politique)」という表現がより直接に示すように——神を疑い宗教を軽蔑する知識人を明らかに政治的な叛乱分子に重ねている。
ル・ブランは、ここでの知識人批判が、同時代のリベルタンに宛てられていると推測している[42]。たしかに、「エピクロス主義者」は、リベルタンとみなされた著述家にしばしば貼り付けられたレッテルであり、また、実際にリベルタンはルクレティウスを中心とするエピクロス主義哲学を、しばしば自説に援用した[43]。理性の制限なき適用による宗教ないし信の危機は、極めてアクチュアルな問題であり、ボシュエもまた幾度となく主題的に取り上げている。リベルタンに対するかれのまとまった駁論のひとつが、これまで論じてきた『政治学』第7巻と重複した内容を含む『普遍史論』の第3部に見られることも、当該の箇所の標的をリベルタンに定めるための傍証となるだろう[44]。
ただし、範囲を第7巻前半部の「誓約の宗教」に関わる議論全体に広げたときには、リベルタンによる宗教への攻撃とは、別の仮想敵も浮かびあがる。それは宗教による王権への攻撃、具体的にはイエズス会を中心とした暴君放伐論である。
思想史上に取り上げられることは極めて少ないが、1682年、フランスで『誓約の宗教』という題の書物が出版されている[45]。名目上の著者は16世紀後半の司教シモン・ヴィゴール——後述するガリカニスム運動に関与した知識人のひとり——だが、遺稿を整理し出版した法学者フランソワ・デマレが大胆な加筆修正(実質的な再執筆)を行なったことがわかっている。この書物の目的は、「王殺し(régicide)」を法的・道徳的に擁護しようとするイエズス会の反王権的言説を「言葉の詐術(artifice de parole)」と名指し、「誓約の宗教」がそうした言葉の氾濫を抑圧する機能をもつことを示す点にある[46]。
論争の契機となったのは、イギリスの動向である。ジェームズ1世が国内の聖職者に王への例外なき服従の宣誓(いわゆる「忠誠の誓約(serment d’allégeance)」)を求めると、カトリックおよびピューリタンの聖職者の一部は王権に抵抗し、誓約の有効性や誓約と宗教の関係をめぐって議論が紛糾し[47]、1649年のチャールズ1世処刑によっていよいよ論争は切迫する。こうした議論、とりわけ誓約に関する問題は、フランスにおいては、ガリカニスムの文脈と結びついた[48]。教皇に対する王権の世俗的な自律の確認を要求するガリカニスムは、中世以来の伝統を有しつつ、絶対主義王権のもとで新たな展開を迎えていた。そのひとつの頂点となるのが、ボシュエ自身も起草に主導的に関与した1682年の四箇条宣言であり、その第一箇条には、「国王や君主が、直接にせよ間接にせよ教会の鍵の権威により廃されることはないし、その権威の名において、臣下が君主に果たすべき服従から免除されたり忠誠の誓約が無効とされることはない」との文言が読まれる[49]。
以上の歴史的な観点から、『政治学』における「誓約の宗教」に関する議論の射程を測ることができよう。「誓約の宗教」の第一の目的は、「宗教的な原理」が「偶像崇拝や誤謬に適用されていても十分に国家と統治の堅い構成を築きうること」の証明にあったのだった。社会と国家の条件である宗教的な原理が、しかし必ずしも真の宗教たるカトリック教会でなくてもよい、さらにいえば、カトリック教会以外でもよいのでなければならない理由は、政治的な状況を念頭に置くことではじめて理解される。すなわち、国家を教皇権力から独立して存立しうるものとして示すことが、その目的である。実際、ボシュエは当該の箇所で次のように述べている。宗教的な原理は、たとえ偽の宗教にあっても国家と統治にとって十分に有効である、「そうでなければ、真の宗教と真の教会の外には真正かつ正統な権威は存在しないことになってしまい、偶像崇拝的であろうと、不信仰者に支配されていようと、国家の統治は神聖不可侵であり、神命によって良心に義務づけられたものだという、ここまでわれわれが見てきたことに抵触してしまう[50]」。そして、この宗教的な原理の機能は誓約の場面において説明され、そこでは、偽の神に誓われるのであっても、当事者間に「良い信」を生む限りでその誓約は神聖不可侵であるとされていたのだった。こうした議論が、上で見たような背景、とりわけ四箇条宣言の第一箇条を理論的に補強しつつ再確認するものであることは、明らかであろう。しかし、議論はそこで止まることなく、今度は偽の宗教の機能上の脆弱性を説きながら、真の宗教の保護を君主に推奨することに転じる。このことを含み入れれば、「誓約の宗教」をめぐる議論には、世俗権力の正統性を教皇権力からは独立に措定しつつ、同時に、それでもなおカトリック教会こそが君主の擁護すべき宗教であることを説くという二重の課題があったのだといえる。
はじめに、「誓約の宗教」がこれまで十分な検討をされてこなかった理由のひとつとして、議論の見かけ上の仮設的な性格を挙げたが、いまや、まさにそうした議論構成こそ、すぐれて戦略的かつアクチュアルな判断の結果であることがわかるだろう。これは、教皇に対する王権の自律の主張とカトリック教会の擁護という、一見して相反するかにも思われる課題を、同時に引き受けるものとして、ボシュエの政治的言説の理解のために格好の端緒となりうる。つまり、「誓約の宗教」は、直接的な紐帯である神を失った人間が社会を形成するための条件の説明として、『政治学』における人間本性論と社会および統治をめぐる実践的な教説を結ぶ議論であると同時に、また、『政治学』を同時代の状況、とりわけ絶対主義とガリカニスムの問題から考える上でも、枢要な論点を構成しうるのである。
Notes
-
[1]
Discours sur l’histoire universelle. 初版1681年。
-
[2]
Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, édition critique avec introduction et notes par Jacques Le Brun, Genève, Droz, 1967[1709]. 以下、参照文献としてはPEで指示し、文中では『政治学』と略記する。『政治学』は、生前に公刊されることのなかった未完の書物である。1677年からの2年間に、第1巻から第4巻が執筆されたのち、20年をあけて、90年以降、公刊に向けた大幅な加筆修正および第5巻以降の執筆が進められた。ほぼ完成に近い遺稿を、ボシュエの没後すぐに甥が編纂し、1709年に公刊された。以上の事情については、批評校訂版の編者ジャック・ル・ブランによる序文の他に、以下を参照した。Thérèse Goyet, L’Humanisme de Bossuet, Paris, Klincksieck, 1965, 2 vol, t. II, p. 451-458.
-
[3]
「君主の鑑」について、日本語文献の中では、以下の巻末に付された訳者による解説が詳しい。トマス・アクィナス『君主の統治について』柴田平三郎訳、岩波文庫、2009年。
-
[4]
ル・ブランは、『政治学』について、政治理論についての体系的著作というよりも道徳的な性格をもつ書物であると指摘したうえで、以下のように述べている。「実のところ、この時代には、この学問[政治学]を実定的な方法によって練成しようとする一群のひとびとが存在していて、かれらとボシュエの関係も、今後、解明されるべきである。その論壇とは、国家統治をめぐる省察に意欲的であった篤信貴族たちのことではない。そうではなく、法学者、歴史家、地理学者であり、高等法院院長ラモワニョンのサロンに集った文人(hommes de lettres)たちである」。ラモワニョンのサロンは、17世紀中葉において大きな影響力をもっていたサロンであり、政治的著作の著者が多数集まっていた。Jacques Le Brun, « Introduction », PE, p. X.
-
[5]
ル・ブランは、ピロが君子教育を掲げる書物に起こっていた変化、つまり、この種の書物が、ただ王侯の子女だけでなく「まさしく『公衆(public)』と呼ばれるもの」へも宛てられるようになったという変化を正しく測れていなかったのではないか、と述べる。 Jacques Le Brun, « La Politique de Bossuet : les débats autour de sa publication d’après des documents inédits », Bossuet à Metz (1652-1659), Berne, Peter Lang, 2005, p. 277-289.
-
[6]
PE, p. 212.
-
[7]
Goyet, op. cit., p. 421-478.
-
[8]
Gérald Ferryrolles, « Bossuet politique », Gérard Ferryrolles, Béatrice Guion et Jean-Louis Quaintin avec la collaboration d’Emmanuel Bury, Bossuet, Paris, PUPS, 2008, p. 151-179.
-
[9]
この文脈については、第4節で扱う。
-
[10]
PE, p. 213.
-
[11]
PE, p. 214.
-
[12]
PE, p. 5.
-
[13]
ジェラール・フェリロルは、複数の著作を比較しつつ、ボシュエが説く人間の社会的な原理は、「一体性(unité)」、「平等(égalité)」、「友愛(amitié)」の3つにまとめることができると主張している。このうち、前者のふたつは人類の起源から、「友愛」は——究極的には起源に由来することは当然として——むしろ共時的な人間学的観点から、それぞれ説明される。ただしここでは、論考の目的に鑑みて、『政治学』の記述に範囲を限定した。Ferryrolles, art. cit., p. 153-153.
-
[14]
といって、ボシュエの見解がキリスト教教義の標準である、というのではない。詳述することはできないが、とりわけ起源の単一性の強調には、プラトンおよびネオプラトニスムの影響(ボシュエは、プラトンとアリストテレスの著作について詳細かつ大部のノートを作っている)、そしてフランス君主制顕揚の意図が認められる。Bossuet, Platon et Aristote. Notes de lecture, transcrites et publiées par Thérèse Goyet, Paris, C. Klincksieck, 1964, p. 117. 加えてLe Brunによる下記のページの註14を参照。PE, p. 7, note 14.
-
[15]
PE, p. 17.
-
[16]
以下に見る人間の非社会性の起源についての考察が含まれる節は、「人間社会は情念によって破壊され、犯された」と題されている。PE, p. 11.
-
[17]
PE, p. 11.
-
[18]
「再び、アダムは妻を知った。彼女は男の子を産み、セトと名付けた。カインがアベルを殺したので、神が彼に代わる子を授け(シャト)られたからである。」(新共同訳:創世記4-25)
-
[19]
PE, p. 11.
-
[20]
PE, p. 12. イザヤ書内の該当箇所は「わたしだけ、わたしのほかにはだれもいない」(新共同訳:47. 8)。これ以後、この節は基本的に現在形の動詞によって書かれている。カインのアベル殺しによって形成された人間の在り方は、過去のものではなく、現在にまで至る人間の普遍的な条件であるからである。
-
[21]
PE, p. 12.
-
[22]
PE, p. 12.
-
[23]
La Rochefoucauld, Maximes et réflexions diverses, édition de Jean Lafond, Paris, Gallimard, « folio classique », 2021, p. 48.
-
[24]
PE, p. 12.
-
[25]
PE, p. 12. ここまで見てきたボシュエの人間本性論には、ホッブズの影響が明白である。実際、『政治学』のうちには「万人の万人に対する戦い」や「人間は互いに対して狼」といった表現が散見される。17世紀フランスにおけるホッブズ受容については、註48を参照。
-
[26]
PE, p. 13.
-
[27]
PE, p. 13. 『神の国』第12巻第22章の議論に相当する。
-
[28]
PE, p. 14.
-
[29]
PE, p. 213.
-
[30]
PE, p. 214.
-
[31]
PE, p. 215.
-
[32]
新共同訳では、当該の文章は「そもそも人間は、自分より偉大な者にかけて誓うのであって、その誓いはあらゆる反対論にけりをつける保証となります」(ヘブライ:6-16)とされており、「何か不変なものに誓うこと」は誓約の構成要素に数えられていない。だが、正確な内容や文脈を問わない引用方法は、ボシュエに特有のものではなく、むしろ近世以前のキリスト教のテクストでは一般的であると言ってよい。ただし、ルメートル・ド・サシらの聖書研究や、リシャール・シモンの聖書に対するテクスト批判などの業績もあって、『政治学』が執筆された17世紀末から18世紀初頭において、すでにボシュエのような引用方法は古びていた。『政治学』の出版前検閲の記録には、ボシュエの聖書の引用方法に関する指摘が認められる。Le Brun, art. cit., p. 277-289.
-
[33]
PE, p. 215.
-
[34]
PE, p. 215.
-
[35]
PE, p. 215.
-
[36]
アウグスティヌス『アウグスティヌス著作集別巻1 書簡集⑴』⾦⼦晴勇訳、教⽂館、2013 年、121-128ページ。
-
[37]
PE, p. 216.
-
[38]
PE, p. 216.
-
[39]
PE, p. 217.
-
[40]
PE, p. 217.
-
[41]
PE, p. 218.
-
[42]
PE, p. 217, note 20.
-
[43]
ポール・アザール『ヨーロッパ精神の危機』野沢協訳、法政大学出版局、1978年、150-156ページ。
-
[44]
たとえば、『普遍史論』第2部第28章「ひとが聖書に対して拵える異論は、分別と信仰のある人々にとっては容易に論駁できる」を参照。Œuvres completes de Bossuet, éd. François Lachat, 31 vol., Paris, Louis Vivès, t. 24, pp. 548-553.
-
[45]
Simon Vigor, La Religion du serment contre l’artifice de parole ou l’équivoque, Paris, Christophe Journel, 1682.
-
[46]
Frédéric Gabriel, « Une réponse aux “artifices de parole” : la religion du serment. François Desmarest sur les pas de Simon Vigor », Stratégies de l’équivoque, Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 33, 2004, p. 175-185.
-
[47]
広く知られた例を挙げれば、グロティウス『戦争と平和の法』(原著1624年)の第2巻第13章「誓約について」がある。ボシュエはグロティウスを非常に高く評価していた。Hugo Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, traduit par P. Pradier-Fodéré, édité par D. Alland et S. Goyard-Fabre, Paris, PUF, 1999[1867], p. 349-367.
-
[48]
ガリカニスムについて、日本語で読むことのできるほとんど唯一の総論的な著作として、以下がある。エメ゠ジョルジュ・マルティモール『ガリカニスム フランスにおける国家と教会』朝倉剛・羽賀賢二訳、文庫クセジュ、1987年。ボシュエとガリカニスムの関係については、同じ著者による以下の研究が代表的である。Aimé-Georges Martimort, Le Gallicanisme de Bossuet, Paris, Édition du Cerf, 1953. この文脈においては、フランスにおけるホッブズの受容も重要である。ホッブズの初のフランス語訳は、1648年出版の『市民論』であるが、これは5年のうちに4つの版を重ね、1660年には別の訳者によるホッブズの引用集がルイ14世に献上されるに至った(G. Lacour-Gayet, L’Éducation politique de Louis XIV, Paris, Hachette, 1923, p. 280-289.)。指摘するに留めるが、「誓約の宗教」に関係して重要なのは、『戦史』の翻訳者でもあるホッブズがトゥキディデスから引き継いだ、叛乱勢力による言語の意図的な濫用というトポスである(同様の主題が、プラトン『国家』第8巻にも継がれている)。トゥキディデス、プラトンの内乱論とホッブズの自然状態論を結ぶ系譜については、たとえば以下の先駆的な研究を参照。神崎繁『内乱の政治哲学 忘却と制圧』講談社、2017年。
-
[49]
マルティモール、前掲書、117ページ。
-
[50]
PE, p. 215.
この記事を引用する
伊藤 連「誓約の宗教——ボシュエ『政治学』における「宗教的な原理」」 『Résonances』第14号、2023年、ページ、URL : https://resonances.jp/14/la-religion-du-serment/。(2025年07月08日閲覧)