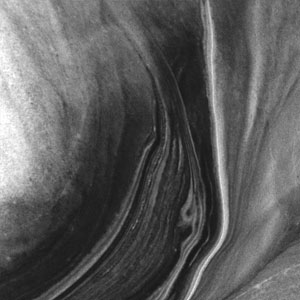19世紀フランスにおける「非人間の社会」の思想的一系譜デュラン・ド・グロ、エスピナス、タルド
はじめに
今日の人文学・社会科学では、人間中心主義を批判する思想が脚光を浴びているが、そこではしばしば人間ならざるものが構成する社会──則ち、「非人間の社会」──が賭け金となる。人間の中心性を削減するにあたり、伝統的に人間に特権化されてきた「社会」という現象を、非人間にも拡張して論じようとする戦略がしばしば取られるのである。例えば、ブリュノ・ラトゥールに代表されるアクターネットワーク理論はその一例として受容されており、人間と非人間の双方が含みこまれる多様な要素の共同体を念頭に置いたネットワーク分析を手法とすることから、人間ならざるものにもアクターとしての主体性を見いだす理論として革新性が強調されてきた。
だが、こうした思潮の中では新理論の発明性を強調するあまり、押し並べて今日の文脈が特権化され、過去にも存在したはずの「非人間の社会」を巡る思想的脈絡は看過されやすい。実際、ラトゥールその人が、『虚構の「近代」』(Nous n’avons jamais été modernes)において、17世紀以来人間(=社会)/非人間(=自然)の厳密な境界が維持されてきたこと、その区別が実在に即さない憶見であることを、「近代憲法(Constitution moderne)」[1]という表現でもって告発している。だがそれは、今に至るまで自然と社会の分割は無批判に受容され、両者がハイブリッドな性格を持つことは認識されず、「非人間の社会」の可能性も構想され得なかった、という主張に等しい。ときおり19世紀以前の思想家を取り上げて評価することもあるが、時代文脈から切り離された先駆者として、現代の思想から逆算したアナクロニックな肯定がなされるに留まる。ラトゥールに即して言えば、19世紀フランスの社会学者であるガブリエル・タルド(Gabriel Tarde, 1843-1904)はその代表例であり、「自然と社会の分割」を拒み人間外部の社会を論じ得た先駆者として、当時の文脈を度外視する形でアクターネットワーク理論の「先祖(forefather)」や「先駆者(precursor)」[2]と評されてきた。
しかし、非人間と社会の混交的な性格を求める発想は現代人の専有物なのか、過去の人々も固有の文脈・関心に即して自然と社会の境界を揺るがそうとすることがあったのではないか。アナクロニズムではない仕方で、こうした思想を理解することはできないのか。以上の問題意識に従い、本論は19世紀フランスにおいても、「非人間の社会」に関わる思想的な系譜が存在したことを思想史的に明らかにするものである。以下に論じるように、19世紀には紛れもなく「非人間の社会」を問題化する思想的文脈が存在していたし、「先駆者」タルドの思想もまた、この土壌なくしては開花し得ないものであった。それ故に、この論文は「非人間の社会」を巡る思想史的探究であると同時に、タルドと19世紀フランス思想とのこれまで明らかにされてこなかった紐帯を探る試みでもある。
そこで本論は、社会学と生物学の関係性に注目する。19世紀に黎明を迎えた社会学は生物学から多くのヒントを得ており、「生物学的社会学(sociologie biologique)」と呼ばれる潮流を形成していた。事実、「創始者」オーギュスト・コントその人が「第一に生物学が、社会に関する思弁全体の必然的な出発点を与える」[3]、と生物学的な基礎づけを是認しており、後進にも同様の発想が継承されていく。他方で、生体の内に社会を見いだす「社会的生物学(biologie sociale)」の潮流が、生命科学の側にも存在した。例えば、「生理学的分業」という概念により、生命の原理が社会的な作用に類するものであることを主張した博物学者アンリ・ミルヌ=エドワール(Henri Milne-Edwards, 1800-1885)は、その顕著な事例である。社会学と生物学のこうした相互交流の中で、「非人間の社会」は活発に論じられ、社会/自然の境界も揺るがされるわけだが、タルド思想の前提条件の一部はこの中で設けられたのである。
本論は、生理学者デュラン・ド・グロの議論(第一節)、社会学者エスピナスの議論(第二節)、そしてタルドの議論(第三節)を通時的に配置することで、19世紀フランスにおける「非人間の社会」の思想的系譜を再構成し、彼らの思想内容ならびに影響関係を明らかにする[4]。そして、19世紀という「近代性」を所与とする時代にあっても、自然/社会の分割が必ずしも「憲法」のようには機能していなかったことを示す[5]。
1. デュラン・ド・グロにおけるポリゾイスムの思想
1-1. デュラン・ド・グロについて
ミルヌ=エドワールに代表される19世紀の「社会的生物学」の中で、とりわけ重要であるのは「ポリゾイスム(polyzoïsme)」と呼ばれる一潮流である。この一見して奇妙な語彙は、「多数の(poly-)」「生命・動物(zoo-)」「主義・論(-isme)」の各部分からなり、「多生命主義」とでも訳出できる[6]。文字通り生命が多数であることを指示しているが、この多数性は動物個体に内在するものとして規定されている。則ち、個体の生命は多数の小さな個体の生命を内包していること、動物個体はより小さい生命個体が複合してできた一つの全体であることが主張されている。だが、我々にとってポリゾイスムの要点は、内在する生命個体間で結ばれる社会的な諸関係を、生命体の基礎原理として掲げることにある。その意味でポリゾイスムは、有機物全般という非人間の内に社会を看取する試みであり、まさしく社会と自然とを架橋する思想的な立場であった。
ポリゾイスムの確立には、アルフレッド・モカン=タンドンやアントワーヌ・デュジェスなど、多くの博物学者が参与しているが、本論では代表的なポリゾイストとして生理学者のジョゼフ=ピエール・デュラン・ド・グロ(Joseph-Pierre Durand (de Gros), 1826-1900)に注目する。この万能人に関しては、その生涯を紐解くだけでも十二分に興味深い──共和主義の闘士として1851年のクーデターで亡命を余儀なくされたこと、亡命先の米国で催眠という事象を先駆的に見出したこと、人種理論で悪名高いヴァシェ・ド・ラプージュに影響を与えたこと──が、本論では彼の思想における社会と(非)人間の関係にのみ注目しよう[7]。
1-2. 「生命の要」の否定
デュラン・ド・グロは1866年の『哲学的生理学試論』(Essais de physiologie philosophique)の時点で、デュジェスらの研究に依拠した共同体的有機体観を(ポリゾイスムの語を用いずに)示していた。一つの有機体を生命諸個体の「社会的凝集(agglomération sociétaire)」だとすること、そしてこの結合が「生理学的連帯(solidarité physiologique)」[8]を獲得することなど、明確なポリゾイスムの特徴が見られる。だが、デュラン・ド・グロの特異性は、さらに踏み込んで、生物学/社会学の間に学問体系レベルでのアナロジーを示すことにある。有機体と人間社会の比較にあたり、これを「動物学的系列を通じた絶対的動物有機体の進化を司る法則」と「歴史を通じた社会形態の発展についての法則」──「社会学的系列(série sociologique)」[9]と表現される──の並行関係として理解している。未だ明確な形を取らない「社会学」について、デュラン・ド・グロが生理学者の立場から自然的な基礎づけを図ったことは特筆に値する。
1868年に発表された論文『ポリゾイスムあるいは人間における動物的多数性』(Polyzoïsme ou pluralité animale chez l’homme)において、上記思想の発展形がポリゾイスムの名の下で語り直される[10]。デュラン・ド・グロは、動物を「単純で分割不可能な一つの動物[個体]ではなく、一種の生命協同組合=社会(société de coopération vitale)を形成する個別の動物たちの複合体や集合」[11]と捉える有機組織法則として、ポリゾイスムを定義する。有機体を個体間の社会的な関係(協同や連帯など)の複合物として扱う図式は相変わらずだが、適用範囲の広さについて、彼の議論は他と一線を画す。「ポリゾイスムは、動物体節論(zoonitisme)という名で、デュジェスやモカン=タンドン以来の科学において無脊椎動物については認められていた。私は、この基本的な有機組織法則が、同様に脊椎動物の系列においても支配していることを確証したかったのだ」[12]と後に述懐するように、ポリゾイスムを下等動物から高等動物へ、そして人間にまで拡大しようとする意志が彼の思想を貫いている。そして、まさにこの「人間における動物的多数性」を論じ得たことこそが、当該論文の白眉である。
彼の議論は、博物学者アンリ・ド・ラカズ=デュティエに対する批判から始まる。ラカズ=デュティエは脊椎動物と無脊椎動物の非連続性を「ほとんど絶対的(presque absolue)」と固守し、無脊椎動物の生命は無中枢的である一方、脊椎動物には統一的な生命の存続を担保する唯一の中心──「生命の要(le nœud vital)」[13]──が存在する、と考えた。
だが、こうした概念は、デュラン・ド・グロにすれば「体系精神に由来する急場しのぎ、フィクション、妄想、おとぎ話でしかなく、もはや科学が捨て去らねばならない」[14]ものだった。先行するポリゾイストらが、いくつもの反証を与えている。解剖学者グラティオレは脊髄が複数の体節からなる集合体であることを示したし、生理学者カーペンター[15]は脊髄を環形動物になぞらえて、「神経回路という中枢(le centre du circuit nerveux)」[16]が髄節ごとに備わることを主張した。あるいは神経学者ヴュルピアンも、「動物体節」とその社会的関係が脊椎動物に内在することを明らかにした。脊椎動物が多中心的存在であること、その内部には社会が存在することは、こうして証明が済んでいる。
1-3. 人間における動物的多数性(と社会性)
しかしながら、既存のポリゾイストもみな一様に、ある限界に直面した。人間という限界である。人間存在へポリゾイスムを拡張することに関しては誰もが及び腰になり、人間内部の多中心性・社会関係という考え方を拒否してきた。グラティオレは体節が持つ被刺激性(excitabilité)と人間の脳の感覚性(sensibilité)とを峻別し、カーペンターは体節や下等動物のような機械的に働くものの内に「心理的な作用主(un agent psychique)」[17]を見出すべきではなく、人間の脳にのみ意識の心的能力を与えるべきだとした。ヴュルピアンも、動物体節は「少なくとも見かけ上(du moins en apparence)」[18]自発的運動をするばかりで、本当は機械的な運動をするに過ぎないと付け加えた。いずれにしても、人間の脳だけが中枢的意識を持つに値するとの制限が設けられる。「生命の要」を人間の特権として温存している。
なぜ、人間内部における心理的多数性──そして、これら心理的個体が形成する「非人間の社会」──を拒絶し、人間の意識だけは不可分で比類なき権能を有すると考えてしまうのだろうか。デュラン・ド・グロは答える。
生理学・医学あるいは心理学・道徳は、今日に至るまで人間というものを、完全に凝縮していて還元不可能であるような、生存・感覚・思考する一つの統一性として、単一かつ単純な生きた一つの身体として考えることを、一致して認めてきた。そして、この共通する最初の思い込みに基づいて、あらゆる彼らのドグマ的・実践的体制が形成されてきたのだ[19]。
問題は全て、「人間存在の不可分かつ絶対的な統一性というドグマ」を堅持する偏見──「モノゾイスム(monozoïsme)」──および、それと表裏をなす「ただの自動機械としての獣(« pur automatisme des bêtes »)」20)[20]という偏見、この二つに由来する。しかし、人間存在の唯一性を守るために、下等動物や脳以外の体節を心理なき機械だと考えることなど、デュラン・ド・グロにすれば不条理でしかない。
そもそも、他動物の脳と解剖学的な類似があるにもかかわらず、高等な心的能力を人間に特権化することに明確な根拠はない。それは、脳/その他体節の関係についても同様である。頭のないカエルがピンセットを脚で除ける作用は、「見かけの上でのみ意図的・意識的である」[21]と機械的に説明されるが、私たちが他者の感覚や意志を認めるにあたっては、「見かけ」以外の判断材料はない。さらに言えば、脳の有無を問わず、カエルの脚の運動に見かけ上の変化はない。となれば、一方で頭部のある運動を随意的と、他方で身体各部位の運動を機械的と判断することは恣意的である。つまるところ、ある部位に心的作用を認めるならば、それは有機体に全般化されるべきで、人間身体の各体節や下位の動物についても、心理的な能力・個体性およびその社会的な相互関係を認める他はない──その帰結が「人間における動物的多数性」であり、あらゆる動物に普遍化されたポリゾイスムである。
だが、今日では新たな諸事実が、[人間存在の統一性という]思い込みは誤謬であることを、我々に教えてくれているように思われる。新しい事実は、人間存在とは現実には有機体たちの集合であり、互いに異なる生命や自我(moi)の集合であることを教えてくれる。さらに、人間の見かけ上の統一性は、階層をなした一つの全体が持つ調和の内に存すること、この全体を構成する諸要素は緊密な協働や従属によって近接しながらも、各々の要素が自らの内に、個体としての動物が持つ本質的な諸属性や原初的な特徴を備えていることを教えてくれるのだ[22]。
いずれにせよ、非合理な偏見は退けられなければならず、生命におけるポリゾイスムは普遍化される必要がある。その過程で、人間存在は絶対的な単一人格としての立場を喪失し、代わりに「生理学的・精神的な意味における真の諸個体」[23]の社会的な凝集と化す。こうして、人間の絶対性を保護する旧来の観念体系は崩壊するが、それは嘆くべき事態ではない。デュラン・ド・グロにすれば、ポリゾイスムを認めて初めて、人間を動物学に立脚して理解することが可能となり、より豊かな人類学への道は開かれる。
デュラン・ド・グロは生理学者の立場から、人間の統一性・特権性を解体して、自然界のあらゆる非人間的な生物との連続性の内で人間を捉えることを最大の目的としており、人間例外主義に対する鋭い批判の視点に導かれた議論を展開した。生命体の内部に個体の多数性・社会的関係を見いだすのは、そのための方途であった。「非人間の社会」を人間の内部に導入することで、人間存在は単一の精神という本質的な根拠を喪失し、非人間たちのネットワークが作り出した効果へと帰される。本論の主旨に即せば、社会を生命の構成原理にまで高めた彼の議論は、「非人間の社会」を拡張したのみならず、人間存在の自明性をその内に解消した点でも重要である。
2. アルフレッド・エスピナスにおける「動物社会」の思想
2-1. エスピナスについて
デュラン・ド・グロが明示したポリゾイスムの思想は多くの学者を啓発し、19世紀末フランスを代表する動物学者であったエドモン・ペリエのような後進を生む一方で、他方では哲学の領域においてもベルクソンの言及するところとなった[24]。そして、社会学に対しても深い影響を及ぼすこととなる。現に、黎明期社会学の制度化にいち早く着手したある人物は、「生物の構成に関するデュラン・ド・グロの諸観点は、社会科学にとって最高の重要性を有するように思われる」[25]との称賛を残している。
その人物とはアルフレッド・エスピナス(Alfred Espinas, 1844-1922)である[26]。エスピナスは高等師範学校の文科で正統派の哲学的教育を受けた知的エリートであるが、既存の学問体制に従属するような人物ではなかった。フェリックス・ラヴェッソンが高等教育総視学官および哲学アグレガシオンの審査長を務めるなど、1860-70年代当時の学問的環境では、いわゆるフランス・スピリチュアリスムが哲学教育の規準を定めていた。だがエスピナスは、コントの実証主義やスペンサーの進化論など、科学主義や唯物論とも同一視された諸議論を前提として、「社会学」の学問的確立を目論む野心を持ったため、時に割を食わされた[27]。事実、アグレガシオンには幾度も落とされ、1871年──ラヴェッソンが審査に不在の年──になってようやく合格したし、博士論文『動物社会論』(Des sociétés animales)(1877)も審査員のポール・ジャネおよびエルム=マリー・カロから、コントやスペンサーを論じるべきではない、と不興を買っている[28]。だが、実証精神に肯定的な学者たちに受容され、第三共和制に移行する頃から学界の事情・趨勢も変化したことで、彼は学問的な成功を収めていく。
我々が問題としている、19世紀フランスにおける自然と社会との関係性ならびに「非人間の社会」というテーマに照らした際に、エスピナスが展開した社会学的な議論は以下の二点において際立った重要性を備えている。第一の点は、社会学の学問的な確立・制度化という野心的なプログラムの全体が、社会を自然との連続性の内で理解しようとする企図に導かれていたことに存する。そして第二の点は、社会を自然的な存在として理解するにあたり、社会的生物学の知見に立脚して「非人間の社会」を旺盛に論じたことにある。以下に我々は、『動物社会論』を参照し、これらの点を確認する。
2-2. 自然的実在としての社会
第一の点から見ていこう。社会を自然との連続性の下で、さらに言えば自然的実在として理解しようとするエスピナスの所信は、『動物社会論』の「歴史的導入(Introduction historique)」の内で強力に表明されており、エピグラフに掲げられたアリストテレスの文言──「国家は自然によるものの一つである」[29]──がそれを物語っている。全体の1/4以上を占める、この「歴史的導入」では彼の哲学史的素養が濃密に表現されており、社会を論じた数々の哲学思想が古代から19世紀に至るまで渉猟されていく。その中で、西洋思想史の全体は、社会を自然的実在として、あるいは人為的所産として考える二つの思想潮流の対立の場として描き出される。
当然のように、エスピナスは前者の系列を正当化し、自身をその末裔に位置づける。例えば、前者の立場についてはアリストテレスに、後者の立場については社会契約説の思想家たち(ホッブズ、ロック、ルソー)に、それぞれ代表的な地位が与えられるが、両者についてエスピナスが加える解説は全く中立的ではない。彼の解釈によれば、アリストテレスは『政治学』でポリスを一つの生き物として理解し、生命を持つ以上は成長・衰弱など有機的な自然法則が適用されると考えた。ゆえに、アリストテレスは「人間社会が構築・統治される技術は自然法則の一つの応用に過ぎないことを明らかにした最初の人物」[30]であり、社会を自然化する系列の父祖に相当することになる。
それとは対照的に、ホッブズやロックの議論は諸個人の自然状態や自然権を前提として、社会を事後的な同意によって形成されるものと考えるために、「市民社会は規約・人為でしかあり得ない」[31]ものになり下がる。ルソーも同様に、諸個人の本性的な権利・自由を絶対化するために、社会集団を抽象的な理想状態でのみ存続可能なものにしたとされる。則ち、彼らは社会の実在を否定し、観念的虚構としてしか存在しない人為的メカニズムに還元してしまった、と言うのである。それゆえ、エスピナスにとって社会契約説とは、社会学の発展を妨げる「障壁」 [32]に過ぎない。
だが、19世紀に入ってからは新たな三つの科学群──言語学・歴史学・古生物学、統計学・政治経済学、生物学・動物学──の展開を通じて、自然的実在としての社会が証明されてきた。自然と社会との連続性を強調する系列の勝利を決定的なものとした同時代の科学動向は、エスピナスによれば、総じてコントが先鞭を付け方向を示したものである。コントは諸科学を数学・天文学・物理学・化学・生物学・社会学に分類し、運動から社会的事実に至るまでの秩序を「単純から複雑へ」と向かう一つの系列にまとめ、直接的には生物学が「社会的生」を下支えしていると考えた。エスピナスにとり、社会学を諸科学、特に生物学を基礎として、初めて体系的に理解した──則ち、自然の中で社会科学を構想した──のがコントであった[33]。当時の学問環境において、コントは意図的に無視されていた。それでもなお、19世紀における諸学の綜合者としてコントを担ぎ出すエスピナスの姿勢には、社会を自然的実在として確証することへの覚悟が表れている。
2-3. 社会学への生物学的基礎づけ/生物学への社会学的侵略
エスピナスの根本的な企図が示されたところで、第二の点──エスピナスはいかに社会的生物学を援用したか、いかに「非人間の社会」を論じたか──に移ろう。
コントの遺志を引き継いで、生物学に立脚した「自然な」社会学を確立するにあたり、エスピナスが論拠を求めた先は、やはり生物学であった。審査員ジャネの「動物学の博士論文」という苦言[34]にも表れているように、エスピナスは19世紀社会的生物学について有する該博な知識を駆使して『動物社会論』の議論を組み立てている。参照の対象は、ミルヌ=エドワールにはじまり、デュジェスやデュラン・ド・グロ、高等師範学校の同期であったペリエにまで及び、代表的なポリゾイストは網羅されている。
実際、議論内容に関しても、先行する研究者たちのポリゾイスムを下敷きにしたことは明白で、アリやミツバチが作るような、いわゆる「動物社会」にはとどまらず、生物個体内に存在するより広範で微小な「非人間の社会」についても射程が及んでいる。そして例のごとく、社会を同種に属する諸個体の間に成立する相互的な協同・協働によって定義し、生命個体の発生原理が社会的であることを示唆すると同時に、デュラン・ド・グロと同じく要素となる諸個体を「精神的な諸アトム(atomes spirituels)」[35]と表現している。また、ペリエらと同様に生物の最小要素を細胞に見出した上で、そのポリゾイックな社会的関係から複雑な有機体が順次構成されるとした。エスピナスは、社会的生物学から得た知見を、以下三つの命題に要約する。
第一に、個体とは一つの社会であること、則ち、どんな生物もそれ自身が諸生物からなる一つの複合体であること。第二に、複合体の個体性は、構成諸要素の個体性を排除せず、むしろそれを前提として成長すること。第三に、有機的な構成は層状に重なり合った無数の段階(というより同心円状の圏域)からなること[36]。
こうしてエスピナスは、社会的生物学の最新研究を動員することで、一定の個体的・精神的権能を有する構成要素たちが形成する(メタファーではなく、正しい意味での)社会として生命個体を描写する。それは、デュラン・ド・グロと同じ意味で「非人間の社会」を肯定することである。
だが、ポリゾイストとは異なり、エスピナスがコントの精神──「社会学は、社会的事実が姿を見せるところであれば、どこにでも適用可能である」[37]──を継承した「社会学者」であった事実を忘れてはならない。彼は、生物学者の立場から生命体の内に社会関係を読み取っているわけではない。社会学の範疇において、社会学の拡張のために、社会の自然的実在を肯定するために、これら「非人間の社会」を論じていた。
個体を構成する有機的諸要素が呈する恒常的な集合現象を、社会学の中で理解する[社会学の中に含める(comprendre dans la sociologie)]べきなのだろうか。我々はやはりそう信じる[38]。
この観点から、グワラン・ド・ヴィトリー──共産主義的な性格を持った編集者・著述家──のような、社会学と生物学とを学問として分断しようとした先行議論は厳しく批判される。ド・ヴィトリーもまた、「社会学要綱のスケッチ」を著すなど社会学を確立する野心を持った人物だったが、人間社会だけが社会の名に値すると考えていた。彼にとり、科学の対象は最も顕著で高次な現象に限られるからである。反対にエスピナスは、「科学の対象は、知覚できた瞬間から知覚できなくなる瞬間までの、各現象集合の進化全体である」[39]と考える。ゆえに、わずかでも社会性が見出せるならば、その現象は社会学の範疇に含まれなくてはならない。
エスピナスが細胞理論を援用するのも、結局は社会学の下限を規定するためである。「細胞の最初の集合からこそ、社会学は始まらなければならない」[40]、とエスピナスは断言する。ただし、これも暫定的な結論に留まる。「もし観察によって滴虫類・卵核胞の内により単純な生命要素が発見されたなら、社会学はその領域にまで拡大することになる」[41]というのが、より一般的な彼の主張となる。要するに、ポリゾイックな関係が持たれ得る範囲、生物学的最小要素の関係から産業社会に至るまでの全領域が、社会学の対象なのである。エマニュエル・ドンブルが指摘するように、エスピナスの議論は、もはや社会学によって生物学の(ほぼ)全体を「侵略」[42]しているに等しい。
以上、エスピナスは社会学を確立するという責務を自らに課して、社会を自然的実在として確立することを目論んだ人物であった。だが、社会が人間的な契約よりも以前に存在する自然物であることを証明するにあたっては、生物学的領域は「非人間の社会」で埋め尽くされることになった。これらを勘案するに、エスピナスの議論は社会を自然化すると同時に、自然を社会化するものでもあった。黎明期社会学において、自然と社会の分割が疑問に付される中で、両者のハイブリッド性が露になった一幕と言えよう。
3. ガブリエル・タルドにおける「普遍的な社会学的観点」──継承と転倒
3-1. タルドについて
最初期社会学の制度化において立役者であったエスピナスの思想は、次世代の社会学者たちにも多大な影響を与えた。例えば、社会学の学問的確立を果たしたエミール・デュルケームも、エスピナスを「科学を作り上げるために社会的事実を研究した最初の人」[43]などと評価している。こうした影響は、デュルケームと立場を異にしたタルドについても例外ではない。実際タルドは、各所でエスピナスの『動物社会論』の重要性を認め、自らの議論に反映している。
タルドの社会学を表現するにあたっては「模倣」が代名詞となる。現に、主著『模倣の法則』(Les Lois de l’imitation)においては、「社会とは模倣であり、模倣とは夢遊催眠状態である」[44]というテーゼが提示される。ごく簡単に要約すれば、個人の精神間に成立する心的コミュニケーションを通じて、人々の間にある種の共通了解が育まれる現象が社会だ、というのがテーゼの内容である。この意味で、タルドの社会学は一般に「心理学的」と説明され、生物学的風潮には与さなかったと言われる。部分的には正しい。彼にとって社会の構成要素は第一に心理作用であったし、生物学的決定論で社会問題を論じる者は厳しく批判した。だが、タルドは生物学と社会学を結び付ける諸説を全否定していたわけではなく、これらに目を通し、ここから(も)自らの思想の材料を引き出していたのである。タルド思想における自然/社会のハイブリッド性、あるいは「非人間の社会」の観念を理解したければ、タルドと生物学的思潮の関係を把握する必要があるだろう。
こうした問題に取り組むにあたり、我々は「モナドロジーと社会学」(« Monadologie et sociologie »)に注目する。この小品はタルドが「形而上学的放蕩」[45]を自称するもので、人間の外部の社会を主題とした極めて大胆な哲学的思弁が高密度に展開されている。事実、「モナドロジーと社会学」において、タルドは躊躇わずにこう断言するのだ。
どんなものも一つの社会であり、どんな現象も一つの社会的事実である[46]。
あるいは、「あらゆる科学は社会学の下位分野と化す運命にあるように思われる」[47]という箇所を引用してもよい。いずれにしても、この世界に存在する万物が社会として理解可能であること、ひいては、自然の全てが社会として実在することを主張しており、「非人間の社会」が常識外れなまでに拡張されている。
以下、我々はこれらのラディカルな言明が導出されるまでに、生物学の知見が参照・活用されている様子を手短に通覧する。「非人間の社会」を普遍化するタルド思想の展開を追う中で、19世紀フランスにおける社会的生物学の系譜から、彼が何を継承し、何を批判・超克したかを確認していくこととしよう[48]。
3-2. 社会としての有機体──生物学的観点の継承
タルドによる社会概念の拡張が最も顕著に展開されるのは、生物学の領野においてである。現にタルドは、「有機体を社会に([l]es organismes aux sociétés)」[49]同一視することを宣言する。彼は、一般的な意味での「動物社会」──例えばアリやハチが営む社会──を越えて、そもそも生命なるものが社会的関係を原理とするということを言わんとしている。有機体そのものを社会と見なすこうした発想について、19世紀フランスにおける先行諸思想を豊富に引用しつつ、タルドは相当の紙幅を割いて論証することになる。
タルドは、社会/有機体のアナロジー[50]を否定するような議論をいくらか想定し、それに対して応答することから始める。例えば、「生体は明確かつ対称的な輪郭を持つ一方で、国境や都市の外郭は気まぐれで不規則に大地の上に描き出される」[51]という異論が考えられる。幅・奥行・高さの三次元的均整を考慮したとき、有機体はどれか一つの値が突出して大きくならない(ヘビやポプラのように長くとも極端な偏りは持たない)が、社会体の場合、建物を積み重ねて凝集した中世の城塞都市でさえも、二次元方向の広がりに比すれば高さは取るに足らない、これが反論の趣旨である。
だが、タルドにすればこうした対比は容易く相対化される。「巨大な公共建築物や国立学校、兵舎、修道院」[52]のような集団は、それ自体中央集権化された小さな国家として扱えるが、これらの機構は三次元に一定の均衡を保っている。一方で有機物の中でも、地衣類などは細胞の薄い層を形成して拡大し、明らかに高さ方向を欠いた非対称性を示しているし、その外縁も曖昧である。いずれにせよ 、社会/有機体間に絶対的な区別はなく、それゆえに、両者のアナロジーを拒絶するに足るような論拠は見いだされない、とタルドは(しかしかなり安易に)考える。
想定反論への応答を踏まえ、社会-有機体間に成立するアナロジーの正当性は証明されたとばかりに、有機体内で生じうる現象を軒並み社会的に説明し直す作業が進められる。細胞もまた心理的性質を有する個体であり、彼らの心的コミュニケーションを通じて「細胞社会(sociétés cellulaires)」[53]が形成されるとタルドは考えるが、これは宗教団体に類比される。信念と欲望を前提とした布教や改宗が存在する、閉鎖的な集団でありながら新規の成員は歓待する、成員だけが知る奇妙な符牒を用いた一見奇妙な集団である、成員の自己犠牲によって伝統的な儀礼を維持する保守的な世界である等、有機物を(宗教的な)社会として理解している。以上の行論について、タルドは単なる表現上の便宜には帰さず、実在的な意義があることを強調する。
生物学的な現象を、我々の社会における宗教的な現行──軍事・産業・科学・芸術的な側面というよりも──に同一視するからといって、少しもアナロジーの自由を濫用しているわけではない、ということに納得してくれるはずだ[54]。
こうして、「有機体を社会に」同一視することは正当化されるのだが、タルドは天啓を受けたようにゼロから全てを着想したわけではない。社会的生物学および生物学的社会学の著述が多数参照されている。
タルドの個人的交流や書簡、蔵書などの外在的な状況からも、これら先行潮流から受けた影響は推し量ることができる。タルドの活動拠点の一つであった『哲学雑誌』(Revue philosophique)はデュラン・ド・グロやエスピナスの主な寄稿先であったし、彼の書架にはエドワールからペリエまでポリゾイストらの著書に加えて、社会的生物学者の論考を多数掲載した『科学雑誌』(Revue scientifique)が並んでいた[55]。
事実、タルドはしばしば著作中で彼らを引用し、思想内容についても多くを享受した。まずもって、要素となる個体間の社会的関係が生命原理を構成するという発想は、ポリゾイスムとの顕著な一致を示している。現にそれは、先行する社会的生物学の思想を直接的に引用する中で発せられた主張である。幾度か言及したポリゾイストのペリエがその最たる例だ。タルドはペリエの「協同による進化(l’évolution par association)」[56]──生命進化は内属する有機的要素間の協同的関係により進展する──という概念を引きつつ、「ペリエ氏のような極めて慎重な科学者・博物学者が、有機体を社会に同一視することの内に生命の神秘の鍵や進化の究極公式を見いだし得たことは、実に特筆に値する」[57]との賛辞を与えている。「非人間の社会」の実在を生物学的次元で正当化するものこそ、デュラン・ド・グロらが展開してきたポリゾイスムだったのである。
そして、エスピナスもこの列に加えられることは言うまでもない。エスピナスに対するタルドの言及は頻繁であり、とりわけ動物社会の発想に関しては留保抜きに賛同している。「モナドロジーと社会学」においては、「この主題[動物社会]についてはエスピナスの素晴らしい著作を参照せよ」[58]と非人間的な社会を論じるためのモデルの一つとして扱われる。「社会学者」の立場から社会概念を自然へと拡張した点で、エスピナスは紛れもなくタルドの先駆者であった。
いずれにせよ、19世紀には社会現象をアナロジカルに生命領域へと拡張する風潮が存在したことは疑いようがなく、これがタルド思想における「非人間の社会化」を惹起したことも間違いない。ペリエやエスピナスのような生物学的な先行者の存在があるからこそ、タルドは社会概念を人間外部へと拡張する足掛かりを得られたのである。
3-3. 無機物への社会の拡張──生物学的観点の転倒
しかしながら、タルドは先行する生物学的思想の議論を無批判に受容したわけではなく、最終的に多くの社会的生物学者・生物学的社会学者と袂を分かつことになる。タルドが「有機体を社会に」同一視すると主張しつつ、同時に「社会を有機体に(les sociétés à des organismes)」[59]同一視する観点を廃棄したときが、決裂の瞬間である。言い換えれば、社会有機体論──社会を有機体の一種と見なし、構成員に対する「社会的意識」の超越的実在を主張する立場──を認めるか否かという点で、彼らは意見を異にするのだ。
実際、社会と有機体の関係を論じる者は、概して社会有機体論を結論とした。デュラン・ド・グロは有機体や社会体が構成員に対して超越した単一の知性・意志を持つことに対して例外的に懐疑的[60]で、有機体論とは一定の距離を置いていたように思われる。だが、ラヴェッソンはこう予言した──ポリゾイスムが正当であるにせよ、生命的統一性を認めることは不可避だ[61]、と。デュラン・ド・グロの後継はこの轍を踏んだと言えよう。例えばペリエは諸要素の協同の中から統一的な「社会的意識」が「実在的な人格」[62]を伴って生ずると述べた。エスピナスも社会有機体論的な観点を明らかにしており、『動物社会論』の結論部で「社会は、それ自身でそれ自身のために存在する意識としても実在する」[63]と社会的自我を肯定した他、「フランスにおける社会学的諸研究」という一連の論文ではアルフレッド・フイエに抗して社会的意識の存在を強く擁護している[64]。
だが、タルドにとって有機体論は不条理に過ぎない。諸個人の精神的なコミュニケーションの中から全く新しい精神的実体が創発されると考えるのは、無から有が「創造」されることを認めるに等しい。何よりこの帰結は、「社会を有機体に」還元する点で、「[包含関係の]流れる方向を誤解することで」[65]導かれているのである(その意味ではペリエに関するタルドの論評は正確でなかった)。だから、タルドにとってエスピナスは重要な参照先であると同時に、批判すべき対象でもあった。タルドは「エスピナス氏への応答」として、諸個人の中から「集合的自我(moi collectif)」が飛び出してくると考えるエスピナスの有機体論を、単なる神学的な神秘化として切り捨てることさえあった[66]。
我々が見るところ、社会的生物学を継承しつつも、有機体論を拒んだことにこそ、タルドによる社会の普遍化の要点はある。「社会を有機体に」同一視する方向では社会性の限界が細胞レベルに留まる一方、「有機体を社会に」の方向ならば無機物にまで押し広げられる可能性が生じるからだ。エスピナスは「天体は生物ではない。無機的な物質の塊については、いかなる相互的な機能もそれらを統合し得ない[、ゆえに社会は存在しない]──言葉を濫用して、万有引力をも相互的な機能と呼んだりするのでなければ」と述べたが、これは有機体論者が無機物に社会を否定することの例証である[67]。
こうして、有機体論を批判しその論理を転倒させることによって、(そしてデュラン・ド・グロの分析を引き継ぐがごとく)タルドは無機物の地平へと進んでいく。実際に彼は、エスピナスが否定した「原子社会(sociétés atomiques)」や「天体社会(sociétés d’astres)」[68]の存在を正当化するに至る。有機体と細胞がそうであったように、分子とは原子の社会であり、恒星系とは天体の社会だというのだ。社会の存在を有機物のみならず無機物を含む万物へと拡大するに当たり、タルドは以下のように社会概念を定義している。
社会とは何か。我々の観点に従い、こう定義することができるように思われる──極めて多様な形でなされる、各人による全員への相互所有[69]。
社会が相互所有であることの証明は、人間社会を例としてなされる。各人は「自分の」政府や公権力を所有するが、それと同時に閣僚や暴力装置の方も「自分の」国民を、監視対象を所有している。あるいは、労働者と消費者は異なるサービスや品目を通じて、必ず一人の消費者は「自分の」労働者を持ちながらも誰かの労働者となることで、相互に所有しあっているという具合である。こうして、社会現象の万事が所有関係として理解されるわけだが、それはあくまでも個人間の関係に立脚するものであって、諸個人に対して君臨する上位の意識が要請されることはない。
社会の要件として有機的統一性が求められず、構成要素間の所有関係で十分だとすれば、無機物もまた社会として理解可能になる。構成要素の主体性が担保されているか、という点は問題になり得るが、実を言えば既にタルドは「宇宙の精神化」[70]を論証しており、有機物だろうと無機物だろうと、相互的なコミュニケーションの条件は整備済みであった。例えば、熱・光・電波がある一点を中心に拡散すること、また、ある原子の振動が他の原子と競合しつつ無限のエーテルを専有しようとすることは所有領域を拡大する欲望の反映であるし、分子や天体というのはその結果生じた無機的な社会であるとされる。あるいは、ニュートンの重力理論において、ある一点を中心とした重力的な圏域が論じられることも所有傾向の表現として理解され、この重力圏=所有領域が交錯することで原子たちは支配者/臣下からなる帝国を建築するとされる。まさしく、エスピナスが拒んだところの相互性を、「無機的な物質の塊」にも認めるのである。
生命現象の社会も、改めて相互所有として語り直され、有機体の各部分は各々の欲望と企図を抱きながらも、全ての部分が目的かつ手段となるような仕方で連帯しているとされる。そこでは、他の有機体を捕食するような行動も、他者を自らの企図の下に服従させる「布教」という宗教的な形式の所有として解釈されている。人間社会については既述の通りだ。これら無機的・有機的・人間的な様々な所有関係について、タルドは「天体や分子の、有機や都市の国家」[71]と名指す。有機物は相互所有=社会であるし、無機物も相互所有=社会である。つまるところ、社会関係とは自然に存在する万物の存在論的な原理なのである。これが、タルドが言うところの「普遍的な社会学的観点」[72]に立った際に見えてくる世界の像である。
まとめよう。タルドは「どんなものも一つの社会である」という極めてラディカルな命題を提出し、「非人間の社会」をこれ以上望めないほどに拡張すると同時に、自然/社会の区別を骨抜きにした。だがこの議論はタルドが19世紀の時代文脈から独立に考えたものではなく、既に生物学的領域において「非人間の社会」を論じていた社会的生物学者やエスピナスの研究を吸収することによって成立したものであった。確かに、タルドは無機物にまで社会を拡大した点でより遠くへ到達した。だがこうした徹底は、先行する試みを踏み台にした継承・転倒を通じて可能となったのである。
おわりに
以上、19世紀フランスに「非人間の社会」を論じた思想的系譜が存在していたこと、そしてタルドのラディカルな思想もこの文脈を基礎として築かれていることを明らかにしてきた。確かに、取り上げた三者の立場は様々に異なる。デュラン・ド・グロは生理学者として、人間を動物学の延長線上で理解するために「非人間の社会」を過程として論じた。エスピナスは社会学者として、社会が自然物として実在することを証明するために「非人間の社会」を目的として論じた。そして、(少なくとも「モナドロジーと社会学」での)タルドは形而上学者として、自然の全体を説明するために「非人間の社会」を原理として論じた。各人の企図や思想的徹底の程度に隔たりがあることは事実である。
しかし、人間(=社会)/非人間(=自然)の絶対的な区別を拒む点では一致していた。なおかつ彼らは、(確かに一部では社会有機体論へと傾斜する傾向が存在していたとは言え)社会と自然の連続性を担保しても、単純に「自然」の内に「社会」を還元するような議論には至らなかった。有機体論に対して懐疑的・批判的なデュラン・ド・グロやタルドはもとより、『動物社会論』におけるエスピナスに関しても、生物学的領域を社会によって「侵略」する側面があったことは事実である[73]。彼らは「非人間の社会」を論じることで、社会を自然化すると同時に、自然を社会化していたのである。19世紀という「近代化」の進行する時代にあっても、自然/社会の分割(およびそれに起因する還元)というのは必ずしも自明ではなかったと結論付けられよう。
Notes
-
[1]
Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, [1991]1997, p. 23.
-
[2]
Id, “Gabriel Tarde and the end of social”, P. Joyce (ed.), The Social in Question. New Bearings in History and the Social Sciences, London, Routledge, 2002, p. 117-118.
-
[3]
Auguste Comte, Cours de philosophie positive, t.IV, Paris, Bachelier, 1839, p. 479.
-
[4]
本論で取り上げる三人の人物について、比較的または系譜的に取り上げた先行研究には一定の蓄積がある。三者すべてに言及しつつ一定の系譜を導き出そうとする包括的な研究としては、特にFrançois Vatin, « À quoi rêvent les polypes ? Individuation et sociation d’Abraham Trembley à Émile Durkheim », Trois essais sur la genèse de la pensée sociologique, Paris, La Découverte, 2005, p. 121-217、および Gauthier Autin, « Monadologie et biologie: lectures savantes de Leibniz au XIXe siècle », Revue de philosophie, No LXVIII, 2015, p. 139-159の二つを挙げられる。前者は、生物学/社会学の19世紀的な相互交流の諸相をデュルケームへと至る社会学史の中で系列化するもので、本論と企図を同じくする重要な先行研究である(ただし、タルドは反-生物学的社会学の論者として登場する)。後者は、19世紀フランスにおけるライプニッツのモナドロジー受容の一系譜に注目する哲学史的な研究であり、哲学的な射程を備えた生物学の諸理論を論じた末に、タルドを19世紀フランス的なモナドロジー受容の到達点として最後に取り上げている。
また、個別の二者関係を比較して取り上げたものも、寡少ではあるが存在する。例えばデュラン・ド・グロとエスピナスの関係については、先述のヴァタンに加え、Emmanuel d’Hombres, « “Un organisme est une société, et réciproquement ?” La délimitation des champs d’extension des sciences de la vie et des sciences sociales chez Alfred Espinas (1877) », Revue d’histoire des sciences, t. LXII, 2009, p. 402でも断片的に取り上げられている。デュラン・ド・グロとタルドの関係については、先述のオータンにある程度詳しいが、現状他には見当たらない。そしてエスピナスとタルドの関係については、Jean Milet, Gabriel Tarde et la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, 1970や赤羽悠「もうひとつの社会実在論──エスピナスとの論争から見たタルド思想の一側面とその政治的射程──」、『日仏社会学会年報』34号、2023年、137-156ページなどが存在する。以上、思想史を標榜する本論は、もっぱら哲学史・生物学史・社会学史の先行研究に立脚している。 -
[5]
19世紀において人間と自然との連続性を意識させ、人間の中心性の解体に資した議論として第一に挙げられるべきはダーウィンが理論化した進化論であろう。実際、マイアーやグールドなどの代表的な生物学史家がこれを認めているし(Ernst Mayr, “Introduction”, Charles Darwin, On the Origin of Species, Cambridge, Massachusetts and London, Harvard University Press, 1964, p. vii-xxvii, Stephen Jay Gould, Ever since Darwin. Reflections in Natural History, New York and London, Norton & Company, 1977)、日本でも山脇直司などが社会思想史的な観点から同様の議論を展開している(山脇直司『ヨーロッパ社会思想史』東京大学出版会、1992年、137-142ページ)。本論で取り扱う生物学的な議論は、いずれも『種の起源』の出版(1859年)・仏訳(ロワイエ訳1862年、ムリニエ訳1973年)以後のものであるため、ダーウィニズムの影響が予想される。だが、本研究で取り出す系譜において、ダーウィンへの言及はまちまちであるし、その理解や受容の程度にもむらがある。
例えば、以下に見るデュラン・ド・グロの「ポリゾイスム」論は、「種の起源」をめぐる論争への若干の言及はあるものの、人間と他の動物を結ぶ際に理論的に依拠しているのはジョフロア・サン=ティレール的な「プランの一致」の観念である。エスピナスの「動物社会」論はダーウィンからの引用に富んでおり、実際に進化法則を通じて社会本能が動物から人間へと伝達されていることを主張してもいるが、ここで「進化」の観念はスペンサーの理論に従っている。タルドにおいても、進化論は人間外の社会を論じるための重要な一要素として扱われているが、ヘッケルやペリエが媒介にされている。いずれにせよ、人間/自然の連続性について、ダーウィンの貢献は多少なりとも意識されていながら、彼の進化理論だけが決定的に重要な役割を果たしたとは考えられていないように思われる。本論は、必ずしもダーウィン一人の貢献には帰属されない(しかしダーウィン自身も当然関与している)、「非人間の社会」に関する広い時代思潮の一端に触れようとしている。 -
[6]
この語について、ラ・ヴェルガータは本論で扱うデュラン・ド・グロの造語だとしているが(Cf., Antonello La Vergata, « Lamarckisme et solidarité », C. Blanckaert et al. (éds.), Le Muséum au premier siècle de son histoire, Paris, Publications sciqntifiques du Muséum, 1997, p. 313-327)、確かではない。動物学者ポール・ジェルヴェ(1816-1879)が1858年の『人間骨格理論』(Théorie du squelette humain)で、既にこの表現を用いている。専門領域や活動の場の近さから見て、デュラン・ド・グロはジェルヴェから用語を引き継いでいる可能性がある。なお、ポリゾイスムに関してはVatin, art. cit., Autin, art. cit., Claude Blanckaert, La Nature de la société. Organicisme et scoinces sociales au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2004などを参照のこと。
-
[7]
多面的な活躍にもかかわらず、デュラン・ド・グロに関する先行研究は極めて少ない。主なものとして、以下を参照のこと。Dominique Parodi, « L’idéalisme scientifique : M. Durand de Gros », Revue philosophique de la France et de l’étranger, t. XLIII, 1897, p. 144-159 et p. 280-295. Autin, ibid. 日本語文献としては、フェリックス・ラヴェッソン『十九世紀フランス哲学』杉山直樹・村松正隆訳、千泉書館、2017年における、「脳生理学、神経学」、「精神異常」の各章および「人名索引」を参照のこと。
-
[8]
Joseph-Pierre Durand de Gros, Essais de physiologie philosophique, Paris, G. Baillière, 1866, p. 259. なお、この「生理学的連帯」という表現はエティエンヌ・ジョフロア・サン=ティレールの息子、イジドールが1859年の段階で用いていた。Cf., Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire naturelle générale des règnes organiques, t. II, Paris, Masson, 1859, p. 297.
-
[9]
Durand de Gros, op. cit., p. 271.
-
[10]
なお同論文は、『生理学・医学的哲学』(La Philosophie physiologique et médicale)(1868)および『比較生理学・比較解剖学が明らかにした人間の動物的起源』(Les Origines animales de l’homme éclairées par la physiologie et l’anatomie comparatives)(1871)で複数回採録されていく。本論では1868年の版を参照した。
-
[11]
Joseph-Pierre Durand de Gros, « Polyzoïsme ou pluralité animale chez l’homme », La philosophie physiologique et médicale, Paris, Germer Baillière, 1868, p. 84.
-
[12]
Id, « Qu’est-ce que la physiologie générale », Revue philosophique de la France et de l’étranger, t. XXXI, 1891, p. 638.
-
[13]
Henri de Lacaze-Duthiers, « Considérations générales sur les animaux invertébrés », Revue des cours scientifiques de la France et de l’étranger, NoIX, 1865, p. 142-145, cité par Durand de Gros, « Polyzoïsme ou pluralité animale chez l’homme », art. cit., p. 88. 強調原文。ただし、さらに元を辿れば「生命の要」は、生理学の大家フルーランが提唱したものである。キュヴィエ亡き後、博物学における裁定者としての姿勢と種の不変性の理論とを引き継いだ人物がフルーランであった。彼は「プランの一致」と進化論を混同して批判したこともあって、守旧派の博物学者として理解されることが多い(実際の彼の説はジョフロアとキュヴィエの折衷のようものだったが。Cf., Toby A. Appel, The Cuvier-Geoffroy Debate, French Biology in the Decades before Darwin, New York and Oxford, Oxford University Press, 1987, p. 210-212(『アカデミー論争 革命前後のパリを揺るがせたナチュラリストたち』西村顯治訳、時空出版、1990年、358-361ページ))。「ダーウィンのブルドッグ」ハクスリーも、フルーランによるダーウィン評──自然選択説は擬人主義に過ぎない──を最も愚かな批判の一例として取り上げている(Cf., Thomas Henry Huxley, “Criticism on “The Origin of Species””, The Natural History Review, No. XIII, 1864, p. 566-580)。
なお、ラカズ=デュティエはデュラン・ド・グロにとって必ずしも常に批判対象であったわけではない。現に、『哲学的生理学的試論』ではラカズ=デュティエに依拠した論が展開され、肯定的な影響は明らかである。ラカズ=デュティエもまた多数の個体からなる生物の観念を抱いており、その意味でポリゾイストではあったが、脊椎動物の優位を一際強固に支持したために批判されている。 -
[14]
Durand de Gros, « Polyzoïsme ou pluralité animale chez l’homme », art. cit., p. 89.
-
[15]
カーペンターは、ジョフロア・サン=ティレールの哲学的解剖学をイギリスで推進したグラントの弟子であり、『一般および比較生理学の原理』(The Principles of General and Comparative Physiology)を著すことでイギリスにおけるジョフロア派の活動に資した人物である。また、ダーウィンに先立って進化論的な世界観を提示してセンセーションを引き起こしたチェンバース『創造の自然史の痕跡』(Vestiges of the Natural History of Creation)を、表立って支持した数少ない専門家の一人がカーペンターでもあった。松永俊男『ダーウィン前夜の進化論争』名古屋大学出版会、2005年、31-59ページを参照のこと。
-
[16]
Durand de Gros, « Polyzoïsme ou pluralité animale chez l’homme », art. cit., p. 92. 強調原文。
-
[17]
Ibid., p. 95. 強調原文。
-
[18]
Ibid., p. 96. 強調原文。
-
[19]
Ibid., p. 98.
-
[20]
Ibid., p. 85. なお、「単生命主義」と訳出可能なこの語に関しても、ジェルヴェが1858年に用いている。Cf., Gervais, op. cit., p. 75.
-
[21]
Durand de Gros, «Polyzoïsme ou pluralité animale chez l’homme », art. cit., p. 97.
-
[22]
Ibid., p. 98-99. 強調原文。
-
[23]
Ibid., p. 84.
-
[24]
少なくとも『創造的進化』(L’Évolution créatrice)および『道徳と宗教の二源泉』(Les Deux sources de la morale et de la religion)では言及されている。ベルクソンがポリゾイストとして言及するのは専らペリエであるが、当のペリエはデュラン・ド・グロをポリゾイスムの「先駆者」として明示している。Edmond Perrier, « M. Edmond Perrier, à l’occasion de la Communication de M. Durand (de Gros), présentée par M. Marey », Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, t. CXX, 1895, p. 507-509.
-
[25]
Alfred Espinas, Des sociétés animales, Paris, Alcan, [1875]1935, p.68.
-
[26]
エスピナスに関する先行研究は少なくない。以下を参照のこと。山下雅之「動物社会から有機社会へ」、『社会学雑誌』10巻、1993年、46-62ページ。白鳥義彦「『動物社会』と進化論──アルフレッド・エスピナスをめぐって」、『変異するダーウィニズム』京都大学学術出版会、2003年、237-264ページ。Wolf Feuerhahn, « Les “sociétés animales” : un défi à l’ordre savant », Romantisme, NoCLIV, 2011, p. 35-51. d’Hombres, art. cit. André Lalande, « Notice sur la vie et les travaux de M. Alfred Espinas », Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 87e année, 1er trimestre, Paris, Alcan, 1927, p. 335-336.
-
[27]
エスピナスの実証主義的な思想は、フランス実験心理学の父と見なされるテオデュール・リボーとの交流の中で育まれたと考えられる(リボーがエスピナスに宛てた書簡群を参照のこと。 Raymond Lenoir, « Lettres de Théodule Ribot à Espinas », Revue philosophique de la France et de l’Étranger, t. CXLVII, 1957, p. 1-14)。だが、リボーの「実証主義」はヴァンサン・ギランも指摘するように、曖昧さを含んでいる(Vincent Guillin, “Théodule Ribot’s Ambiguous positivism: Philosophical and Epistemological Strategies in the Founding of French Scientific Psychology”, Journal of History of the Behavioral Sciences, Vol. XL(2), 2004, p. 165-181)。19世紀後半のフランスでは晩年のコントの「人類教」の可否をめぐってリトレ派(『実証哲学』誌)/ラフィット派(『西洋評論』誌)で派閥が分かれていたわけだが、リボーは(リトレ派の貢献を首肯しつつも)自らの『フランス国内外哲学雑誌』をリトレのように教条的な「セクト」にはしないことを明言していた(Lenoir, ibid., p. 14)し、そもそも心理学という分野そのものがコントの認めた学問体系の埒外にあるものだ。リボーは実証主義という語の意味を広く取り、ミルやスペンサー、ハクスリーなど科学志向的な議論を一括する形で理解していた。そして、エスピナス自身の実証主義にもまた、一定の捉え難さがある。リトレの議論との近さはあるが、実際に読んだかどうかは定かではない。コントに特別な役割を課していることは本文でも論じる通りだが、(リボーと同様に)スペンサーも同じ範疇で論じている。エスピナスに関しても、リボー的な、広義の実証主義を読み取るべきなのかもしれない。なお、当時の学問環境におけるエスピナスの立ち位置や試みの意義に関しては、Feuerhahn,« Les “sociétés animales” : un défi à l’ordre savant », art. cit.. に詳しい。また、エスピナスとリボーの交流に関しては、Id., « Autoportraits de Théodule Ribot en correspondant », Revue philosophique de la France et de l’Étranger, t. CXLI, 2016, p. 521-540を参照のこと。
-
[28]
Lalande, art. cit., 335-336. ラランドによって引用された、1877年1月19日のジャネによるエスピナス宛書簡を参照している。なお、ジャネとカロがスピリチュアリストとして経験論や唯物論に対して、しばしば厳しい防御的姿勢を取った人物であることは強調してもよい。19世紀の科学的唯物論を代表するビュヒナー『力と物質』(Kraft und Stoff)がフランスに紹介された際に、ジャネは『ドイツの現代唯物論 ビュヒナー博士の体系の検討』(Le Matérialisme contemporain en Allemagne. Examen du système du docteur Büchner)で批判的な応答を行ったし、連合心理学と決定論を融合したテーヌの哲学に対してジャネは『哲学の危機』(La Crise philosophique)を、カロは『神の観念とその新たな批判』(L’Idée de Dieu et ses nouveaux critiques)を著して対応している(杉山直樹「J・S・ミルとフランス・スピリチュアリスム」、『精神の場所 ベルクソンとフランス・スピリチュアリスム』青土社、2024年、95-98ページを参照のこと)。アカデミズムの哲学教育の内側からコントやスペンサーを論じるエスピナスに対して、相当の危機感が抱かれたことは想像に難くない。
-
[29]
アリストテレス『政治学』、1253a。邦訳は、アリストテレス『政治学』牛田徳子訳、京都大学学術出版会、2001年、9ページに準拠した。
-
[30]
Espinas, op. cit., p. 22.
-
[31]
Ibid., p. 23.
-
[32]
Ibid., p. 3. なお、ラトゥールもまた『虚構の「近代」』において、ホッブズやルソーなどの社会契約説を社会/自然を分断する思想として批判していた。
-
[33]
Ibid., p.74-77.
-
[34]
Lalande, art. cit., p. 335. ラランドによって引用された、1877年1月15日のジャネによるエスピナス宛書簡を参照している。
-
[35]
Espinas, op. cit., p. 169.
-
[36]
Ibid., p. 65.
-
[37]
Ibid., p. 79.
-
[38]
Ibid., p. 168.
-
[39]
Ibid., p. 166. ド・ヴィトリーは1848年に編集者としてテオドール・ダザミーやフランソワ・ヴィルガルデルの共産主義的・唯物論的・フーリエ主義的な著作を出版したほか、二月革命直後には自ら『共産主義とは何か? 共有ではない(Qu’est-ce que le communisme ? Ce n’est pas le partage)』という本を著した。その後は宗教批判の著作も残し、1870年代にリトレの『実証哲学』誌にて詳細かつ長大な社会学の構想を示した。ド・ヴィトリーによる社会学構想の詳細な議論内容、およびエスピナスとの論争の様子に関しては山下雅之『コントとデュルケームのあいだ 1870年代のフランス社会学』木鐸社、1996年、102-172ページを参照のこと。
-
[40]
Espinas, op. cit., p. 174.
-
[41]
Ibid., p. 178.
-
[42]
d’Hombres, art. cit., p. 405.「ほぼ」という限定を付したのは、当の最小要素に関しては単体であって社会は存在しないためである。
-
[43]
Émile Durkheim, « Cours de science sociale. Leçon d’ouverture ». La science sociale et l’action, Paris, puf, [1888]1970, p.96.
-
[44]
Gabriel Tarde, Les Lois de l’imitation, Genève, Slatkine, [1890]1979, p. 95 (『模倣の法則』池田祥英・村沢真保呂訳、河出書房新社、[2007]2016年、138ページ).
-
[45]
Id, Monadologie et sociologie, Paris, Institut Synthélabo, [1895]1999, p. 102(『社会法則/モナド論と社会学』村澤真保呂・信友建志訳、河出書房新社、2008年、163ページ). 『国際社会学雑誌』に投稿された「モナドと社会科学」と題された一年の論文が初出で、その加筆版が『社会学試論集』(Essais et mélanges sociologiques)に「モナドロジーと社会学」という一本の論文として収められている。今回は1999年に単著として再販されたものを参考したが、元の形式に即し論文として表記した。
-
[46]
Ibid., p. 58. 強調原文。
-
[47]
Loc. cit.
-
[48]
本論では、社会的生物学と関連する範囲の議論のみを扱うため、彼のモナドロジーの枢要にまでは踏み込めない。タルドのモナドロジーを扱った先行研究として、以下を参照のこと。Alexis Bertrand, « Les thèses monadologiques de Gabriel Tarde », Archives d’anthropologie criminelle, t. XIX, 1904, p. 623-660. Jean Milet, Gabriel Tarde et la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, 1970. 鈴木泉「哲学と社会学の幸福な闘争──タルドという奇跡についての一考察──」、『社会学雑誌』20巻、2003年、95-110ページ。笠木丈「表象と所有──ガブリエル・タルドにおけるモナドロジーの受容について」『フランス哲学・思想研究』20巻、2015年、157-167ページ。中倉智徳「19世紀末フランスにおける「科学の哲学」としての社会学──ガブリエル・タルドのネオ・モナドロジー成立過程」『フランス哲学・思想研究』20巻、2015年、15-28ページ。
-
[49]
Tarde, Monadologie et sociologie, op. cit., p. 59.
-
[50]
アナロジーは、一見して異なる現象集合間の間に論理的・法則的な秩序の相同性を見出す方法として、タルド哲学の根幹をなしている。単なる表現上の便宜に帰される「メタファー」とは異なり、直接的に「認識されたもの」と「認識されてないもの」との間に実在的な共通性を検出するものとして理解されている。以下を参照のこと。Anne Devarieux, «Différence(s) et analogie(s) : la méthode Tarde », Cahiers de philosophie de l’université de Caen. Lectures de Gabriel Tarde, no LIV, 2017, p. 35-58.
-
[51]
Tarde, Monadologie et sociologie, op. cit., p. 60.
-
[52]
Ibid., p. 62.
-
[53]
Ibid., p. 58. この語彙はエルンスト・ヘッケルからの借用である。フランスのポリゾイスムとは文脈が異なるために本論では触れなかったが、ヘッケルは生命体を細胞の社会として理解しつつ、精神と物質、人間と非人間との間に一切の本性的な区別をもたらさない一元論的で進化論的な世界観を構築した。ヘッケルこそ、19世紀後半の思想界で人間と自然を分割することに抗った代表者である。佐藤恵子『ヘッケルと進化の夢 一元論、エコロジー、系統樹』工作舎、2015年を参照のこと。
-
[54]
Ibid., p. 100.
-
[55]
以下の蔵書目録を参照のこと。Louise Salmon, Le laboratoire de Gabriel Tarde, Paris, CNRS ÉDITIONS, 2014, p. 307-427.
-
[56]
Tarde, Monadologie et sociologie, op. cit., p. 42. 強調原文。
-
[57]
Ibid., p. 58-59.
-
[58]
Ibid., p. 58.
-
[59]
Loc. cit.
-
[60]
Durand de Gros, Les Origines animales des hommes, Paris, Germer Baillière, 1871, p. 34-35.
-
[61]
Félix Ravaisson, La philosophie en France au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1867, p. 205(『十九世紀フランス哲学』杉山直樹・村松正隆訳、千泉書館、2017年、256ページ).
-
[62]
Edmond Perrier, Les colonies animales et la formation des organismes, Paris, Masson, [1881]1898, p. 214.
-
[63]
Espinas, op. cit., p. 432.
-
[64]
Id, « Les études sociologiques en France (2e article) », Revue philosophique de la France et de l’étranger, t. XIV, 1882, p. 337-367.
-
[65]
タルドによる有機体論批判が最も重点的に展開されたものとして、Gabriel Tarde, « L’idée de l’ “organisme sociale” », Revue philosophique de la France et de l’étranger, t. XLI, 1896, p. 637-646を参照のこと。ただし、こちらの論文では有機体論批判を強めるあまり、社会と有機体の間にアナロジーが成立しない事例が多数取り上げられる。
-
[66]
Gabriel Tarde, « Réponse à M. Espinas », Revue philosophique de la France et de l’étranger, t. LI, 1901, p. 661-664. 強調原文。
-
[67]
Espinas, Des sociétés animales, op. cit., p. 167-168.
-
[68]
Tarde, Monadologie et sociologie, op. cit., p. 58.
-
[69]
Ibid., p. 85.
-
[70]
Ibid., p. 45.
-
[71]
Ibid., p. 98.
-
[72]
Ibid., p. 85.
-
[73]
ただし、(恐らくデュルケームなどの批判を受けて)エスピナスは『動物社会論』で社会の範囲を拡大しすぎた点を後年になって反省し、有機的要素が凝集してできた動物個体を単なる「集合」として、「社会」とは峻別することになる。最終的に彼は「非人間の社会」から撤退し、自然/社会の分割を認めてしまう。Alfred Espinas, «Être ou ne pas être, ou du postulat de la sociologie », Revue philosophique de la France et de l’étranger, t, LI, 1901, p. 464.
この記事を引用する
上田 圭「19世紀フランスにおける「非人間の社会」の思想的一系譜——デュラン・ド・グロ、エスピナス、タルド」 『Résonances』第15号、2024年、30-49ページ、URL : https://resonances.jp/15/duran-de-gros-espinas-tarde/。(2026年02月28日閲覧)