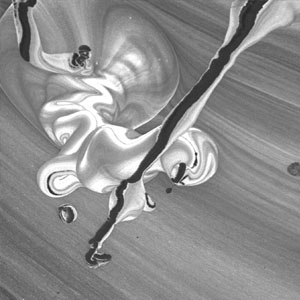喪の作業に抗って不可能な赦しと回復をめぐる哲学的考察
はじめに
本論文は、赦しと回復の関係性について取り扱う。赦しは特に第二次世界大戦後、多くは国家間や国内での争いにおけるものを対象に哲学的にも多く考察がなされてきた概念である。本論文の関心はより臨床的な視点に近く、個人が受けた外傷[1]に対する赦し、そしてその回復との関係を対象とする。
外傷、トラウマという言葉が発されることが今までになく日常的になった今日において、個人の中での赦しと回復との関係について取り上げることは、赦しの哲学的考察の系譜にとって決して無駄ではないだろう。赦しは常に国家間や国内の紛争における和解、すなわち関係性の回復と共に語られてきた。また個人間においても、相手の過失があり、赦すことで関係性が回復するというのは多くの人が身に覚えがあることだろう。赦しがこのように回復との関連性を持つ以上、個人の外傷からの回復においても、赦しは無関係ではありえない。そこに加害者がいることで、その人を赦すかどうかという問いが現れるからである。回復と赦しはその時、どのような関係にあるのだろうか。この論点から、本論文は出発する。
まずトラウマ研究の主要な理論家であるジュディス・L・ハーマンにおける赦しの位置づけを概観する。次に、赦しそのものを喪の作業として考えたポール・リクールの赦し概念について確認する。続いて、赦しの哲学的研究の系譜の中でも一際特異な議論を行うジャック・デリダの赦し論を確認し、ハーマンとリクールの理論との比較をした上で、赦しと被害者の回復との関係性の考察を試みる。医学領域において全ての病気に共通するような回復の明確な定義はないが[2]、本論文においては広く「症状の改善を感じること」を指すこととし、何が回復かという点はここでは問わない。
1. トラウマからの回復と赦し─ジュディス・ハーマンの回復理論
外傷からの回復を考えるとき、赦しはどのように捉えられているだろうか。まずはトラウマ研究の主要な理論を確認し、赦しと回復の関係性を確認する。
トラウマ研究の第1人者ジュディス・L・ハーマンは、被害者の回復は1)安全の確立、2)想起と服喪追悼、3)通常生活との再結合、そして近年追加された4)正義という4段階に分けられると述べる[3]。被害者が加害者から距離をとり、最低限の安全や見通しを確保し、自分や他人への信頼を少しだけ取り戻せてきたならば、第1段階の安全の確立が終了する。赦しが関わってくるのは、次の第2段階における服喪追悼(喪の作業)である。
まず第2段階の前半にあたる、想起について概観しよう。ハーマンの想起においては、被害者は外傷のストーリーを詳細に語ることが求められる。主要なトラウマ研究においては、トラウマの記憶は外傷性記憶と呼ばれ、正常な記憶と区別される。正常な記憶はストーリーのように語れるものであるのに対し、外傷性記憶は正常な記憶と異なり、言葉を持たず、断片的な、生々しい強烈な感覚やイメージだという[4]。この断片的で、いわば物語以前の外傷の記憶を、感覚や感情を思い起こしながら詳細に想起するのが第2段階の始まり、想起である。この作業は被害者に大変な努力を求める。ただ概略や事実を確認していくのではなく、その時に感じた気持ち、匂い、聞こえた音などを仔細に治療者に語ることが求められるためだ。そのようにして想起した外傷性記憶を、ストーリーの再構成を経て正常な記憶に変化させること。それがまず第2段階の肝要な点である[5]。治療者は、被害者が「現在という護られている投錨地から過去に身を沈め、また元に戻るという時間軸の往復」[6]と、その「価値と威厳とを肯定するような、外傷体験の新たな解釈を構築する」[7]手助けをする。被害者は断片的だった外傷体験を語ることで正常な記憶としてのストーリーとし、それを治療者とともにより肯定的なものに作り上げていくのである。
第2段階の後半に行われるのが赦しと関わってくる作業、服喪追悼である。しばしば「喪の作業」の名前でより良く知られているこの概念は、ジークムント・フロイトが1917年に発表した「喪とメランコリー」の論文により示され、現在では医療や心理学の分野において広く知られている[8]。フロイトによれば喪の作業とは、愛する人や理想など、各人の大切な対象を喪失した時に生じる心的過程(=喪)にある人が、その対象との結びつきから最終的に離脱していくまでの過程のことを指す[9]。ハーマンは喪の作業を、「外傷が破壊した古い自己の喪に服」[10]すこととして捉えている。ハーマンにおける喪の作業は、外傷によって失われてしまったものを認め、それを悼むことである。
この服喪追悼への抵抗として、復讐幻想、そして赦しの幻想が現れるという[11]。
生存者は、自分は怒りを超越することができ、そして、自己の意志による、優越者としての愛の行為を行うことによって外傷の打撃力を帳消しにすることができると空想する。しかし、憎しみと愛のどちらによっても外傷を悪魔祓いして消し去ることは不可能である[12]。
被害者はしばしば復讐(=憎しみ)か、赦し(=愛)を、どちらも自分に力を取り戻そうとして試みようとする。だがハーマンによると、結局はそれで回復することは不可能だという。復讐をたとえ遂げたとしても「負わされた傷のつぐないには決してならない」[13]し、加害者が罪を悔いて赦しを求めることはほとんどないからだ。復讐や赦しの幻想は、服喪追悼作業や回復にとって逆にひどい足枷となる[14]。復讐や赦しを考えずに失われたものを悼み悲しむという過程を通じて、被害者は加害者から真に自由になり、回復へと向かえる。
この回復への方向性は、加害者がいない場合の他の回復手法とも類似した点がある。例えば80年代にマイケル・ホワイトとデイヴィッド・エプストンにより考案されたナラティブセラピーや、リタ・シャロンらにより、90年代末から2000年代にかけて提唱された広く医療全般を対象とするナラティブ・メディスンなどは、患者に自己の物語を語らせ、その証人になるとともに、しばしばより良い物語への書き換えとともに過去と再統合を図る[15]。どちらも物語を語らせる点、そしてそれを書き換えながら、過去との再統合を行おうとする点においてハーマンの治療と類似している。これらの治療法と見比べてみると、トラウマからの回復においても回復の手法は通常の心理療法とそこまで大きく差はないということがわかる。もちろん被害者にとって加害者の存在は大きいが、治療の過程には関与せず、むしろ積極的に無視していくべきである、と言うこともできよう。
ハーマンはこのように、赦しを復讐の幻想と共に捨てなければならないものとして描く。傷を負った被害者にとって、赦しを考えることはむしろ回復を妨げると彼女は考えるからだ。被害者たちは、辛い想起や喪の作業のプロセスを経ながら、加害者を顧みることなく回復へと向かうことしかできないのだろうか。トラウマになるような加害──性暴力、戦争、虐待、パワハラ、セクハラなど──には、精神的拷問との共通点が多く見出されるとトラウマ研究者の宮地尚子は述べる[16]。精神的拷問が行う共通の行為として、「1)自己像の破壊2)他者や世界への基本的信頼感(basic trust)の破壊3)加害者の内在化」[17]がある。そして「拷問のメカニズムを知ることは、トラウマの本質を理解することにつながる」[18]という。彼女のいうようにこれらがトラウマの本質に繋がるとするならば、被害者は自己像が壊れ、世界に対する信頼を失い、真っ暗な感情の只中で、加害者との繋がりの中に取り残されているということになる。何らかの被害により、このような世界に一人放り出された人に、復讐でも赦しでもなく、ただ失われたものを服喪追悼することを要求する。これは、いくらそれが有効であるにせよ、あまりにも酷な要求ではないだろうか。ハーマンの記述はおそらく、最短の回復の道筋を描こうとしている。だが、回復を最優先にするあまりに、そこに寄与しないものは排除するという、ごく初歩的かつ、精神科医としては不可避なミスをもまた犯していると言えないだろうか。
修復的司法の研究者で、性暴力被害の当事者でもある小松原織香は、回復の大切さを重視しながらもこう批判する。
性暴力被害者にとって、回復することは最も大切なことだろう。私は自分が自助グループで回復の道を歩んだからこそ、心からそう思う。しかしながら、回復するだけがサバイバーの人生だろうか。私(たち)は、「心の傷が癒やされるべき存在」として、矮小化されていないだろうか[19]。
確かに傷を負って苦しい時には、誰しも回復を望む。だが現状のトラウマ研究やナラティブセラピーが示す回復の道筋は、あまりにも辛いことをさらに被害者たちに要求する。そればかりではない。トラウマがもたらす痛みを私たちが直視したとき、回復への希求と共に、とても赦せない、簡単になかったことにしてたまるか、という声もまた聞こえないだろうか。それは、この憎しみは、傷つきは、どうすればいいのかという被害者たちの叫びである。
このような叫びは、何度もトラウマ的事象を想起してしまうような「外傷への固着」[20]や、赦しや復讐幻想という姿をとって現れる服喪追悼への抵抗[21]として言及はされるが、最終的には乗り越えられるべき外傷記憶からの回復の特徴として語られるに過ぎない。ハーマンは加えてこうも語る。
復讐幻想を捨てることは正義の追求の断念を意味しない。逆である。そのことによって、他の人々と手をたずさえて加害者にその犯罪の弁明責任を問う過程が始まるのである[22]。
回復のためには、被害者と加害者の間の赦しや復讐の幻想ではなく、正義を社会的に追求していくことが必要なのだとハーマンは考える。だからこそ『心的外傷と回復』の31年後に書かれた『真実と修復』では、第4段階である「正義」が付け加えられたのだろう。「社会のあり方から心的外傷が生じている以上、そこからの回復も個人の問題ではありえない」[23]からだ。被害者が外傷経験を経て、人々と手を携えて社会正義の追求へと向かうこと。それがたどり着くべき地点なのである。『真実と修復』では赦しについて主に宗教的な圧力という観点からさらに考察が加えられているが、彼女の見方は一貫している。和解や赦しがもしなされるなら、正義が果たされた後であるというものだ[24]。それはあくまで回復が達成された後にくるのであり、回復の途上にある被害者たちの服喪追悼への抵抗としての赦しの幻想は捨象するよう求められる。
ハーマンの提唱するようなトラウマからの回復実践はもちろん重要だが、回復に抵抗する感情や加害者への複雑な心情など、回復に直接寄与しないかもしれない側面もまた、加害からの回復を考える際には、重要な要素としてもう少し深く検討されるべきではないだろうか。被害者のとても赦せないという声は、ただ切り捨てられるべきものだろうか。このような問いを持って、次章ではフランスの哲学者、ポール・リクールの赦し論を概観したい。
2. 喪の作業としての赦し─リクールの赦し論
ハーマンは復讐や赦しを正義とは分けたうえで回復の最終段階に正義を置き、赦しがたとえあるとしても正義がなされた後だと述べた。一方リクールは、正義と復讐は同じく不正に対する怒りから発される同根のものであるとした上で、「訴訟」という制度を持つかによって正義と復讐を区別する[25]。だが彼の赦しは正義の側にも、もちろん復讐の側にも属さない。
リクールの正義は訴訟によって復讐から区別されるが、訴訟という正義の制度のもとでは、赦しにその主立った場所を確保するのは難しい。なぜなら赦しが政治制度の中に存在してしまえば、それは罰を与えないこと、すなわち正義を貫かないことを認めることになってしまい、不正を認めることにつながるからである。そのため彼は特赦の制度にも強く反対する。彼が言うように、「赦しの政治学はないのである」[26]。リクールの赦しは「有罪性と過去との和解の問題系」[27]ではあるものの、このような理由から法的な領域には場を持たない。
リクールは後述するデリダの赦し論と多くの要素を共有する。特に、赦しの無条件性と、対象が赦し得ないものであるというのは重要な点である。「赦しは赦しえないものに向けられるのであり、さもなければ赦しではない。赦しは無条件であり、それに例外はなく、制限もない。それは赦しを乞うことを前提としない」[28]。また赦しはけっして義務ではなく、赦しの拒否も正当になされうるものである[29]。この点においても、デリダと共通する考えを持つ。
だが彼は最終的にはデリダと袂を分かち、赦しは赦し得ないものに向けられるべきであるが、それでも赦しは不可能ではない、と結論する[30]。この不可能な赦しを可能にするのが、赦しを「〈ひそかな行為〉(incognito)」[31]と定義することであった。この定義は、ドイツの哲学者クラウス・コダーレの議論を念頭に置いたものである。コダーレは20世紀に起こった解放戦争や民族的マイノリティ等の要求により起きた紛争・戦争を論じ、国民どうしは赦すことが可能かという問いを提出する。その答えは否であるが、「病的な記憶の治療薬」[32]として仲直りまでいかずとも関係の修正を可能にするような方向性を探求した。それが、「赦しの一種の『〈ひそかな行為〉(incognito(Incognito der Verzeihung))」としての正常性」[33]である。それは例えば西独首相がワルシャワで謝罪時に膝まずいたような制度の外にあるふるまいであり、制度化され得ない例外的性格のものである。制度の外で相手への思いやりや寛容さをもとうとし、関係の修正を行おうとすること。そのようなものとしてリクールは赦しを〈ひそかな行為〉(incognito)と定義する。
リクールは以下のように述べる。
赦しが悲劇性の増大するこうした状況と関わるなら、そこで重要になるのは、絡み合った、和解できない、償いえないといった典型的状況を待ち、受け入れようとする一時的でないような作業のみである。この無言の受け入れは、記憶よりも、永続的傾向として、喪と関係する。ここで言及した三つの形態は、じつは喪失の形態である。永久に喪失されたと認めることは、行動の悲劇性において、赦しの〈ひそかな行為〉とみなされるに値する[34]。
ハーマンが赦しを放棄して喪の作業に専念せよ、と主張したのとは異なり、「リクールは自らの赦しのモデルを、精神分析的な『喪の作業』に求める」[35]。リクールは喪の作業を、基本的にはフロイトに沿った形で「生者が生き残るために、自分から遠ざかり、離別する故人からの分離を受け入れる行程」[36]として記述している。この記述からして、ハーマンとリクールにおいて喪の作業そのものの理解はそれほど隔たったものではないといえるだろう。だが、ハーマンにおいては厳密に切り分けられていた赦しと喪の作業は、リクールにおいては同様のプロセスとして捉えられる。本当の意味で喪の作業を行うことができたならば、それは各人の中で起きる赦しになるという。
赦しの〈ひそかな行為〉とは一体、どのようなものを指すのだろうか。その例としてリクールは南アフリカの「真実と和解」委員会の事例を挙げる。デズモンド・ツツが議長を勤めたその委員会では、「理解し、復讐しない」という意図が掲げられ、かといって特赦もなかった。加害者たちは罪を告白し、被害者たちは受けた被害を公の場で語り、何が行われたかが公にされた。公聴会で被害を語ったことは、一部の被害者にとっては、記憶の作業と喪の作業を公的に行う機会となり、赦しへの道が開けた。だが同時に多くの人は特赦が拒否されたときには喜び、赦しの道には進まなかったという。「アパルトヘイトの暴力はもっと深く、もっと永続的に傷を残したのであって、数年間の公聴会ではその傷を癒すには足りなかった」[37]のだ。だがこれは絶望的な結果ではない。公的な場で行われた記憶と喪の作業は、確かに和解をしようとすることの構造的な限界を示しはしたが、公聴会で赦せなければそれで終わりというわけではない。その裏で時間をかけて、その後も行われる個々人の中での喪の作業、そこに「赦しの『〈ひそかな行為〉(incognito)』のようなもの」[38]をリクールは見出すのである。彼は公的制度が持つ赦しの実現への構造的限界は認識する一方で、「公的な承認はけっして些細なことではない」[39]、とその重要性も強調する。公的に被害が承認されることによって、名誉や自尊心といった自己評価が回復され、それは喪の作業すなわち赦しに役立つのである[40]。公聴会では赦しに至らない人々も、その後ゆっくりと、被害が公となったことで喪の作業は進む。喪の作業がいつの日か達成されうること、それそのものをリクールは赦しと呼んだ。
リクールの赦しは大々的に誰かに授けられるような、仰々しい制度だったものでは決してない。公的な制度の役割も視野に入れつつ、しかし制度の外側で起こり得るひそかなプロセスとして、赦しはある。
3. 2つの赦し─デリダの赦し論
ここまで、トラウマ研究の視点からの赦しとしてハーマンの、そして哲学的研究としてリクールの赦し論を概観した。ハーマンは、回復には不要な幻想かつ、加害者の悔悛が望めないのでほぼ不可能なものとして赦しを論じる。あり得るとしても正義がなされた後にのみそれは想定される。一方リクールは、同じく限りなく不可能に近いと考えながらも、被害者の記憶の喪の作業を通じ達成されるものとして、ひそかに、徐々に時間をかけて困難だが可能となりうる赦しを論じた。ここでもう一人、最後に確認したいのが、リクールも部分的に依拠する、ジャック・デリダの赦し論である。
デリダはまず、哲学史において赦しを論じたアレントとジャンケレビッチについて、その赦しが、2つのことを前提してしまっているとして批判する。赦しが「人間的な可能性(possibilité humaine)」にとどまらなくてはならない」[41]ということ、赦しが罰することとの相関項にあるということである[42]。ショアーのようなとても人間的尺度では償い得ないものについて、ジャンケレビッチは「死の収容所で赦しは死んだ」と述べる。赦しが人間的な可能性にとどまるのであればその通りとデリダは同意しつつ、赦しが不可能なものと共に始まるものだとすれば?と問う。デリダが主張するのは、「無条件の、非エコノミー的な、交換を超えた、贖罪や和解の地平さえ超えた赦し」[43]の必要性である。
デリダの赦しは無条件であり、通常求められるような加害者の悔悛を必要としない。だがそれはより倫理的であろうとするためのものではない。もし加害者が悔い改めてしまったら、それは以前の加害者とはもはや同じではない。そんな中で誰を、何を赦すのだろうかと彼は問うのである[44]。「赦しがあるためには、反対に、過ちと罪人とを、それ自体として、その両方が、悪と同じほど取り返しがつかないような仕方で、悪そのものとしてとどまり、赦しえないような仕方で、変化もなく、改善もなく、改悛も約束もなく、反復されうるようなところで、赦さなくてはならない」[45]のだ。
このようにデリダにおいては、通常の意味での赦しのほかに、上で語られたような無条件的な赦しという2つの赦しが存在する。無条件的な赦しが達成されるためには、それはいかなる目的とも全く関わりのないものでなければならない。
赦しが、たとえ高貴で精神的な(償いあるいは購い、和解、救済といった)ものであれ、ある目的に資することになるそのつど、喪の作業によって、何らかの記憶のセラピーやエコロジーによって、赦しが、(社会の、国民の、政治の、心理の)正常性の回復へと向かうそのつど、そのつど「赦し」はそしてその概念も──、純粋ではない。赦しは、正常[normal]でも、規範的[normatif]でも、正常化するもの[normalisant]でもあるべきではないでしょう。それは、不可能なものの試練に耐えつつ、例外的なまま、異常な[extraordinaire]ままであるべきでしょう。まるでそれが、歴史的時間性の通常の[ordinaire]流れを断ち切るかのように[46]。
デリダの思想では、たとえどんなに高貴な心の動きからであっても、ある目的に向かうような、ある種の「正常化」を希求するような赦しであれば、それは純粋な赦しではなくなる。つまり、デリダにとって、国交正常化のための赦しや、トラウマ被害者が回復や自己のエンパワメントのために加害者を赦そうとすることは、それがどんなに重要かつ高潔であったとしても、純粋な赦しではない[47]。デリダは、加害者の悔悛も赦しを請うことも要求しない。加害者は全く悔い改めないまま、そして被害者は全く回復への道を歩まず、和解や忘却の道を微塵も歩まないままでなくてはならない[48]。そのような赦しが果たして可能かどうかわからないと彼は前置きした上で、純粋な赦しは「赦すことのできないもの、赦されずにあり続けるものに対して与えられる」[49]という。それは「変形や喪の作業や犯罪者の告白を待たない、一つの絶対的な贈与」[50]なのである。「外傷が喪の作業に屈する」ような、「正常化」への圧力がこの社会には蔓延る、と彼は鋭く指摘する[51]。外傷から回復しようとする時、国民国家が分裂を超えて一つになろうとする時、そこには常に「正常化」を要請する社会の圧力がある。そんな社会の中で、デリダの希求する純粋な赦しは和解や忘却とは、全く別物でなくてはならない。
このように正常化の要請に決して応えることのない純粋な赦しのもとでは、喪の作業も、ましてやハーマンらトラウマ治療の専門家たちが目指す回復手法も行えない。ハーマンやナラティブセラピーなどの主要な回復理論は外傷を語り、言語化可能な物語にすることが肝要だとする[52]が、デリダにとっては、もはや言葉が介在した時点で通常の意味での赦しが始まってしまう[53]。むしろそこでは外傷は語りえぬまま、了解不可能なまま、傷は傷のままにあることが要求される。歴史の流れが中断され、例外状態という形のままにおいて。
歴史は、歴史の中断という基底のうえで、むしろ、一つの無限の、それも瘢痕化そのものにおいて、ぱっくり口を開けた非―縫合可能な傷のままであり、そのままであらねばならないだろう、そんな一つの傷の深淵の中で、続いていく。われわれがしばしば自らを保ちあるいは活動しなければなるまいのは、いずれにせよ、このような誇張法とアポリアとパラドックス性の地帯の中でなのである[54]。
純粋な赦しは、このようなアポリアの中で行われる、不可能なものとしか考えられないようなものである。実際彼は純粋な赦しを、狂気とまで評する[55]。ではデリダは、このような純粋な赦しを考えることで通常の赦しの全てを否定したかったのだろうか。そうではない。「無条件的なるものと条件的なるものは、なるほど、絶対的に異質であり、永久に、一つの限界線の両側であるが、両者はまた分離不可能なものでもある」[56]と彼はいう。2種の赦し──純粋な赦しと和解=通常の赦し──は両輪で駆動する、脱構築不可能なもの[57]である。通常の赦しにおいてほとんど同一視されてしまうような概念群である和解や喪の作業といったものとは切り分けて、純粋な赦しを我々は考えなくてはならない。だが一方で、否応無しに世界は通常の赦しのもとで進んでいく。そのことを理解していたデリダは、赦し(純粋な赦し)と和解(通常の赦し)は、脱構築不可能だが同一化は決してしてはいけない概念対として、赦しを論じる。純粋な赦しの実現は不可能かもしれないが、それはそこにあることで常に通常の赦しに揺さぶりをかける。
4. 赦しと正常化への圧力
我々はここまで、赦しに関連させてハーマンの理論、そしてリクールとデリダの赦しの理論を概観してきた。デリダの理論に則って考えるならば、ハーマンの赦しは、純粋ではない通常の赦しである。なぜなら彼女は、「神の許しでさえも、ほとんど全ての宗教体系を見れば、決して無条件ではない」[58]と前置きした上で、「真の許しというものは、加害者の方が求めて、告白し、痛悔し、つぐないをするまではさずけたくてもさずけられない」[59]と赦しを理解しているからである。明らかにハーマンの赦しは通俗的な、条件付きのものであって、デリダの考える純粋な赦しとは異なる。
一方、リクールはデリダの赦し論の多くの部分に同調し、赦しが不可能なもののみに与えられるべきであることや、無条件的であるべきことなどの考えを同じくしている。リクールはコダーレに依拠し、赦しを困難だが起こりうる、〈ひそかな行為〉(incognito)と定義づける。ここで元のコダーレの定義をもう一度確認するならば、それは「敵対する隣人間の正常な関係」[60]としての、「赦しの一種の〈ひそかな行為〉(incognito(Incognito der Verzeihung))としての正常性」[61]である。つまりそれは、病的な記憶を治療し、正常化するための行為であるということだ。その意味においては、確かにリクールはデリダのように無条件的で、贈与としての赦しを構想しているが、同時にその赦しは「正常化」を目指していると言う時点で、デリダの無条件的赦しとは全く異なる。デリダにおいて、ある目的を持ってしまった時点で、その赦しは純粋ではなくなるからだ。
「喪の作業は過去を現在から決定的に引き離し、未来に席を譲る」[62]とリクールは考える。リクールにとって「赦しは記憶の一種の癒し」[63]であり、それは過去に縛られた記憶を解放し、赦したものを未来へと導いてくれる。それは確かに好ましいことだろう。通俗的に言い換えてしまえば、「いつまでも過去にこだわらずに、前に進もうよ。」という声かけに近いだろうか。そんな声を苦しむ人に我々は善意からかけたくなるものである。だが同時にここで言えるのは、ハーマンのように赦しや復讐を無視してただ回復に努めたとしても、リクールのように困難ながらも赦しを授けようとし、記憶の喪を達成したとしても、それはどちらもデリダが言うような、「外傷が喪の作業に屈する」[64]ような正常化への圧力のもとで、同じ目的のもとで行われているということだ。リクールはデリダに基本的には同意しているがここが異なり、そしてそれは決定的な違いである。
純粋な赦しは傷跡が開いたままであることを要求する──純粋な赦しのためには、我々はそれを許容しなくてはならない。外傷は決して、喪の作業に屈してはならないのである。ハーマンのトラウマの回復理論やリクールの論じる赦しは、それがどんなにその後の人生に「良い」影響を与えるとしても、正常化という目的のもとに働く赦しであることに変わりはない。もちろん被害者個人個人が回復を希求することは多くの場合当然であり、それを否定する必要はない。だが社会に蔓延する、外傷を受けたらすぐに回復しなければならないといった正常化への圧力が孕む暴力性もまた、見過ごされるべきでない。デリダの純粋な赦しは、そのことを暴き出す。
5. 傷が傷のままにいる場所
デリダは結局、純粋な赦し概念を掲げることで何を実際には求めていたのだろうか。リクールのように、具体的に何をするのか、どのように純粋な赦しを実現するのかといったことまでは彼は語っていない。文学作品の例を挙げながらその可能性を示すにとどまっている。デリダの赦し論に関しては、講義録が出版されたこともあり、哲学分野を超えて近年多くの研究がなされてきている。例えば政治学者のエルネスト・ベルデハは他の論者がデリダの赦し論の無条件的赦しと条件付きの赦しとの交渉という点を重視していることを批判し、無条件的な赦しの優位性を強調する。そして無条件的な赦しが達成されるには、加害者の側に「負債」が残らないために完璧な忘却がなされなければならず、デリダの赦しは重要であるが、同時に忘却との結びつきがあると言う危険性を提示する[65]。また、ビジネス倫理分野のグリエルモ・ファルデッタは、職場での赦しというテーマでデリダの赦し論を論じる。とても赦せないような状況でも無条件的な赦しが加害者と被害者両者に新しい未来への可能性を開くとして、職場での赦しが条件付き赦しと無条件的赦しの両輪で考えられるべきだとする[66]。また宗教学者の杉村靖彦はデリダの無条件的な赦しについて、それは単なる非合理ではなく「思考を見張る狂気」であり、「赦しの名の下で現実に生起する営みの不純を暴き続けること自体が、この地点から見れば、不可能な赦しを夢見続けることとなる」[67]と評する。
このように無条件的な赦しは先行研究においておおむね好意的に解釈され、その哲学を超えた意義までもが強調される。一方で、我々が前節で主題的に取り上げた、外傷が喪の作業に屈すること、すなわち純粋な赦しが正常化の圧力を批判するような文脈で論じられたものはあまり見受けられなかった。だが、被害者の回復という臨床的な関心を持つ我々にとって、デリダの純粋な赦しが持つ意義は、この文脈においてこの上なく大きい。セラピー的な赦しが語られすぎる時、被害者は沈黙し、痛みを享受する可能性を奪われてしまう。回復とは真逆の方向性を持つように見えるデリダの純粋な赦しという場が確保されることで、傷が開いたままにあるための場、痛むがままに、沈黙のままにいさせてくれる場もまた、確保されうる。
赦しは、それが通常の意味の条件付きの赦しであっても、日常生活の中では根本的に善いものとして語られがちである。この社会が正常性を強く求めるが故に、それを何処か強要するような圧力の暴力性はその善性の影に隠されてしまう。例えばそれは、トラウマ研究の領域で近年言及されるようになってきた「心的外傷後成長(PTG:Post Traumatic Growth)」の概念にも如実に現れている。これは「困難な出来事の後にその当事者が経験する,「ポジティブな」心理的変容を指す概念」[68]である。ポジティブな変容、という表現から分かる通り、困難な出来事があっても人は常に正常に戻ることができ、それどころかその経験を糧にさらに成長することが善なのだ、といった強力な健常主義 (ableism)の現れた思想である。起こってしまった出来事は取り返しがつかないのだからポジティブな変化を得られた方が良い、というのは日常的感覚の中では間違ってはいないかもしれないが、それがトラウマからの回復のゴールとして、善いものとして据えられる時、それは危険性を帯びるのではないだろうか。「善意」から目指されたはずの成長や正常化はいつの間にか規範となり、圧力を帯びる。「いつまでも過去にこだわらずに、前に進もうよ。」とつい言ってしまいたくなる我々には、何処かそれに心当たりがないだろうか。
デリダの純粋な赦しは、喪の作業や忘却、和解を一切許容しない。外傷は外傷のまま、鮮血が流れ出るままでいることを要求する。それが確保するのは、正常化を求めるどころか拒絶してくるような、被害者にとって逆説的にも見つけ難い領域である。不可能な赦し、縫合されぬままでいることを求める傷。それは、とても赦すことができない、と叫ぶ被害者を肯定しうる。和解や喪の作業など、全ての正常化を拒むようなデリダの純粋な赦しはこの意味において、この上なく高い倫理性を示すのではないだろうか。
おわりに 喪の作業に抗うこと、それでも生きていくこと
デリダの純粋な赦しは、通常の赦しと両輪で駆動するようなものでありながらも、それは常に通常の赦しを見張り、傷が痛むままにしておける領域を確保するようなものである。その領域はセラピーが蔓延する今日では見つけ難く、我々はともすれば、その意義を見つけることすらままならないかもしれない。被害者が正常化も目指さずにただ痛みや悲しみを享受することは、今日ではほとんどの場合においてその意義は認められていない。正常化を希求せずにただ痛むがままにすることは、純粋な赦しを夢見ながらやっと行える例外的な行為である。
だが正常化の圧力に屈さないことは、赦さずにいられる代わりに、被害者にとって回復もできずに苦しみ続けるという新たな苦難にもなりかねない。我々は今、赦さないままに、別の仕方で回復することは可能なのかという新たな問いへと向かわねばならない。つまり、了解不可能性(外傷性記憶)を了解可能(正常な記憶)に変換することが従来のトラウマからの回復アプローチであったとするならば、了解不可能なまま、それでも痛む傷と共にあることができるような、正常性の外側へと回復することを考えなくてはならない。ハーマンは確かに赦すことなく回復することを提示したが、その赦しは合目的的なものにとどまり、正常化や赦しそれ自体については十分に検討していない。我々が検討すべきは赦すことなく回復することであるが、それは正常性の外側において、という条件付きである。
不可能な可能性として、純粋な赦しが考えられる必要があるのだ、とデリダはいう。純粋な赦しとは、決して忘却のことではない。赦しは忘却とは全く手を切らなくてはならない。言葉にすることとは別の仕方で、そこにあったことを確かに忘れないこと。傷は傷のままに残ること。そこにこそ、これまで主要なトラウマ回復理論で目指されてきた回復とは別の形の回復の契機が開かれるのではないだろうか。言葉でかたどった途端に和解や通常の赦しが始まってしまうのなら、しかしそれでも痛む傷と共に生きていかねばならないのならば、直接それを表象しない形で、しかしその傷に輪郭を与えることを目指す必要がある。
文化人類学者の田辺明生は、通常のトラウマ治療のアプローチと文化人類学のアプローチの違いについてこう語る。
文化人類学におけるアプローチでは、語ることによってトラウマ経験を解消するのではなく、語ることのできないトラウマ経験をむしろ関係性の中で分かち合いながら、日常の生きられる世界をいかに再構築しているかに着目する。そこでまず必要なのは、歴史語りに解消されない痛みの記憶が存在することの承認である[69] 。
受けた傷を客体化して語り、了解可能な物語に変容させていくハーマンのアプローチとは違い、外傷の了解不可能性を受け入れ、それと共に生きていく。そのような方向があるという[70]。人類学者のヴィーナ・ダスは、インド・パキスタン分離独立時に女性たちが受けた傷と生き延びについて、沈黙したままに、「それぞれの絶望を承認しまた同時に否定することによってお互いを支える」ことによってなされた、と述べる[71]。そして、「この沈黙を聞くこと、そこにいることによってそれに形を与えること」[72]が男性たちの仕事であった。
東日本大震災の後、ある看護師が被災地支援に行ったが、することがなかったのでただたこ焼きをみんなで焼いていたというエピソードがある[73]。このエピソードを紹介する哲学者の榊原哲也は、これは看護実践だと断言する。もちろん、いざとなればすぐに医療措置を受けられるという安心感、看護師がそこに居合わせて気遣ってくれているということは大きいだろうが、それだけではないだろう。それ以上に、被災者一人一人には傷があるということを、居合わせてそれに形を与えるような実践として、このエピソードは捉えることができる。そこに「いる」ことで、他者が沈黙のままに痛みを聞き取り、傷に場を与えることの可能性が開かれる。臨床心理学者の東畑開人はケアとセラピーを比較し、セラピーが変化を目指す営みであるのに対し、ケアはこれ以上の傷つきを避け、現状を続けていくための営みであると述べる[74]。つまり、ケアにおいては通常、向かうべき目的が存在しない。ケアとセラピーという二項対立において、セラピーに対し、ケアには目的がないというのならば、それはそこにある痛みの承認、傷の承認でもあるはずである。包帯を巻かれるだけで、ベッドサイドで手を握られるだけでときに我々はかすかに回復を感じることがある。それはそこにある傷に輪郭を与え、その痛みを承認する営みに他ならない。そしてそのことによって、我々は回復しうるのである。
デリダは、「赦しは和解のセラピーには属しません」[75]、ときっぱりセラピーと赦しを切り分ける。それは何より、赦しが合目的的になること、正常化のレールに乗ることを警戒するからである。「将来において、来るべき諸世代において、償い得ぬものの赦しが生じ=場を持ったときでさえ、赦しは生じず=場を持たなかったことになる」[76]ことを我々は感じ取る。我々は時間が流れるに従い、否応なしに正常化に向け回復し、忘却や和解は進んでしまう。だが純粋な赦しは、決して生じないという場をただ一つ保持することで、赦さないことや、傷のままであるということに場を与える。赦さぬままに、回復を拒みながら、正常性の外側へと向かうこと。純粋な赦しが可能にするのはそのような道程である。それは喪のある風景の中でそれでも生きていこうとする人に寄り添い、回復を拒む強張った身体に刻まれた言語化不可能な外傷に、忘れないよう形をあたえる。
本論文は、決して記憶に意味づけや物語化をして回復する、という王道のトラウマ回復の手法や喪の作業を否定するものではない。ただあまりにもセラピーが語られすぎていること、そして、トラウマからの回復の道のりに、赦せない、といった声を捨象するような正常化への圧力がどこか働いていないかということ、そのことを問題にするのみである。デリダの考える純粋な赦しは、不可能でありながらもそれを考え続けることで、正常化を目指す回復において積極的に捨象されてしまう「無駄」な抵抗を、秘匿し続けてくれる。そしてそれは絶えず、我々にその未だ到来しない赦しを考え続けさせることで、傷は傷のままに、しかしそれでも生きていく契機を開いてくれるのではないだろうか。
Notes
-
[1]
外傷は元々単に身体についた創傷のことを指す言葉であったが、19世紀末になって心の傷を包含するより広い意味にまで拡張された。本論文においてはトラウマになるような経験で受けた傷を総称し、外傷と呼ぶ。
-
[2]
山川裕子「うつ病患者の回復過程における改善の認識」『川崎医療福祉学会誌』16号、第1巻、2006 年 7月(1)、92ページ。
-
[3]
ジュディス・L・ハーマン『真実と修復』阿部大樹訳、みすず書房、2024年、3ページ。トラウマ研究の古典であり広く読まれている彼女の前作『心的外傷と回復』においてステップは3段階とされており、世界的に知られているのはそちらの方である。
-
[4]
ジュディス・L・ハーマン『心的外傷と回復[増補版]』中井久夫訳、みすず書房、1999年、55ページ。
-
[5]
同上、259-268ページ。
-
[6]
同上、263ページ。
-
[7]
同上、264ページ。
-
[8]
島薗進『ともに悲嘆を生きる グリーフケアの歴史と文化』朝日新聞出版、2019年、73ページ。
-
[9]
ジークムント・フロイト「喪とメランコリー」『メタサイコロジー論』十川幸司訳、講談社学術文庫、2018年、132-134ページ。
-
[10]
ジュディス・L・ハーマン、1999年、前掲書、293ページ。
-
[11]
本稿では紙幅の関係で詳述はしないが、ハーマンは修復的司法の主要な思想家であるハワード・ゼアがChanging Lenses: A New Focus for Crime and Justiceの中で赦しの必要性を説いたことを批判し、加害者志向で被害者への配慮が十分でないことに警鐘を鳴らしている(小松原織香「赦しについての哲学的研究 修復的司法の視点から」、『現代生命哲学研究』第1巻、2012年、 25-45ページ)。ハーマンは復讐も赦しも否定するが、加害者を擁護しているわけではない。むしろ被害者は加害者の悔悛を待つ必要はなく(ハーマンは赦しを、加害者が罪を告白し悔い改め赦しを求めたときに初めて与えられるものと考える)、赦しという愛を加害者に分ける必要はないというのがその主張の趣旨である(ジュディス・L・ハーマン、1999年、前掲書、282ページ)。
-
[12]
同上、281ページ。
-
[13]
同上、282ページ。
-
[14]
同上、282ページ。
-
[15]
リタ・シャロン [ほか] 著『ナラティブ・メディスンの原理と実践 』斎藤清二・栗原幸江・齋藤章太郎訳、北大路書房、2019年; 宮坂道夫『対話と承認のケア : ナラティヴが生み出す世界』、医学書院、2020年、228-242ページ。
-
[16]
宮地尚子『トラウマの医療人類学』みすず書房、2019年、244ページ。
-
[17]
同上、239ページ。
-
[18]
同上、233ページ。
-
[19]
小松原織香『当事者は嘘をつく』筑摩書房、2022年、86ページ。
-
[20]
ジュディス・L・ハーマン、1999年、前掲書、53-54ページ。
-
[21]
同上、279ページ。
-
[22]
同上、281ページ。
-
[23]
ジュディス・L・ハーマン、2024年、前掲書、4ページ。
-
[24]
同上、102ページ。
-
[25]
佐藤啓介『死者と苦しみの宗教哲学 宗教哲学の現代的可能性』晃洋書房、2017年、24ページ。
-
[26]
Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2000, p. 635(『記憶・歴史・忘却(下)』久米博訳、新曜社、2005年、297ページ).
-
[27]
Ibid., p. 536(同上、196ページ).
-
[28]
Ibid., p. 605(同上、273ページ).
-
[29]
ポール・リクール『正義をこえて 公正の探究1』久米博訳、法政大学出版局、2007年、198ページ。
-
[30]
本稿ではやや脱線となるので詳述はしないが、リクールは「赦しえない過ちと不可能な赦しとの間の隔たりを探索する」(Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli , op. cit., p. 637(ポール・リクール著『記憶・歴史・忘却(下)』久米博訳、新曜社、2005年、299ページ.) ことで最終的には不可能な赦しを達成しようとした。より具体的には、「行為者をその行為から切り離す」(Ibid., p. 637(同上、299ページ).)こと、そしてその行為者が別様に振る舞い、再び社会の中で生きていけることの可能性に賭けることを模索し、そこに困難ながらも不可能な赦しがある、と考えた。「赦しの星のもとでは、有罪者はその罪やその過ちよりほかのものも可能である、とみなされよう。有罪者はその行動能力を取り戻され、行動は継続する能力を取り戻されよう。考慮という些細な行為において敬意を表されるのはこの能力であろうし、そこにおいてわれわれは公的場面で演じられる赦しの〈ひそかな行為〉(incognito)を認めたのである。」(Ibid., p. 642/(同上、303ページ).)
-
[31]
Ibid., p. 594(同上、261ページ).
-
[32]
Ibid., p. 618(同上、284ページ).
-
[33]
Ibid., p. 618(同上、284ページ).
-
[34]
Ibid., p. 653(同上、315ページ).
-
[35]
佐藤啓介、前掲書、25ページ。
-
[36]
ポール・リクール『死まで生き生きと 死と復活についての省察と断片』久米博訳、新教出版社、2010年、41ページ。
-
[37]
Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli , op. cit., p. 629(ポール・リクール著『記憶・歴史・忘却(下)』久米博訳、新曜社、2005年、293ページ).リクールにおいて赦しは、時間的な側面からも考えられている点に特徴がある。「正義も赦しも決して一回的・瞬間的な行為ではない」 (佐藤啓介、前掲書、25ページ。)。確かにリクールは赦しはある、と考えはする。だが、注37の引用部分にも明らかなように、それは公的な公聴会で簡単に達成されるようなものではなく、公的な場の裏でひそかに(困難だが)起こりうるもの、と彼は考えていた。赦しに、例えば加害者の悔い改めとの短絡的かつ直線的な因果関係を認めるのではなく、それは悔い改めのように都度起こるものとの循環的関係を見出すのである。彼の赦しが一回的・瞬間的なものでもなければ、あるタイミングで都度起こるのではなく、常に既にそこにとどまるようなものであることは、リクールの赦し理解において重要な点だろう。
-
[38]
Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli , op. cit., p. 629(ポール・リクール著『記憶・歴史・忘却(下)』久米博訳、新曜社、2005年、293ページ).
-
[39]
ポール・リクール著、2007年、前掲書、190ページ。
-
[40]
同上、190ページ。
-
[41]
ジャック・デリダ「世紀と赦し」、鵜飼哲訳、『現代思想』2000 年 11 月号、95ページ。
-
[42]
ジャンケレヴィッチは「赦し得ないもの」が赦される可能性も認めていたが、そこをデリダはとりあげていないという批判もある。(奥堀亜紀子「 『赦し』とは何か 無条件的な赦しは必要なのか」、『 21世紀倫理創成研究』2015年3月号、 66-83ページ。)
-
[43]
ジャック・デリダ、前掲論文、92ページ。
-
[44]
同上、95-96ページ。
-
[45]
同上、96ページ。
-
[46]
同上、92ページ。
-
[47]
「しかじかの形で、たとえば形を変えたり和解や喪の作業といった形で、忘却が浸透しかねないようなところではどこでも、赦しはもはや純粋なものではなくなります。」(ジャック・デリダ『言葉にのって 哲学的スナップショット』(林好雄・森本和夫・本間邦雄訳、ちくま学芸文庫、2001 年、201ページ。)
-
[48]
同上、202-203ページ。
-
[49]
同上、202ページ。
-
[50]
同上、204-205ページ。
-
[51]
ジャック・デリダ、前掲論文、97ページ。
-
[52]
ジュディス・L・ハーマン、1999年、前掲書、261-269ページ; 野口裕二『物語としてのケア ナラティヴ・アプローチの世界へ』、医学書院、2002年、56-59ページ。
-
[53]
「被害者が罪人を「理解」するやいなや、和解の舞台はすでに始まっており、そしてそれとともに、普通の意味での赦しも始まっています。」(ジャック・デリダ、前掲論文、102ページ。)
-
[54]
Jacques Derrida, Le Parjure et le Pardon, op. cit., p. 62(前掲書、66ページ).
-
[55]
「赦しは狂気であり、理解不可能なものの夜に、しかし明晰に、没入していくのでなくてはなりません。」(ジャック・デリダ、前掲論文、102ページ。)
-
[56]
Jacques Derrida, Le Parjure et le Pardon, op. cit., p. 67(前掲書、75ページ。)
-
[57]
鵜飼哲・高橋哲哉「討議 和解の政治学」『現代思想』2000 年 11 月号、66ページ。
-
[58]
ジュディス・L・ハーマン、1999年、前掲書、282ページ。
-
[59]
同上、282ページ。
-
[60]
Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli , op. cit., p. 618 (前掲書、284ページ). 強調引用者。
-
[61]
Ibid., p. 618(同上、284ページ).強調引用者。
-
[62]
Ibid., p. 649(同上、310ページ).
-
[63]
ポール・リクール著、2007年、前掲書、198ページ。
-
[64]
ジャック・デリダ、前掲論文、97ページ。
-
[65]
Ernesto Verdeja, 《 Derrida and the impossibility of forgiveness 》, Contemporary Political Theory , 2004, 3(1),p. 23-47.
-
[66]
Guglielmo Faldetta, 《 Forgiving the unforgivable: The possibility of the ‘Unconditional’ forgiveness in the workplace》, Journal of Business Ethics, 2022, 180(1), p.91-103.
-
[67]
杉村 靖彦「『困難』と『不可能』の間で 『赦し』をめぐるリクールとデリダの論争から」、『創文』 創文社 、2005年4月号、4ページ。
-
[68]
菊池美名子「トラウマ・スタディーズと批判的障害学を接続する」、『臨床心理学』2021年増刊第13号、133ページ。
-
[69]
田辺明生「生き延びてあることの了解不可能性から、他者との繋がりの再構築へ——インド・パキスタン分離独立時の暴力の記憶と日常生活」、『トラウマを生きる—トラウマ研究1』田中雅一・松島健編、京都大学学術出版会、2018年、507ページ。
-
[70]
本論文では詳細には立ち入らないが、ハーマンが部分的に依拠するピエール・ジャネは、ハーマンの理解とは異なり、過去のトラウマ的出来事を詳細に語ることではなく、〈あの時〉の私を過去化し、〈今ここ〉の私を意識することに重点をおく。ジャネの理論を研究することで、より具体的なアプローチの構想も可能だろう。(松嶋健「トラウマと時間性 死者と共にある〈いま〉」、『トラウマを生きる—トラウマ研究1』(前掲書、2018年))
-
[71]
Das, Veena, 《 Composition of the Personal Voice: Violence and Migration 》, Studies in History , 1991, 7(1):65
-
[72]
ヴィーナ・ダス「言語と身体 痛みの表現におけるそれぞれの働き」、『他者の苦しみへの責任 ソーシャル・サファリングを知る』坂川雅子訳、みすず書房、 2011年、62ページ。
-
[73]
榊原哲也『医療ケアを問いなおす 患者をトータルにみることの現象学』、筑摩書房、2018年、204ページ。
-
[74]
東畑開人『居るのはつらいよ』、医学書院、2019年。
-
[75]
ジャック・デリダ、前掲論文、97ページ。
-
[76]
Jacques Derrida, Le Parjure et le Pardon, op. cit., p. 61(前掲書、65ページ。)
この記事を引用する
若杉 茜「喪の作業に抗って——不可能な赦しと回復をめぐる哲学的考察」 『Résonances』第15号、2024年、ページ、URL : https://resonances.jp/15/contre-le-travail-de-deuil/。(2025年07月01日閲覧)