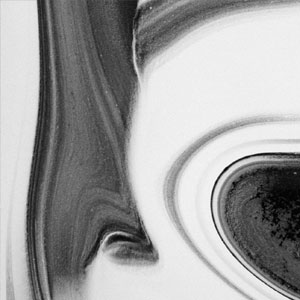フランスの「ユダヤ人生存者」をめぐる歴史論争なぜ、約24万人のユダヤ人がナチ占領下のフランスを生き延びたのか?
はじめに
1940年、ナチス・ドイツ占領下のフランスには、約32万人のユダヤ人が住んでいた。弁護士、そして歴史家としても著名なセルジュ・クラルスフェルトの調査によると、その約32万人のユダヤ人のうち、約7万4150人がナチ占領下のフランスで逮捕され、強制収容所で死亡したという[1]。この調査は、フランスのユダヤ人の約4人に1人が死亡したという悲惨な実態を明らかにした一方で、1940年時点でフランスに居住していたが、収容所に連行されることのなかった約24万人のユダヤ人の存在を同様に浮かび上がらせた。近年、強制収容を免れ、ナチス・ドイツ占領下のフランスを生き延びた約24万人のユダヤ人──「ユダヤ人生存者(survivants juifs)」に焦点を当てた研究が増えている。というのもフランスはユダヤ人生存者の数が極めて多く、またフランスに住んでいたユダヤ人に占める彼らの割合が約4分の3にあたり、ナチ占領下の他国にくらべて高かったことから、何らかの「フランスの特殊性」があるのではないかと考えられたためである[2]。ホロコーストに関する歴史研究では、論争や記憶の整理を目的とした史学史研究が多くあるが、本稿ではこうした研究で未だ取り扱われていない「ユダヤ人の生存」に視座を置いた研究の論点を整理する[3]。本稿の目的はかかる論争を整理し、ホロコースト史家がユダヤ人生存者の生存要因をどのように考えているかを明らかにするとともに、彼らに関する分析がホロコースト研究にどのような意義をもたらすのかを明らかにすることである。
なおユダヤ人生存者に類似する用語に、「ホロコースト・サバイバー」や「ホロコースト生還者」がある。ただ、これらは「収容所を生き延びたユダヤ人」としても用いられることがあるため、本稿では使用しない[4]。フランス史家のなかで議論されているのは、強制収容所を生き延びたユダヤ人ではなく、強制収容所への連行を免れ、ナチ占領下のフランスで生き延びた約24万人のユダヤ人をめぐる境遇である。なお、本稿では後者のユダヤ人たちを先行研究に則り「ユダヤ人生存者」と定義づける[5]。以下、第1章ではホロコースト研究の潮流を簡単に整理する。同章では歴史研究の動向および記憶に関する政策が変化するなかで、ホロコーストに対する関心が、死亡したユダヤ人からユダヤ人生存者に移行していく過程を描く。第2章ではこのような動向のなかで、約24万人のユダヤ人がフランスで生き延びたのはヴィシー政府の統治のおかげだと解釈する「ヴィシー擁護論」が復活したことを示す。同章ではこの代表的論者である歴史家アラン・ミシェルと政治家エリック・ゼムールの主張を分析し、ヴィシー擁護論が支持され、拡散されるにいたった政治的背景と史学史上の要因を明らかにする。第3章では、歴史家たちがこうした「歴史の歪曲」にどのように応答したかを明らかにする。そして「なぜ約24万人のユダヤ人がナチ占領下のフランスを生き延びたのか」という問いに対する歴史家たちの見解を整理し、それを踏まえたうえで、ユダヤ人の「生存」という事象に歴史研究として取り組むことがホロコースト研究にどのような意義をもたらすのかを明らかにしたい。
第1章 フランスのホロコースト研究の潮流
フランスのホロコースト研究は戦後まもなくの1950年頃から行われ始め、現在までに膨大な量の研究があるが、この研究動向については大きく3つに分けることができる。第一は「ヴィシーの神話」が色濃く残る1950年代から1960年代にかけての研究で、第二は1970年代から現在まで続く「パクストン革命」以後のホロコースト研究である。そして第三は、2000年代以降に第二の動向と並存するかたちで現れる「レジスタンス主義」に即した研究である。以下、時系列順にこの3つの動向を整理しよう。
1-1.「ヴィシーの神話」に基づくホロコースト研究
第二次世界大戦後、フランスのユダヤ人は元どおりの生活を送ることが優先事項であった。というのも、悲惨な経験をした多くのユダヤ人が殺されたことに加え、生き残ったとしても、彼らの仕事や財産がすでに収奪されており、その財産の回収や仕事への復帰、そして病気や怪我などの治療が当時のユダヤ人にとって最優先であったためである。このようにユダヤ人迫害を経験しても自らの生活を取り戻すために、またつらい記憶を忘れるために、ホロコーストの経験に口を閉ざす人々が大半であった[6]。歴史家アンリ・ルソーが終戦から10年後までを「服喪の時代」、1950年代半ばから1960年代末の時代を「忘却、公的な沈黙、抑圧の時代」と表現したのはこのためである[7]。
こうした状況下では、被害者であるユダヤ人たちの語りというよりも粛清裁判の記録からホロコーストを考える評論が多数であった。当時、粛清裁判にかけられたヴィシー政権期の副首相ピエール・ラヴァルは同政府の下でユダヤ人を迫害する政策を行ったことについて次のように釈明した。
フランスのユダヤ人たちによって判決を下されることを私は強く願います。というのも、現在、この[ホロコーストの]事実を知っている彼らは、私が権力の座についていたことを歓迎し、私が彼らに施した保護に感謝しているためであります[8]。
このような考えはレイモン・アロンにも共有されていた。彼は、「ピエール・ラヴァルが自らの国[フランス]のためになしたことは、とても素晴らしいと考える」と称賛し、ラヴァルが裁かれることを嘆いた[9]。そして同様の主張は歴史学者ロベール・アロンの『ヴィシー体制』においてもみられる。同書は1960年代までのヴィシー政府理解を支える歴史研究である。彼は、多数の外国籍のユダヤ人がナチに引き渡されたことは「恥辱である」と指摘しつつも、他方でフランス系ユダヤ人の「多くの命を救った」人物としてピエール・ラヴァルを捉えた[10]。
こうしたユダヤ人迫害に関する理解は、戦後のフランス国内政治によって支えられていた[11]。ド・ゴール派はヴィシー政府の存在を否定しつつも旧ペタン派を取り込むために、ド・ゴールという「剣」とペタンという「盾」の二つが当時のフランスにあったという解釈を生み出した。この解釈はロベール・アロンによるヴィシー政府理解と適合し、外国籍のユダヤ人を犠牲にしつつも、大多数のフランス国籍のユダヤ人をヴィシー政府が救ったとする「ヴィシーの神話」を醸成したのである。またこの時期には「レジスタンス神話」というもう一つの神話が流布されていた[12]。ド・ゴール派は自らが創設したレジスタンス組織「自由フランス」をフランスと同一化するイメージをひろめ、ヴィシー政権崩壊後のフランスの統一に自由フランスとド・ゴールが重要な役割を果たしたと主張していく。他方で、フランス共産党はフランス国内で一貫して抵抗運動を組織した唯一の政党として自らを描き、正統なレジスタンス組織としてのシンボルを占有しようとした。このように1960年代まで、ヴィシー政府とレジスタンスの実態は二つの神話によってそれぞれがヴェールで覆われていた。とはいえ戦後、レジスタンスはユダヤ人迫害と結びつけて語られることはなかった。実際、占領下のフランスでは一部の民間人あるいはレジスタンス組織がユダヤ人を迫害から逃そうと尽力したが、戦後から1960年代にかけて、こうした救援行為はレジスタンスとみなされなかった。例えば、1951年に設立された「第二次世界大戦史委員会」はレジスタンス運動を祖国の解放のための愛国主義的運動として位置づけたため、同会が編纂した刊行史料ではユダヤ人迫害やユダヤ人の救援に言及することはなかった[13]。したがって1960年代までのユダヤ人迫害に関する語りは、多くのユダヤ人を救ったフランス政府というイメージをうえつけたヴィシーの神話に大きな影響を受けていたといえる。
1-2.「パクストン革命」以後のホロコースト研究
このように1960年代末ごろまで支配的であったヴィシーの神話やレジスタンス神話は、1970年代に入り、打ち崩されることとなる。その契機となったのが、1971年に出版されたアメリカ人研究者ロバート・O・パクストンの『ヴィシー時代のフランス』である[14]。本書は上述の粛清裁判の記録に加え、これまでの研究者が用いてこなかったドイツ側の史料を利用している。具体的には、終戦後に連合軍が持ち帰ったドイツ政府やドイツ軍関係の資料であり、ワシントンの「合衆国国立博物館」やロンドンの「公的記録オフィス」に収められていたものである[15]。本書の特徴はこうした史料をもとに、ロベール・アロンのヴィシー政府理解を批判することで、「ヴィシーの神話」を暴いた点、またユダヤ人迫害に関与したフランス政府の動きを追うことで、フランス政府のコラボラシオン(対独協力)の実態を明らかにした点にある。そして、マイケル・マラスとの共著である『ヴィシーとユダヤ人』では、ユダヤ人迫害に対するヴィシー政府の加担の実態がより詳細に明らかにされる。例えば、1940年に出されたユダヤ人身分に関する法律がナチス・ドイツではなく、ヴィシー政府に由来すること、また1942年にフランス全土で行われたユダヤ人検挙にフランス警察が積極的に関与し、その結果、被害者数が増大したことを本書は明らかにした[16]。1970年代当初、彼らの著作を否定的に捉える研究者は少なくなかったが、多くの歴史家たちにヴィシー政府の実態を再考する契機を促した。1979年1月3日に制定された「文書保存法」では公文書の公開が30年後に制定され、占領期のフランスに係る行政文書が閲覧できるようになり、フランスの公文書を用いてヴィシー政府のユダヤ人迫害に関する政策を研究することが可能になった[17]。このように「ヴィシーの神話」を打ち崩し、同政府の再考を促し、そして当時の法制度までも改正させた点で、この研究成果は彼の名をとって「パクストン革命」と呼ばれている[18]。
また1970年代には、本論文の冒頭で紹介したセルジュ・クラルスフェルトによるユダヤ人被害者数に関する緻密な調査が開始していた。この調査はユダヤ人迫害に加担したフランス人やナチの官僚を裁くケルン裁判の証拠収集を目的として実施され、1978年に『フランスのユダヤ人迫害に関する記録名簿』として出版された[19]。さらに、彼は1980年代後半から2000年代にかけて、『フランスのショアー』と題した全四巻の著作を出版する[20]。第一巻はフランスのユダヤ人迫害を時系列順に整理したクラルスフェルトの論考で、第二巻と第三巻はその根拠となる文書を掲載した史料集である。第四巻は強制収容所で亡くなったすべてのユダヤ人の子供たちの名前を記載した名簿であるが、これはクラルスフェルト自身が第二次世界大戦期当時に10代のユダヤ人で、迫害を命からがら生き延びた経験があったためであり、同世代のユダヤ人に対する追悼の意がこめられている。加えて、アメリカで制作されたテレビ・ドラマ『ホロコースト』やクロード・ランズマン監督の映画『ショアー』は研究者のみならず、多くの人々のあいだでホロコーストに対する関心を高めた[21]。
このようにホロコーストの実態が明らかになる一方で、この時期のフランスは修正主義が台頭した時代でもあった。歴史家の武井は当時のフランスを「ホロコースト否定の中心地」と評したが、リヨン大学の歴史学者ロベール・フォーリンソン、政治家では国民戦線のフランソワ・デュプラやジャン=マリ・ルペンらが否定論者の代表に挙げられる[22]。彼らの否定論の特徴はホロコースト自体の否定ではなく、根拠となるテクストや史料の歪曲によるホロコーストの矮小化にある[23]。このような修正主義には次の2つの対抗策が講じられた。第一は、ユダヤ人生存者や生還者の証言の聞き取りおよびホロコースト研究の深化による対抗である。パクストンが指摘するように、1970年代以降、ユダヤ人生存者たちは「語り伝えることがあまりに遅くなって、自分たちの記憶が孫に伝わらなくなることを恐れ、フランスのホロコーストについて急いで語ろうと望むようになった」[24]。そうした証言は上述のような映画やドラマ、小説だけでなく、インタビュー調査としてショアー記念館やイスラエル・ホロコースト記念館(通称ヤド・ヴァシェム)に保管されている[25]。またホロコースト研究については、ナチでもヴィシーの官僚でもないフランスの「ふつうの人々」によるホロコースト加担の実態を叙述する「下からの歴史」を重視した研究が増加した[26]。こうした研究は、迫害の加害者であるフランス警察やヴィシー政府の行政史料に加え、回想録や証言集などの様々なエゴ・ドキュメントを用いて占領下のユダヤ人の境遇を描く「ユダヤ人の社会史」として発展していく[27]。第二は、法令や「記憶」に関する政策による抵抗である。1990年、ホロコーストの否定を処罰する法令である「人種差別・反ユダヤ主義・排外主義行為抑止法(通称ゲソ法)」が公布された[28]。また1995年7月16日、フランス最大規模のユダヤ人検挙であったヴェル・ディヴ事件のコメモラシオン(記念行事)において、ジャック・シラク大統領はヴィシーが主導で実施したユダヤ人迫害を国家犯罪として認め、その責任を負うことを表明した[29]。
以上みてきたように1970年以降、ヴィシー政府に関するそれまでの研究の欠陥が指摘され、フランス政府が主体的にユダヤ人迫害を行ったことが明らかにされた。またそのような研究に呼応するかたちでホロコースト否定論も台頭したが、1990年代以降、現在まで続く歴史研究や記憶に関する政策によってホロコースト加担の事実は多くのフランス人のあいだで認識されることとなった。他方で2000年代以降、フランス社会における戦争やユダヤ人迫害に対する関心や記憶の変化も相まって、ホロコーストに関する歴史研究の動向は変化していく。
1-3.「レジスタンス主義」に即したホロコースト研究
上述のクラルスフェルトのユダヤ人被害者に関する調査はその後も継続して行われ、2000年代頃にはナチ占領下のフランスを生き延びたユダヤ人生存者の数は24万人であると正確に判定することができるようになった。この頃から、ユダヤ人生存者に関心を抱く人々が増える。自らもユダヤ人生存者であり、また政治家として著名なシモーヌ・ヴェイユは、2008年にパリ政治学院(シアンスポ)において開催された、とあるシンポジウムの終了後に、ホロコースト研究者に対して次のようなことを尋ねたという。
なぜ、あなたはユダヤ人の救援に関する研究を行わないのですか?[…]私はいつも考えることがあります。それは、ヴィシー政府が統治したにもかかわらず、またナチに占領されたにもかかわらず、どうして多くのユダヤ人がフランスで生き残ることができたのかということです。[…]彼ら[フランスにおいて生き延びることができたユダヤ人]は75パーセントにあたると、セルジュ・クラルスフェルトは示しました。[しかし、]私はこの問題に関する歴史研究を知りません[30]。
続けて、ヴェイユはユダヤ人生存者の存在を当時の「フランス人の行動」に基づいて説明すべきだといい、彼女はユダヤ人の子供を助けたフランス人やカトリック教徒の話題を挙げたという[31]。このようなヴェイユの問いや関心に付随するかのように、2000年代にはホロコーストに関する記憶政策に変化がみられるようになる。例えば2007年、ジャック・シラク大統領はナチス・ドイツ占領下においてユダヤ人を守った人々──いわゆる「正義の人」の存在に目を向けるように、記念行事に関する法律に修正を施した[32]。つづく、ニコラ・サルコジ大統領は、森や山岳地帯を主たる活動拠点としたレジスタンス組織である「マキ」の少年で、占領下に処刑されたギ・モケの遺書を教材として高校で読ませることを義務付ける[33]。またフランソワ・オランド大統領の時代には「レジスタンスの国民記念日」を制定する法案が可決されるとともに、ユダヤ人迫害に関するフランス公権力への複数の補償要求が国務院の判決によって退けられた[34]。これらの動きはユダヤ人迫害に加担した歴史を忘却させる試みでは決してないが、ユダヤ人犠牲者に主として向けられていた占領期フランスの関心や記憶が、2000年代にレジスタンスの英雄的な記憶へシフトチェンジしたと捉えることができる。
こうした状況下で、レジスタンスの視座からのホロコースト研究の見直しが一部の歴史家たちの間でも主張されるようになる。歴史家ピエール・ラボリは『悲しみと憎しみ』にてパクストンの著作をレジスタンスの悪いイメージを広めたとして批判するとともに、レジスタンス神話が醸成されたころに忘れ去られた、民間人やレジスタンス組織によるユダヤ人の救援活動の実態を検証する必要があると主張した[35]。この点に賛同したのが歴史家ジャック・セメランである。シモーヌ・ヴェイユの上述の話にも感化されたセメランは、「ユダヤ人の75パーセント」が迫害から逃れることができた要因を分析し、パリ市民のような「ふつうの人々」によるユダヤ人救援活動を挙げている[36]。また歴史家オリヴィエ・ヴィヴィオルカは、フランス共産党や自由フランスらによってユダヤ人住民をかくまうレジスタンスが行われたと指摘する。そして彼は、このレジスタンスによって「フランス在住ユダヤ人の75パーセントが死を免れたのだ」と結論付けた[37]。しかし歴史家アンリ・ルソーはこのような動きを「レジスタンス主義」と呼び、ヴィヴィオルカの主張について「レジスタンスとは、[ユダヤ人救助のための]システムとしては、大した意味を持たなかった」ため、「全く同意できない」として退けている[38]。またルソーは、セメランの研究では「占領期フランスのユダヤ人の死亡率の低さの主たる理由として、ユダヤ人抵抗者の存在を過大評価」していると指摘し、それによりセメランは「過ちを犯して信頼を失った」と批判している[39]。加えてパクストンも、反ユダヤ主義に同調していた当時のフランスの世論を矮小化する恐れがあるとしてセメランの上述の研究を批判した[40]。
以上、ホロコースト研究の動向を整理してきた。「なぜ約24万人のユダヤ人が占領下のフランスを生き残ることができたのか」という問いは、ホロコーストに関する記憶のシフトチェンジが行われる2000年代頃のフランス社会の中で生まれた。この問いは当時のフランス史学にも影響を与え、一部の歴史家はレジスタンス運動にその答えを見出そうとした。こうした政治における力学や歴史学における研究動向の変化が相まって、迫害によって亡くなった約7万4150人のユダヤ人から約24万人のユダヤ人生存者へ関心が移行し、後者のユダヤ人をヴィシー政府が救ったとする「ヴィシー擁護論」が復活していくこととなる。この点については次章で分析しよう。
第2章 ヴィシー擁護論の復活──「ヴィシーはユダヤ人に良い影響を与えた」
2-1.「フランスのパラドクス」と「ドクサ」──歴史家アラン・ミシェルと政治家エリック・ゼムール
まず、ヴィシー擁護論復活のきっかけとなった歴史家アラン・ミシェルの主張を検討する。彼はイスラエルに住むラビでありながら、イスラエル・ホロコースト記念館の元研究員であった。彼は2012年に『ヴィシーとショアー フランスのパラドクスに関する調査』を出版したが、本書の主題にもある「フランスのパラドクス」とはミシェル自身が提唱した概念である[41]。まず彼は強制収容所で殺害された約7万4150人のユダヤ人たちの国籍を調査し、逮捕された外国籍のユダヤ人は86パーセントにあたることを指摘する[42]。このことからミシェルは、ユダヤ人迫害にヴィシー政府が加担したのは確かに事実であるが、それはフランス国籍のユダヤ人を助けるためであり、それゆえ約4分の3のユダヤ人が強制収容を逃れることができたと考えた[43]。そして彼は逮捕されたユダヤ人の人数を年代別に分類した。彼は1943年6月から終戦にかけてユダヤ人逮捕者数が減ったと主張し、その要因にはピエール・ラヴァルがヴィシー政府のトップになったことが関係しており、ラヴァルがユダヤ人を救ったと結論づけた。加えて彼はヴィシーの統治がユダヤ人に良い影響を与えたと証明するために、他国のユダヤ人生存者の数と割合を引き合いに出し、比較している。具体的には、彼は「類似した地域であり、戦前の政治体制や政治文化に多くの共通点があり、かつ迫害が同時並行で進行した」ベルギーやオランダのユダヤ人生存者の数や割合を比較した[44]。彼はベルギーでは40パーセント、オランダでは75パーセントのユダヤ人が殺害された一方で、フランスでは殺害されたユダヤ人の割合は25パーセントのみであると指摘する[45]。そしてミシェルは、「フランスではヴィシー政権の高官のコラボラシオンが抑制する効果をもたらした」のに対し、ベルギーやオランダでは「ドイツ当局が自由に行動できたことが、強制収容の侵攻を加速度的に進行させた」と結論付けた[46]。また彼はこれをヴィシー政府の策略として捉え、コラボラシオンを積極的に実行し外国籍のユダヤ人の引き渡しに加担したが、その結果多くのユダヤ人が助かったという「フランスのパラドクス」があると主張した[47]。
そして本書では、これまでのホロコースト研究の研究史整理が行われる。この分析のなかで、彼はパクストンとマラスの『ヴィシーとユダヤ人』がヴィシーを悪く描こうとする先入観を作り上げ、こうした善悪の二元論的な「ドクサ(doxa)」がフランスのホロコースト研究を支配していると批判した[48]。他方でクラルスフェルトを「ヴィシー政府の理解あるいは発見に重要な役割を果た」したと部分的に肯定しつつも、その一方で反ユダヤ主義的政策の実施の責任がヴィシー政府にあるとクラルスフェルトも考えていたため、パクストンの「ドクサ」が歴史家たちのあいだで固着化したと非難する[49]。このようにアラン・ミシェルは統計分析によって「ヴィシー政府の統治がフランスのユダヤ人に[…]いい影響を与えた」ことを証明しようと試みた一方で、ヴィシーの「良い面」を考慮しない現代の歴史学には「ドクサ」があると指摘した[50]。
アラン・ミシェルのこの主張を取り入れ、「ヴィシー擁護論」をテレビやラジオなどのメディアで大いに吹聴したのが政治家のエリック・ゼムールであった。次に、彼のヴィシー擁護論の特徴を整理しよう。エリック・ゼムールはアルジェリア系ユダヤ人で、パリ政治学院出身の元ジャーナリストとして、TVフランス2やラジオ・ルクセンブルクなどに出演し、歯に衣着せぬ物言いで差別的発言を繰り返し、人気を得た人物であり、また政治スタイルの穏健化を狙う「国民戦線」に失望した人々から支持を得た人物である[51]。ゼムールは排外主義や伝統的なナショナリズムに基づく発言を繰り返すとともに、積極的にヴィシー擁護論を主張し続けた。例えば、彼は『フランスの自滅』という著作を2014年に出版したが、同書においてゼムールは、ペタン元帥がユダヤ人迫害からフランス国籍のユダヤ人を救った人物であると主張する[52]。また上述のヴィヴィオルカは、レジスタンスやユダヤ人の救援活動がフランスのユダヤ人を救ったと考えたが、ゼムールはそうした活動には限界があり、「実質不可能である」と指摘する[53]。そして彼は、仮にユダヤ人をこうした活動が救ったとしても、それは人々の「強力な連帯」ではなく、ヴィシー政府の統治のおかげであると結論付けたのである[54]。
またゼムールは、アラン・ミシェルのように現在のホロコースト研究を偏向的であると非難する。彼はパクストンとマラスの著作である『ヴィシーとショアー』以降の歴史学研究を「パクストン的ドクサ」と非難し、アラン・ミシェルの主張を支持する。ゼムールによれば、パクストンに影響をうけた「現代史家たち」は、ナチス・ドイツからかけられた圧力を考慮せず、ヴィシー政府の主導者が反ユダヤ主義的政策を実行したと指摘しているが、「私たちの唯一の歴史家」、つまりアラン・ミシェルはその占領下の圧力を考慮してヴィシー政府の実態を捉えることができている唯一の人物であるという[55]。したがってゼムールは、フランス現代史学には「ドクサ」が支配しているというアラン・ミシェルの主張を継承し、主張することで、歴史家ではない人々を取り込み、これまでの歴史研究の成果をなし崩しにしようとしたのだ。
2-2.「ユダヤ人生存者」をめぐる二つの問題
以上、ヴィシー政府がユダヤ人を救ったとするヴィシー擁護論の代表的論者の主張を整理してきた。クラルスフェルトの研究以降、正確に割り出せるようになったユダヤ人生存者の人数と彼らの割合を根拠として、ユダヤ人に対して「ヴィシー政府は良い影響を与えた」と主張している点に第一の特徴があるだろう。こうしたエリック・ゼムールやアラン・ミシェルの試みについて、当初、歴史家たちは対処しなかったという。というのも、ヴィシー政府のユダヤ人迫害への加担を明らかにしたこれまでの歴史研究の積み重ねをもって、改めて歴史家が反証する必要がないとも考えられたためである[56]。
しかし、この二人のヴィシー擁護論者による「歴史の歪曲」の試みは、放置されてはならない二つの問題点を孕んでいた。第一の問題は排外的な移民政策の導入の正当化に利用されたことである。先述のようにゼムールはペタン元帥がユダヤ人を救った人物として考えたが、この主張にはペタン元帥を肯定的に評価したいというねらいがあった。2014年の10月8日のBFMテレビでは「ナチの政策だと即座に見なされない真の移民政策を私たちが行うことができることを、私はペタンをとおして知ろうとしている。これが私の目的である。」と語っている[57]。つまり、ペタン元帥を評価することで、ヴィシー政権期の排外主義的な移民政策を肯定的に受けとめ、現代のフランスにも適応したいという思惑が政治家ゼムールにはあったのである。2021年に大統領選に出馬した彼は、「ホロコーストに対してヴィシー政府が良い影響を与えた」ことを認めない「エリートたちの歴史観」を否定し、支持者を獲得していく[58]。そしてこのゼムールの試みは極右あるいはポピュリスト系統のメディアに共有されるようになる。このように、ゼムールはホロコースト史家によって積み重ねられてきた歴史像を無視したが、この試みは彼の支持者たちにも共有されていくことで、排外主義の正当化がなされており、歴史研究者が無視できない状況になった。
第二に、歴史家たちのあいだでユダヤ人生存者の生存要因について見解が分かれていたという研究史上の問題が挙げられる。例えば、先述のヴィヴィオルカのようにフランス共産党や自由フランスが行ったようなレジスタンス活動がユダヤ人の生存者を増加させたと考える歴史家がいれば、ヴィシー政府の統治を肯定的に受け入れる歴史家もいた。その一例がラウル・ヒルバーグである。彼はホロコーストの先駆的研究である『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅(上)(下)』を著したドイツ史の大家である[59]。この著作は膨大な資料と文献も用い、またホロコーストを一国史としてではなくヨーロッパ規模で初めて検討した金字塔である。本著の初版はヴィシー政府の神話やレジスタンス神話が依然として支配的であった1967年であるが、その後、1997年の改訂版においてもフランスのホロコーストは次のように記されている。
1942年にドイツの圧力が強まったとき、ヴィシー政府は[…]外国籍ユダヤ人と亡命者を放棄し、自国のユダヤ人を保護しようとした。ヴィシーの戦略はかなり成功した。一部を放棄することで、大部分が救われたのである[60]。
加えてユダヤ人生存者の生存要因について、ヴィシーの加害の実態を明らかにした二人の大家のあいだでも見解が揺れていたことは特筆すべきであろう。ロバート・O・パクストンとマイケル・マラスは、フランスのユダヤ人生存者の生存要因をナチス・ドイツが実施した検挙や逮捕に係る措置によって説明を試みた[61]。他方でセルジュ・クラルスフェルトはユダヤ人生存者が増えた要因に、ヴィシーという国家と相反して存在していたフランス社会のおかげだと考えている[62]。このように、ユダヤ人生存者に対する関心が高まる2000年代頃からヴィシー擁護論が拡散された2010年代前半にかけて、歴史家たちはユダヤ人生存者の生存要因について一致した答えを出すことができなかった。
ただこれには、ユダヤ人生存者の実態にせまることがそもそも困難であるという問題がある。先ほどから何度も触れている「約24万人のユダヤ人生存者」とは、1940年時点で居住していたユダヤ人の数(約32万人)からホロコーストの犠牲者となったユダヤ人の数(約7万4150人)を引いただけの単純計算で導き出された人数である。彼らひとりひとりの名前を行政記録から確認することはできても、彼らの占領下の境遇を得るための史料が少なく、加えて彼ら全員に共通する生存要因を論じることはかなり煩雑な作業である。また「ユダヤ人を生存させるに至った要因あるいは事柄」そのものが定義しづらい。例えば、1942年7月16日から17日にかけてパリでは大規模ユダヤ人検挙(通称ヴェル・ディヴ事件)が起きたが、一部のパリ市警察はその検挙の情報を事前にユダヤ人に流し、逃がそうとした。ある警視は電話で幼馴染のユダヤ人に検挙の予告をし、また検挙当日、ある警察官はユダヤ人に身支度のための準備として1時間の猶予をあたえて彼らの逃亡を黙認したという[63]。しかしこのような事実から、パリ市警察の行動がユダヤ人の生存要因とみなすことができるだろうか。パリ市警察の行動はユダヤ人の救援活動だったとみなすことができるかもしれないが、そのユダヤ人が「占領下を生き延びることができた要因」だとは判断し難い。またこの事実から、ヴィシー政権下の役人がユダヤ人にいい影響を与えたと結論付けることも難しい。というのも、こうしたパリ市警の働きかけによってヴェル・ディヴ事件当日の検挙を逃れ、生き延びることができたとしても、その後の占領下の日々をこのユダヤ人が生き延びることができるかどうかは、また別の生存要因がかかわってくるためである。つまり、上記の警察の行動が一概に生存要因と判断することはできないのである。このように史料上の制約と定義づけの問題がユダヤ人生存者の生存要因を分析することを困難にしている。しかし、こうした論点を無視するかたちでヴィシー政府擁護論が提唱されているのであり、アラン・ミシェルやエリック・ゼムールの主張は根拠が薄弱であると言わざるを得ない。その点でレジスタンス主義に即した歴史研究も同様の問題があるが、移民排斥の正当化のために利用されているヴィシー擁護論を否定することは、歴史家たちにとってより喫緊の課題となった。だが、善悪の二元論的な「ドクサ」に歴史家たちが支配されていると主張したゼムールの著書『フランスの自殺』はベストセラーになり、彼の言説はテレビやラジオ、ソーシャル・メディアで広く拡散され、歴史研究が硬直化しているとみなされる現状が2010年代ごろにはあった。では、フランスのホロコーストを専門とする歴史家たちはこのような「歴史の歪曲」にどのように対応し、ユダヤ人生存者の実証をどのように進めたのだろうか。この点は次章で検討する。
第3章 ヴィシー擁護論への応答
3-1.歴史家たちの応答
2010年代前半に興隆した「ヴィシー擁護論」に対して、2010年代後半から2020年代にかけて多くの歴史家が応答し、批判した。彼らの批判の内容は大きく二つに要約することができる。第一に歴史家たちが非難したのは、数や割合を過度に強調してしまう危険性である。この点を指摘したのはヴィシー擁護論者の論敵にされたロバート・O・パクストンとマイケル・マラスである。彼らは共著『ヴィシーとユダヤ人』の第二版を出版するかたちで、ヴィシー擁護論に応えた[64]。パクストンとマラスは、そもそも「フランスは他国に比べて多くのユダヤ人が逃れることができたという問いそのものがミスリーディング」だと指摘する[65]。そして彼はフランスよりユダヤ人生存者の割合が多い国として、デンマーク(98.7パーセント)やフィンランド(97.2パーセント)、ブルガリア(86パーセント)、そしてイタリア(84パーセント)を挙げており、数や割合に過度に着目しすぎる危険性を指摘している[66]。
第二は、ユダヤ人生存者の生存要因を単一の事柄で説明しようとする試みへの批判である。第1章でみたように、アンリ・ルソーは様々な「要素を考慮することなく」、「ユダヤ人の死亡率の低さの主たる理由」を判断することの危険性を指摘している。彼の批判はレジスタンス主義に主として向けられていたが、この批判はヴィシー擁護論にも向けることができるだろう。また、ジャック・セメランもユダヤ人生存者の生存要因の複雑さを自らの政治的理念に基づいて無視しているとエリック・ゼムールの見解を批判している[67]。
そして、歴史家たちの第三の批判は、そもそも「ヴィシーはユダヤ人に良い影響を与えた」という主張は正しいのかという指摘である。この代表的論者がローラン・ジョリーである。彼はフランスのホロコーストに関して数多くの著書を出版しているが、主たるテーマとして彼が取り組んだのは、フランスの政治家や「ふつうの人々」のコラボラシオンである。2023年、彼はそのほか多くの歴史家たちとコラボラシオンの実態を再度検証し、ヴィシー擁護論のテーゼを検証した。それが『フランスとショアー』である[68]。同書は総勢16名、計14報の「フランスのショアーに関するフランス国内と国外の最新の研究を紹介する」ことで、本当にヴィシーが多くのユダヤ人を救ったのかという点を追究している[69]。そして本書は、ヴィシーの官僚が外国籍のユダヤ人だけでなく、フランス国籍のユダヤ人に対しても、反ユダヤ主義的措置をナチス・ドイツ以上に積極的に採用とした点を明示し、ヴィシー政府のコラボラシオンの実態を再確認することで、ヴィシー擁護論の欠陥を指摘した[70]。また歴史家ジョリーは『歴史の歪曲』という本で、ゼムールが自らの政治思想を正当化するために歴史の歪曲を図ったこと、そしてミシェルがラヴァルの甥と交友を深めたころからヴィシー擁護論を提唱するようになったと指摘している[71]。
以上、これまでみてきた歴史家たちは、ヴィシー擁護論がユダヤ人生存者の「数」や「割合」に着目しすぎている点、またヴィシー政府の統治のみでユダヤ人の生存要因を説明することの危険性を指摘し、加えてコラボラシオンの実態を再検討することで、同政府がユダヤ人を守ったという主張の根拠が薄弱であることを示す。加えてヴィシー政府を擁護する彼らの思惑には、排外主義かつ国家主義的な言説の正当化という政治的思惑が隠れており、そのために都合のいい解釈がなされたことを批判している。こうした歴史家たちの応答を踏まえ、ユダヤ人生存者に関する叙述を実証研究の水準にまでひきあげたのが、先述の歴史家ジャック・セメランである。
3-2.ユダヤ人生存者の歴史研究の実践──ジャック・セメラン
ジャック・セメランは当初、ユダヤ人の生存要因をレジスタンス活動によって説明していたが、第1章で触れたように、パクストンやルソーから当該活動のみでユダヤ人の生存要因を語ることはできないと批判されていた。彼はこうした批判を受け、2018年に『フランスのユダヤ人の生存』を出版し、ユダヤ人生存者の生存要因を改めて論じる[72]。本研究の特色は、ユダヤ人生存者の生存要因は単一的な要素で語れるものではないとし、より複合的な視座からユダヤ人の生存要因を検証した点にある[73]。まず彼は、フランスのユダヤ人生存者数が多い要因を次の3つの視点から説明する。
第一は、「地理的要因」である[74]。フランスは占領下の各国に比べ、領土が広く、なおかつ南部にはナチス・ドイツが直接統治していない「自由地域」があった。またこの「自由地域」は南部にスペイン、東部にはスイスという、ナチス・ドイツの占領を受けていない国と隣接している。したがって、比較的容易に他国へ逃亡できるこの地理的条件がユダヤ人生存者の増加につながったとセメランは指摘する。第二は彼が「文化的要因」と呼ぶものであり、具体的にはユダヤ人の救出活動やフランス社会へのユダヤ人たちの同化、そしてユダヤ人たちのソシアビリテなどを指す[75]。まずセメランは、フランスのユダヤ人救援活動は他国に比べて大規模であったと指摘する。「ユダヤ人をかくまう」ないしは「ユダヤ人を逃がす」といった活動はキリスト教団体や愛国者らを中心に行われており、なかには反ユダヤ主義的感情を持った人もいたようだが、反ドイツ感情やフランスに対する愛国感情に突き動かされ、実践されたという。またユダヤ人が他国に比べて同化していたことも彼らの生存要因の一つとして挙げている。ポーランドなどの東欧諸国に比べ、フランスでは長い歴史のなかで社会に同化したユダヤ人が多く、フランス人とのソシアビリテを持っていた彼らは、ナチス・ドイツやフランス警察から逃れることが容易であったという。したがってセメランは、外国籍のユダヤ人に比べ、フランス系ユダヤ人の生存者数が多いのはこのためだと考えている。またセメランは、ユダヤ人の身柄を保証するための賄賂として、財産や金銭を有していることがユダヤ人の生存を左右したとも指摘している。第三は「構造的要因」であり、ナチス・ドイツと被占領国の間でみられた国際的な統治体制のことを指している[76]。ヴィシー擁護論者が指摘したように、1943年から1944年にかけて、フランスではユダヤ人検挙の数が低下し、逮捕されるユダヤ人の数も減る。しかしこれは、ペタンやラヴァルが交渉したおかげではなく、当時のナチス・ドイツがベルギーやオランダでユダヤ人検挙を行うよう指令を出していたためでだと指摘する。つまり1943年から翌年にかけては、ナチス・ドイツがフランスでのユダヤ人検挙の実施を控えており、このナチス・ドイツ側の政策の変更がユダヤ人の生存者の増加に与えた影響が大きいとセメランは考える。
このようにセメランは地理的要因、文化的要因、構造的要因の3つがユダヤ人の生存の機会につながったことを明らかにしたが、彼の主張の第二の特筆すべき点はこうした要素を獲得しつつ、迫害を逃れようとしたユダヤ人自身の逃亡戦略が最大の生存要因であったと指摘する点である。迫害から逃れようとするユダヤ人自身の意志や戦略が彼らの生き延びる最大の理由になったという指摘は至極当然のように聞こえるだろう。しかし、多くのユダヤ人の証言を史料として用いて、このことを実証し、ヴィシー擁護論を真っ向から反証した点にこの研究の最大の特色がある。なおセメランの指摘する生存戦略とは、主として身分証明書の偽装、ユダヤ人検挙の対象外となるユダヤ人扶助組織で活動すること、警察に申請した住居とは他の場所に隠れること、「自由地域」ないしは他国(スペイン、スイス)への逃走することの4点である。
おわりに 今後のユダヤ人生存者研究──ミクロストリア、都市史研究へ
以上、本稿を整理しよう。フランスのホロコースト研究は1970年代のパクストン革命をきっかけに本格化する。1970年代から1990年代にかけては、フランス政府によるユダヤ人迫害への加担に焦点を当てた研究が増加した。それゆえ、迫害によって亡くなったユダヤ人7万5000人の境遇が明らかになったが、約24万人のユダヤ人生存者の存在も同様に明確化する。2000年代頃から、ホロコーストに対するフランス社会の関心の変化に伴ってユダヤ人生存者への関心が高まり、「なぜ約24万人のユダヤ人が占領下のフランスを生き延びることができたのか」という問いが生まれた。そしてこうした問題に取り組むなかで、ユダヤ人の救援活動にその答えを見出すレジスタンス主義とヴィシー政府がユダヤ人を救ったとするヴィシー擁護論が出現する。レジスタンス主義にせよ、ヴィシー擁護論にせよ、単一の事象によってユダヤ人生存者全員の生存要因を論じている点に限界がある。ただ、ヴィシー擁護論については排外主義的な移民政策の導入のために歴史を利用し歪曲していたこと、また歴史研究の成果を「パクストン的なドクサ」に支配されていると批判することでなし崩しにしようとしたことから、レジスタンス主義以上に、実証的な批判が喫緊の課題とされた。そして、ローラン・ジョリーやアンリ・ルソー、ロバート・O・パクストンといった歴史家たちは、生存者の数や割合を過度に強調し、生存者数の多さを政府の統治体制のみで説明することは、ヴィシー政府によるコラボラシオンの実態を矮小化するとしてヴィシー擁護論を批判した。
ただこうした歴史の歪曲の試みが拡散された要因のひとつに、占領下のユダヤ人生存者の生存要因について歴史家たちの見解が揺れており、一致した答えを提示できなかったことが関係していた。それゆえ2010年代後半から、歴史家たちのなかでこの問題は実証的に取り組まれるようになる。ジャック・セメランは、約24万人のユダヤ人生存者の生存要因として、フランス特有の地理的要因・文化的要因・政治的要因、そしてユダヤ人たち自身の生存戦略を挙げた。「なぜ約24万人のユダヤ人がナチ占領下のフランスを生き延びたのか」という問いについては、セメランの提示したこのモデルでおおよそ説明がつくであろう。それゆえヴィシー政府の統治という要素のみがユダヤ人にいい影響を与えたとするヴィシー擁護論は現在では完全に否定されている。なお2025年4月、エリック・ゼムールには排外主義のためにホロコーストの史実を修正したとして罰金刑の判決が下されている[77]。
他方で、ユダヤ人生存者に関する歴史研究に全く課題がないわけではない。セメランが示した生存要因は依然として曖昧であり、地域や集団によってそれぞれ異なる傾向がみられることが推測される。またセメラン自身も指摘するように、今後はこれらの生存要因の複雑なつながりを解明したり、これらの要因のみでは説明できない事例を検討したりする必要があるだろう [78]。このようにホロコースト研究はユダヤ人生存者の存在に視座を据えた第4の潮流を迎えており、ユダヤ人生存者に関する歴史研究は次の二つの手法を取り入れ、進展している。第一は、ユダヤ人生存者の対象を絞って、彼らの生存要因の複雑な実態を明らかにするミクロストリア研究である[79]。これらの研究は、セメランの提示したそれぞれの生存要因の複雑なつながり、具体的にはユダヤ人の救援行為や当時の政治的状況や統治体制がどのように相互的に作用し、いかにしてユダヤ人生存者たちに生存機会を与えたのかを詳細に明らかにすることができるだろう。第二は、ユダヤ人生存者の存在や生存要因を通じて、占領期の都市およびフランス社会の状況を明らかにする都市史研究である[80]。この研究は都市に分析対象を限定することで、ユダヤ人生存者の境遇を明らかにできるだけでなく、第2章で言及したように、パクストンとクラルスフェルトのあいだで議論になったナチ占領下の複雑な統治構造や世論の実態を解明にする手がかりになると考えられる。というのも、対象地域においてユダヤ人生存者と身近な存在であった「ふつうの人々」の思惑や戦略、具体的には反ユダヤ主義への加担、適応、抵抗の過程を明らかにすることができるためである。このようにユダヤ人生存者に視座を置くことは、強制収容所で亡くなったユダヤ人に対する分析ではみえてこなかった占領下および迫害の実態を叙述することができると期待できるが、この点においてはフランスに限らずナチ占領下の各国の歴史研究にいえることであろう。最後に、本稿でみてきたユダヤ人生存者をめぐる歴史否認主義の隆盛とそれに対する歴史家たちの応答は、現代の日本においてソーシャル・メディアを中心に拡散されている修正主義への対策を考えるうえで貴重な事例である。今後はこうしたフランス史家たちの実践を追いつつ、否認主義と歴史認識をめぐる問題に取り組みたい。
Notes
-
[1]
Selge Klarsfeld, La Shoah en France 1. Vichy-Auschwitz la « solution finale » de la question juive en France, Paris, Fayard, 2001.
-
[2]
「フランスの特殊性」ないしは「フランスの例外」とは、ヴィシー政府による統治がフランスでは認められたという観点から、当時のフランスにはドイツやそのほかの被占領国とは異なる状況があったのではないかと考える概念であり、占領下のフランスに関する研究のなかでよく用いられる語である。
-
[3]
一例に、次のような研究がある。副島美由紀「ドイツの『歴史家論争2.0』と『コロニアル・ターン2.0』 『想起の文化』の継続と記憶の連帯に向けて」、『小樽商科大学 人文研究』第148号、2025年、9-31ページ。渡辺和行『ホロコーストのフランス—歴史と記憶』人文書院、1998年。
-
[4]
「イスラエルと“ホロコースト生還者(サバイバー)” 殺りくはなぜ止まないのか」、『クローズアップ現代』NHK、2024年1月29日放送。https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/episode/te/RP187K9K92/ 「アウシュヴィッツの生還者たち」、『映像の世紀 バタフライエフェクト』NHK、2025年4月14日放送。(2025年8月31日確認)
-
[5]
Jacques Semelin, Laurent Larcher, Une énigme française. Pourquoi les trois quarts des Juifs en France n’ont pas été déportés, Paris, Albin Michel, p. 47.
-
[6]
ロバート・O・パクストン「2001年版序文」、渡辺和行・剣持久木訳『ヴィシー時代のフランス』柏書房、2004年、14ページ。
-
[7]
アンリ・ルソー『過去と向き合う 現代の記憶についての試論』剣持久木・末次圭介・南祐三訳、吉田書店、2020年、20ページ。
-
[8]
Géo London, Le Procès Laval, Lyon, Roger Bonnefon, 1946.
-
[9]
Raymond Aron, « Apres l’événement, avant l’histoire. A propos du procès Petin », Les Temps Modernes, 1, octobre, 1945, p. 159.
-
[10]
Robert Aron, Histoire de Vichy, Paris, Fayard, 1954, p. 528.
-
[11]
渡辺和行『ホロコーストのフランス』28ページ。
-
[12]
渡辺和行『ナチ占領下のフランス 沈黙・抵抗・協力』講談社、1994年、16ページ。
-
[13]
Renée Poznanski, “Rescue of the Jews and the Resistance in France: From History to Historiography”, French Politics, Culture & Society, Summer 2012, vol. 30, no. 2, Special issue: The rescue of Jews in France and its empire during World War II: History and memory (Summer 2012), Berghahn Books, p. 19-20.
-
[14]
Robert O. Paxton, Vichy France. Old guard and new order, Columbia University Press, 1972.
-
[15]
川上勉『ヴィシー政府と「国民革命」 ドイツ占領下フランスのナショナル・アイデンティティ』藤原書店、2001年、226ページ。
-
[16]
Robert O. Paxton, Michel Marrus, Vichy et les Juifs, Paris, Calmann-Levy, 1981.
-
[17]
ロバート・O・パクストン、前掲書、16ページ。
-
[18]
Jean-Pierre Azéma, « La révolution paxtonienne », Fishman Sarah (dir.), La France sous Vichy. Autour de Robert O. Paxton, Bruxelles, Complexe, 2004, p. 23-25.
-
[19]
Serge Klarsfeld, Le Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Paris, Fayard, 1978.
-
[20]
Serge Klarsfeld, La Shoah en France, Paris, Fayard, 2001. なお本書は1980年代から1990年代にかけて出版された著作で再構成されている。Tome 1. Vichy-Auschwitz la « solution finale » de la question juive en France, Fayard, 1983. Tome 2. Le calendrier de la persécution des Juifs de France. juillet 1940 – août 1942, F.F.D.J.F, Fayard, 1993. Tome 3. Le calendrier de la persécution des Juifs de France. septembre 1942 – août 1944, F.F.D.J.F, Fayard, 1993. Tome 4. Le mémorial des enfants juifs déportés de France, F.F.D.J.F, Fayard, 1993.
-
[21]
アンリ・ルソー、前掲書、82ページ。
-
[22]
武井彩佳『歴史修正主義 ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで』中公新書、2021年、94ページ。
-
[23]
同上、98-99ページ。
-
[24]
ロバート・O・バクストン、前掲書、14ページ。
-
[25]
ショアー記念館については次のサイトを参照。https://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah.html (2025年8月31日確認) またイスラエル・ホロコースト記念館(ヤド・ヴァシェム)については次を参照。https://www.yadvashem.org/collections.html (2025年8月31日確認)
-
[26]
一例に、次の研究がある。Laurent Joly, Dénoncer les juifs sous l’Occupation. Paris, 1940-1944, Paris, CNRS Editions, 2017.
-
[27]
一例に、次の研究がある。Renée Poznanski, Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, Hachette, 1994.
-
[28]
武井、前掲書、200-206ページ。ちなみに、ゲソ法で最初に処罰されたのは上述のフォーリンソンである。
-
[29]
アンリ・ルソー、前掲書、87-90ページ。
-
[30]
Jacques Semelin, Laurent Larcher, op. cit., p. 8.
-
[31]
Ibid.
-
[32]
アンリ・ルソー、前掲書、90ページ。
-
[33]
同上、91-92ページ。
-
[34]
同上、93-95ページ。
-
[35]
Pierre Laborie, Le Chagrin et le Venin. La France sous l’Occupation, mémoire et idées reçues, Paris, Bayard, 2011, p. 255.
-
[36]
Jacques Semelin, Persécutions et entraides dans la France occupée. Comment 75% des Juifs en France ont échappé à la mort., Paris, Le Seuil-Les Arenes, 2013.
-
[37]
Oliver Wieviorka, Histoire de la Resistance(1940-1945), Paris, Perlin, p. 466.
-
[38]
アンリ・ルソー、前掲書、143-144ページ。
-
[39]
同上、143、293ページ。
-
[40]
Robert O. Paxton, Jean-François Sené, « Comment Vichy aggrava le sort des juifs en France », Le Début, no. 183, janvier-février 2015, p.173-181.
-
[41]
Alain Michel, Vichy et la Shoah. Enquête sur le paradoxe français, Paris, CLD éditions, 2012.
-
[42]
Ibid., p. 47.
-
[43]
Ibid., p. 46.
-
[44]
Ibid., p. 113.
-
[45]
Ibid.
-
[46]
Ibid., p. 117.
-
[47]
Ibid.
-
[48]
Ibid., p. 90.
-
[49]
Ibid., p. 97-100.
-
[50]
Ibid., p. 369.
-
[51]
渡邊啓貴『ルペンと極右ポピュリズムの時代 〈ヤヌス〉の二つの顔』白水社、2025年、212ページ。
-
[52]
Éric Zemmour, Le Suicide français, Paris, Albin Michel, 2014.
-
[53]
Ibid., p. 89.
-
[54]
Ibid., p. 385.
-
[55]
Ibid., p. 528.
-
[56]
Laurent Joly, « Vichy et la Déportation des Juifs. Essai historiographique autour du livre d’Alain Michel, Vichy et la Shoah. Enquête sur le paradoxe français(Paris, Éditions CLD, 2012, 407 p.) », PHDN, 2013-2020. https://phdn.org/histgen/vichy/joly-michel-2013.html (2025年8月31日確認)Laurent Joly, Zemmour contre l’histoire, collection Tracts no. 34, Paris, Gallimard, p. 3.
-
[57]
Éric Zemmour, op. cit., p.93-94. Propos d’Éric Zemmmour sur BFMTV, 8 octobre 2014.
-
[58]
Laurent Joly, Zemmour contre l’histoire, p. 4.
-
[59]
Raul Hillberg, The destructuion of the European jews, Raines, New York, 1997(望田幸男・原田一美・井上茂子訳『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅』柏書房、2016年)。
-
[60]
同上、461ページ。
-
[61]
Robert O. Paxton, Michel Marrus, op. cit., p. 355.
-
[62]
Serge Klarsfeld, Vichy-Auschiwitz, tome 2, p. 190-191.
-
[63]
渡辺和行『ナチ占領下のフランス 沈黙・抵抗・協力』133ページ。
-
[64]
Robert O. Paxton, Michel Marrus, Vichy France and the Jews, Stanford university press, 2019.
-
[65]
Robert O. Paxton, op. cit., p. xii.
-
[66]
Ibid.
-
[67]
Jacques Semelin, Laurent Larcher, op. cit, p. 192.
-
[68]
Laurent Joly(dir.), La France et la shoah, Paris, Calmann-Lévy, 2023.
-
[69]
Ibid., p. 17.
-
[70]
Ibid., p. 549-550.
-
[71]
Laurent Joly, La falsification de l’Hisoire :Éric Zemmour, l’extrême droite, vichy et les Juifs, Paris, Grasset, 2022.
-
[72]
Jacque Semelin, La suivie des juifs en france, Paris, CNRS éditions, 2018.
-
[73]
Ibid., p. 377.
-
[74]
Ibid., p. 377-378.
-
[75]
Ibid., p. 378-389.
-
[76]
Ibid., p. 389-400.
-
[77]
“French far-right politician Éric Zemmour fined for contesting crimes against humanity.”, Le Monde, 2 April 2025.
-
[78]
Ibid.
-
[79]
一例に、次の研究がある。Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus. Une enquête, Paris, Seuil, 2012(田所光男訳『私にはいなかった祖父母の歴史 ある調査』名古屋大学出版会、2017年). Ruth Zylberman, 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. Autobiographie d’un immeuble., Paris, Seuil, 2020(塩塚秀一郎訳『パリ十区サン=モール通り二○九番地 ある集合住宅の自伝』作品社、2024年).
-
[80]
一例に、次の研究がある。拙稿「20世紀前半のパリにおける公衆衛生と反ユダヤ主義 サン・ジェルヴェ地区を例に」『年報地域文化研究』第28号、2025年、1-19ページ。Isabelle Backouche, Sarah Gensburger, Eric Le Bourhis(dir.), « Persécution des Juifs et espace urbain Paris, 1940-1946 », Histoire Urbaine, 2022, no. 62. 後者の研究はパリを研究対象とする都市史研究者らによって組まれたユダヤ人迫害に関する特集である。本特集の内容の詳細については次の拙稿(書評)を参照。拙稿「特集 « Persécution des Juifs et espace urbain Paris, 1940-1946 » , Histoire Urbaine, 2022, no. 62.」『神戸大学史学年報』第38号、2023年、22-30ページ。
この記事を引用する
古城 一樹「フランスの「ユダヤ人生存者」をめぐる歴史論争——なぜ、約24万人のユダヤ人がナチ占領下のフランスを生き延びたのか?」 『Résonances』第16号、2025年、1-18ページ、URL : https://resonances.jp/16/les-survivants-juifs-en-france/。(2026年02月15日閲覧)