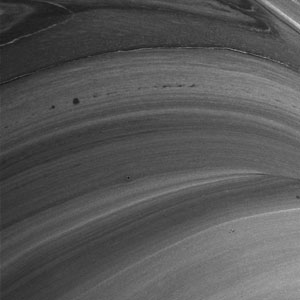思考の試金石としての言語シモーヌ・ヴェイユ『哲学 ル・ピュイ講義1931-1932』書評
フランスを拠点とする「国際シモーヌ・ヴェイユ学会(Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil)」は、創設から約半世紀に亘り、最新の研究動向を伝え合うコロックを実施してきた。会長を務めるロベール・シュナヴィエに招かれた筆者が2024年10月末に参加したコロックは、古代ローマの遺跡が残る南仏アルルにて開催された。その会場には書籍ブースが設置され、学会誌『カイエ・シモーヌ・ヴェイユ』を筆頭に関連図書が陳列されていたが、中でも印象深い一冊が目に入った。その表紙には、自信ありげな表情を浮かべながら腕組みをした一人の哲学者の姿と、« Philosophie. Les cours du Puy 1931-1932 »という文字が映っていた。
昨年の秋に出版された『哲学 ル・ピュイ講義1931-1932』[1](以下『ル・ピュイ講義』)は、哲学者シモーヌ・ヴェイユ(1909-1943)の生徒による講義ノートである。20世紀の初頭にパリで生まれたこの哲学者は、高等師範学校を修了して哲学教授資格を取得後、いくつかのリセの哲学学級で授業を受け持つことになる。初年度の赴任地となったのは、フランス南東のル・ピュイの女子高等学校だった。初回の授業は1931年10月2日に始まり、この年度の生徒は15名だったという[2]。そこにいた生徒のYvette Argaudの講義ノートに、もう一人の生徒Élisabeth Chanelの講義ノートを補完し、さらに校訂と注釈を加えることで生まれたのが本書である。
本稿では、この新たな講義ノートの内容を手短に紹介し(第一節)、シモーヌ・ヴェイユ研究史における刊行の意義を吟味するとともに(第二節)、哲学を教えるとはいかなる営みなのかを少しばかり考えてみたい(第三節)。
I
本書は三部から構成されている。第一部は「心理学」であり、最も多くの紙幅が割かれている箇所である。当時の心理学者たちの様々な学説が紹介されており、本能、意志、想像、記憶、注意といった多様なテーマが取り上げられている。心理学者のウィリアム・ジェイムズ、フランス反省哲学の文脈ではメーヌ・ド・ビランやジュール・ラニョー、伝統的な哲学者としてはデカルトやスピノザ、ベルクソンへの言及が目立つ。
第二部は「論理学」であり、論理的思考とは何かが説かれている箇所だと言えるだろう。無矛盾律や因果律のような古典的テーマに加えて、幾何学から天文学、物理学なども扱われ、数学的思考や科学的思考が問われている。また人文科学として、オーギュスト・コントの実証主義やカール・マルクスの史的唯物論が解説されていることも興味深い。
第三部は「道徳」であり、その他と比較すると紙幅としては最も短い箇所である。現代社会の分析が主題となっており、労働、国家、法権利、植民地、連帯、職業といった多岐に渡るテーマが取り上げられている。シモーヌ・ヴェイユがリセで生徒たちに哲学を教える傍らで、労働者たちと連帯して組合運動に身を捧げていたことを、ここで思い起こしてもよいだろう。
また本書に付された巻末付録には、少なからぬ貴重な資料が含まれている。例えば、シモーヌ・ヴェイユ自身による講義メモが所収されており、この新たな講義ノートと比較しながら読むことができる。さらに、ル・ピュイの四人の生徒たちが第二次世界大戦後に、夭折した哲学教師の姿を振り返った証言も再録されている。服装にはまったく無頓着だった「若き優秀な哲学教授資格者」(p. 252)は、失業者たちの支援に勤しみながら、生徒たちにも真摯に向き合っていたようだ。
II
本書の出版に至るまでの詳細は、シモーヌ・ヴェイユ研究の第一人者であるEmmanuel Gabellieriと編纂者のAviad Heifetzが説明しているが(p. 7-16)、それよりもここで問うてみたいのは、本書が2024年に刊行されたことの意義である。
そこで問題となってくるのが、すでに1959年に出版されていたシモーヌ・ヴェイユの講義ノート『哲学講義』(Leçons de philosophie)である。この哲学教師はル・ピュイで一年を過ごしたのち、何度も異動を繰り返しており、1933年から1934年にはフランス中東部ロアンヌの女子高等学校に着任していた[3]。この『哲学講義』は、ロアンヌの生徒の一人だったアンヌ・レーノーの講義ノートであり、哲学教師としてのシモーヌ・ヴェイユの姿を伝えるものとして読まれてきた。さらに言えば、どの年度の講義も、当時のフランス政府が指定したカリキュラムに沿って行われていたため、当然ながら新旧の講義ノートには重複する内容が少なくない。
以上の事実を踏まえながら二つの講義ノートを比較するとき、いくつかの重要な事柄が浮かび上がってくる。
第一に、アンヌ・レーノー自身が強調しているように[4]、講義ノート『哲学講義』は厳密に言えば、シモーヌ・ヴェイユ自身の著作ではない。例えば、実際の講義では、声の抑揚などが断定を和らげたりすることがあるが、急いで筆記せざるを得ないノートでは細かいニュアンスが抜け落ちてしまう。要するに、シモーヌ・ヴェイユの意図がどこまで反映されているのかを判断するのは困難である。だが、二つの講義ノートを比較してその異同を調べることで、あるテーマをめぐってどんな説明や注釈が施されていたのかを、より正確に把握することが可能となった。
第二に、新たな講義ノートの方には、この数十年に及ぶシモーヌ・ヴェイユ研究の成果を大いに反映した、きわめて詳細な注記が施されている。この哲学教師は講義のなかで数多くの著述家たちに言及しているが、典拠となっているテクストを特定するのは容易ではない。だが新たな講義ノートの方は、旧講義録とは異なって、その出典の正確な跡付けにも取り組んでいる。この作業においては、とりわけ1988年に始まった『シモーヌ・ヴェイユ全集』(Œuvres complètes de Simone Weil)の公刊が果たした寄与が少なくなかっただろう。このガリマール社による全集版は、これまで不明だった文献学的な事実を次々と明らかにし、ほとんど出典を明記することのないシモーヌ・ヴェイユが参照していたテクストを特定した点で画期的であり、その成果は『ル・ピュイ講義』にも惜しみなく活かされている。
第三に、この講義ノートには「哲学」と題された序論に相当するテクストが所収されており、旧講義録には見当たらない記述も含まれている。そこにあるのは、哲学とは何かを、リセで学ぶ生徒たちに伝えようとする教師の姿である。シモーヌ・ヴェイユは自身の講義メモのなかで、簡潔な表現を用いて次のように定式化を試みている。すなわち、哲学によって私たちが学ぶのは「言語をうまく使うこと(bien user du langage)」(p. 228)である。意外なことに、この哲学教師が言語そのものを主題的に論じたテクストは数少なく、この新たな資料を手掛かりに知りうることもあるはずである。
新たな講義ノートを読むための筋道はいくつもあるだろうが、以下では一つの方向を探ってみたい。すなわち、シモーヌ・ヴェイユにとって哲学を教えるとはいかなる営みだったのかを、言語という観点から考えるというものである。
III
哲学とは何かという問いに対して、シモーヌ・ヴェイユはこう答えている。「哲学は一般的な学問とはまったく異なるひとつの学問である」(p. 19)。この哲学教師は「汝自身を知れ(Connais-toi toi-même)」という文言に立ち返りながら考察を進めてゆく。ソクラテスによって言い伝えられるこの古代ギリシアの碑文は、認識対象よりも認識主体の方に目を向けるという、一種の視点の転換を求めている──そこに哲学という学問の固有性がある。人間が「自分自身を知る」というのは、人間は何を望み、何をなすべきかを知るということであり、それは人間が何を目的として生きるのかという道徳的な問いにも通じてゆく。
また、この哲学教師はリセの生徒たちに対して、哲学的反省が目指すものを簡潔に説明していたようだ。それは一種の価値判断であり、「善い」や「悪い」といった言葉について思考することである。そこで問題となるのが、思考が形成されてゆく過程であり、人間の思考それ自体についての反省的思考である。さらに、そこには言語も関わってくる。というのも、「哲学は一例として、言語を上手く使えるよう規則づける」(p. 27)からだ。
ある言葉を吟味することは、西洋哲学──少なくとも、プラトンの哲学──の出発点となってきた。人々が「正しい」と呼んでいるものは、実のところ何を表しているのか。それは本当に「正しいもの」なのか。そもそも「正しさ」とは何なのか。こうした哲学的な問いかけは、まさに『国家』といったプラトンの対話篇のなかで反復されてきた。いかにして言葉を用いるのかという問いは、古代より多くの哲学者たちが取り組んできたものであり、20世紀の哲学教師シモーヌ・ヴェイユをそこに加えることもできるだろう。
だが、これまでの刊行著作を読むかぎり、言語とは何かという問いが正面から取り上げられることはほとんどなく、例外的に『哲学講義』のなかで少し扱われている程度に過ぎなかった。この観点からすると、『ル・ピュイ講義』を参照することにはいかなる重要性があるのか。二つの講義ノートを比較するとき、この哲学教師がどのような言語論を展開していたのかがより精緻に把握できるようになる。
ロアンヌでの講義ノートによると、シモーヌ・ヴェイユは「言語とは優れて人間的なものである」と指摘しつつ、さらに言語を二つの類型に区別している[5]。一方には、自然的・個体的な言語があり、それはある意味では動物的であり、諸々の情動を伝達するものだ。他方には、人為的・社会的な言語があり、思考の伝達を目的としている。例えば、間投詞や擬音語は自然的であり、書かれた言語は人為的である。
また続く箇所では、ある種の社会的な視点から、言語が思考に及ぼしうる影響が分析されている。この哲学教師はいくつかの語彙を例示しながら、言語はそれ自体がすでに思考を内包していると指摘する[6]。例を挙げると、「頭」を意味する« tête »という語には、「思考力」や「司令塔」といった複数の意味があり、また「所有」を意味する« propriété »という語が、「ひとが所持しているもの」と「本質的な特性」という二つの意味を備えているように、ある語句は異なる事象に繋がりを持たせうる。さらに言えば、ある言葉には一つの社会の見方が映し出されており、こうした意味の結びつきを介して、私たちの思考は否応なしに言語から一定の影響を受けている。
このように旧講義ノートにおいては、言語は二つの類型によって整理されており、また言語の社会的性格が強調されている。だが、この『哲学講義』だけに依拠するかぎり、なぜシモーヌ・ヴェイユがそうした考えに至ったのか、より正確に言えば、どんな学説に立脚していたのかが判然としない。他方で、『ル・ピュイ講義』を読んでゆくと、似たような論点が取り上げられているだけでなく、どんな文献に基づいて講義が実施されていたのかが明白になってくる。
新たな講義ノートにおいて、シモーヌ・ヴェイユは言語の起源を問うなかで、やはり言語を二つの類型に区別している。一方には、自然な言語があり、それは叫びや身振りという形で現れてくる。例えば、子どもが泣くのはどこかが悪いということを表している。他方で、言語は自然的なものから意志的なものになるにつれて、より正確に思考を表現できるようになる。その典型となるのが「書かれた散文」(p. 148)である。
さらに問題となってくるのが言語の社会的特徴であり、言語には「本質的に集団的な性質(nature essentiellement collective)」(p. 149)がある。つまり、言語をつうじて社会は個人に影響を及ぼすのであり、言語には個人に還元されない固有の性質が備わっているということだ──デュルケームが「社会的事実」と呼ぶものをここで想起することもできるだろう[7]。
シモーヌ・ヴェイユは複数の意味を持つ語句を挙げて、そこに人間精神が結晶化された固有の思考を見出している。例えば、「人間性」を意味する« humanité »という語には、「人間という種(espèce humain)」の他に、「人徳(vertu)」や「教養(culture)」といった複数の意味がある。あるいは「人民」を意味する« peuple »という語には、「国民全体」と「国民のうちで労働する人々」という二つの意味が含まれる[8]。そして、言語はそれ自体が人間の思考と切り離すことができず、シモーヌ・ヴェイユの表現を用いるならば、「私たちは何世紀にも渡る人間の思考という型のなかに、私たちの思考を注ぎ込んでいる」(p. 150)。
以上のように、ある語には一つの社会の文化が反映されており、その語を使用するや否や、個人の思考は社会からの影響を免れえない。こうした言語の社会的特徴が示しているのは、シモーヌ・ヴェイユの表現を借りて言えば、「言語は思考に先立っている(le langage précède la pensée)」(p. 150)ということだ。言語はこのように社会的かつ人間的なものであり、また人間の思考を深く規定するものであるからこそ、それは「真の思考の試金石(pierre de touche de la véritable pensée)」(p. 149)となるのである。
この哲学教師が講義のなかで示そうとしていたのは、真の思考を形づくるには言語をうまく使いこなさなければならないということだった。シモーヌ・ヴェイユにとって哲学を教えるとは、個別の対象──心理学における諸問題や、現代社会における諸課題──を媒介に、そして何よりも言語の使用をつうじて、思考それ自体を鍛え上げてゆくことにあったのだろう。
無論、このような言語論はシモーヌ・ヴェイユのまったくの独創だったわけではなく、他の著述家にも負うところが少なくなかったようだ。事実、この講義ノートではオーギュスト・コントが明確に参照されている。この社会学の創始者による『実証政治体系』(1851-1854年)には言語を主題とする章があり、そこでは言語の形式が、音楽、詩から散文へと展開するという歴史観が提示されている他、ある言葉が異なる意味を結びつけるという事態が、« humanité »、« peuple »、« propriété »といった語句を例に指摘されている[9]。言語の起源やその特徴をめぐって、20世紀の哲学教師がこの箇所を紹介していた可能性も考えられるだろう。
このように新たな講義ノートに依拠することで、シモーヌ・ヴェイユがどんなテクストに基づいて哲学講義を行っていたのかが浮き彫りになってきた。すでに出版されていた旧講義ノートだけでは読みとりづらかった文献学的事実は、今後の研究によって益々明らかになってゆくはずだ。本稿で取り上げた問題の他にも、一例を挙げるならば、意志、記憶、注意といったテーマを介して、フランス反省哲学やベルクソン哲学、実験心理学がこの哲学教師に及ぼした影響を明らかにすることも可能だろう。
『哲学 ル・ピュイ講義1931-1932』には、シモーヌ・ヴェイユ研究の数十年来の成果が反映されていると同時に、その分野の専門家だけに読み継がれるには惜しいほどの豊かさがある(詳細な注釈、かつての生徒たちの証言、当時の哲学カリキュラムなど)。そして講義ノートから浮かび上がってくるのは、哲学の果たすべき役割が何であるかを問い、真の思考とは何であり、言語をうまく扱うとはどういうことなのかを、リセの哲学学級の生徒たちに伝えようとする一人の哲学教師の姿である。
Notes
-
[1]
Simone Weil, Philosophie. Les cours du Puy 1931-1932, d’après les notes prises par Yvette Argaud, complétées par celles d’Elisabeth Chanel, établies et annotées par Elinore Darzi, Aviad Heifetz, Gabriël Maes, préface d’Emmanuel Gabellieri, Paris, Édition de l’éclat, 2024. 以下、この著作から引用する場合、本文中にページ数のみ表記する。
-
[2]
Simone Pétrement, La vie de Simone Weil, Paris, Fayard, 1973, p. 136-137(シモーヌ・ペトルマン『詳伝シモーヌ・ヴェイユⅠ』杉山毅訳、勁草書房、1978年、143-144ページ).
-
[3]
シモーヌ・ヴェイユは1931年から1937年の間に、ル・ピュイ、オセール、ロアンヌ、ブールジュ、サンカンタンへと渡り、五つのリセに勤務している。鈴木順子『シモーヌ・ヴェイユ 「歓び」の思想』藤原書店、2023年、108-114ページを参照。
-
[4]
Leçons de philosophie, transcrites et présentées par Anne Reynaud-Guérithault, Paris, Plon, 1959, p. 9(『ヴェーユの哲学講義』渡辺一民・川村孝則訳、ちくま学芸文庫、13ページ).
-
[5]
Ibid., p.66-67(同書、85-86ページ).
-
[6]
Ibid., p.80(同書、103ページ).
-
[7]
Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, « Quadrige », 1986 [1937](『社会学的方法の規準』菊谷和宏訳、講談社、2018年を参照). デュルケームは『哲学講義』と『ル・ピュイ講義』のいずれにおいても取り上げられており、後者には「沸騰(effervescence)」に関する言及があることから(p. 81)、『宗教生活の基本形態』は少なくとも参照されていたと思われる。「職業の道徳的機能」と題する学生時代に執筆された小論では、『社会分業論』と『自殺論』が扱われている。Cf. Œuvres complètes de Simone Weil, tome I, Paris, Gallimard, 1988, p. 263(『シモーヌ・ヴェイユ選集Ⅰ』冨原眞弓訳、みすず書房、2012年、229ページ).
-
[8]
ジョルジョ・アガンベンによると、「人民」という概念には両義性があり、政治的主体を表すと同時に、貧民や恵まれぬ者たち、政治的に排除された者たちも表している。例えば、「フランス人民」と言うと政治体としての市民の総体を指し、「民衆出身の人間」という意味では下層階級の成員を指す。「人民と何か?」『目的のない手段 政治についての覚え書き』所収、高桑和巳訳、以文社、2024年、35-43ページを参照。
-
[9]
Auguste Comte, Système de politique positive ou Traité de sociologie, tome II, Édition présentée et annotée par Michel Bourdieu et Emmanuel d’Hombres, Paris, Hermann. 2022 [1852], p. 176-177, 191.
この記事を引用する
谷 虹陽「思考の試金石としての言語——シモーヌ・ヴェイユ『哲学 ル・ピュイ講義1931-1932』書評」 『Résonances』第16号、2025年、47-52ページ、URL : https://resonances.jp/16/les_cours_du_puy/。(2026年02月15日閲覧)