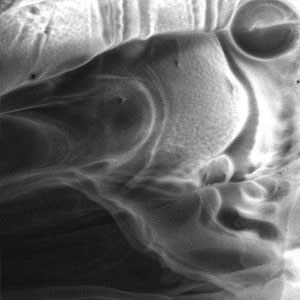死にゆく身体と超越初期から中期レヴィナスにおける超越の内的条件としての身体について
はじめに
現在では、独自の他者論を打ち立てた哲学者として知られている、エマニュエル・レヴィナス(Emmanuel Levinas,1906-1995)は、実は自身の思想を《ままならない身体》[1]の哲学的分析から展開させていた。ままならない身体とは、私たちが意のままに動かすことのできる身体のことではなく、物質として、重圧や障害となる身体のことである。
さらにレヴィナスの哲学において、自分とは異なるものとの関係へ向かう動きの第一の源泉も、いわゆる「他者(Autre)」ではなく、重圧や身体的苦しみといった、主体に内在する他者性やままならなさから、抜け出そうとする欲求にあったと言える。
それに対し、中期思想を代表する『全体性と無限』(1961)[2]では、他者の他者性が強調され、主体に関しては、その自己同一性の方が強く打ち出されている(cf. TI, 26/46-47)。
本稿はこの変化に着目して、他者と関係し、その関係に開かれている状態を、《超越》として問題化し[3]、初期レヴィナス思想において論じられていた、身体のままならなさを通じた超越の問題が、いかに彼の中期思想を代表する『全体性と無限』において位置付けられているのかを分析することを目的とする。そして、本稿はこの分析から、中期レヴィナスの倫理思想を主体の具体的な一人称的観点から捉え直すこともまた目的としている。これは、以下の背景からである。
『全体性と無限』は、レヴィナスの主著である一方、その議論には、現象学の発想や用語を利用しつつも、結局は独断的かつ神学的な他者論となっているという批判[4]や、他者関係を抽象化して、人種やジェンダーを介した具体的な社会関係を隠蔽していると、その理論の応用不可能性などについて批判[5]がなされてきた。後者の指摘を行ったサラ・アーメッドによれば、本来、他者への倫理的な応答責任は、レヴィナスが論じているような、特殊性の削ぎ落とされた他者の普遍的な他者性によってではなく、主体と他者の身体的で感情的な出会いや、意思疎通を通じて生起する[6]。
確かに、『全体性と無限』には次のような特徴がある。同書は、主体と他者が絶対的に分離しつつも関係しあっているという、形而上学的関係を記述することを主題とするが(TI, 32/56)、しかしその定義が非常に抽象的であり、かつ、私たちがいかなる段階を経てその関係を持てるのかということが明確ではない。そのために、そこでは独断的に(他者と言ってしまえばそれ以上の論証はいらないかのように)、他者と、他者との関係である形而上学的関係なるものが、絶対的なものとして措定されているように見受けられるのである。
それに対して初期思想では、主体の身体という非常に具体的な場から超越の問題が語られていた。さらに、既に成立している形而上学的関係を記述する中期思想の姿勢とは異なり、初期思想では「孤独がいかなる点で乗り越えられるかを理解する」(TA, 19/6)という、主体から他者へ、という流れへの注目が掲げられている。そのために、主体がいかに他者と関係することが可能となっており、そしていかに両者が関係し始めるのかが、レヴィナスの著作の中でも明示的なのだ。
そこで、初期思想のように《一人称の私がいかに他者との出会いを果たすのか》という観点をもって、レヴィナス哲学の核をなす『全体性と無限』を捉え直すならば、レヴィナスの思想に対する従来の批判への応答や、更なる発展可能性を考えることもできるかもしれない。その鍵となるのが、《身体のままならなさ》という論点である。初期思想で提出された、超越の内的条件としての身体の他者性が、『全体性と無限』においてどのような位置付けにあるのかを分析することは、レヴィナスの倫理思想を、主体の内的で具体的な水準から読み解くことに寄与するだろう。
そこで、本稿は次の流れで論述を進める。まず、初期レヴィナスが、いかに身体に基づき超越を語っていたのかを確認し(第1節)、次に、その初期思想と中期思想の前提の違いを示したうえで、「欲望(désir)」概念を、中期思想における超越を分析するための鍵概念として提示し(第2節)、最後に、欲望の条件と言われる死に関する議論が、いかなるものかを分析して(第3節)、以上の初期から中期思想の分析から見える、私たちの具体的な《死にゆく身体》が、超越を可能にしているという議論の内容をまとめる(おわりに)。
1.初期思想における超越の問題
1.1 「逃走について」における超越の動向の芽生え
レヴィナス哲学において、最初に本格的に主題とされた超越の問題、それは「逃走について」(1935)[7]での身体を基礎とした「欲求(besoin)」に関する議論であろう。「ヒトラー主義哲学に関する若干の考察」(1934)[8]では、主体と身体の同一性、そして、私は私以外ではありえないというような、人間存在の分割不可能な同一性が問題となっていた[9]のに対し「逃走について」では、その同一性の中の「二重性/二元性(dualité)」に付随する超越の動向が主題となっている。
この頃のレヴィナスは、マルティン・ハイデガーの『存在と時間』(1927)における、主体の実存から存在を分析するという、存在論的分析の発想を採用しつつも、そもそも存在者が身体によって生きている限りで、存在は「内在する矛盾」を抱えている(DE, 90/169)のだと、身体という論点から持論を展開させている[10]。ハイデガーは、「実存(Existenz)」を、主体が自分自身をどのように了解し、そしてその都度どのように実現させるかという、固定的でない、動詞的な身分から捉えていた。ここには、自分の実存は自分が何を為すかによって決定され、統合されるという前提が見てとれる。
それに対し、のちのレヴィナスは、「純粋で真っ直ぐでもありえた実存の動きは、屈折し、その動きのうちでぬかるみにはまるに違いな」いと論じている[11]。主体は、それ自体が身体である限りで、「存在はその根底において自分自身にとっての重みであ」(DE, 88/167)り、矛盾なのである。例えば、霊魂など精神的な存在者であれば、精神的な内容それ自体が、その存在の全体であり矛盾は生じない。しかしながら、私たち身体的存在者にとって、基礎である身体そのものが、主体の完全な統制の行き届かない物質である限り、主体には常に内的な他者性があり、自分自身を自分では完全に支配できない。確かに、意識や思考、記憶など、精神的なものによってこそ、その人の性格など自己同一性は保たれているが、身体を土台としていることで、主体のうちでは精神的なものと身体的なものの軋轢があり、それに付随して、主体には二重性が生じているのである。
「自己自身への準拠において人間は一種の二重性を見分ける」(DE, 73/151)と言われるように、主体に内在する二重的な自己存在をレヴィナスは区別している。自分自身に密着した自己存在は、より精神的な「自我(moi)」、そして、ある程度主体自身によって対象化され、他者性やずれを伴って感じられる自己存在は、より身体的な「自己(soi)」と呼ばれる。
他なるものと関係する以前の孤独な主体の様態は、このように、自分自身との苦痛を伴った関係に閉じてしまうことである。のちの著作によれば、「自己同一性の関係は、自己による自我の閉塞であり[…]、つまり、物質性(matérialité)」(TA, 51/51)である。この時、主体は自分自身に「繋縛(enchaînement)」され、「釘付け(rivé)」にされているが、同時に主体はそこから逃走したいという欲求を持つとされる。
逃走の欲求が最も純粋に表れているのが「吐き気(nausée)」という身体的現象である。吐き気は、外力ではなく、主体の内側の引力に引きずられるようにして生じる。吐き気に支配された主体は自分以外との関係を持たないが、しかしそれ自体は自分自身から逃れようとする内的運動である(DE, 89-90/167-168)。
自分自身を否定し、自分自身から逃れようとする吐き気における欲求は、身体という自己存在の基礎が、それ自体として主体内部にもたらす二重性から湧き出る動向といえる。しかし、逃走の欲求の動きは、主体が他のものに到達している・関係していることではないために、超越そのものではない。そこで、欲求はあくまでも第一の超越の動向の芽生えと言えるだろう。
「逃走について」では、以上のように、身体が、主体の内的感覚において同一性を内破させていることで、可視的でも論理学的な意味とも異なる形で、主体の内的感覚において超越の動向が欲求として生じていることが確認できた。
1.2 『時間と他者』における主体の死と他者関係
『時間と他者』(1948)[12]では「孤独がいかなる点で乗り越えられるかを理解する」(TA, 19/6)という意図が示されているように、孤独な主体が実際に他者と出会うまでの過程が、ある種、弁証法的に描かれている。
まず主体が最初に結ぶ関係は、世界の物質との関係である「享受(jouissance)」であり、その対象である物質は、食べ物などを代表とする「糧(nourriture)」である。この時に主体は「他なるもの(autre)」[13]との関係によって、自己忘却できることで「世界による救済」(TA, 45/42)を得る。「欲求の超越の瞬間において、主体は糧の前、糧としての世界の前におかれ、物質性は主体に自分自身からの解放を与える」(TA, 51/52)のだ。この次元は『全体性と無限』第II部において、幸福な生を生きる段階として発展されているように、主体にとって肯定的なものである。しかし糧は、空間や光という共通性を通じて認識により把握されるものであることから、それは完全な他者ではなく、また、結局は私のものとして消費されてしまう限り、主体を孤独から解放はしない(TA, 53-54/53-54)。
この主体にとって第一の他者性の経験が、主体自身に内在する身体の他者性、つまり苦痛や死の現象である。主体における死の接近、それは「主体のうちに純然たる孤独への回帰に尽くされることはないような関係を垣間見る」(TA, 20/7)ことである。
しかし、レヴィナスにとって死は主体のうちにあると言っても、ハイデガー的な先駆、何らかの構えの対象ではない[14]。私が死んでいる時に私は存在しないのであって、主体は急に死に襲われるものであり、死に対して厳密な意味ではどのような準備も予測もできない。何かとして問題にできない以上、死は「神秘(mystère)」と呼ぶこともできる(TA, 56/57)。
死は予測の不可能性であるからこそ、死であり、他者性である。しかし、死に対していかなる形によっても接近できないというわけではない。それは、予測を放棄し、死の接近の中で苦痛を被ることである。レヴィナスによれば、苦痛には、被る者にその際限のなさを実感させることに特徴がある。例えば、浅い擦り傷の痛みは、さらに深い痛みや、その先の死がもたらされうることを予感させるように、苦痛はその絶頂としての死を含んでいる(TA, 56/56-57)。苦痛の感覚によって、存在者は死の接近を、予測ではなく内的に実感する。
これは、具体的には、「雄々しさ=男らしさ(virilité)」を棄て、まるで子どものように嗚咽の状態に至ること、このような受動性の状態である(TA, 59-60/61)。そして、クリスチャン・シオカンが指摘するように、この第1の他者性が、第2の他者性の出来事を可能にする[15]。
苦痛を通じて孤独の痙攣と、死との関係へ至った者だけが、他者との関係が可能となった場所に位置している(TA, 64/66)。
彼がここで強調するのは、主体の雄々しさや、支配力の終焉である。例えば、世界との関係に閉ざされた主体は、自分とは異なるすべてのものを主体の支配下にあるものとして捉えており、他者をも対象であるモノとして認識するかもしれない。これが同一性の次元であるが、しかし自分に対する自分の支配の終焉は、主体に二元性を与え、自分には引き受けられないものが生起しうることを主体に示す(TA, 62/65)。このことによって主体は、他者と出会うことが可能になる。
簡単にまとめよう。糧との関係までは、レヴィナスにとって同一性の次元である。それは、自分とは異なる他者が現れていない状態であり、他者の不在は主体の権能の充満と同じである。しかし、私の死は、私に内在してはいるものの、私の権能や支配は行き届かない。このことが、それまでの主体の同一性を最初に破壊する。この破壊とはつまり、支配の終焉であり、支配の終焉は、支配とは異なる態度によって自分とは異なる何ものかと出会うことへと主体を導く。
死が、苦痛を通じて他者性たるものを内的に実感させることによって、実際の他者の他者性を受け取ることを、主体に可能にするとも言えるだろう。このように、他者と出会う第一の条件として、『時間と他者』においても、主体のままならない身体、しかし特に《死にゆく身体》が提示されている。
2.『全体性と無限』における〈同〉と〈他〉の形而上学的関係と欲望
2.1自我の他者性の否定
それでは初期思想までの姿勢は、他者概念が明確に押し出された中期思想において、どのように変化しているのだろうか。おそらく、すでに指摘されている通り、初期思想における分析は、『全体性と無限』(1961)や『存在するとは別の仕方で』(1974)などの、のちの一切の思索の前提であると思われる[16]。なぜならば、レヴィナスの中期以降の思想では、初期思想で論じられていた、主体の原理的な生成については明示的に展開されなくなるからである。
一方で、『全体性と無限』においてレヴィナスは、初期思想で提示していた孤独な主体と、その他者性の議論に対し否定的に言及している。
嫌悪として生きられる自己を拒絶する自我、倦怠として生きられる自己に釘付け(rivé)にされた自我、それらは自己意識の諸様態であり、自我と自己の引き裂けない同一性に基づいている。1人の他人と思い込んでいる私の他者性は、それが〈同〉の戯れでしかないからこそ、詩人の想像力を鼓舞することができるのだ。自己による自我の否定とは、正確に言えば、自我の同一性の諸様態の一つなのである(TI, 26/46-47)。
中期レヴィナスによれば、私の他者性は自己同一性の一つの様態にすぎない。さらにそれは「戯れ」とされるほどに、低く見積もられていると思われる。自己同一性があるからこそ、その他者性なるものも問題化できるのであり、より本質的なのはこの私の同一性の方である。
そして、その同一性を考えるためには、「自我と世界との間の具体的関係から出発しなければならない」(ibid.)とされる。つまり、孤独そのものではなく、世界との関係にこそ、主体の同一性の根源がある。これらの姿勢の変化はいかなる事情に起因するのであろうか。
2.2〈同〉と〈他〉の形而上学的関係
主体に内在する他者性への否定的言及の理由として、〈同〉と〈他〉の形而上学的関係という構造の導入が考えられる。そこで、その関係の概要を以下に簡潔に示したい。
冒頭に確認した通り、他者との関係である形而上学的関係を記述することが、『全体性と無限』における研究の主題であった(TI, 32/56)。レヴィナスによれば、その第Ⅰ部は、一連の研究の地平を示していることで予備的な性格を持っており(TI, 16/30)、形而上学的関係の概要が簡潔に語られているため、ここを参照する。
形而上学的関係とは、端的に言えば〈同〉と〈他〉が完全に分離しながらも、関係を有している状態である。それは、同じものと異なるものが、混ざり合うことで同一のものとなることがなく、また、第三者の視点から比較可能ではない状態で関係している状態のことである。そのために、自我は自我として自らを自己同一化する存在であり、同じものとしてとどまっている必要がある(TI, 25/45)。
この自己同一化を達成するのが、主体と世界(糧)との関係(享受)である。この糧という、自分とは「他なるもの」との関係を経由して、主体は初めて自己同一化の運動を達成する[17]。世界の介在しない完全な孤独を認めていた、「逃走について」などの初期思想とは異なり、『全体性と無限』において自己同一性は、世界との関係がなくては形成されないと捉えられているのである。
そして、他者とはその〈同〉としてとどまる自我に対して、〈他〉である存在者のことを指す。他であることとは、単に自我の否定という形式的なものではなく、共通性を持たず、その内実そのものが他者性であるという意味で、他であることを指す(TI, 28/50)。共通性を持ち、比較可能であれば、それは同じものになってしまう。
そこで、これらの定義に当てはまる〈同〉と〈他〉の関係は、俯瞰的に捉えられた二者関係ではなく、自我の一人称的視点において、〈他〉として現れる他者との関係ということになる。他者はまず客観的に主体から独立して存在するのではなく、自我に他者性(無限性)をもって現れてくるのが他者である(TI, 12/24)。そこでレヴィナスは、あくまでも『全体性と無限』は(一人称的な)現象学的手法に依拠していると述べている(TI, 13/27)[18]。
この形而上学的関係を記述するという目的のために、中期レヴィナスは主体自身の他者性なるものについて、否定的に言及するほかなかったと考えられる。世界との関係を通じて、〈同〉が保たれていない限り、〈他〉はありえないからだ。
2.3 主体に内在する超越の動向 ——欲望
『全体性と無限』において問題と思われるのが、以上のような形而上学的関係の厳密な定義によっては、〈同〉と〈他〉の出会いが、いかに可能となっているのかが明白ではないということだ。〈同〉は〈同〉として自己同定することにその本質があるならば、いかにそのエゴイズムから離脱し、他者と出会うに至ったのだろうか。おそらく、この点を説明するために、『時間と他者』では、主体に内在する他者性としての苦痛や死が必要とされていたのである。
従来、この問題に対しては、他者に開かれた構造が既に主体に存在するという立場(空間・構造論観点)[19]や、後期思想をそれより以前の著作にも読みこみ、他者は既に主体の生成に先行するとする立場(他者の先行性)[20]、そして主体の生の生成と、他者との社会的関係は既に重なりあっているとする立場(生の多層性)[21]などによって説明がなされてきた。これらの解釈はいずれもレヴィナスの哲学体系に沿い、適切な解釈ではある。
しかしながら、超越の条件を考えるときに、扉や窓のようにすでに他者への通路を有する主体の構造論的説明[22]を用いることも可能ではあるが、外へ出られる構造が存在することは、実際に外へ出ることを意味はしない。他者と出会うのは、この具体的な《私》なのだから、具体的な《私》が具体的な他者と出会うための内的条件を、レヴィナスのテクストから探ることも必要であろう。《一人称の私がいかに他者との出会いを果たすのか》を探る本稿の問題意識に沿えば、やはり、主体から他者へという実際の内的な動きを捉える必要がある。
その分析の鍵となる概念が、「欲望(désir)」である。これは主体の動きではあるが、他者を起点とすることにその特徴があり、欲求とは区別されている。中期思想において欲求は、主体を起点とし、主体の満足や幸福に向けて「他なるもの」を消費する営みである享受の推進力である[23]。レヴィナスによれば、欲望は欲求とは異なり、主体を起点として能動的に働かせられるものではなくて、「〈他なるもの〉の隔たり、他者性、外部性を聞き取る」(TI, 23/42、強調はレヴィナス)ものとして、その他者性を受け取るような動きに近い。他者が現れるとき、私がその他者の他者性を自分自身の思惑などを介さずに、受け取る段階が存在する。
しかし、この現象自体は私自身のうちで生じており、私は他者に欲望を抱いているともいえる。他者性を受け取るということと、他者へと向かうことが矛盾しないものとして両立する動きが、欲望である。そして、私は欲望を持つことで、その存在を無視できないという形で他者との関係へと向かってゆく。「絶対的欲望を介して〈同〉は他者との関わりに入る」(TI, 187/303)のである。
欲望を介して参入する主体と他者との実際の関係が、『全体性と無限』第Ⅲ部の第B章「顔と倫理」で詳細に論じられている、言語を介した関係であり、レヴィナスの思想の中でも特によく知られた議論である。しかしながら、本稿の主眼は、関係を形成するきっかけとなるような主体に内在する超越の動きにあるために、この欲望自体の条件を探ることにする[24]。
レヴィナスは次のように述べている。
遠隔が徹底的なものとなるのは、[…]欲望が欲望をそそるものに当てもなく向かう場合、つまり、予期不可能な絶対的他者性に対して人が死へ赴くように向かう場合においてのみである。欲望は、欲望する存在が死をまぬがれず、そして欲望されたものが不可視の場合に、絶対的なものとなるのだ(TI, 22/41)。
欲望が絶対的なものとなることとは、ここでは主体と他者の遠隔が徹底的になることを意味する。つまり上の引用箇所からは、欲望が主体から明確に隔絶された他者に対するものであるという、欲望の前提条件には、欲望する主体が「死をまぬがれない(mortel)」ことと、欲望の対象が不可視であることという、2つの条件があると分かる。
確かに、欲望は他者を起点とする限りにおいて他者の条件も必要ではあるが、しかし同時に、欲望する主体に内在する条件も存在する。そして、それは初期思想と同じく、死が訪れることという身体の他者性、つまり《死にゆく身体》が関係するのであり、特に絶対的な他者に対して「死へ赴くようにして向かってゆく」ことが重要となっている。それでは、これはいかなる事態を示すのか。
3.『全体性と無限』におけるままならない身体のゆくえ
3.1 死をまぬがれない者たちの形而上学的関係
本節では、欲望の条件として提示された「死をまぬがれないこと(形容詞mortel;名詞mortalité)」の議論を分析し、中期レヴィナス思想にも維持されている《身体のままならなさ》と、他者への超越の問題を整理する。しかしながら、2.1で確認したように、この身体のままならなさは初期思想のように、主体の同一性を破壊する要素としては機能していないと推測される。
「死をまぬがれないこと」の概念は、『全体性と無限』第Ⅲ部の第C章「倫理的関係と時間」において詳細に論じられているため、この章を具体的な分析対象とする。
本章は、従来の研究においてもあまり定まった解釈は提出されていない章ではあるが、倫理的関係を、有限な時間性を備えた身体の介在する水準から捉え直す箇所といえる。特に、倫理的な言語的関係を問題にしていた第Ⅲ部第B章とは対比をなすようにして、身体的存在者同士による「戦争(guerre)」も射程に入れ、形而上学的関係が単なる形式的・論理的意味に限定されないための具体的条件が探究されている。本節では、その一連の議論の概要を示す。
レヴィナスによれば、他者関係が形式的構造に尽きるなら、それは他者との分離が保たれた多元性を可能にはしない(TI, 242/393)。このとき、「多元性(pluralisme)」や「多様性(multiplicité)」は、主体と他者の絶対的な分離が保たれている様態そのもの、または、その分離した諸関係から成る社会全体などを指すと考えられ[25]、形而上学的関係を有する諸個人は、その多元性の諸項とも言い換えられている。
つまり、ここで問題となっているのは、形而上学的関係は〈同〉と〈他〉の分離の形式的・論理的意味によって示すだけでは、当の関係そのものの身分を裏切ってしまうということである。そこで、「分離した諸存在の間の関係が可能となるには、多様な諸項が部分的に独立しており、部分的に関係のうちに存在するのでなければならない」(TI, 246/399)とされる。ここから、他者関係は常に平和的なものではなく、戦争のように、互いが互いの影響下にある暴力的関係へと発展しうることが認められる(TI, 244/393)。〈同〉の形式的意味にこだわれば、多元性の諸項(諸個人)は内奥性(内面性)にとどまるだけだろう(ibid.)。
そして、互いに独立しつつも関係し合う諸存在が「時間的な存在」と呼ばれるものであり(TI, 247/400)、これが死をまぬがれない存在のことなのだ。死をまぬがれない存在とは、死を延期しながら生きている存在のことである。死からの延期が、その存在者の時間を成しているという意味で、死をまぬがれない存在は、時間的な存在でもある。
また、時間的な存在や、死をまぬがれない存在は「意志(volonté)」とも同義である。そして意志は意識とも言い換えられているが、『全体性と無限』第II部において意志や意識は、身体を基礎とするが身体のうちで身体性(物質性)から距離を取ったものであるという意味で「身体の身体性の延期」(TI, 179/292)と定義されていた。つまりレヴィナスにおいて、意志や意識など精神的なものは、それ自体が独立しているのではなく、身体を土台とする[26]。そして、この意志が私の〈同〉性、自己同一性を確立している。本章でのレヴィナスの論点は、しかし、その〈同〉が既に他のものからの影響を被る、死をまぬがれない身体であるという点である。
意志は意志という身分を持ち、「自分のために」(pour soi)という身分を持つのであって、あらゆる攻撃に対して免疫を持っているべきであった[が、そうではなかった]。[…]この意志の地位が、身体である(TI, 254/409)。
〈同〉の本質とも言える「自分のために」という意志のエゴイズムは、同時に意志が身体であることで、根源的に破壊されうる。そして、このことこそが本来の形而上学的関係を可能にするというのが、レヴィナスの主張である。
ここまで、形而上学的関係は、単に〈同〉と〈他〉が分離していることの形式的・論理的意味に回収されず、それは互いに関係し合う者同士の関係であることが論じられてきた。そして、そのような存在者は、具体的には物質という、始まりと終わり(有限性)を有する身体を基礎とした、時間的存在、死をまぬがれない存在であることが分かった。
この主体の曖昧で矛盾したあり方が、他者関係における本来の多元性を可能にする。レヴィナスは結論部分で、多元性と平和を結びつけている(TI, 342/548)が、「戦争をすることが可能な者のみが、平和へと高まることができる」(TI, 245/397)と言われるように、互いに影響しあえる者同士のうちで、それでもその有限性に固執し傷つけ合うのではなく、分離しながら関係することが、平和な形而上学的関係なのである。
3.2 身体の物質的現実としての死
では、互いに物質的に関与しうる者同士の形而上学的関係はどのように成立しているのだろうか。ここで、より詳細に問題となっている要素を分類すると、(1)身体の物質的現実(私は常に死にうること)、(2)そのことに他人が関係すること(他人が私を殺すこと)、そして(3)その他人のために死ぬこと、という、身体を基礎とした3つの点に分けられると思われる[27]。以下でまず(1)の点を確認する。(2)と(3)については、3.3で確認する。
意志において、自己への忠実さと、裏切りのうちで〈同〉の同一性が発揮されている[…]。意志はこの裏切りと忠実さの二元性を、その死をまぬがれないことのうちに含んでおり、死をまぬがれないことは、身体性のうちに生起し、発揮される。[…]そこにおいて多様性が、全体の部分への単なる可分性を描くのではないような存在は、死にうることと身体性を必要としており、それらがなければ、帝国主義的な意志は全てを復元するか、死にうるわけでも不死でもない、物理的な身体として一つの塊を形成するだろう。死をまぬがれない意志における死の延期——つまり時間——は、他人との関係のうちに入った分離的な存在の実存の様式であり、そして現実である(TI, 257-258/415)。
意志の核心には、自分自身への忠実(物質性を延期して、「自分のために」という主体の同一性をなす側面)と裏切り(物質を通じて破壊されうるという側面)があるが、確かに、後者の主体に内在する他者性は、初期思想で言われていたように主体の同一性を破綻させるものではない。しかしながら、「死をまぬがれないこと」というままならない身体性が、「他人との関係のうちに入った分離的な存在の実存の様式」とされているように、初期思想と同様に他者関係の根本に措定されていることが分かる。
「死をまぬがれないこと」という死からの延期の時間性は、生きる身体が独自に有する切迫の時間性である。『時間と他者』では、この抱えきれない時間性があるからこそ、主体が実際の他者との関係へ導かれることが可能になっていた。『全体性と無限』においても、この時間性が主体をエゴイズムの充足だけには閉じず、他者関係のうちに入ることをすでに可能にしている。なぜなら、「死をまぬがれないこと」の時間性や物質性がなければ、そもそも主体は永遠の精神として君臨するか、または単なる物質の塊となってしまうからである。やはり、絶対的な他者がいきなり現れることではなく、主体には身体の有限性という綻びがあるからこそ、形而上学的関係は築かれるといえる。
確かに、ここでは世界との具体的な関係を生きる主体が想定されているために、孤独な身体や、同一性の破壊は問題とはなっていない。しかしながら、「身体は健康と病気の間にある」(TI, 254/410)と、享受の次元のうちの健康で肯定的な生も、すでに身体の物質性に引き裂かれていることが示されている。『時間と他者』では、死の可能性に気づく前と、その後という、死の自覚の有無の段階があったが、中期思想では生があらかじめ死との揺れの間にある点において、その哲学的主体は常にすでに他者関係へ開かれているといえる[28]。
一方で、『時間と他者』、『全体性と無限』両者における死、そして《死にゆく身体》の役割は、単なるエゴイズムにとどまらない有限性を主体に生起させているという点で共通している。ここにレヴィナスの身体の他者性に関する一貫した議論を見出せる。
3.3 私を殺しうる他者と、その他者のために死ぬこと
身体が物質であり、既に自分とは異なるものから影響をもたらされうる様態であることは、そこに他者が介入しうることを意味している。この、(2)の点が、すでに指摘されているように[29]『時間と他者』とは異なった、新たな論点である。死は主体にとって全くの他者性だが、その死の他者性と実際の他者の存在が重ね合わせられるようになるのだ。
死との関係である私の存在を心配する恐怖は、無の恐怖ではなく、暴力の恐怖なのだ(そしてまたその恐怖は〈他人〉の恐怖、絶対的に予見不可能なものへの恐怖へと延長される)(TI, 262/422)。
予測不可能な死は、それが事故や病気と同じく、「敵(ennemi)」としての他人によってもたらされる可能性があることから、私の死の恐怖は、その敵や殺人者としての他人へと延長される。
つまりレヴィナスはここで、物質的様態にとらわれて自分の死を案じ、恐怖する主体はまず私を殺害しうる敵として他人と出会うとしている。確かに死は既に、主体がエゴイズムに閉じるのを防ぐ限界性を主体に与えてはいる。しかし、実際の主体と死の関係である、死への恐怖は、主体がまだ自分自身のみを軸として生きていることを意味するのであり、そのような状態では、他人は敵として出会われるのだ。
次に(3)の点である。この敵は私を一方的に狙う存在であり私の権能は及ばないが、しかし私と関係しており、私がその相手に向かって何かを成そうと「意欲すること(vouloir)」も可能である。
しかし、その意欲はエゴイズム的なものではなく、その重心の中心が欲求の自我とは一致しないような、欲望の本質へと流れてゆくような意欲であり、それはつまり〈他人〉のため(pour Autrui)欲望なのである(TI, 263/423、強調は引用者)。
ここでは、主体の「自分のため」の意欲や欲求から、「他人のため」の欲望への変化が記述されている。私を殺しうるものとして出会われた他人に対して、逆にその「他人のため」に意欲するとき、その意欲は欲望といえるのだ。
2.3で、他者性を受け取ると同時に、他者へ向かうことが両立する動きが欲望であることを確認した。ここで論じられている欲望も、この定義に当てはまっている。この時の主体は「エゴイズム的重力」から解放され、その重力が他者の方へと移動していると表現されている(cf. TI, 263/423;267/430)。レヴィナスは、存在者の重心が他者の方にある状態のことを「善性(bonté)」と呼んでおり、具体的に言えば、「善性とは、私自身よりも他人の方が重要であるという仕方で、存在のうちに身を置くこと」(TI, 277/443)である。他者と出会うということは、このような主体自身の根本的な変容を伴わずしてはありえない。主体が他者と出会い、その重心が他者の方にあるとき、主体の意欲は「他者のために」として生起する。上の引用では、このように他者との出会いの証となる、主体から他者への欲望の生起が示されているのだ。
主体の経験的世界においては、自身の物質的な有限性を通じて、物理的に私の死に関与しうる敵としての他者と出会う。しかし、そのように出会われた他者に、自分の死をものともせずに相手のために死ぬ可能性さえ有して相手と向き合うとき、欲望は生起していると言える。そうであるからこそ、レヴィナスにとって、主体の死は欲望の条件なのである。
しかし、そもそも主体はいかにして、敵としての他者のために欲望することができたのか。この点に関しては未だ飛躍があるだろう。そしてこれはおそらく、レヴィナスが、他者から主体に対する第一の言葉だと論じる「殺人を犯してはならない」という、他者の「顔(visage)」の呼び声(TI, 217/352)とも関係する。この言葉は今までの議論に沿えば、主体が、他者を主体として考える(重力が他者にある)ことで、自分自身をその他者にとっての殺人者だと考えていることを意味しているのではないだろうか。しかし、主体はいかにそのことに目覚めたのだろう。つまり、「死の恐怖が殺人を犯すことの恐怖へと反転するとき」(TI, 273/439)は具体的にはどのように生起したのだろうか。共感とは区別されるが、主体と他者の死という比較不能な限界性を通じた倫理[30]なるものがそこにはあるのか。このことについては、今後の課題としたい。
おわりに
孤独から超越への流れを有するレヴィナスの初期思想において、超越の内的条件であった身体の死や苦痛は、中期思想でも同様の位置を有している。しかしながら、中期思想では、完全な孤独状態の想定は放棄されており、主体は、常に既に単なる精神でも単なる塊でもなく、死にうる存在であるということを内的に感じ、生きているとされる。これは、主体に内在する矛盾や限界が、主体を孤独には閉じさせず、常に主体とは異なるものへと切り開いていることを意味する。
さらに、中期思想では新たな論点として、この物質の有限性を介して出会われる、実際の敵としての他者に対し、しかしその「他者のために」死ぬようにして存在することが、倫理的関係の根本にあることが示された。初期から中期を通じて、存在者が《ままならない身体》のうちに生きており、それが特に、死へと向かいゆく、《死にゆく身体》であることが超越の条件といえる。
本稿ではあえて、《一人称の私がいかに他者との出会いを果たすのか》という具体的な視点から、初期思想の議論を参照して、抽象度の増した中期思想を捉えなおすことで、レヴィナスによる倫理的関係の具体的な様相を確認することができたと思われる。
レヴィナスの倫理は、形而上の論理によってのみ完遂されるものではなく、肉体を有する人間のその物質性や暴力性に起因して駆動する。そして、その人間とは、今を生きる私たちであるとも言える。レヴィナスによれば1人の主体は、常に暴力と倫理的応答を他者になしうるのであるが、本稿からみえてくるのは、それらが矛盾ではなく、互いが互いの条件をなしている可能性である。
現代においてあらゆる暴力は、一般に、身体を有して傷つきうる存在にめがけてなされるが、その際には、互いの身体的特性(肌や髪の色、性的な特徴、障害の有無など)による、敵と味方の判断や、支配の対象としてよいかどうかなどの判断が介在することが多い。身体は常に具体的なものであり、特有の形象を有するのなら、レヴィナスの身体を介した他者との出会いの議論にも、これらの身体的特性が介入する余地はあるかもしれない。
そう考えるならば、殺人や、物理的・精神的・性的暴力が平然と行使される現代社会の中で、レヴィナスの哲学は、互いの身体性に基礎を置きつつも、その身体性に固執しない倫理的関係の生起について示唆を与えてくれるだろう。暴力は、確かにあらゆる文化的・歴史的要素抜きには語れない。しかし、その被害に対して倫理的な応答が果たされることを目指すなら、当の暴力の要因である、歴史や表象によって固定化された反応を突き崩すような、何か別の論理が必要となりうる。そこにこそ、レヴィナスの語る形而上学的な倫理の意義が見出されるのではないだろうか。本論では、特にその倫理的関係の成立において、主体自身の身体的な綻びが条件となっていることが示された。暴力がなされうるからこそ生起するとされる、レヴィナスによる倫理的応答の議論の現代的な発展可能性について、残された課題を含めて、さらなる分析を行いたい。
本稿は日本学術振興会・特別研究員奨励費(研究課題番号:25KJ0869)の助成を受けたものである。
Notes
-
[1]
本文では、レヴィナスの文章の引用や用語には「」を用いて示しているが、レヴィナスが頭文字を大文字にしている用語にのみ、原則的に〈〉の山括弧をつけている。そして、レヴィナス自身が使用しているわけではないが、本稿におけるキーワードや、括弧の中に入れる方が分かりやすい一文などは、二重山括弧《》とともに示している。
-
[2]
Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité [1961], La Haye, Martinus Nijhoff, « Livre de Poche », 1990(『全体性と無限』藤岡俊博訳、講談社学術文庫、2020年). 本文中には、丸括弧内に略号であるTIとともに、原文のページ、翻訳のページの順に参考箇所を示している。なお、これ以降の本文中における訳文は、既存の邦訳を参照しつつ、原則的に拙訳を記載している。
-
[3]
レヴィナス哲学において「超越(transcendence)」の語にはさまざまな哲学的意味が含意されている。例えば、小林嶺「エマニュエル・レヴィナスにおける『超越』の諸相」『早稲田大学大学院研究科紀要』第67号、2022年、349-365ページを参照のこと。しかし、本稿では、レヴィナスの用語法にこだわらず、主体が自分とは異なるもの、つまり他者と関係しているという至極単純な事態を表すものとして使用することとする。
-
[4]
Dominique Janicaud, Le Tournant théologique de la phénoménologie française, Paris, Éditions de l’Éclat, 1991(『現代フランス現象学 その神学的転回』北村晋、本郷均、阿部文彦訳、文化書房博文社、1994年).
-
[5]
Sara Ahmed, Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality, London; New York, Routledge, 2000, p. 137-160.
-
[6]
Ibid.
-
[7]
Emmanuel Levinas, De l’évasion [1935], Montpeiller, Fata Morgana, 1962 (「逃走論」『レヴィナス・コレクション』所収、合田正人編訳、ちくま学芸文庫、1999年、143-178ページ). 本文中には、丸括弧内に略号であるDEとともに、原文のページ、翻訳のページの順に参考箇所を示している。
-
[8]
Emmanuel Levinas, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme [1934], suivi d’un essaie de Miguel Abensour, Paris, Payot & Rivages, « Livre de Poche », 1997(「ヒトラー主義哲学に関する若干の考察」『レヴィナス・コレクション』所収、合田正人編訳、ちくま学芸文庫、1999年、91-107ページ).
-
[9]
Ibid., p. 17 (同上、101ページ).
-
[10]
ディディエ・フランクは、ハイデガーの存在論的差異を、レヴィナスが身体の生起によって読み替えていると指摘しており、そのような意味の負荷がかかったレヴィナスによる身体概念を、「差異の身体」と呼んでいる。Didier Franck, Dramatique des phénomènes, Paris, PUF, 2001,p. 96(『現象学を超えて』本郷均・米虫正日・河合孝昭・久保田淳訳、萌書房、2003年、103ページ).
-
[11]
Emmanuel Levinas, De l’existence à l’existant [1947], Paris, Vrin, « Livre de poche » , 2004, p. 38 (『実存から実存者へ』西谷修訳、ちくま学芸文庫、2005年、53ページ).
-
[12]
Emmanuel Levinas, Le temps et l’autre [1948], Paris, PUF, onzième édition, « Livre de Poche », 2014 (『時間と他者』原田佳彦訳、法政大学出版局、1986年). 本文には丸括弧内に略号であるTAとともに、原文のページ、翻訳のページの順に参考箇所を示している
-
[13]
レヴィナスは、主体が取り込むことのできない、原則的に人間存在としての他者を示す「他者(Autre)」や「他人(Autrui ; autrui)」と、主体の消費の対象となる、世界の物質としての「他なるもの(autre)」を区別する。そのために、後者の他なるものを本文では「他なるもの」として記載する。
-
[14]
本論では紙幅の都合上主題化できないが、レヴィナスにおける死の議論は、ハイデガーの『存在と時間』における死の議論を下地とし、それを深化させたことによって形成されているとも言える。マルク・クレポンによれば、レヴィナスは自身の死に関する思索に、身体的苦痛、死が他者からもたらされる可能性、そして他者のために死ぬ可能性、という3つの点を採用することで、ハイデガーの議論を深化させつつ、そこから差別化している。このいずれも本稿に関わる論点であり、のちに本論で触れている。Marc Creapon, « Vaincre la mort », Jacques Taminiaux (éd.), Études phénoménologique, n° 43-44, Belgique, Éditions Ousia, 2006, p. 43.
他に、レヴィナスとハイデガーの死の議論を比較分析する研究として、Cristian Ciocan, « Les repères d’une symétrie renversée: La phénoménologie de la mort entre Heidegger et Lévinas », Emmanuel Levinas 100, Zeta Books, 2007, p. 241-278、高野浩之「レヴィナス『全体性と無限』における『私の死』について」『大学院研究年報』(中央大学文学研究科)第53号、2024年、343-352ページを参照のこと。本稿はこれらの分析に多くを負っている。 -
[15]
Cristian Ciocan, p. 261.
-
[16]
François-David Sebbah, L’épreuve de la limite. Derrida, Henry, Levinas et la phénoménologie, Paris, PUF, 2001, p. 184 (『限界の試練 デリダ、アンリ、レヴィナスと現象学』合田正人訳、法政大学出版局、2013年、218ページ)
-
[17]
この具体的な営為が、1.2でも触れた「享受」である。『全体性と無限』において享受は、飲食に代表されるように、生において「幸福(bonheur)」という状態を志向する主体が、欠乏や空腹をきっかけとして欲求を抱き、物質を主体のうちに取り込むという営みである。つまり享受は、基本的に主体を起点として、「他なるもの」へと向かい、さらに主体に巻き戻るという動きである。
-
[18]
『全体性と無限』で採用されている現象学的手法については、小手川正二郎『甦るレヴィナス 『全体性と無限』読解』水声社、2015年、43-52ページや、渡名喜庸哲『レヴィナスの企て 『全体性と無限』と「人間」の多層性』勁草書房、2021年、282-289ページを参照。
-
[19]
例えば、藤岡俊博『レヴィナスと「場所」の倫理』東京大学出版局、2014年、174ページ以降、板部泰之「閉ざされた窓、開かれうる窓 〈自己閉塞〉論としてのレヴィナス読解」『レヴィナス研究』第6号、2024年、108-120ページを参照。
-
[20]
François-David Sebbah, op. cit., p. 184-185(前掲書、218-219ページ).
-
[21]
例えば、石井雅巳・高井寛「倫理は分離を前提とする 『全体性と無限』における自我論と他者論の関係について」『レヴィナス研究』第1号、2019年、65-75ページや、渡名喜庸哲、前掲書、329ページ以降を参照。
-
[22]
板部泰之、前掲論文、113-114ページ。
-
[23]
欲求と欲望の違いに関して、以下の論考が簡潔に解説している。小手川正二郎「欲求(besoin)と欲望(désir)」レヴィナス協会編『レヴィナス読本』所収、法政大学出版局、2022年、48-50ページ。
-
[24]
身体論からレヴィナスの哲学を捉えなす方針を採用している伊原木大祐も、そもそもなぜ倫理的関係において言語が必要となるのかを、身体的次元から捉え直す必要について言及している。伊原木大祐『レヴィナス 犠牲の身体』創文社、2010年、79ページ。
-
[25]
他所で多元性は、俯瞰的眼差しから把握される数的多様性から区別されている(TI, 242/393)。数的な問題とは区別される形で、互いに分離した存在同士による社会関係のあり方を、レヴィナスは「社会の多元的様態」(TI, 229/370)と呼んでいる。
-
[26]
レヴィナスの哲学における、肉を通じた意識や時間の生成については、ベルンハルト・カスパーの論考に詳しい。Bernhard Casper, « La temporalisation de la chair », J.-L. Marion (éd.), Positivité et transcendance : Emmanuel Lévinas. suivi de, Lévinas et la phénoménologie, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 165-180.
-
[27]
(2)と(3)の点に関しては、すでにクレポンが指摘していた。注14を参照。
-
[28]
ただし、それは既存の先行研究とは異なる意味においてである。従来の多くの先行研究では、主体の「自分のために」という自己形成と、他者との出会いや関係が直接的に結びつけられていた。そこでは、他者の現れと、その平和な関係の生起は自己同一的な主体にとって常に可能であることになるだろう。しかしながら本稿では、主体に対する他者の現れをそのまま両者の平和的な他者関係の成立に結びつけるのではなく、主体に内在する他者性がその関係の条件になるのだと分析を進めている。
-
[29]
Marc Creapon, art. cit., p. 49.
-
[30]
Agata Zielinski, « Le visage, « corps expressif » ? Merleau-Ponty et Levinas interprètes du corps », Philippe Fontaine et Ari Simhon (éd.), Emmanuel Levinas : phénoménologie, éthique, esthétique, herméneutique, Argenteuil, Cercle herméneutique, 2007, p. 101.
この記事を引用する
髙井 実奈「死にゆく身体と超越——初期から中期レヴィナスにおける超越の内的条件としての身体について」 『Résonances』第16号、2025年、19-34ページ、URL : https://resonances.jp/16/le-corps-mortel-et-la-transcendance/。(2026年02月15日閲覧)